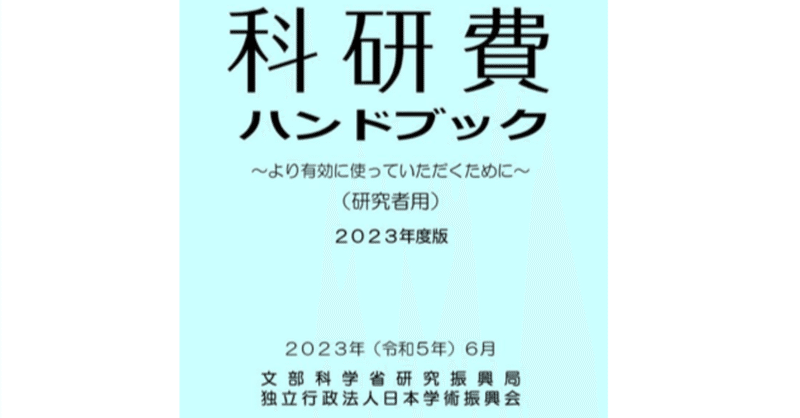
元教授、科研費の報告書にそろそろ取りかかって下さい!:定年退職52日目
私はこの3月末に大学を定年退職し、研究の現場から一歩退きました。しかし、少しですがいくつかの仕事が残っています。旧研究室にも学生がまだ少数残っていますし、企業からの依頼や各種審査などの業務もあり、それなりに多忙な日々を送っています。中でも一番忙しいのは、毎日の「note」執筆ですw(これがなかなか大変なんです!)。
さて、科研費報告書の締め切りが近づいてきました(タイトル図:注1)。科研費とは、国からいただく研究費のことです(正確には科学研究費助成事業で、文部科学省・日本学術振興会から助成されます。下図(注2))。大学で研究を行うためには研究費が必要で、大学からの運営費(毎年減少傾向)だけでなく、多くの場合、自分で研究費を調達しなければなりません。一般には、企業などとの共同研究費や受託研究費、文科省以外からの国の研究費などもありますが、基礎研究を行う上で最も馴染みがあるのは上記の科研費です。科研費には、その目的により年間数億円から百万円程度までいろいろなグレードがあります。
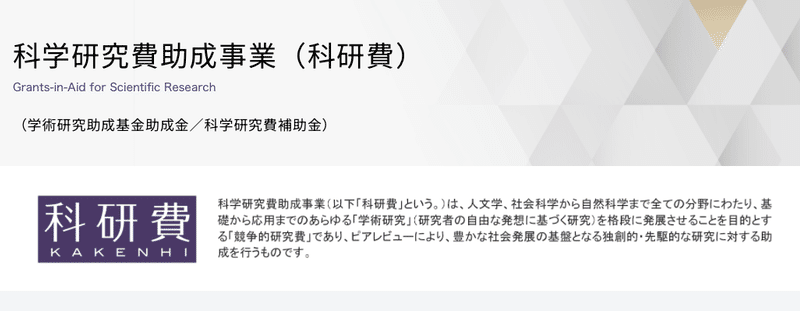
ただし、科研費を助成してもらうためには、単に手を挙げるだけではなく、半年以上前から詳細な申請書を作成し、多段階の厳しい審査を経る必要があります(いわゆる競争的研究費制度です)。その結果は4月1日頃に発表されますが(最近はネットでの発表。以前は紙面でした)、学生たちが春休みのその時期に、先生たちはドキドキしながら結果を待っています。申請が通れば、少なくとも数年間は研究室の予算の心配をあまりせずに済みますが、通らなかった場合は他の申請を考えなければなりません。
“ 日本の場合は、まだ大学からの運営費があるので良いのですが(ただし、電気代高騰などにより減少率が著しいです)、アメリカなどでは研究費が無くなると悲惨な状況になります。私の知り合いの研究室では「1年間お休みします」ということもありましたし、教授が費用を厳しく削減し「先週に糊を買ったのに、なぜ今セロテープが必要なんだ」などと細かく指摘することもあるそうです。”
話を戻しますと、その科研費を使用した後には報告書の提出が必要になります(国民の税金を使わせていただくわけですから当然です)。通常、年度ごとの報告書は5月末に、数年の研究期間全体の報告は終了後の6月末に提出が求められます。ただし大学事務でのチェックが必要なため、その約一ヶ月前が大学への提出締め切りとなります。私は年度ごとの報告書は既に提出しましたが、後者の全体の報告書をそろそろ準備しなければなりません。実は、なかなか腰が重いので、こんな文章を書きながら時間稼ぎして(自分をごまかして)いる状況ですw。
最近、教員の事務の負担が増えて研究時間が圧迫されていることが問題視されています。日本の研究レベルが他国に比べて低下しているのではないかという懸念もあり(THE(英、高等教育専門誌)やQS(英、大学評価機関)の「大学ランキング」報告などによる)、このような申請や報告の事務作業を減らす方向を模索してほしいものです。
もちろん、少しずつ改善は行われています。例えば、先日作成した報告書では、発表した論文のDOI(国際的な識別子)を記入するだけで著者名、論文名、雑誌名、ページ数などのデータが自動で挿入されるシステムが導入されていました。
さて、ブツブツ言ってないで、そろそろ報告書作成を開始します。事務の方、もう少しお待ちください。
ーーーーーーー
注1:文部科学省、日本学術振興会作成「科研費ハンドブック」より
注2:日本学術振興会HPより
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
