
コンパス・ポイント・スタジオ~アイランド・レコード周辺(3)
コンパス・ポイント特集の最後はアルバム1枚のみこちらで録音しているアーティストが中心です。
(「CPAS」は「コンパス・ポイント・オール・スターズ」の略です。詳しくはパート1をごらんください。)
<バリー・レイノルズ>

'49年、英ランカシャー州ボルトン出身のギタリスト。'70年代初頭にパシフィック・ドリフトやブラッドウィン・ピッグ等のバンドに参加するもヒットには繋がらず、数年間はアメリカ~メキシコを放浪。'70年代半ばにロンドンに戻りビリー・オーシャンのバックでギターを弾いていたが、その頃知り合ったキーボード奏者のデイヴィッド・ウィルキーの勧めでマリアンヌ・フェイスフルのバンドに加わる。オランダや西ドイツをツアーした後、マリアンヌとスタジオ入りして曲作りを始め、彼女のカムバック作"Broken English"の制作に大きく貢献。

アルバムのラストに収められた曲"Why D'Ya Do It"でのバリーのギター・プレイに強く印象づけられたクリス・ブラックウェルは彼をCPASの一人に抜擢し、マリアンヌとのコラボは継続しつつナッソーでのグレイス・ジョーンズ他のレコーディング多数に参加していくことになる。
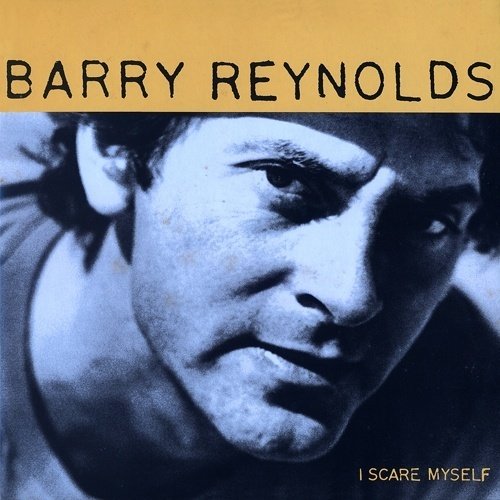
唯一のソロ・アルバムはコンパス・ポイントが最も頻繁に稼働していた時期と重なる'82年のリリース。プロデュースはアレックス・サドキン、参加メンバーはCPAS全員に加えて2曲でアイ・スリーズの女性陣がコーラスをつけるというもので、曲はダン・ヒックスのA-1とアイルランドの古くからの楽曲だというラストの"The Bold Fenian Men"以外はバリーの作曲。A面はCPASらしいレゲエ~カリブ風味を感じられる楽曲が中心だが、B面にはバリー本来の持ち味であるロック~シンガー=ソングライター色の出た曲が収められている(B面は言われなければスライ&ロビーが演奏しているとは全く思えない)。グレース・ジョーンズまんまなリズム・トラックにファルセットで唄う"More Money"がベスト・トラックか。
<マリアンヌ・フェイスフル>

'46年、ロンドン生まれの女性シンガー。'60年代半ばにストーンズ周辺の人脈のバックアップでデビューし、ストリングス多用のソフトなポップスやフォーク・ロック的な演奏をバックに容姿通りの可憐な唄声を聞かせるアイドル・シンガー的な存在だった。'60年代後半はミック・ジャガーと交際していたが、ミックと破局した'70年前後からドラッグ、酒、煙草等の乱用で喉をつぶし、ドスの効いた魔女声になる。その後は'76年に一枚アルバムを出したきりだったが、バリー・レイノルズの好サポートとクリス・ブラックウェルの後押しで'79年に復活。悲壮感や孤独を包み隠さず表す作品が高く評価されている。

アイランドからの3枚目になるアルバムで、プロテュースはバリーとウォーリー・バダルー、NYのメディア・サウンドのエンジニアであるハーヴェイ・ゴールドバーグの3人。ナッソーで基本的なレコーディングを行った後、メディア・サウンドでフェルナンド・サンダースらNY組をオーヴァーダブしたものと思われる。前2作よりポップに仕上げたかったのか全体にソフトな曲が目立ち、バダルーによるキーボード・アレンジもやや平版な感じも。
<リジー・メルシェ・デクルー>

'56年パリ生まれの女性シンガー。学生時代にパリでレコード店のオーナーでパンク系のファンジンを制作していたミッシェル・エステバンと出会い、彼と行動を共にするようになる。二人はNYのパンク・シーンの取材のため渡米し、パティ・スミスやリチャード・ヘルらと親交を深めた。その後リジーは独学でギターを学び、エステバンの弟らとローザ・イェーメンを結成してレコード・デビュー。そのシングルはセールス面では不発に終わり、今度はエステバンが設立したZEレコーズからソロ名義で再デビューすることになる。ファーストはダークなエレクトロとパンクが融合したような音だったが、セカンド、サードではカリブやラテン、アフリカ音楽を大胆に取り入れ、後にフランスでのワールド・ミュージックの先駆として評価された。

プロデュースにスティーブン・スタンリーが関わっているが、演奏でCPAS関係者から参加しているのはウォーリー・バダルー(パリ育ち)のみで他はリジー周辺から、ということでフランス人ミュージシャンで固められている。トーキング・ヘッズを意識したと思しきアフロ・ファンクのA-1、ラテン・リズムにカリプソ風アレンジがのるアルバム・タイトル曲が印象深いが、全体としては強力なベースを軸にしたトリッキーなファンクが中心。クール&ザ・ギャング"Funky Stuff"のカヴァーにも個性があふれている。
<セット・ザ・トーン>

シンプル・マインズのドラマーだったケニー・ハイスロップを中心にグラスゴーで結成されたダンス・ロック・グループ。結成してすぐにアイランドと契約してデビュー・シングル"Dance Sucker"を発表し、つづいてアルバムの制作に入るがベーシストが脱退したため、コンパス・ポイントのセカンド・エンジニアだったケンダル・スタブスがベーシストとして加わり6曲入りミニ・アルバム"Shiftin' Air Affair"を完成させる。セールスは不調でアイランドとの契約は切られ、グループは解散、短命に終わった。

これがデビュー・シングルで、両面ともアルバムには未収録。"Dance Sucker"はフランソワ・ケヴォーキアンがリミックスを手掛け、ブヨブヨのシンセ・ベースが繰り返される中、ダブ処理されたヴォーカルやシンセが次々と現れる、なかなかカッコ良い曲。B面はスティーブン・スタンリーも加わったインストで、TR-808のビートにスラップ・ベースが絡むクールなファンク。
<ジョー・コッカー>

'44年、英シェフィールド出身のシンガー。しゃがれた独特の声質、レイ・チャールズの影響をうけたソウルフルな唱法で知られる。'64年にレコード・デビュー、その後しばらくはイギリス国内での活動が中心だったが、'69年のウッドストックへの出演、翌年のレオン・ラッセルのバックアップをうけた大規模なライブ・ツアー等でアメリカでも人気を獲得する。'74年にビリー・プレストンの作品を取り上げた"You Are So Beautiful"がヒット、それからは渋味あふれるオトナのロック・ヴォーカリスト的な作風へと変化していく。今回取り上げている"Sheffield Steel"はアイランドに移籍後初のアルバムだが、リリース直後に映画「愛と青春の旅立ち」のサントラに提供したバラード"Up Where We Belong"がチャート一位の大ヒット、その曲は収録されていないのにその時点での最新作ということで"Sheffield~"もチャートを上昇するという現象が起きた。

CPASが全員参加、プロデュースはアレックス・サドキン(マイアミでの修行時期にコッカーの前作のエンジニアもつとめていた)。レコーディングはグレイス・ジョーンズ"Nightclubbing",マリアンヌ・フェイスフル"A Childs Adventure"と並行して行われたそうで、コッカーの個性に合わせたところもあるのだろうがそれほとヒネらずシンプルなアレンジの曲が多い。レゲエ・リズムのB-1以外はロビー・シェイクスピアのベースもおとなし目。
<セルジュ・ゲンズブール>

'28年パリ生まれの歌手・作曲家。'58年に歌手としてデビューするが、いっぽうで作曲家として他人への曲の提供も行っていた。特に女性シンガーとの相性が良く、フランス・ギャル、ブリジット・バルドー、フランソワーズ・アルディ、ジェーン・バーキン等が彼の作品でヒットを飛ばしている。自身のアルバムは作品ごとに組むアレンジャーによって音が変わる印象があるが、パーカッションを大きくフィーチャーしたラテン~アフロ色濃厚な"Gainsbourg Percussions"(アレンジはアラン・ゴラゲール)、ジャン・クロード・ヴァニエのダークなアレンジがダウンテンポ系の音に通じる"Histoire de Melody Nelson"あたりは今の耳で聴いてもカッコ良い内容だ。
ゲンズブールは'70年代後半に突如レゲエに接近、キングストンのダイナミック・サウンド・スタジオでスライ&ロビーやアイ・スリーズをバックに従えたレゲエ・アルバム"Aux Armes Et Cætera"を録音する。

アルバム・タイトル曲はレゲエのトラックにフランス国歌から引用した歌詞を乗せたものだったが、サビの部分をオリジナルとは違う文言に改ざんしていたことが軍部や右寄りの関係者の怒りを買い、放送禁止の措置になる。それが却って話題を呼んでアルバムは50万枚を超える大ヒット、「ジェーン・バーキンのヒモ」的なところに落ち着きつつあった世間の評価が「パンクなオヤジ」へと好転したという。
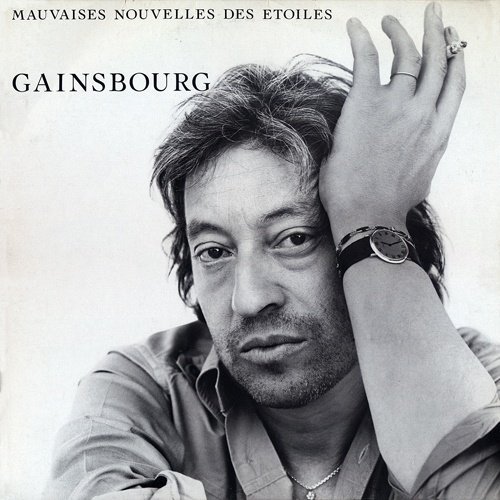
その2年後の本作はスタジオがコンパス・ポイントに、エンジニアはスティーブン・スタンリーに代わっているが、基本的なメンツは前作と同じでウォーリー・バダルー&バリー・レイノルズのヨーロッパ組を除いたCPAS全員にプラスしてアンセル・コリンズやアイ・スリーズが加わったもの。'70年代後半のウェイラーズをお手本にしたような演奏に、ボソッとつぶやくようなセルジュのヴォーカル、サビなどのメロディアスな部分はアイ・スリーズに任せるといった具合。ダブ処理もA-3,B-2,3,5あたりで聴ける。くどいほどオナラの擬音が連発されるB-3はセルジュが前年に発表した小説にリンクした内容。
<リー・"スクラッチ"・ペリー>

'38年、ジャマイカ、ハノーバー教区のケンダルで生まれたプロデューサー/シンガー。'50年代後半から'60年代半ばにはコクソン・ドッドやジョー・ギブスの下でレコーディングを学ぶ。'60年代末からは自身のグループ、アップセッターズを率いて活動を開始、'73年には自宅の裏庭にブラック・アーク・スタジオを設立してプロデュース業も本格化する。アップセッターズでヒットを飛ばす一方でボブ・マーリーやマックス・ロメオ、ジュニア・マーヴィン等の作品を手掛ける。ブラック・アークを'79年に漏電事故で焼失して以降はイギリスやスイス等ヨーロッパでの活動が増えていくが、2021年に亡くなるまで旺盛に活動を続けた。ブラック・アーク期の作品はチープな音が個人的には苦手なのだが、"Super Ape"、"Roast Fish Collie Weed & Corn Bread"、コンゴスの"Heart Of The Congos"等名作も数多い。

トム・トム・クラブに入りそこねた(?)ペリー先生にもコンパス・ポイント録音があった。3人のバック・ヴォーカリストの他にアップセッターズのクレジットもあるが、ペリー以外の演奏者は不明。打ち込みやシンセ類を多用したポップなトラックをバックにコンパス・ポイントならではのクリアなミックスでペリーが唄う内容で名作のひとつにあげる人もいるようだが、この後にイギリスでエイドリアン・シャーウッドらと組んだアルバムのほうがこの人の毒気をうまく生かしている気がする。
ジャマイカ勢は数も多いのでここからはしばらく駆け足で。

映画「ハーダー・ゼイ・カム」で知られるシンガー'81年のアルバム。キングストンのダイナミック・サウンズでメインの録音を行った後、コンパス・ポイントで追加のオーバーダブとミックスを行っている。CPASからはスライ&ロビー、ウォーリー・バダルー、スティッキー・トンプソンが参加。オーガスタス・パブロやブラック・ウフルの男性陣二人等がバックメンとして参加しているところには政治力的なものを感じる。

ルーツ・レゲエ・ファンから絶大な支持を得るウィンストン・ロドニーのプロジェクト。ファミリーマン・バレットやホースマウス等のレギュラー・メンバーに加えてアスワドのメンバーやリコ、サード・ワールドのアイボ・クーパー等のゲストを迎えたアルバムで、音の厚みを増しつつ、それでいて浮ついたところのない重厚なアルバムに仕上がっている。

ロックステディ期に活躍したジョン・ホルトらのコーラス・グループがスライ&ロビーの仕切りで再結成。カヴァー曲でも知られる"The Tide Is High"、"Man Next Door"等の'60年代の彼らのヒット曲を再演している。ほぼオリジナルのままのヴォーカル・アレンジで、スライ&ロビーのタイトかつ無駄のない演奏がパラゴンズの甘いコーラスを蘇えらせている。

'73年にインナー・サークルの元メンバーらによって結成されたグループ。彼らは早くから海外マーケットを意識した展開をしていたが、レゲエ・アーティストを手掛けることが少ないアレックス・サドキンがプロデュースしていることにも意図が感じられる。ヴォーカルにUS産ソウルの強い影響を感じられる曲が多いが、それがうまく作用したのがシングル・カットされた"Now That We've Found Love"。オージェイズのカヴァーだが、イギリスではほぼソウル/ディスコ系の曲という売れ方でヒットした。

'60年代後半のスカ期に"Israelites""007 (Shanty Town)"等のヒットを放ったシンガー。2トーン・レーベルの成功でスカがリヴァイヴァルしていたイギリスのスティッフ・レーベルの制作で録音されたアルバムで、プロデュースはロバート・パーマー。ベースも担当するパーマーのほか、演奏はパーマーのバンドの白人ロック勢が中心。"80年代のモダンな演奏にデッカーの持ち味であるハイ・トーンのヴォーカルを生かした音作りだが、いま聴くとけっこうつらい感じも。
<トンプソン・ツインズ>

'77年にシェフィールドで結成。当時はギタリスト/ベーシスト/ドラマーも居るロック・バンド然とした編成だったが、セカンド・アルバムからのシングル"In The Name Of Love"がヒットして以降はトリオに変わり、作曲とキーボード/プログラミング、リード・ヴォーカルを担当するトム・ベイリーを中心としたシンセ・ポップ・グループに生まれ変わる。このメンツで作られた"Quick Step & Side Kick"からはダンス/ディスコ・チャートを中心に3曲がヒットするが、次作"Into The Gap"以降はよりポップ志向を強めた穏やかな作風へ。

この頃の彼らはシンセ・ポップど真ん中といった感じの音だが、トム以外の二人が担当するパーカッションの乾いた響きもいい味を出していて、アレックス・サドキンのエンジニアリングがうまく貢献している。B-1"Watching"では外部のレコーディングに関わることは珍しいグレイス・ジョーンズがヴォーカルで参加。リアルタイム当時はこのアルバムとヘヴン17のセカンドがシンセ・ポップ系では好きでした…
<マヌ・ディバンゴ>

'33年カメルーン生まれのサックス奏者/ヴォーカリスト。十代後半の頃にクラシック・ピアノを学ぶため留学していたフランスで音楽活動を開始する。'60年にコンゴでアリカン・ジャズというグループに参加した後カメルーンに戻り、'63年から自身のグループで活動を開始。'70年代に入るとフランスのフィエスタ・レーベルからアルバムをつぎつぎと発表、特に'72年の"Soul Makossa"はアメリカでもアトランティックからライセンス・リリースされてチャートのトップ40入りするヒットになり、ミリアム・マケバ等につづいてアフリカン・ポップスが欧米に伝わるきっかけになった。その後もアフリカ音楽とジャズやポップス/ソウル、ラテンの融合をテーマにした作品を多数発表している。2020年、新型コロナウイルス感染症のため逝去 。

それまでフィエスタ・レーベル経由でアルバムを発表してきたマヌが初めてアイランドと契約してのアルバムで、バックをつとめるのはスライ&ロビーらのジャマイカ勢。ジョセリン・ブラウンやユランダ・マックロー等の女性コーラスとブレッカー兄弟やバリー・ロジャース等のホーン類はNYでオーヴァーダブされている(ミキシングはロンドンとコンパス・ポイント)。演奏はレゲエ・リズムが中心だが、サックスはレゲエとも相性の良い楽器なので全く違和感なし。女性コーラス陣が活躍する曲はサックス+コーラスということで殆どムード音楽に聞こえてしまいますが…
<ロバート・パーマー>

'49年ヨークシャー州バトリー生まれのヴォーカリスト。'60年代からアラン・ボウン・セット、エルキー・ブルックスらとのヴィネガー・ジョー等のグループで活動した後ソロに転向。ソロ・デビュー当初はミーターズやリトル・フィートのメンバーを従えたニュー・オーリンズ・ファンクにパーマーのソウルフルなヴォーカルというスタイルで、セールス面では今ひとつだったものの玄人好みのアーティストとして評価されていた。'70年代末にコンパス・ポイントがオープンするとスタジオの通りをはさんだ向かいに別荘を購入、以降'88年までのアルバムにはいずれも同スタジオでのレコーディングが含まれている。'85年にデュラン・デュランのメンバーらと結成したパワー・ステイションで人気を獲得、同年リリースのソロ"Riptide"からのシングル"Addicted to Love"では初の全米No.1ヒットを記録した。

上にも書いたとおり'80年代のパーマーはコンパス・ポイントで多数のレコーディングを行っており、意外なミュージシャンの作品にもひょっこり参加していたりするのだが、スタジオのカラーにも合った代表作ということでこちらを。ギャスパー・ラワルの曲にインスパイアされたというカリプソ+レゲエ風味のアルバム・タイトル曲をはじめ、カリブや北アフリカの音楽とシンセ類をうまく融合させたナンバー、ザ・システムやクール&ザ・ギャングをカヴァーしたコンテンポラリーR&B、シモンズ・ドラムの響きが耳に残るシンセ・ポップ系ナンバー等をパーマーのソウルフルなヴォーカルがまとめ上げている。バックの面子はパーマー作品のレギュラー・メンバーが中心だが、シンセ類の的確な使用は初めて組んだルパート・ハインの起用が鍵か。
スティーブン・スタンリーによれば、アーロンズ(Earons)のシングル"Land Of Hunger"('84年)のレコーディングの頃までがスタジオの最盛期で、その録音を境に徐々に減退していったそう。他所でのプロデュースが増えたアレックス・サドキンに代わって雇われたNY出身のE.T.ソーングレンは働きづめで余裕のない状態。この頃新たに雇われたスタッフたちの間ではコカインやクラック等のドラッグが流行し、あまりよろしくない雰囲気が出来上がりつつあったところ、ナッソーに戻ってきたアレックス・サドキンはバイク事故で急逝。2年間ほど何も仕事のなかったスティーブン・スタンリーはジャマイカに帰ることに。主であるクリス・ブラックウェルはアイランドのビジネス面での業務で多忙のためスタジオに顔を出すことはなくなり、潮が引いていくように人気(ひとけ)が無くなっていくのでした…コンパス・ポイントのスタジオとしての営業はこの後もつづき、2010年ごろまではレコーディングは行われているのですが、アイランド・レーベルのハウス・スタジオ、最高のハウス・バンドとスタッフをそろえた自社のスタジオとしての機能は'86年前後に終わったと言っていいでしょう。

コンパス・ポイントの特集はこれで終わりですが、次回もアイランド・レコードとの関わりが深いとある人物について書く予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
