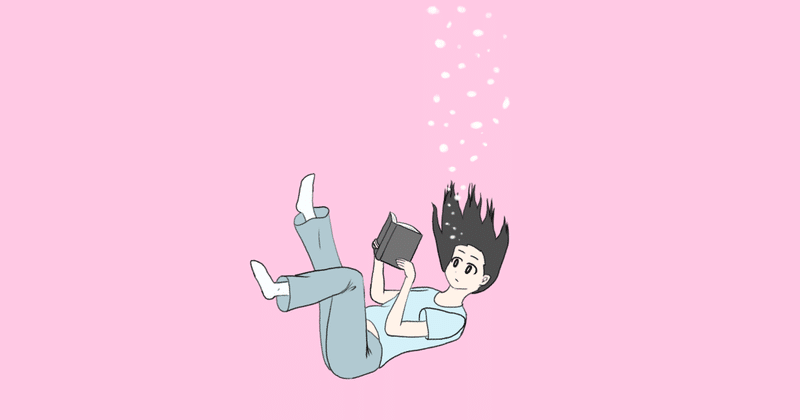
ふるさと納税について③
今回はふるさと納税の申請による上限金額の違いに関する解説です。
少し難しいかもしれませんがなるべく分かりやすく説明します。
前回のふるさと納税②で解説した様にふるさと納税の申請には『確定申告』と『ワンストップ特例制度』の2つがあります。
確定申告とワンストップ特例制度どちらで申請したかで戻ってくるお金の出どころが変わります。
確定申告では主に所得税が対象となりお金が返ってきます。
そしてワンストップ特例制度では主に住民税が対象となりお金が返ってきます(正確には所得税が上限に達しても損をしないように住民税を優先して対象とします)
所得税は国・住民税は自治体が各々計算しているので人によって上限が違います。
極端な話をすると所得税上限30000円・住民税上限10000円の様な人はワンストップ特例制度より面倒でも確定申告した方がふるさと納税の恩恵を大きく受ける事ができます。
但し基本的に上記の様にアンバランスになる事は無いのでワンストップ特例制度で良いです。
では何故この所得税と住民税の話をするのかというと住宅ローン減税を受けている方などが勘違いをしてふるさと納税をやらないパターンが多いからです。
住宅ローン減税は20〜30万円と大きなお金が返ってきます。
そのため『こんなに沢山の金額を減税されているから他の減税を受けられないだろう』と思い込んでしまいます。
これは半分正しいですが半分間違いです。
確かに住宅ローン減税をすると申請して返金される対象の上限を全て使い切ってしまいます。
しかし住宅ローン減税の対象となる税金は主に所得税となり所得税の上限を超えると次点で住民税を対象にします。
つまり住宅ローン減税をしていても住民税の上限がまだ残っている人が大半です。
ここで思い出して頂きたいのがふるさと納税の申請による返金対象の違いです、確定申告すると所得税、ワンストップ特例制度だと『住民税』を対象とします。
ということで住宅ローン減税は所得税を対象としふるさと納税のワンストップ特例制度は住民税を対象として返金されるので基本的にふるさと納税による恩恵を受けられます。
※所得が高くなく住宅ローン減税の返金額が多い人は住民税の上限が少ない場合があるので要注意です。
今回は以上となりますが『税金の仕組み』が少し見えてきたのではないでしょうか?
所得税と住民税を分けて考えられるようになれば知識の幅がかなり広がります^_^
それでは失礼します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
