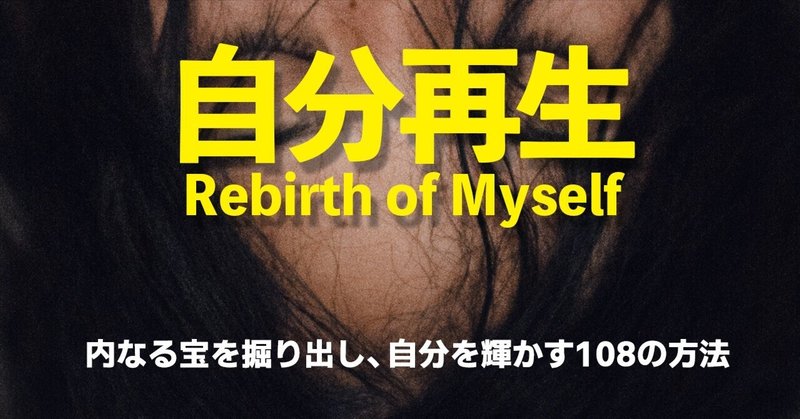
内なる宝を掘り出し、自分を輝かす108の方法
こんにちは! つなワタリ(@27watari)です。
「【2023】内なる宝を掘り出し、自分を輝かす108の方法」に来ていただき、ありがとうございます。簡単にこの記事の目的をお伝えします。
もっと自分らしく輝きたい! だから……
この記事は「自分の中に眠っている内なる宝を掘り出し、自分を輝かし、世の中を照らしていくこと」を実現するために意識しておいた方がいいと思える108の方法を備忘録として書く残していくものです。
個人的にnoteは苦手なので、更新は不定期です。また、構成を考えて書いてはいません。修正・加筆をしながら書き進めていきます。内容の重複などもあるかもしれませんが、笑って大目に見てください。
簡単な自己紹介
簡単に経歴を説明しておきます。出身は宮城県。50代の男性です。若い頃はたくさんの夢を抱いていました。挑戦もした方でしょう。東京に来て無軌道に生きてきて現在に至ります。本業は編集者。キャリアは長いです。独立して会社を作って20年以上になります。取材、原稿書き、撮影、デザイン(DTP)などをこなす一人親方です。大きくはありませんが、イベントなどのプロデュースなども手がけています。現在は疲れ切っている自分に喝を入れようとしつつ、結局はパワーダウンしていく自分に危機感を抱いています。まぁ、よくいる「昔はこうだった」と過去を懐かしむ自分を切り捨てようと四苦八苦している最中です。
「なんとか自分を変えたい!」という気持ちは年齢や環境、性別には関係ないことです。何かの役に立てば嬉しい限りです。
では、いきましょう。

私は器用貧乏です。好奇心に任せて好き勝手に生きてきました。好奇心旺盛で、さらに「人好き」というキャラだったこともあり、かなり充実の人生を送ってきた気がします。しかし人生後半戦になり、自分が何も成し遂げてきていないことを痛感します。いや、正確に言えば、「自分が納得する成果を何ひとつ出していない」ということに気づかされました。
人生は長いようで短いものです。「自分が納得する成果」を出したいのであれば、無軌道に生きるのは危険です。時間やエネルギーをロスするリスクをはらんでいます。だから『自己再生』のためには、自分のベクトルを定めることが大切だと考えます。
自分のベクトルを定める方法は、一つしかありません。それは「対話」をすることです。
対話とは、会話ではありません。挨拶でもありません。想像して自分の中にある本質を炙り出す行為です。
自分自身と、仲間と、家族と、先輩と、自分の成果物と、尊敬できる存在など、自分と関係が深い相手と対話をするのです。実際の対話でも、想像上の対話でもかまいません。対話しながら自分の強み、夢、理想、性格、性質、得手不得手などと向き合い、自分の人生に相応しいベクトルを決めてください。すぐに決められなくてもかまいません。定期的に現状と心情を確認し、対話を重ねながらベクトルを調整していってください。

ベクトルを定めたら、止まらずに前進していくのみです。
止まらずに前進するのとは、かなりハードルが高く、エネルギーを激しく使う印象を受けるかもしれません。しかし、まったく違います。
コツは自然体。具体的には、水の如く流れていくだけです。イメージしてください。最初は地面から滲み出てくるかすかな湧き水であっても、時間をかけ、まわりを巻き込むことで大河へと変わっていきます。
自分の思ったように世の中はうまくいきません。大小の障壁が無数に現れ、連続する妨げに衝突することも数限りなく出てきます。もちろん自分の外部だけではなく内部から足を引っ張られることもあります。多くの人はそこで衝突エネルギーを使ってしまいます。しかし、水の如く柔軟に流れることでエネルギーの無駄遣いを回避することができます。
愚直に、無心に、柔軟に、変幻自在に、エネルギーの浪費を極力避けて、自分の思い描くベクトルに向かって流れていってください。外部のエネルギーに流され、飲み込まれ、翻弄されていては、自分らしさを確立させることはできません。老子の『上善如水』は、まさにこのことです。
念のために補足しておきます。流れていくということは、「動きを止めない」「休まない」ということです。24時間365日動き続けることはできませんが、自分との約束で決めたことは、達成するまで水の如く続ける覚悟が必要ということです。水の如く続けるとは、立ち止まらないことです。足を踏み出し続けてください。もちろん立ち止まってしまっても自分を責めてはいけません。改善すればいいだけです。

みなさんは情緒についてどれだけ真剣に向き合っていますか? 私が情緒について考え、「そうかっ!」と腑に落ちたのは10代半ばから後半の頃です。数学者の岡潔さんの『数学は情緒です』という言葉がきっかけです。
当時、ある事件が起き、私は日常が不安定となりました。日常が不安定となったことが、理系の大学に進学して某研究に没頭することが夢だった私のドロップアウト人生の始まりとなりました。
集中力が激落ちしました。持続力も低下しました。とくに高等数学や物理、暗記教科が壊滅となりました。原因はいつも脳が疲れている状態だったからです。そして岡潔さんの『数学は情緒です』という言葉と出会い、やっと自分なりに腑に落ちました。
その時に私が導き出した答えは、「情緒が不安定となると、身体の体液が濁ってくる」というものです。情緒不安定になったことで脳のどこかにスイッチが入り、なんらかの不純物質が身体に広がり、身体の体液が濁るというメカニズムです。結果として “ 濁り ” が細胞全体の活性化を阻害し、体内を駆け巡る電子の動きに悪影響を及ぼし、あらゆる機能……その一つとして脳(論理的思考)や脳に関連した機能が低下していくというカラクリです。
荒唐無稽だと笑っていただいてかまいませんが、10代後半から私は情緒というのが身体の細胞の活性化……つまり能力を最大限に引き出すカギとなっていると考えています。根拠はありませんが、情緒不安定の状態はできるだけ避けてください。もし自分の思うようにいかない状況の場合、情緒不安定になっていないか確認してください。そこでのセルフケアの有無が、自分のポテンシャルを左右することになります。

情緒不安定になる原因は、心の動き、心の揺れなどによるものです。つまり動揺することで情緒が乱れ、脳が不安定となり、集中力も持続力も低下し、その結果、ラクな方向に流れていってしまいます。試験前にマンガを見るなど、肝心なときにラクな方向に舵を取る逃避行動は、心の揺れが引き金となり、自分の潜在意識が危険回避に動いているわけです。危険回避と言えば正しい行為にも感じられますが、単なる逃避行動にすぎません。
心の動きや心の揺れを過剰に増幅するのが、一喜一憂することです。
「一喜一憂するな!」と言うと勘違いする人がいます。決して喜んでいはいけないわけでもないし、憂いていけないわけでもありません。人生は思いっきり喜ぶ必要がありますし、もちろん自分の力ではどうしようもない場面も必要です。自分の感情を殺して、氷のように冷たい人間になる必要もありません。
一喜一憂とは、状況が変化する度に心を振り回されてはいけないということです。心が揺れると、情緒不安定を加速させ、冷静な判断を狂わせます。安定したパフォーマンスが発揮できなくなります。手が止まったり、反対にオーバーワークしてしまう可能性もあります。
大事なことですので繰り返しますが、喜んでもいいし悲しんでもいいのです。しかし、その心の揺れにどっぷりと浸ってはいけません。自分を俯瞰して眺め、目先のことを重要視せず、もっと大きな人生のテーマという視点から「現在」を眺める心の余裕を持つことが、一喜一憂しないコツです。
もっと具体的なことを言えば、「人生など51勝49敗くらいでいい」という感覚を持つといいかもしれません。「勝ったらラッキー! 負けたらドンマイ!」程度でいいのです。勝ち続ける人もいるでしょうし、負け続ける人もいるでしょう。しかし、そんなものは長い人生の中でのヒトコマにすぎません。
人生で優先させることは、心を揺らすことではなく、行動することです。理想は、行動して自分ではなく他者の心を揺らすことを楽しむ境地かもしれません。

悩んでいるのは時間の無駄。人生はそんなに長くはありません。ヘタな考えは休むに似たりどころか、後退にしかならないのです。悩む暇があるなら、行動して砕けるだけです。ひたすら手を動かし、一歩を踏み出し、自分を磨いていくしかありません。
行動にも種類があります。ラクなことは排除した方がいいでしょう。個人差はありますが、いきなりハードルを上げるのではなく、少しだけ苦しい負荷を自分に課すのがコツです。少しだけ苦しみ、やり遂げ、そこから得られる喜びや楽しみを求めていくのです。この快感を知ってしまえばしめたものです。
ラクなことと、楽しいとことは別物です。ラクに流れるのはキケンです。ラクなことはボーッとしていることと同じです。脳も身体も磨かれません。
ちなみに「磨く」とは、家の中で麻を使って石をこすっている様子を表現した言葉です。ひとつの物事に愚直に取り組み続ける姿勢を意味しています。
宮本武蔵『五輪書』の真髄は、「千里の道を一歩また一歩と進んでいくのである。千日の稽古を『鍛』とし、万日の稽古を『練』とする」という言葉にあります。宮本武蔵の「鍛錬」は自分によった考え方ですが、「鍛錬」の方法も多種多様です。自分ひとりによる「修練」、そして他者との関係性を大切にした「切磋琢磨」など、磨き方にも工夫を凝らして自分を磨き上げていきたいものです。

行動は大切ですが、ただ行動するだけでは意味がありません。ヘタすれば「鍛錬」も「修練」も逆効果にもなりかねません。そうならないためにも竹の節のように一定のタイミングで試行錯誤を繰り返し、常に自分を省みて、改善していくことが必要です。
試行錯誤のキーポイントとなるのが、「脳」です。大切なのは「脳」のパフォーマンスを最高レベルに押し上げて思考する姿勢です。では「脳」のパフォーマンスを向上させるためには何をすればいいのでしょうか。……これがわかればいいのですが、どうやら「脳」は個体別に癖?のようなものがあるために、「この方法がベストだ!」と言い切れない側面があると私は考えています。
では、どうすればいいのか?
こういうときは逆の発想から最適解を導けばいいのです。つまり「脳」を破壊する行為をやらなければいいのです。少なくとも「脳」のパフォーマンスを低下させなければなんとかなります。
「脳」を破壊する行為は、2つあります。
ひとつは「ネガティブな意識を持たないこと・ネガティブな言葉を発しないこと」ということです。ネガティブなことは一瞬たりとも考えてはいけません。「脳」は考えたことを実現させる癖がありますのでご法度です。
もうひとつは「インプット過多を避けること」です。過度の情報は脳をショートさせます。もちろん個人差はありますが、情報過多になってしまうと、脳が情報を整理することができなくなります。まして現在は情報社会です。ネットに溢れている情報を見ているだけで「脳」は疲れて壊れてきます。もしも情報を大量に入れたいならば、それ以上にアウトプットする必要があります。もしアウトプットしないのであれば、情報過多の環境に自分を置くのは絶対に避けてください。情報デトックスは「脳」の負担をかなり軽くします。
今日(2023/10/04)はここまで!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
