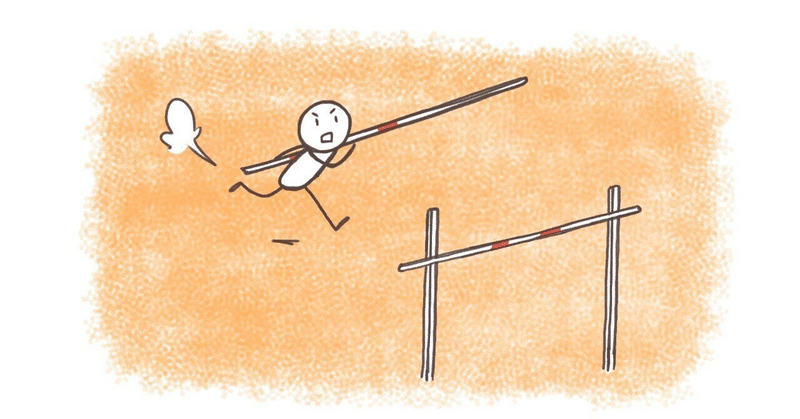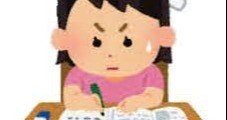
近頃、保育士養成校卒業組と保育士試験合格組を分けて見られるようになってきました。私自身、保育士試験を受けて保育士資格を取得した身なので、複雑な気持ちです。そんな国試組保育士さんの…
- 運営しているクリエイター
#子育て

再生
【子ども主体の保育への道】講義3:人間関係の築き方と継続の秘訣 動画版
見るだけで保育現場の人間関係がわかる動画です。この動画は、保育士にとって重要なテーマの人間関係をとりあげています。保育現場における人間関係の構築や維持が、子どもたちにとってどれほど大切かについて考えました。保育士同士や保護者とのコミュニケーションを通じて、子どもたちの成長や安全を支えるためには、信頼関係の構築が欠かせません。また、問題解決においては、相手の立場や考え方を尊重し合い、協力して解決策を見つける姿勢が重要であることが強調されました。最終的には、子どもたちのために一つになり、全力で保育に取り組むことが肝要であり、それを実現するためには保育士同士の協力や継続的な努力が欠かせないことが示唆されました。
講義10 講義9までを振り返り、どんな保育士になりたいか?それはなぜか? あなたが働きたい子どもの施設の仕事内容や魅力についてなど
講義10 講義9までを振り返り、どんな保育士になりたいか?それはなぜか? あなたが働きたい子どもの施設の仕事内容や魅力についてなど 講義1では現時点でのあなたがなろうとしている保育士像についてお話をいたしました。最後の講義10では、これまで講義を受けて頂き、あなたの理想の保育士像が変化したのか、全く変わらなかったのか、またそれはなぜなのかを一緒に考えたいと思います。 そして、国家試験で保育士になられた方も、働きたい子どもの施設は保育所だけじゃなく、それ以外の施設もあると思い