
ヒーローのヒーロー
初めて、ヒーローになりたいと思った。
小学1年生の時。
ピンチの時にかけつけてカッコよく敵をやっつける、漫画に出てくるような正義のヒーロー。
強いだけじゃない。優しくて、前向きで、一瞬で周りの空気を明るくしてしまうような人。
その存在を思い出すだけで勇気が湧いてくるような、太陽みたいな人。
男性的なイメージが強いけれど、そんなの関係ない。
女だって、ヒーローになりたい。
私が本気でそう思うようになったのは、彼女との出会いがきっかけだった。
いつだって、君のヒーローでいたいと思ったんだ。
**
「結婚式の余興で、新郎新婦をよく知る人にインタビューしようという企画があるんですが、ご協力いただけませんか?」
4年前の冬、地元の親友の結婚式1ヶ月前のことだった。
余興の司会は、彼女の大学時代の友人だという。結婚式で、親友にまつわるいくつかの質問に答えて欲しいという内容だった。
「もちろん協力します」
私は、即答した。けれど、不安だった。
自分の気持ちを上手く伝える自信がなかったからだ。
彼女と出会ったのは、小学1年生の春。1年5組。
ぶかぶかな黄色い帽子を被り、胸元に桜色の名札をさげていた、あの頃。
第一印象は、ふわっとした笑顔が外国のお人形みたいにかわいくて心優しい子、だった。私の出席番号は、クラスで一番後ろ。彼女は、前から1番目か2番目くらい。教室の端から端まで離れていたはずなのに、私たちはすぐに仲良くなった。
休み時間は決まって一緒に外で遊んだ。ふたりで少し低い雲梯の上に寝そべったり、ボール遊びをしたり。雨の日は教室でお気に入りのシールやビーズを交換したり。もちろんクラスメイトと一緒にいる時間も多かったけれど、2人でいる時間がいちばん多かった。
春、夏、秋、冬。季節が進む毎に少しずつ少しずつ、一緒にいる時間が増えていった。
ある日の放課後、私は先生に呼び出され、こんな話をされた。
「これから6年生になるまで、りりちゃんはAちゃんと一緒のクラスになるかもしれない。仲良くしてくれると嬉しいな」
クラス替えで離れることがないなんて、最高だ!
私は、ただ嬉しかった。いつも一緒にいられるし、一緒に遊べるんだから。
彼女は、生まれつき、耳が聞こえない。
先生は、サポートしてほしいというつもりで私に話をしたのだろうけれど、当時の私には、なぜ先生がそんな風に頼むのかよくわからなかった。彼女を助けているという意識はなかったからだ。むしろ、私が教室に忘れ物をすると「また忘れてるよ!もう!」と追いかけて渡してくれるし、「エプロンはこうやって結ぶんだよ」と、絡まった紐を結んでくれる。真面目な学級委員のように見えて実は生粋のお間抜けな私が、しっかり者の彼女に助けてもらうことは、本当に多かったのだ。
そのお返しになるかはわからないけれど、彼女には「先生の話や授業でわからないことがあれば何でも言って欲しい」と伝えていた。休み時間でも放課後でもいい。それは私にとって何の苦労でもなく、ただ2人で過ごす楽しい時間だった。
彼女が頼ってくれるのは、すごく嬉しかった。頼られることで私は少しずつ自信を持てるようになり、もっともっと彼女のために頑張りたいと思った。いつどんな風に頼られても、しっかり答えられる自分でいたかった。
彼女のヒーローになりたいと思った。
放課後は、一緒に習い事にも通った。
年に1度、日本武道館で行われる大きな書道の大会。限られた時間の中で、道具の準備から席書、作品の選定、片付けまで1人で行わなければならない。配布された半切用紙を広げて道具を準備し、心を落ち着ける。
「ドーン!」と心臓に響く太鼓の音。
ピリッとした緊張の中、1枚目の半紙に墨汁をこぼしてしまったことがある。どうしよう。私は動揺したけれど、隣にいた彼女が「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と口を動かして、微笑みながらティッシュを置いてくれた。それを見てなんだか落ち着いて、堂々と書き上げた2枚目は、これまでにないくらい良い出来だった。
「ドーン!ドーン!」
2回の太鼓が、終了の合図。書き上げた作品を高々と掲げ観客席に披露しながら、どうだ世界よ、私たちの作品を見てくれ!となぜか誇らしく思っていた。
夏には毎年、家族で一緒に海水浴に行った。先日、2人で砂だらけになって遊んでいる写真を発掘したときはつい笑ってしまったけれど。
誰もいない田舎道をふたりで歩いて、宿から少し離れたゲームセンターに行った。よく飽きないなと思うくらい撮った何枚ものプリクラ。人生で初めて行ったお寿司屋さん。宿の人に教えてもらった夜のマルガニ釣り。翌日の朝食でお味噌汁に入っていた彼らを見てちょっぴり申し訳ない気持ちになったけれど、すごくおいしかった。
彼女と過ごす時間は、どこを切り取っても、私にとってかけがえのない幸せな時間だった。
先生の予告通り、私たちは6年間同じクラスで過ごすことができた。6年も一緒にいれば、顔色を見るだけで感情がわかるくらいになる。幼馴染や親友という言葉では、なんだか足りない。家族同然の、大切な存在。それは私にとってだけではなく、私の父や母、兄にとっても同じだった。
私は地元の中学に進学し、彼女は少し離れたろう学校に進むことになった。
彼女は将来のために手話を習わないといけない。
わかってはいるけれど、どうしようもなく寂しかった。
春、夏、秋、冬。
私たちが一緒にいられる時間は、少しずつ、少しずつ、減っていった。
お祭りや遊びで年に数回は会えるけれど、前みたいに学校や習い事で毎日会えることは、もうない。
彼女は中学生になってから、手話を完璧にマスターした。身振り手振りや口の形でしか会話ができない私なんかより、きっと手話を使える人との方が話もはずむんだろうな。そんな風に考えることもあった。
私は私の世界で、中学、高校、大学、バイト先でたくさんの人に出会った。
勉強もした。甘酸っぱい恋もした。悔しい思いもたくさんした。彼女と共有できない出来事が、少しずつ、積み重なっていく。
彼女は彼女の世界で、中学、高校、大学、バイト先でたくさんの人と出会ったはずだ。当たり前だけれど、昔みたいに私を頼ってくれることはなくなった。まやかしのヒーローなんて、きっともういらない。
ずっとずっと大切で仕方なくて、かけがえのない存在なのに、会うとなんだか照れくさくて、昔みたいに素直な言葉で伝えられない日々が続いていたと思う。
私が彼女と一緒にいられたのは、初めのたった6年間だけ。
だからこそ、彼女の結婚式でどんな言葉を伝えて良いか、少し迷ってしまったのだ。
**
司会を担当するという彼女の大学の友人に「私以外の方には、どんなインタビューをする予定ですか?」と聞いてみた。
するとどうやら、固い友情スピーチではなくユーモアのあるものにしたいのだという。例えば、新郎新婦の共通の知り合いなら「好き同士なのになかなか付き合わなくてじれったかった」とか、その人ならではのエピソードも交えたいという。
それを聞いて、さらに悩んでしまった。
結婚式に参列される方の中で私が知っているのは、彼女の家族と親戚だけだ。中学、高校、大学の友人たちが集まる中、小学生の昔話なんて語っても良いのだろうか。(本業の悪い癖か、せっかくマイクを持つのだから参列者たちを楽しませないと、という謎の意気込みがあった)
でも、ふと、思った。
そもそもインタビュー相手に私を指定してくれたのには、意味があるんじゃないのか。
そこで、もう1つ質問をしてみた。
「今回のインタビューで、逆に私に聞いてみたい彼女のことはありますか?」
すると、こんな返事がきた。
「個人的には、障がいがあるなし関係なく手話ができるできない関係なく、長い関係を築いているのがすごいなあと思っていて、そのコツを知りたいです」
そうか。昔の彼女を知っている私だからこそ、話して欲しいと思ってくれているんだ。私は、彼女に対する想いを素直に話せば良いんだ。
それから何度かメールで打ち合わせを重ね、インタビュー内容が決まった。
①小さい頃からの知り合いとのことですが、どんな風に一緒に過ごしましたか?
②今、彼女に伝えたいことはありますか?
私からの希望もあり、②の質問を追加してもらった。
「りりさんは声でお話されるとお伺いしていますので、通訳の方には手話で通訳するようお願いしています。当日は宜しくお願いします」
結婚式では、手話ができない私の方が珍しいのだ。なるべくわかりやすく、はっきりとした文章を作ろう。通勤時間や帰宅後に練習もして、カンペなしですらすら話せるくらい完璧になった。
あとは、本番を迎えるだけだ。
今の気持ちが彼女にしっかり届くように、堂々と答えよう。
**
結婚式当日。
挙式は、あたたかな木々の中ひっそりと佇むチャペルの中で行われた。
トワイライトウエディング。
まるで、昔読んだ物語の世界に入り込んだみたいだった。
彼女はとても美しかった。
驚いたのは、私たちの方を向いてから、彼女がずっと涙ぐんでいたこと。
たくさんの人たちに見守られながら2人で堂々と歩く姿は、凜として、本当にかっこよかった。
新郎新婦共通の知り合いが多いこともあり、披露宴は和気あいあいとアットホームな雰囲気の中進んでいく。同じテーブルには彼女の大学の友人が多くいらっしゃり、そこには聞こえない方も、聞こえる方もいた。
ファーストバイトでは、彼女が巨大なバット型のスプーンで新郎にケーキを食べさせている姿を見て大声で笑ってしまったし、恩師の方のスピーチで嬉しそうに笑う2人の姿を見て、あたたかな気持ちになった。
メイン料理をいただき、デザートが出される前くらいのタイミングだったと思う。
余興が始まった。
新郎新婦を知る友人や先生たちへ、オリジナリティあふれるインタビューが進んでいく。
「学生時代から仲の良い2人をずっと近くで見守ってきました」
「アメリカに行く夢を叶えたときは本当にびっくりしたよ」
友人や恩師の方のインタビューから、私が知らない時代の彼女が少しずつ紐解かれていくようで、不思議な気持ちになる。時折会場から笑いが起こるエピソードもあった。
その後十分くらい経過しただろうか、ついに私の番が回ってきた。なんと、トリだった。
ナプキンを席に置き、背筋を伸ばす。
ふう、と少し息を吐いてから、マイクの前に立った。
横には手話通訳の方が立ってくれている。
「小さい頃からの知り合いとのことですが、どんな風に一緒に過ごしましたか?」
1つ目の質問には、ゆっくり落ち着いて、予定通りうまく答えられた。
彼女も、うんうんと頷きながら、優しい笑顔で見守ってくれている。
「今、彼女に伝えたいことはありますか?」
私は、自分で決めた2つ目のこの質問に、答えることが、できなかった。
その場で、泣いてしまったのだ。
大勢の前で、信じられないくらいに。
生まれて初めてのことだった。どうコントロールしていいか、わからなかった。
挙式・披露宴を通して、彼女が中学生から今大人になるまで、こんなにもたくさんの人に出会ってきたこと。あたたかく優しい雰囲気の中で、結婚式を迎えられていること。そして今、ここに私が友人の1人として立てていること。
全てが言葉にならない感情になって、こみ上げてきた。
私があまりにも泣くものだから、遠くから「がんばれー!」なんて声も聞こえてくる。申し訳なくて司会の方を見ると、なんと、つられて泣いてくれている。ああ、私がこんなに泣くなんて、だめじゃないか。少しずつ我に返るけれど、どうにも言葉にするのが難しく、台本になかった言葉で話し始めてしまった。
「私は、あなたの笑い声が、笑顔が、昔から大好きです。本当に……心から、あなたの幸せを、願っています。きっとここにいる誰よりも、あなたのことを思っています。絶対に、絶対に幸せになるんだよ」
多分、こんな言葉を絞り出したと思う。
高砂に座る親友の顔をちらりと見ると、私につられて涙ぐんでいた。
ごめんね、しっかりスピーチができなくて。ここぞというときに、ヒーローみたいにかっこよく決められなくて。
こんな情けない親友で、ごめん。
そう思いながら軽く礼をして、司会の方にマイクを返し、自分の席に戻った。
**
披露宴が終わったあと、彼女にメールを送った。
素敵な式だったよ。お疲れさま。それから、あんなに泣いてしまってごめん、と。
すると、「結婚式なんだから泣いてもいいんだよ」という優しい慰めと共に、彼女から想いもよらないメッセージが届いた。
「りりにインタビューをお願いして、良かった。私が声で伝えられない分、どんな気持ちだったのか気になったのがきっかけで、今回インタビューを頼んだんだ。でも、気持ちを聞けて本当に良かった。」
彼女は私に「声で伝えられない」と思っていたことを、そこで初めて知ったのだ。
だって私は、彼女に「手話で伝えられない」ことにもどかしさを感じていたのだから。
結局は、自分の気持ちをどれだけ目の前の相手に伝えたいか。
ただ、それだけで良かったのだ。
手話ができるできないなんてことに拘らず、伝えたいことを伝えれば良かったんだ。子どもだった、あの頃と同じように。
小学校の6年間同じクラスで、楽しいことも、時には悲しいことも一緒に経験しながら育ってきました。あなたは、障がいがあることなんて忘れさせるような子どもでした。何事にも前向きに挑戦して、できないことがあると私の隣で、一生懸命できるまで頑張っていたことを、今でも覚えています。私は、あなたと一緒にいられることに、心から感謝していました。
あなたが笑うと本当に嬉しくて、いつも私が幸せをもらっています。これから守るべき人が増えて、頑張ることもたくさんあると思います。でも、どんなときも夢を忘れず色々なことに挑戦する、昔から変わらないあなたのままでいて欲しいです。あなたの幸せを、誰よりも祈っています。
用意していた言葉は、上手く伝わらなかったかもしれないけれど、心の奥底にずっとある、あなたを大切に想っているという気持ちだけは。
声でも言葉でもなく、涙で伝わることもあるんだってことを、今回初めて知ったのだ。
**
彼女が大学に行くことに決めたって?
きっと頑張って勉強しているだろうから、私も負けてられない。勉強しなきゃ!
手話サークルで大勢の人の前で講師をやったんだって。
すごく堂々と発表していて、凄いな。私も来週のスピーチ練習、しっかり頑張らなきゃ!
1人で海外旅行に行ったの?しかも結構危ない国じゃない。
私もこうしちゃいられない。怖がってばかりいないで、諦めかけてた夢と向き合ってチャレンジしてみよう。
思い返せば、結婚式で流した涙には、こんな想い出も詰まっていたように思う。その1粒1粒が、まるで私がここまで生き抜くための力になっていたことを示すかのように。
彼女が、彼女の存在こそが、私にとって幼い頃からの頑張る原動力そのものだった。
彼女は去年、母親になった。
気がつけば、私よりはるかに強い、大人の女性になっている。
妻になっても、母親になっても、例えこれからどんなところに住むことになろうとも、彼女は私にとって、大切な家族の1人だ。
例え少し離れていても、彼女が頑張っていると思うと、私も頑張ろうとむくむく勇気がわいてくる。
**
初めて、ヒーローになりたいと思った。
小学1年生の時。
ピンチの時にかけつけてカッコよく敵をやっつける、漫画に出てくるような正義のヒーロー。
強いだけじゃない。優しくて、前向きで、一瞬で周りの空気を明るくしてしまうような人。
その存在を思い出すだけで勇気が湧いてくるような、太陽みたいな人。
そうか。
私は、彼女みたいな人になりたかったんだ。
それでも、欲張りな私は、彼女にとっても自分が頑張るきっかけのエンジンのような存在でありたいと思う。
初めて出会ったあの日から、25年。
すっかり大人になってしまったけれど、たまには頼ってくれるとうれしいな。
ちょっぴり情けなくて頼りない、へなちょこヒーローかもしれないけれど。
どんなに強い敵が来たって、必殺技みたいな攻撃を何度仕掛けられたって、あなたを全力で守る準備だけは、いつだって万全にしておくからさ。
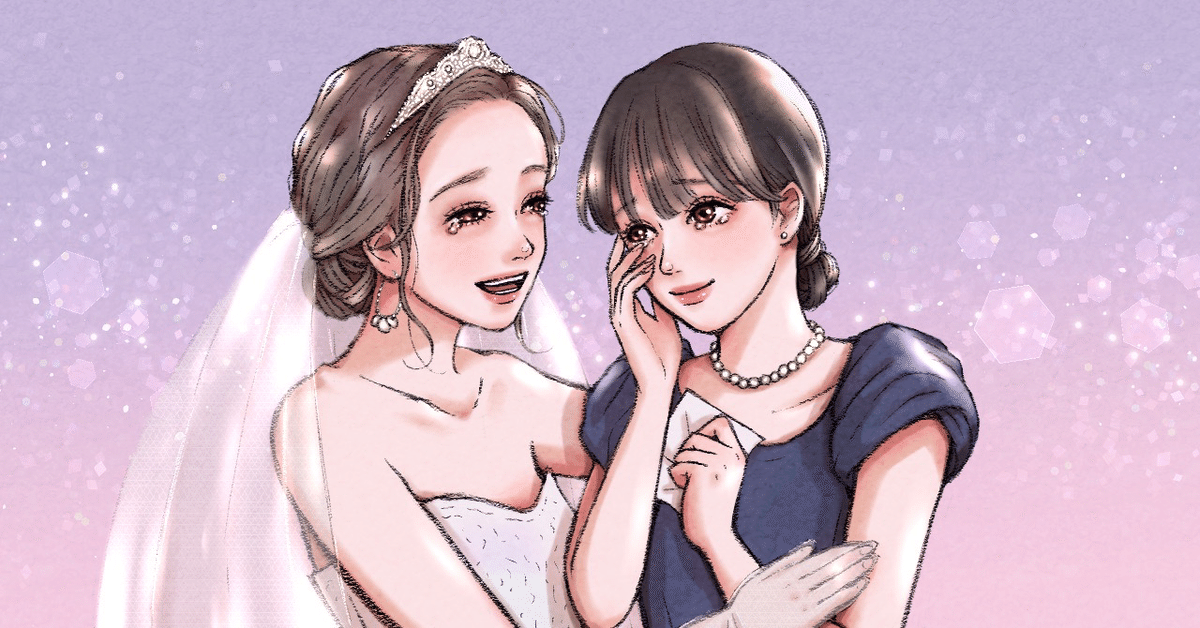
illustration by chiharu
ここまで読んでいただき、ありがとうございます☺︎ いただいたサポートは、今夜のちょっと贅沢なスイーツとビール、そして今後の活動費として大切に使わせていただきます…⭐︎
