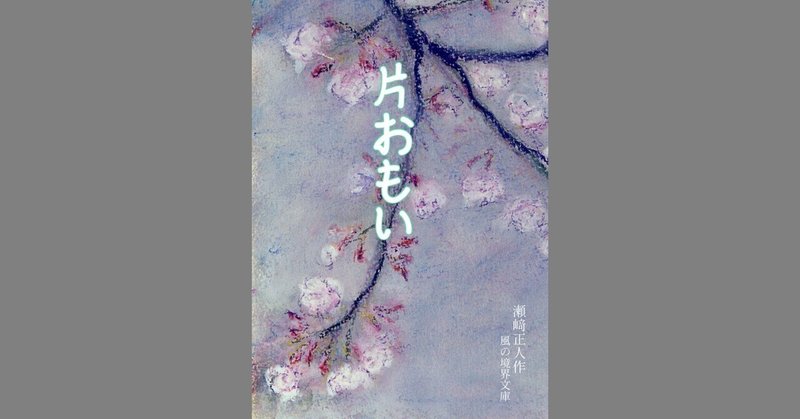
<連載小説>片おもい -7
(エピソード-7) 生い立ち -1
杉とわたしは冬休みのあいだじゅう手紙を出しあった。
返事をもらっては返事をかえして、それをくりかえした。
彼女の家には電話がなく、こちらからの連絡ができなかったので、一日中、彼女からの電話をまった。
ある日、じっとしておれずに、彼女の家の前まで行って昼過ぎから夕方まで待った。
しかし、彼女はいつも留守にしているようで、ときどきゆっくりと通りすぎる磨りガラスの向こうの影は、お母さんのようだった。
「家にはこんでね。キタナカ家けん、はずかしか。」
そんなこと気にするほうがおかしい、と言ったが、彼女はひどく嫌った。
どんよりとくもった雪のふりそうなその日――、
「雪の降らんかね~、」と言いながら、一日中、港沿いをふたりであるいた。
むかし、軍港だった港には海上自衛隊やアメリカ軍の基地が併設されていて、
レンガづくりの建物の横を巨木の立ちならんだ広い道路に沿って歩いてゆくと、
刈りそろえられた芝生の青々と広がるモダンな建物がフェンス越しに見えてきて、
白い肌の外国人やアフリカ系の黒い肌の人たちとすれちがえば、
どこかちがう国に迷いこんでしまったのではないか?
……と、錯覚できた。
横をあるく杉は、ダッフルコートに身をつつんで、雑誌の中のモデルさんのようだった。
「あのさー、すぎ。」
「エッ、」
「手ばにぎってもよか?」
「モー、そがんこと女の子にきくもんじゃなかよっ、」
「あっ、そうや……、ごめんごめん、」と言って握った。
女性の掌。
小学生の集団登校のときに、幼い新入生の手をとってあげた、それとも、
運動会のフォークダンスでにぎった女子の手ともちがう……、
はじめてしったやわらかな感触。
それは、『女性』そのものであるかのように感じられた。
「杉の掌、いがいと小そうしてやわらかかね。
バレーばしょっけん、もっとゴツゴツしとっかねって、思うとった。」
「つむらくんの掌……、おおきかね」
わたしは、女子の手をどう握ってよいものかわからなかったので、
なにかの本で見た、手と手で気持ちをつたえようと、力を入れたり弱めたりと念をこめてみた。
彼女といると、なにもかもが忘れられた。
と同時に、一種、危険な希望さえ抱いた。
『彼女といっしょに暮らしたい。
彼女のためなら、どんなことだってできる……気がする。
命すら惜しくないようにさえ思える。
いや、むしろ、彼女のために死ねるものなら――』
……小雨がふりだした。
しかし、ふたり傘もささず、ベンチに腰かけてうごく街をみていた。
理不尽な世の中のしがらみのなかで、夢も希望も手放して、人生をあきらめたかのように流されて見える人たち。
おなじ仲間を蹴落とすために、どんな仮面も抵抗なく、いやむしろたのしむかのようにつけて……、
にんげんとは、実にこうゆうものだ。
と、ひらきなおって見せているような世の中。
そんな底の知れた世界にあって、彼女こそは……穢れなき花であり、
彼女を愛するこころこそは、唯一信じられる確かなものに思えた。
「杉、毎日なんばしよると?」
「まいにち、って……、」
そう言って彼女はわたしを見た。
さぐるような視線だった。
「杉さ、オイには何でんはなしてくれんや。
オイさ、杉のお母さんのこと友だちから聞いたっちゃん。
お父さんのことも……、
オイさ、おまえば好いとって言うたとは、
おまえの力になりたかって思うとるけんさ。
そりゃー、
なんの力にもなれんかもしれん。
ばってん……、
ばってん、杉の友だちに、そがんはなしのできるとのおるや。」
彼女はしばらくだまっていたが、
「ンー、そがんこと、はなされんたい。
私の問題やもん――。
津村くんも、そがんこと心配せんで。
私よりもっと大変か人のいっぱいおらすとよ。
そいに、私は健康だし、
『若いうちの苦労は買ってでもしなさい』って言うたい。
……あはは、おかしかね、こがんふうに言うたらよっぽど私が苦労ばしょうるごとあるたい。
苦労って思うたことなんか、なかよ。
それよっか、自分のことはしっかりしょうると?」
彼女はそう言って、わたしの肩を軽くたたいた。
わたしは、どんよりとした重たい空を見あげた。
「オイ、はたらきにでろうかねって、思うとる。」
「エーッ、高校は――」
「いかん! いったっちゃいっしょのごとあるもん。
そいよっか、一年でも早よう社会にでて働きたか。」
「なんばすると?」
「長距離トラックの運ちゃん。
楽しかって思わん?
日本全国ば股にかけて仕事ばさるっつぉ。
オイさ、車好いとっし、
そいに、日本中ばまわってさ、いろんなことば見て、勉強して、おおきか人間に、こころのひろか人間になりたかっちゃん。
……ほんとうは、スポーツのほうで働きたかったとばってん。
小学生のときは、オリンピックの選手になりたかっていう夢もあったとばってん、
……そいはまず無理やし、そしたら体育の先生かなんかやろう。
そいにはまず大学までいかんばたい。大学なんかかんがえられもせんもん。」
「なんば言いよると津村くん。そがんと、やってみらんばわからんたい。」
「わかっとる、わかっとる、わかっとるとって――。
自分でもさぁ、
ほんとうは、なんばしたかとか、わからんちゃん。
なんばしたっちゃさー、結局、結果の見えとるごとあっちゃん。
未来に、なんの希望も見えんちゃんね。」
「むずかしかはなしは解らんばってん……」
「ごめん、ごめん、最近、オイびょうきさ、」
「あんまい、ふかく考えんほうが良かよ。私なんかバカけん、
『今日もいっしょうけんめいがんばろう!』って、そがんことしか考えんもん。
そのほうが、気の楽かっちゃなか、」
このときの彼女のことばは、わたしの吐いたことばや考えなどおよびもつかない、深い真理をついていた。
「杉、もう、学校決めたと?」
「ウン。決めたよ」
彼女の口からでたこの歯切れのよいことばに、わたしは一瞬グサリと、胸を突かれたようにかんじた。
それは、そのことばが、
わたしの存在をまったく無視したところから出てきたように聴こえたからだった。
「どこ、ふつうこう?」
「ウン、普通高ばってん、屋島さ。」
わたしは彼女を見た。
屋島とは、当時、わたしたちのすむ街から四〇キロ以上も離れた港から、さらに船で渡らなければ行けない島だった。
「なんで、なんで……、なんもはなしてくれんやったとや、」
彼女は、答えなかった。
しばらく、沈黙がつづいた。
「ハー……、」
わたしが大きくため息を吐いたとき、
「ごめんね、津村くん。
ばってん、ほかの人にはぜったいはなさん、て、やくそくして――、ね。」
そう言って、彼女は、はなしてくれたのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
