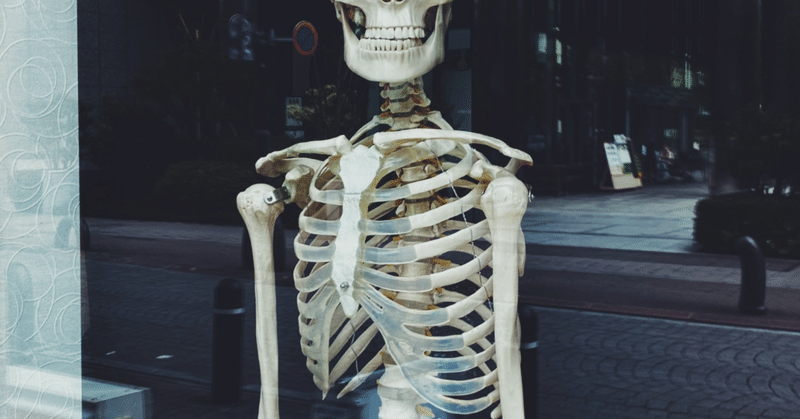
肋骨の変/合わせ鏡の厄 1
※作中に自殺に関する描写が含まれています。閲覧にはご注意ください
基になった逆噴射小説大賞応募作
先取りしたクリスマスパーティーの余興に、坂上李一はこんな話をした。彼には幼いころから定期的に見る夢があり、そこに同じ年頃の子どもが出てくるそうな。見覚えのない顔の、名前も知らない子が。けれども彼にとっては、兄姉だが弟妹だかの間柄なのだそうだ。そういう誰かと彼は一緒にいる。綿を敷きつめたような白い部屋で。クローセットより広く、ベッドよりも狭い場所で。
その子は彼に、おまえと一緒に生まれるのは嫌だと言う。おまえの顔も見たくないし、こんなところにもいたくない。最後にさよならと言い締めて、子どもは李一から瞬く間に遠ざかっていく。待てと声を上げる隙もない、足の早さで。そして、いつも寂しい気持ちで目が覚める。
これはだいぶ長じてから、わかったのですが――。水を打ったような静けさのなかで、彼は続ける。
「どうやら僕は他人様より肋骨が二本、少ないらしいんです。本来なら二十四本あるはずのところを、左右で一本ずつ失っている。ときどき……無くなった骨のことを思うと、一緒に夢のなかの子の顔も浮かぶのです。そして、こうも考える。もしかしたら肋骨はもともと存在しなかったのではなく、本当は過去のどこかの地点で逃げ出したんじゃないかって。何かの拍子に首輪が外れた犬みたいに。馬鹿げた夢物語ですけれど。でも僕の一部が僕自身であるのを拒絶するなんて、とんでもない間違いだとは思いませんか」
塚本小路はもちろん、その話を聴かなかった。宴会場にいなかったのもあるが、時期も時間も悪い。季節は九月の半ば。ちょうど、ぶどうの収穫期にあたる。小路も適当な作業員として、家業に駆り出されたはずだ。だからその晩は疲労困憊で、深く寝入っていたに違いない。夜陰もいよいよ深まる段ならなおさらで、きっと夢すら見なかっただろう。だから、このときの彼らのあいだには通い合う道筋はない。
齢はともに十六。二人ともまだ、お互いのことを知らなかった。
§
祖母の話をしましょう。私は長野県の南信に生まれました。実家はぶどう農家で、小さいですがワイナリーも兼業しています。二足の草鞋と鳴れば、やらなければならないことは多い。そういうときに面倒を見てくれたのが彼女でした。
私が物心ついたころには、すでに彼女は農作業には従事していませんでした。もう肉体作業に耐えられないくらいに、身体や神経が弱っていたのです。代わりにぶどうの搾りかすを使い、染色を行っていました。そうして出来上がったハンカチやスカーフを観光客相手に売るのです。私と弟――二人の孫の面倒を見るのは、そのあいまです。
病を得て老年期に至っても、かつての美貌を残した人でした。病気や加齢が与えた脆弱さに隠れていましたが、若かりし頃にはきっと美青年じみた風貌だったのが察せられました。
聞くところによれば、彼女は少女歌劇の男役だったそうです。少女のころに養成学校に入り、修練を積み舞台に上がったと聞きます。それがどうして一地方の農婦に落ち着いたのか、今となっては知りようがありません。
そういう過去からか、祖母は〝美〟に対し独特の信念を持っていました。この世に在るあらゆる美しさは人の手に余るものだから、敬意は持てども無暗に接近すべきではないと。もちろん見目麗しいモノは力を与えてくれもするが、その作用に無防備であれば必ず災いがあるとも。そうして最後に、詩の一節を必ず口ずさんだものでした。――憂然として明鏡は、まッたゞなかより割れてけり。天罰我が身にくだりぬと、シャロットの姫は叫びけり。――シャロットの姫君です。
こういうことがありました。私が化粧を初めて習ったのは七つの時分で、地狂言に子役として出たときでした。釈迦に説法になって恐縮ですが、地狂言とは農村でも催される素人歌舞伎のことです。江戸時代に都市部へ行商に出ていた農民が観劇した演目を地元に持ち帰り……あるいはドサ廻りの役者から教えを受けたのが始まりだそうですが、私の故郷はこういった古い行事の保存に熱心な土地柄ゆえ、毎年住民から志願者を集めては公演を行うのです。今日日劇場でかかっているような野郎歌舞伎のほかも、女歌舞伎や子ども歌舞伎もやります。地元民のしがらみで私も祖母も、否応となく駆り出されました。祖母は裏方で、私は禿という役柄で。
舞台化粧なので顔や首筋にべったりと白塗りをして、赤く目張りをしました。このとき真っ赤な着物を羽織らせ、黒い帯を締めてくれながら祖母はこう言ったものでした。
「奇麗、美しいってのは良いことばかりじゃない。今度は不細工になる方法を教えてあげよう。そうしたらどんな顔がいいのか自分で選べるようになるし、災難から遠ざけられる」
災難、災い。彼女はよく口にしました。しかし、それが一体どのようなものなのかは教えてはくれませんでした。自分の気持ちや考えたことを、上手く言い表せなかったのかもしれません。とはいえ私は彼女を慕っていたし、この説をありがたく傾聴していました。
――……水を。……ありがとう。
§
十二月。初冬は塚本万里にとって巡礼の季節だ。だから彼は新幹線を乗り継いで、長野の南信地方から京都の嵯峨野に向かう。時期はクリスマスイブ、装いは登山服と決まっている。
終点の清滝バス停から横に反れて、踏み入れた山道をひたすら川沿いに歩いていく。重苦しいほどに濃密になり、深まる森陰と山陰の下。発電所の取水堰を通り過ぎ、保津峡方面に進むさなか。不意に現れる河原が、万里の目的地だ。
天候は文句のつけようのない快晴で、釣りにはうってつけの日和だろう。だが山深い河川敷には万里の他にはいない。梢の葉擦れや川のせせらぎだけが、始終あたりに響いている。物寂しいぶん、明媚な風景だった。もし本当に賽の河原なる場所があるのなら、このようなところであってほしいと願うくらいに。
万里は石砂利をかき集める。そうしてバックパックから、スパウトパウチを取り出す。液体に満ちた薄手のものをを四袋。それらを祭壇に並べて置く。中身はすべてワインだ。赤、白、ロゼ。そしてオレンジ。どれもこれも今年に醸造された新酒――いわゆるヌーヴォーになる。すべて塚本ワイナリーが精魂込めて製造したものだ。彼がフランスに留学していた期間を除けば、ほぼ毎年、小路の死に場所にこれらを供えに来ていた。
四つの異なる酒の入ったプラスチックカップを、それぞれのパウチの前に置く。色彩や濃淡が異なる液体が、陽光を受けて鈍く光を放つ。ぶどう色に淡いライムイエロー、白っぽいローズミストと琥珀色がかったオレンジ。それらがちらちらと揺らめきながら重なり、混じり合う光景に万里はひたすら向き合う。そして彼はやがて呟く。
身の上にまがつひあらんと、若し曾て手をとゞめば、かなたカメロットを見やらんとて……――。幼いころに祖母から教えられた詩だ。耳にタコができるほど聞かされたから、きっと小路にもわかるはずだ。もし声が届くのなら。ひっそりとした声遣いのまま彼は続ける。
――……突然織り物はひるがへり、糸は八散してたゞよひぬ。憂然として明鏡は、まッたゞなかより割れてけり。天罰我が身にくだりぬと、シャロットの姫は叫びけり。
天罰。暗誦を止めて、まもなく万里はこの一単語を繰り返す。話に聞いた小路の死にざまが、ありありと脳裡に浮かんだのだ。ほつれ崩れたタペストリー、砕けた鏡。このように壊れた死に方だったというから。
ざり、と石が崩れた音が起こった。振り返ると、少し離れたところで誰かが立っている。顔つきはよくわからない。ただ背丈からして、女性ではないかと万里は思う。
相手は同じように登山の装いをしていた。灰色のビーニーと闇色のアウトドアパンツ、トレッキングシューズ。風景に浮き上がるレインジャケットは、万里の目を刺すほどに鮮烈な紅色だ。生死はともかくとして、これなら遭難してもすぐに発見されるだろう。完璧か否かは容易に判断できないが、入念と評して問題ない服装だった。
女が胸元に何かを携えているのに万里は気づく。一輪の花だ。形状からしておそらく白バラだろうと万里は合点する。また相手の目的にも察しがつく。
小路の自死から三年後。同じ十二月の今日、この河川敷で、葦なんとかという歌舞伎の女形が死んだのだ。スランプを苦にした自殺だったという。おおかたファンが彼を偲んでやって来たというところか。
このように断言できるのは、小路の友達や知り合いは、こんな険阻な場所に訪れないと承知していたからだ。きっと、そういう人たちは長野の墓に参るだろう。あそこには小路がいるばすがないのを、彼ら彼女らは知らないのだ。両親はわかっているだろうが、この事実をつとめて黙殺している。だからこの十三年のあいだ嵯峨野で姉を弔うのは、ずっと弟である彼一人だけだった。
万里は小さく頭を下げると、あちらも軽く会釈を返す。そうしてまっすぐにこちらに歩み寄り、凹凸の激しい露頭を踏み越えてくる。お互いの距離が詰まるにつれ、相手の容姿がより明瞭になっていく。細筆で引いたみたいな細眉と、切り上がった一重の瞼が涼し気な顔立ちをした女性だ。それを認めた途端、驚きの声が万里の喉までせり上がる。その花嫁人形を彷彿とさせる面影に覚えがあった。
おもむろに彼女は立ち止まる。手にしていたのは、やはり白バラだ。そうして万里をまじまじと眺め、ちらりと並べられたパウチを見やった。そして、いささかの沈黙を経て口火を切る。塚本さんの、ご身内の方ですか。
「その塚本某の名が小路なら、そうですが」相手の問いに万里は返す。
「お邪魔して申し訳ありませんでした。お花だけ供えさせてください。すぐに帰りますので」
「お気遣いは無用です。どうぞ時間の許す限り、いてあげてください。親しい人に悼んでもらえたら、きっと姉も喜びます」
姉――。そう相手は呟く。ついでこちらに流した瞳が下を向き、薄っすらと陰った。逸らしたなと万里は直感する。しかし指摘はしない。かわりに、こう続ける。
「昔、塚本の墓にも来てくれたでしょう。姉の四十九日を半月過ぎた、春休みのころです。あなたはブラックフォーマルのワンピースを着て、お花を供えていた」
十六のころ、小路が去って初めての春。三学期の最終日で、中学生として最後の放課後。万里は塚本家の墓に参った。卒業式を間近に控えたせいか、なんとなく寂しい気持ちになっていたのだ。本当なら京都の川辺に行きたかったが、当時の彼には金銭的な余裕も持たなかった。そうして仏花を引っ提げて、目的の番地まで向かうと先客がいた。
墓前に手を合わせているのは妙齢の女の人で、自分よりも少し年上の――小路と同じ年くらいに思われた。人形じみた端整な横顔を俯かせて、肩を震わせる姿は万里の記憶に残っている。小路の友人を電話越しではなく、実際に目の当たりにしたのは初めてだったから。
「すみません」女は言う。
「あなたは泣いていたんだ。今にも叫び出しそうなのを、精一杯に堪えているみたいに。あのときは気圧されて声は掛けなかったけど、でも俺は今でも覚えています。あそこまでに姉を悼んでくれる人がいるんだって、そうしてくれる友達が出来たんだと。そう思ってたんだ」
「やめてください」
「なにか、あるんですか。俺と長居したくない……できない理由が」
二人のあいだに沈黙が降りた。緩やかな風が頬や襟元を吹きつける。囁きじみた葉擦れの音を奏で、水の流れは絶えない。そんな時間がしばらく続いたのちのこと。女の方が先に動く。彼女は白バラを祭壇の前に置き。これはね――。
「これはね、あなたのお姉さんへの花です。彼女に捧げるつもりでこの花を買って、ここまできたんです。今日は。本当ですよ」
「そうでしょう」万里は言う。
「道があるとはいえ、こんな山深い場所だ。おまけに年度末で忙しさも寒さも厳しくなってくる頃合いでもある。俺の知る限り、姉の命日にここを訪れたのはあなたが初めてです」
「ええ。何年も来られなかった。行きたい……行こうと思っても、どうしてもできなかった。彼女がどんな気持ちで真夜中の川辺まで辿り着いたのか、そこがどんな場所なのか知るのが怖かった」
私たちが殺してしまった人なのに。万里にとって、その言葉は当然聞き捨てならなかった。しかし驚愕も激昂もしなかった。もちろん平手打ちどころではない。ただ、腹の中にすっぽりと収まるものだけがある。十三年前――小路が自死したとき、そして墓前でこの女を見かけたときから、薄々気づいていた事実だった。
*
塚本はもともと一地方の、しがないぶどう農家に過ぎなかった。収穫した果実を出荷して、細々と生計を立てるような。それが何を思ったか、六十年代に祖父が酒造業に手を出したのが事の始まり。黎明期には地元民と観光客相手とした小さな商いだったのが、バブル期のワインブームに乗っかり、支持者を獲得。上手い具合に全国展開へ滑り出した。やがて狂乱が去って長期的な不景気に突入した後も、塚本ワイナリーは熱心なファンに支えられて今日まで経営を続けてきた。
そんな塚本家の息子夫婦に長女が生まれたのは、今から三十五年前になる。二人は名づけの案を各々に持っていた。母親は小町で、父親は路子か路世。このあいだをとって小路と名づけられたのが、万里の幸と不幸の始まりだ。
それから七年後に今度は長男が産まれる。両親は姉と揃えてコウジとしようとした。漢字で広い路と書くのだ。その安易なアイデアに小路は断固反対したと聞く。家系図に隣り合って並べられると、漫才師じみていてあんまりだと。自分も弟も。
このことがあったのち長男は、祖父にあやかって万里と名づけられた。祖父が中国生まれで、名前に城がつくからだ。女の子みたいな字面が気にかかったけれど、『小路』『広路』と並べられるよりは、だいぶましだった。
「塚までは万里の道。長生きしそうだね」
弟の名について、小路はよく感想を口にしたものだった。そういった出生の経緯からか、年が離れていて体格差が明らかだったせいか。自分と小路とはなかなか上手くやっていたと思う。というよりもお互いに手を取り合わざるを得なかったと表すべきだろう。
言うまでもなくぶどう栽培とワイン造りの、二足の草鞋を履く生活は忙しない。平時から土づくりや枝の剪定、房づくりや摘粒などしなければならないことが山ほどある。ことにぶどうの収穫期とワインの仕込みが重なる秋口には、よりいっそう大わらわだ。そういうときの両親は猫の手ならぬ、子どもの手まで借りてくる。
大人がこういった具合なので、子どもたちはお互いに助け合わなければ生活できない。祖母に面倒を見てもらっていたけれども、いかんせん彼女は細腕の上に病がちだったので、頼みになるのは自分らしかいない。その祖母がすぐに死んだのも、年に似合わぬ自立心をさらに強めた。
だから万里が物心ついたときには洗濯や調理、ゴミ集めなどの役割分担が二人のあいだでおのずと決まっていた。また長年の経験から構築された連携も見事なものだった。指揮者とコンマス。あるいは木曽義仲と今井兼平。自分たちはそのような切っても切れない関係だと、万里は信じてやまなかった。
今となってみれば幼い自分を何かと気を遣って、小路がいろいろ譲ってくれていたのだとわかる。でも『小路』と考えなしに呼び捨てにしていたのは、とりかえしがつかなかった。(しかし彼にとって小路はただの姉でなく小路なのだ)己の甘えたい放題の振る舞いで、もっとも印象に残っているのは、小路が進学のために実家を出る前の出来事だ。
京都は多くの大学を抱える志の高い街で、その数は国内でも十本指に入る。宝箱をひっくり返したほどの校数に従い、学生の数もおのずと比例する。万里が十一の春。小路はこの蜘蛛の子ほどいる学徒のうちの一人になった。生活費や交際費を己で稼ぐのと引き換えに、小路自身でここだと決めた場所だった。そこに自分も行きたいと万里も願った。
「あのね、こっちは旅行に行くんじゃないんだ。論文を書きに行くんだから」
ラーメンや錦市場の食べ歩き目当てに、新居の住居を聴き出しそうとしたとき。弟の下心を見抜いた小路がそうたしなめたのを、万里は今でも覚えている。呆れと優しみが混じった声音も、柔和な苦笑いも、しようと思えば、彼はまざまざと蘇らせることが出来た。
「いいじゃん。たまに顔を見るぐらいはさ」「なんか隣の家に行くみたいな口ぶりだけど、今すぐ部屋に戻って地図帳広げて見てみな。長野と京都、どれだけ距離があるかわかるから」
「どんなに遠かったって遊びに行っちゃうもんね」
「休みの日にな。平日になったら送り返してやる」
「どうせ里帰りなんかしないつもりだろ。だったら、こっちから行くしかないじゃん」
「はいはい。わかってます」
「ねえ、そんなに家が嫌?」
彼がそう問うたのには理由がある。小路はかねてから家業である酒造業を敬遠していた。塚本ワイナリーの顧客の中には、少なからずアルコール依存症の患者がいると考えていたからだ。この仕事はたしかに心地よい酩酊や刹那を提供するが、同時に不幸をも生産していると。際限のない浪費と暴力、そして死の匂い。そういった悲しい出来事を。実際に酒により家庭が破綻した子が、小路のクラスメイトにいたのだという。
その病人たちから『搾り上げた』と考えている金で自分が養われ育まれてきたと、小路自身わかっていただろうけれど。しかし嫌がった。こんな循環で成り立つ生活は間違っていると。
そしてこの信念は、両親と仲をぎこちないものにした。彼らは自分の仕事に誇りと自信を持っていた。果実に付着した農薬はきちんと洗い落としているし、ワインには必要以上の添加物や防腐剤は使っていない。機械類や車のローンの返済には滞りなく、税金もきちんと税務署に申告して納めている。何も後ろ暗いことをしていないのに、責められるいわれはないというわけだ。
とはいえ彼らは娘に手を上げたり、声を荒げたりはしなかった。彼らは長女の懊悩を、思春期の通過礼儀と決め込んでいたからだ。けれども不穏な雰囲気は、そこはかとなく当時の家内に漂い、影を落とした。万里が口にした問いは、そのような状況から立ち現われたのだった。
弟から投げかけられたその言葉に、小路はこう答える。
「確かにワイン造りは、あまり好きじゃないよ。確かにつながっている道筋を、素知らぬ顔をするのは善くないと思う。でも、万里やお父さんお母さんが嫌いなわけじゃない。ただ、負けたくないだけなんだ」
「負けたくない?」
「しかたないとかそんなものだとか、そういう言葉に。だから勉強しに行くんだよ。そして、もし折り合いがつく方法が見つかって、大丈夫って思えるようになったなら、うちのワイン仕事もより好きになれるかもしれない」
「じゃあ勉強が終わったら、また家に帰ってきてくれる?」
今度は答えを返さない。かわりに手を差し伸べて、万里の頭を撫でた。指先で髪をかき分けて、手のひらで肌を磨くように。そんな優しい仕草と微笑みだった。与えられる感覚があまりに快いので、万里はつい勘違いしてしまう。なんだかんだ言ってもここは姉が産まれ育った家で、おそらく四年後には燕みたいに戻ってくるはずだと。
小路が自ら命を絶ったのは京都に出て四年後、大学生として最終の冬だ。十二月二十四日の早朝。嵯峨野の川辺で、黒い冬物のコートを着た人物が倒れ伏しているのが見つかった。
発見者のハイカーの証言によれば、小路は水際にある一抱えほどの岩石を枕にして横たわっていたという。泣き顔を隠すみたいに、うつ伏せで。そうして水中で布地のように揺らめく髪から、相手がすでに息絶えているとわかったと。その周囲には血に染まった石礫が、幾つも転がっていたとも。
解剖結果によれば、小路の死因は脳挫傷だという。また死亡時刻は真夜中の三時ごろと推測された。どんなに早く見積もっても、夜半の山道を歩いて河川敷まで向かったことになる。そして最初に握りしめた石で、顔面を執拗に叩きつけたと予想される。そのうちに得物を幾つか取り替え、最終的には岩石に額を打ちつけるようになった。やがて打撃が極限に達して死に至った――。それが警察と解剖医の見立てだった。
小路は完膚なきまでに自分自身の顔を破壊したが、コートの懐にあった遺書と保険証から身元はすぐに割れる。そして二日後にはDNA鑑定と歯科医院の受診記録により、死体が塚本小路であると確定した。
その報告を塚本家は京都で受けた。クリスマスイブの夕方に右京区の警察署から連絡を受けた時点で、彼らは取る物も取り敢えず新幹線に乗っていたのだ。もちろん万里も一緒に。
そうして事情聴取や現場検証に付き合い、あとはホテルで検死の結果をひたすら待つ。そして結論が判然とした後は役所に届けを提出して、火葬を済ませた。長野まで遺体を運搬するとお金がかかるのだ。
このあいだ彼は小路の死に顔を、ついぞ目の当たりにしなかった。しきりに垣間見ようとするのを、両親はことごとく盾のごとく遮ったからだ。お前だけは元気なときの、奇麗なままの姉を覚えておいてくれ。頼むからと。
十三年が経った今でも、長女の有様について彼らは多くを語らない。しかし実際の在りようが、万里にはなんとなく察しがつく。崩れた牡丹や芍薬の花を目にするたび、二人は声を押し殺して涙ぐむので。
自分の顔を壊さねばならなかった理由を、小路は一切書き残さなかった。遺書には財産の処理と遺影に使う写真の指示、それから万里たち家族に対する短い謝罪を記すのみだった。それだけに私物が徹底的に処分された部屋と、完成された卒業論文から伝わる堅固な意思が悲しかった。
病院の霊安室で出棺を待つあいだ。棺の覗き窓と蓋は、終始固く閉ざされていた。
小路を霊柩車に乗せる前に、釘打ちの儀式をする。父と母と、万里。それぞれが一回ずつ、交代で棺の蓋に釘を打つ。使うのはハンマーではなく小石だ。礫で死んだ人間に対し、また石を振り上げるのに、なんとも言いようのない心持が万里にはした。その怒りに基づいた感情は、夜空を飛び交う火矢に似て、絶え間なく彼の胸に猛っていた。
――負けたくないんじゃなかったのか! 小石を釘の頭部に叩きつけながら、万里は胸中で姉の霊に語りかける。自ら死を選ぶことが、何かへの敗北の結果だと捉えられたからだ。そしてこのような幕切れは、小路はとうてい似つかわしくない。揺るぎようのない事実だとはいえ、これが主体的な選択だと彼には信じられない。破局に至る心当たりもなかった。思い出すのはタオルで濡れ髪を拭ってくれた感覚や、変な形の野菜にはしゃぎたつ声。あるいはファミレスのドリンクバーで奇妙な飲物を作る姿、また京都駅で出迎えられたときのおたふくみたいな悪ふざけの化粧。そういった、なんでもないことばかりだ。
追い込まれた、殺された――そんな考えが、当時から万里の脳裡にはちらつく。何に、誰にと名指しには出来なかったが。どちらにしても『負けた』、『追い詰められた』という感じからは逃れられなかった。
当然ながら死人にモノを言う口はなく、答えは返ってない。発せられなかった問いは、万里の血潮に溶け込んで彼の一部となった。そうして現在に至るまで彼の肉体の奥底に潜んで、ずっと息づいている。ある意味では小路ともに歩んできた、十三年だった。
しかし答えを得る機会は、思いがけずにやって来た。
塚本家の墓前、そして清滝川の畔で会った女は倉橋径子という。倉橋の住まいは北区の閑静な住宅街の端、家々を通り抜けたところにある山際にひっそりと佇んでいた。一軒家と邸宅の合間の洋風の瀟洒な家は、手のひらで転がしたようなこぢんまりとして、ドールハウスを思い起こさせる趣だ。巡礼の翌日、万里はそんな家に招かれた。小路について打ち明けるべき事柄があると。
門前の表札には〝奥辻〟と記してある。彼女は仕事(料亭の経営だ)の関係で、旧姓を名乗っているという。このこと自体は問題ではない。もっと気がかりなことはある。京都府北区の奥辻さん。その住所と姓の組み合わせに、万里には覚えがあった。|奥辻成実(せいじ)は十五年来の塚本ワイナリーの御贔屓様だ。
今日は仕事に出ているために、本人は邸内には不在だった。なんでも京都駅の劇場で芝居を観ているという。万里は寡聞にして知らなかったが、奥辻氏は劇作家なのだそうだ。テレビではあまり活動していないが、映画や演劇では名が知れているらしい。現在、駅前の劇場でかかっているのも彼の手掛けた作品で、鑑賞も観客の反応を確かめるためとのことだった。
今日は仕事の付き合いのために、彼の帰宅は遅い見込みになると倉橋は言う。そんな日に、万里はソファセットのある客間に通された。内密な話をするのには、ちょうどいいというわけだ。
「彼、塚本ワインのファンなんですよ」
十月の終わりにはそろそろ新酒だと、うるさくてしょうがないんですから。そう口にしながら、倉橋は卓上にコーヒーソーサーを置く。こちらに笑みを湛える顔を、万里は改めてまじまじと眺めた。文句のつけようのない、鮮明な笑いだった。纏ったコットンセーターやニットスカートの質感が、さらに柔和な印象を与えている。だが、どこか冷ややかなものがある。演出。そんな語彙が頭に浮かぶ。相手を見やりながら万里は言う。
「毎年のお礼状を、いつもありがたく頂戴しています」
「あんなに長々と書いて、鬱陶しんじゃないんですか」
倉橋は向かい側の、ひとり掛けのソファに腰を下ろす。
「いいえ。とても励みになっています。商品に対する感想や意見は、思いのほか少ないものなので」
「そうですか、ならいいのですけど」
「多くの人は商品が気に入らなければ、何も言わずに去っていく。時間は有限ですからね。わざわざ文句を言うよりも、別の商品に切り替えるのが手っ取り早いわけです。だから自分たちのどこが悪かったのか、まるでわからない。それ以前に問題があるのか、否かすら知りようがない。これは、凄まじくおそろしいことです」
そう倉橋が短く返したきり、客間は沈黙に陥った。話し過ぎたか。何となく気まづくなって、万里は視線を相手から逸らす。目を移した先には窓がある。
天井を衝くフランス窓には、冬の庭がよく映えた。伸びきった糸杉と胸丈ほどの生垣が、ステンドグラスや絵ハガキのようにすっきりと窓枠の中に収まっている。そこにガーデンテーブルのセットが加わって、全体を引き締めるアクセントとなっていた。
夾竹桃やサツキや椿との混ぜ垣なのだと、倉橋が問わず語りで述べる。椿の盛りは冬で、サツキの花は夏に咲く。夾竹桃は春先だ。どうやら絵画を掛け替えるみたいに、季節ごとの変化を愉しむ趣向らしい。あいにく今は時期が悪かったようで、花々の麗姿はどこにもない。ただ冷え切った窓ガラスを通して目にする、常緑樹の薄黒い青さは陰鬱ながらも美しい。そんな情動と言葉を引き出させる庭だった。
このような作為や計算は、奥辻家の随所に見受けられた。選び抜かれたアンティークの調度品、シンメトリーを用いたインテリアレイアウト。あえて若干明るさが落とされた照明。そのようなところに。しかし華美なものは片手の数程度しかないので、嫌味はなく、むしろ洗練された優美さを醸し出していた。そして油断がない。どこを写真として切り抜こうが、きっと様になるだろう。
万里が周囲に目を走らせるさなか。おもむろに倉橋が口火を切る。
「お姉さまも、よくこの庭の虜になっていたものでした」
「姉が?」万里は訊ね返す。
「ええ。何も用事がないときにはそこに――あなたと同じ場所に座って、物を想って過ごしていました。あの人は、家の中ではここだけはましだからと。だからあなたにも、どうか私たちの庭を御覧になってもらいたいと」
「解せませんね」
小路と関係するのか、万里には見当がつかなかった。ワイナリーの社長令嬢と呼べば聞こえはいいが、本質は片田舎にあるぶどう農家の娘だ。そんな人物と優雅な劇作家が、いかにして結びついたのか、まったく想像がつかなかった。おそらく倉橋が一枚噛んでいるのは予想がつくが。
「お友達だったんです。そうなるように事を運びました」
そう言い締めると、おもむろに彼女は身動ぎをした。ついでスカートのポケットから何かを取り出し、こちらへ差し出す。ICレコーダーだ。そうして万里の眼前でスイッチを押した。まもなく音声が室内に、二人のあいだに流れ始める。
《祖母の話をします。》
そう何事かを語ろうとしているのが誰なのか、万里には驚きとともにすぐにわかる。幼いころから耳に馴染んで、とうに長じた今でもずっと離れない声だから。しかし、一番に彼を仰天させたのはその口調だった。声音こそ平静を装っているけれど、節々で取り繕いようのないほどに掠れ乱れている。あきらかに打ちのめされ、重苦を押し殺した声遣いだ。
なんですか、これは。……私が友達にしたことの一つ。万里の問いに倉橋は答える。また、この音声が記録された現場には他にも三人の人間がいたとも。自分と奥辻。そして、もう一人。
「葦船鏡世。十年前に、あの河原で死んだ歌舞伎俳優。ご存じない?」
知ってはいる。だが、よく覚えていない。そのころはセンター試験が差し迫った時分で、テレビどころではなかったせいだ。そして、なにより不愉快だった。よりにもよって、どうしてあの場所で? 仄聞にした情報に、そのような反感を彼は抱く。
また悪路を越えて、葦船の死に場に押しかけるファンの狂乱ぶりが、さらに万里の悪感情に拍車をかける。天地崩れるかの如き大騒ぎを眺めていると、小路や自分が馬鹿にされた気がした。
だから万里は、その役者に関わる一切の記憶を脳裏から締め出した。そうして学業や就職活動に没頭するうち、冷ややかな感情は記憶とともに薄らいでいく。留学を経て家業を継いでからはなおさらで、早逝した俳優の存在は、今の今までまるきり消え去っていた。
しかしその名を改めて耳にすると、何か、万里の胸に引っかかものがある。そうして気がつくときょうせい、と彼は口に出していた。憑かれたみたいに幾度も、異なるアクセントと速さと長さで。キョウセイ、キョセイ、キョオォセイ、キヨセエェ。様々な発音を繰り返しし試みていた、ある瞬間。不意に一つの記憶が、彼の眼前に稲光のように閃く。鏡世さん。かつて、このように小路を呼んだ人がいた。
《――……水を》思い至ると同時に、小路の一人語りが途切れた。ついでごくわずかな沈黙の後、かたかたと雑音がスピーカーに入り込む。何か、硬質で薄手のものが当たる音だ。ガラス。そう万里は思う。まもなくどうぞ、と小路ではない誰かが言う。
《ありがとう》《うん。ゆっくりで、いいからね》
礼を述べる小路に対し、相手はこのように応える。透き通るような、針のある男の声だ。語尾に移るに連れて吊り上がり、最後に急激に下がる。関西のアクセントの柔らかい調子は、内容とあいまって一聞すると優しみに満ちていると捉えられた。だが、どこか不穏さがある。押し当てた刃で首筋をつうと撫でている――そんな圧力が感じさせる声音だった。
「大好きだったの。彼女のことが」
誰がと倉橋は明言しない。けれども主語が指し示す人物を、万里には確かに理解できた。
§
祖母の言葉が身に沁みたことがあって。彼女が想像していた状況と、少しだけ違うんですが。小学生のころに、いなくなった同級生がいるんです。たぶん夜逃げだか、なんだかで。
たぶん、というのは噂でしか知らないからです。お父さんがリストラにあったけど、誰にも言えずに抱え込んじゃって。酒浸りになって。それで生活費やなんやらで借金がかさんで、首が回らなくなってと、そういう噂。ずっと昔から、よくある話です。よくあるから、みんな慣れきってしまった。まあ広い世の中には、そんなこともあるよねと。
あくまで噂ですから、本当のところはよくわからない。でも、ある程度は真実に触れているんじゃないかなと思います。少なくとも酒浸りだったのは本当だと。いなくなるまえに、私はその子と話したから。
人生で初めて、石を投げられた日でした。学校から帰り道を歩いていると、突然、ランドセルにかつんと当てられたんです。なんだろうと振り返ってみたら、その子が立っていて。そのへんの石を手当たり次第に投げつけてきました。鬼、悪魔と捲し立てながら。他にも何事かを言っているようでしたが相手は興奮していたし、私も礫から逃げながらの状況だったのですぐには理解できませんでした。それでもよくよく聞いてみるとお前のところのせいで、お父さんがおかしくなったと口にしているらしいのでした。そうして、こうも言いました。吸血鬼。
ご存じかもしれませんが長野県は酒どころで、酒造りがそれなりに大きな産業として成立しています。私の実家ではワインを製造していますが、故郷では日本酒を主に名産としています。
利益や利潤になるということは需要があり、顧客がいるということです。その全員が節度を守って酩酊を愉しんでいるならいいですが、どうにもそういうわけではないようでした。なかには我を忘れたうわばみがいて、陶酔のためには粉骨砕身、労苦を惜しまない。それこそ持ちうる限りの財産や、すべての肉、骨の髄まで差し出すほどに。このような人々の存在ありきで成り立つ仕事、そこで得られる金銭と糧で生き永らえ続ける人々。私の家も、このうちの一つのようでした。吸血鬼。そのように呼ばれるに、まさしくふさわしい在りようです。
そうしてこのシステムは、このとき初めて、私の前に出現したのでした。それもどうしようもないくらいに追い詰められて、深刻に傷ついた子どもの姿で。
嫌だと思いました。多分、純粋な感情だったと思います。そして湧き上がってくる気持ちは、大きな衝撃を伴ってもいました。『突然織り物はひるがへり、糸は八散してたゞよひぬ。憂然として明鏡は、まッたゞなかより割れてけり。』そのような打撃と痛みが。
また祖母の言葉も頭に蘇りました。美しいものには心掛けて、距離をとらなければならない。そうでないと顔も名前も曖昧な、よくわからないものの言いなりになる。
私は家の畑にある、ぶどうの木が好きです。ざらついて節だった木肌は触れると心地よく、うねりながら天を覆う枝ぶりは壮観で。そうして房に可憐な花が咲いて、馥郁とした香りに包まれるといつも嬉しくなった。一喜一憂する大人たちの様子が、印象づけたのかもしれません。また木々が私にとっては初めての、そして生まれながら友達だったのもあるでしょう。それも抜群に美しく、私を飢えや渇きから守ってくれる友達。
私は私の家族を愛しています。両親と弟、みんな気の良い人たちです。死んだ祖父母もそうでした。ときには悪心は抱いたこともあったでしょうが、それに負ける人たちではありません。もちろん機嫌は良いときばかりではないし、ときには喧嘩をしました。私も生意気な行いや物言いをしたと思います。それでもあの人たちは、呆れるような振る舞いはしないでくれた。少なくとも私の知る限りおいては。まさしく賞賛に値することです。
しかし石をもって追われたの後には、どちらも、いちがいに好ましいとは感じられなくなっていました。
私は自分の目の前にある樹木、言葉を交わす人たち。そのものが本当に好きだったのだろうか。掛け値のない、代わりのないモノとして心から愛したことがあったろうか。もしかしたら私が敬愛していると信じていたのは、もっと別のものだったのかもしれない。そんな疑いが、恥とともに頭をもたげました。今も続いています。この心情を別の表現で表すなら、こういうものになります。
吸血鬼にはなりたくない。君はどうだ。
*
葦船鏡世とはいわゆる芸名で、彼の本名は坂下李一という。もともとは伏見にある造り酒屋の息子だった。幼少のころに日舞の発表会で藤娘を演じたおりに、招待されていた芳桂屋に才を見出されて彼の部屋子――ひらたくいえば弟子になった。その際、月若の幼名が彼には与えられた。
また坂下の名義で子役としても活動を行っており、映像作品への出演も多数あるとも聞く。朝の連続ドラマにも出ていたそうだが、万里はまるきり知らなかった。幼年期からずっと毎朝のタイマー代わりにした番組だから、必ず目にしているはずなのだけれど。でも彼の顔どころか、名前すらも覚えがない。主人公の弟というそれなりに大きな役柄だったらしいのだが。
そういうあんばいなので、万里が初めて彼の存在を認識したのは十六年前の春――小路が家を出た翌年の春のことになる。
万里が中学生になる年。彼は有言実行で、春休みに京都を訪れた。赴いたのは彼だけで、両親は忙しいからと同行しない。確かにこの時期は芽かきやら梢の誘引やらで、やることは山積みなので多忙なのに違いなかった。だけれど二人の口ぶりは、なんとなくモノが挟まった奥歯に衣を着せたようだった。もしかしたら顔を合わせるのが、気まずかったのかもしれない。そのためか、彼らは娘が死ぬまで一度も会いに行かなかった。
桜の季節を迎えた京都駅は賑やかだった。特にタワーが見える改札口は忙しなかった。バスやタクシーが始終ロータリー交差点を行き交い、キャリーケースやリュックサックを携えた人々の往来は絶えない。ときおりは入り込んでくる話声も中国語や英語、韓国語など多種多様な言語が耳につく。視覚や聴覚から全身が揺さぶられ、眩むようだ。驚き呆れながら辺りを見回すさなかで一際、目に着く人物がいた。
まず目に入るのはムカデやゲジゲジの如き太眉に、アイラインをくっきりと施した目蓋だ。くわえてファンデーションを塗りたくっているために、このうえなく派手な外見なっている。紅が差された頬と、そのままの唇の対比が極めてアンバランスな印象を与えた。
その人が万里に向かって、大きく手を振る。初めのうち彼は無視していたが、次第にこいつはまさか身内ではないかと疑いが頭をもたげ始めた。そしてその疑惑は、おーいと呼びかけてくる声で確信に変わる。小路だ。すぐにそうとわからなかったのは口の中に綿を入れて、輪郭をしもぶくれに変えていたせいだ。
相手が誰だか明かになると一転、なんだかおもしろくなってきて、反射的に笑いが込み上がってきてしまう。小路も照れ笑いを返してくる。お互いにひとしきり笑い合ったあと、一抹の不安が万里の胸に去来した。まさか、それで学校通ってるわけじゃないよな?
「行ってない、行ってない。これは今日が初めてだからさ」
そう小路は弟に答える。
「でも、おもしろかろ? 新歓コンパで大うけ間違いなし」
「大うけとかどうでもいいから、とにかく直してこいよ。ラーメン喰えないだろ。……持ってるよな、メイク落とし」
「はい、はい。持ってますよ」
軽薄な調子がなんとなく信用できないので、万里は後ろをついていく。しばらくお手洗いの出入り口付近で待機したのち、小路はすっきりとした顔になって出てきた。見慣れた素顔と相対して、万里はようやく胸を撫でおろす。そうして百貨店の方まで歩きながら、食後の行き先についてと話し合っていたときだ。いきなり横からこのように声をかけられた。
「あらあ、キョウセイちゃん。なにしとるの、こないなとこで」
それは四十がらみの女の人で、淡い黄色の着物に黒い長羽織を重ねている。丸く結った襟足と、衿元からすっと抜ける首筋が爽やかだった。そんな人が訝し気な顔つきで、こちらの返事を待っている。
投げられた言葉の意味をすぐさまに判じかねて、小路たちはすぐに問いに答えられない。相手も何も言わない。様々な声や人影が行きかうさなか、お互いに相手をまじまじと見つめう。ややあって万里は事態を理解した。人違いだ。
それは相手も同じだったらしい。にわかに女性の顔色が変わる。怪訝な面持ちから驚きへと。ついで口を開く。――すみません、人違いでした。そう軽く会釈したのち、長羽織の女は足早にその場を去る。
普段ははんなりとか宣うくせに、まったくそそっかしい。瞬く間に遠ざかる後ろ姿を見送る小路は一笑を、万里はありありと思い出せる。けれども今から振り返ってみれば、あれは純粋な笑みだったろうか。表情に陰りはなかったか。
そして悪ふざけじみた小路の面相を、倉橋も目の当たりにした。彼女がまだ学生だったころ、小路と初めて出会ったときだ。あの顔で大学の構内を歩いていたのだという。胸を張って堂々と。しかし聴いてみると倉橋が通っていた大学は、小路が籍を置いていたところとは違う。おそらく他校の講座を受講できる制度を使ったのだろう。
「あんまりもあんまり顔だからつい私、怒ってしまったんです。芳桂の看板背負ってる役者のくせに、その面相はどういうつもりだって」
真昼の煌々とした光が射す通路を往く小路が、倉橋には葦船鏡世に見えた。よくよく考えると、彼がその場にいる理由はない。この時分の葦船は大阪の劇場で、次の公演に向けた稽古のさなかにいたのだから。それを倉橋はあらかじめ知っていた。
彼と倉橋は、日舞における兄妹弟子なのだという。また、二人の上にはさらに奥辻氏がいる。彼と彼女は幼時から師匠や他の兄姉弟子の下で苦楽をともにし、切磋琢磨してきた。いわゆる幼なじみ、筒井筒の仲になる。そして古典から引用された形容句は、まさしく二人の間柄を表すのに相応しかった。彼らは婚約をしていたのだ。
「料亭の娘と、造り酒屋の息子。お似合いというわけです」
二杯目のコーヒーを呷ったのち、そのように彼女は言う。しかし内容に反して、親しみや愛着は感じない口吻だった。節々の言い回しから苦々しさが滲み出ているのが、レコーダーが停止した、静かな部屋ではよくわかる。
だから見間違うはずはない。好むと好まざるとにかかわらず、おのずと突き合わせてきた顔なのだ。けれども彼女にはいるはずのない人物が、いるはずのない場所に突如として現れたように思われた。
「グロテスクでさえある変貌ぶりでした。輪郭が醜く歪んで、肌の質感が跡形もなく変質して。でも確かに面影があったんです。一目で見ただけで、ああ、あの人だと、はなから決めつけてしまうくらいに」
「とはいえ出生地も性別も、まるきり別の人間じゃないですか。それに身体が資本の人だ。スキンケアや体重管理の努力も、一般の人とはなにもかも違うでしょう。そんな人と見まがうなんて、ありえない」
「彼女も同じことを口にしていました」
――どいつもこいつも不見識だ。ファンだか何だかのくせに、敬意がない。
「きっと憤懣が溜まっていたんでしょうね。見間違われる機会が重なっていたから」
小路にとっても葦船にとっても、それが始まったのは十七年前の秋口になる。年末の吉例顔見世興行――それも葦船鏡世の襲名披露を控えた重大な時期でもあった。本当なら市内にある稽古場に詰めていなければならない。遠く離れた嵐山の寺院にいるのを、芳桂屋の後援会員(いわゆるパトロンだ)の一人が目撃した。緋色の木蔭の下。紺のジャンパーとスラックスに黒のアポロキャップを被って、散紅葉の降り積もる山門へ続く石段を降りていたという。
万里には心当たりがある。確かその時分の小路は、嵐山でアルバイトをしていたのだ。紅葉シーズンに臨時雇用されたガイドスタッフで、三時のおやつがついているとメイルで自慢されたのを覚えている。くわえて、バイト先で拾った落ち葉で栞を作って送ってきた。滴るような鮮やかな紅葉だった。
それを皮切りに葦船鏡世に似通った何者か――すなわち塚本小路の影が彼の身辺に浮上し始める。葦船の生き写しは百貨店でクリスマスケーキの受け渡しをしたり、出町柳の駅前でポケットテッシュを配ったりする。あるいは図書館の自習コーナーで本に齧りつき、また百万遍の古本屋から包を小脇に抱えて顔を出す。コンビニやスーパーの袋を提げて道を歩いて、もしくは天津甘栗だかサンドイッチだかを公園で買い食いするのも多数見かけられた。そのいずれもが彼が現れるはずのない場所と時間なのだった。
だから目にした誰もが呆気に取られ、絶句した。ついで相手を呼び止め、肩を叩く。キョウセイ……もしくはキョウと。お前、こんなところで何をしているんだと。時と場合によっては行儀が悪いと、声に怒気を帯びることさえあったと倉橋は述べた。
小路が何故あんな胡乱な粧いをしたのか、万里はにわかに合点する。小路を呼び止めた各人は人違い、見間違いで済む。当人はそうではない。思いがけないタイミングで、知らない人に声を掛けられるのだ。それも同じ名前で、幾度も幾度も。気が休まらないのは想像がつく。
「あの化粧は本当にみっともなかったけれど、でも隠すという方向性は大正解でした。なにせ鏡世は彼女のことを、血眼になって探していたんですからね。信じられないほど、ずっと昔から」
ずっと昔から? 聞き入れてまもない言葉を用いて、万里は相手に訊ねる。するとええと倉橋は頷き、話の続きを紡ぐ。囁くようにも、謡うようにも捉えられる調子で。幾度も夢のなかで出会う子ども、あらかじめ失われた肋骨。別たれた分身という考え方。そんな奇妙な話を彼――葦船は語った。まだ彼と倉橋が子どもと呼ばれるころに今、万里が腰掛けている場所で。
「あの人は、そんな人を待っていたんです。子どものころ……きっと右も左も区別がつかないくらいに幼いころから。長いあいだ分かたれて遠ざかったものを、あてどなく街中に探し求めて。そして、とうとうあてがついた。まあ、あてがついただけでちっとも会えなかったんですが」
相手の口にすることの意味が、万里にはうまく理解できない。なのに、なんとなく薄氷を踏み抜いた心持がする。心臓が一瞬跳ねたあと。慄きが背筋に走って、襟足がちりちりと逆立つ。口内が急速に渇いて、舌が口蓋や歯と一体となる予感がした。それでも万里は、倉橋に問わねばならない。
「それで姉はどうしたんですか?」
「きっぱりとしていました。ほとんど、ずっと」
ほとんど。その一言が暗に示す事柄が、万里の血の気を引かせた。両の指先がすうっと冷たくなり、肌の色が次第に蒼褪めていくのが自分でもわかる。平静や均衡を失った時間が、それらを失わせる出来事が小路の身降りかかった。万里にはけして知りえないところで。そして彼の目が届かないところで死を選んだ。
つらつらと思い巡らせていた刹那。静寂を破るように、がちゃんと激しく繊細な打撃音が室内に響く。倉橋がカップをソーサーに叩きつけたのだ。ついで彼女は再び、テープレコーダーにスイッチを入れる。浜辺に立てたフラッグを掠めとるのに似た、俊敏な身のこなしと手つきで。まもなく小路の音声が、再び室内に流れ始めた。
《祖母の言葉が身に沁みたことがあって》
音声に紛れるか否かの声量で、倉橋はおもむろに口火を切った。
「言い訳がましくなるかもしれないけど、私はお姉さんをすぐに彼と引き合わせたわけじゃない。彼の浮かれようは想像がつくし。どうせ様になるんだから。それにあれの存在は彼女の人生に必要ないのも、わかってた。でも、彼女に見せてあげたの。遠くから。見たいって言うから」
《人生で、初めて石を投げられた日でした》そこで倉橋は姿勢をしどけなく崩す。背もたれに肩を預けて、頬杖をつく。そんな態度のよろめきは、後に続く言葉にも表れた。
「あのときかかってたのは近松の日本振袖始で、彼は岩長姫の役だった。私は南座の、二階席を取ってあげてね。出入口に近くて、割と端っこの方。覚えてる。彼女、包帯ぐるぐるで待ち合わせに来たのよ。もうスケキヨさんかマミーマンかってぐあいで。もしかしたら透明人間かもしれないけど。まあ、なんだってええわ。とにかくポスターやらなんやらで、相手の人相を確かめにきたわけ。そして言ったんだ」
《吸血鬼》
「やっぱり似てないねって」
「そうでしょうね。小路なら」
「うん。そうして公演が跳ねた後。彼女ずっとビクビクしてたのがバカバカしいって、化粧室に入って包帯を解いたの。糸車から糸を紡ぐみたいに、くるくるって。すると真っ白な包帯の下から細いおとがいが、桜色の唇が出てくるでしょ。それに小指の先でそっと描いたような眉や、ぱっと大きく咲いた目蓋も。最後に抑えつけられた髪がふっと膨らむ。別に普通のことなんだけれど、でもなんだが、どきどきした。それは他のヒトも同じだったみたい」
「同じ?」
「化粧室から出てきたところを、観客に見られちゃってね。どうも彼のファンだったみたい。その人、あらっと大きな声でこっちを指差して。周りの人たちも雁首揃えて向けるからもう、しっちゃかめっちゃかで。彼女は私の手を引いて、劇場を出た。そうして縦横に広がる通りを右へ左へ、上へ下へと走って。どうにか追手から逃げ切ったんだけど。あのときは、おもしろかった」
《吸血鬼。そのように呼ばれるに、まさしくふさわしい在りようです。》
「でも、良いことばかりじゃない。彼女の容姿を目にした人たちのなかに、夫がいたんです。具合の悪いことに」
「奥辻さんですか?」
「もう長いつき合いですからね。彼はすぐに、あれが鏡世ではないとわかったそうです。けれど、でも心底驚いたと口にしました。まさか、あそこまで――彼女はけして認めはしなかったけれど――そっくりな人間がいるなんて考えもしなかったと。こんな、お芝居みたいなことがあるのかって。そして、ひどく彼女に興味を惹かれたようでした」
――あの二人を引き合わせて、隣同士で並べたらなかなか素敵だと思わないか。奥辻がそう言ったと彼女は回想する。高揚が抑えきれない口ぶりだった。
《吸血鬼にはなりたくない。君はどうだ》《……――さあ、考えたこともなかったな》
投げかけられた言葉に、わずかに間をおいたのちに鏡世が返す。だろうな、とレコーダー内の小路は応える。
§
さあ、考えたこともなかったな。
だろうな。
僕がやってるのは観る、観られるの商いだからね。僕は良かれ悪しかれ、オーディエンスの反応やおひねりを受け取る。客席の方々も僕が出ている舞台の身振りや台詞から、何らかの感銘を受けたり励まされたりする。それを吸血鬼と呼ぶなら、そうかもしれない。
けっこうな話だ。でも、問題は中身というか性質なんだ。
性質ね。
性質、中身。本質。
僕は楽しいよ。吸って、吸われてってのは。
とはいえ人間の欲望は無尽蔵だから。そんな悠長にかまえてると君……まあ君だけじゃないけど、とにかく、そのうちからからに吸い尽くされて、血肉どころか骨すらも残らなくなる。でも君から何もかもを搾り取った人たちは、きっとそのことを忘れてしまう。そして次に用意された、お楽しみに移っていく。
どこにでもある話だ。ずっと昔から。
でも、限度がある。何事にも。
まあね。
そうして、あらゆるモノやヒトを搾り取って。もう何もなくなったあとは、どうなるんだろう。
……。
……そういえば。あの子がどうなったのか、気にしたことなかった。
作中で言及される詩はアルフレッド・テニスンの『シャロットの姫』から引用した。日本語訳は坪内逍遙による。→『シャロットの妖姫 アルフレッド・テニソン 坪内逍遙訳』https://www.aozora.gr.jp/cards/000140/files/740_20917.html
◆サポートは資料代や印刷費などに回ります ◆感想などはこちらでお願いします→https://forms.gle/zZchQQXzFybEgJxDA
