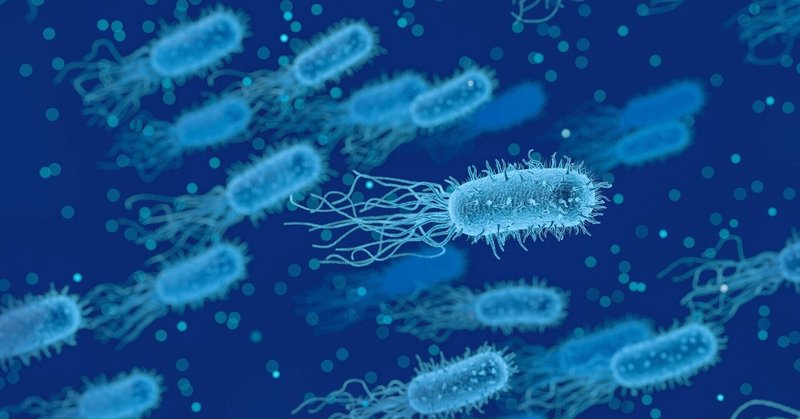
『LIFESPAN: 老いなき世界』書評・パート➁人類の寿命もただの偶然の産物
進化が私たちに渡した寿命の短い「不運なカード」
この本の要点2つ目は、老化は改善できるが、克服することはできないということだ。
これにはそんなバカなと思う人、または中途半端な訴えだと思う人もいるだろう。前者は老化を宿命だと思い込んでいる人に違いない。それにも仕方ない理由がある。
長い人類の歴史上、寿命は実質的に伸びたことがないからだ。
これにもそんなバカなと思う人がいるだろう。だが近代以降、急激に伸びたのは平均寿命だけで、それは単に労働時間が減るなど人類が全般的に豊かになったからに過ぎない。
昔から王侯貴族は長生きだった。つまり健康寿命や最大寿命は何千年と変化していないのだ。そのため宗教が中心になり、老いと死がセットになって人類の普遍法則だとして美化されてきた。
だが、人類の老化は生命進化の草創期で偶然、与えられたものだった。シンクレアはそれを「進化は人類に不運なカードを渡した」とすばらしいレトリックで表現している。
サーチュインが迷子になる老化の基本メカニズム
彼の説では、40億年以上前の地球で激しい火山活動による長期的な乾季が生じ、そこに最適化したマグナ・スペルステスという種が人類を始めとした現在の動植物の起源だという。
老化とはそのマグナ・スペルステスが一時的に獲得した生存方法の負の側面に過ぎない。
そのため科学の力でそれを改善することは充分に可能なのだ。この序盤のパラグラフは私が最もガーンと食らった箇所である。
空が青いとか重力があるといった私たちが当たり前として見ている現象。それらもその最初期は偶然であり、絶対の法則ではない。こういう気づきを与えてくれるところに学術の最大の魅力がある。
老化の根本的なメカニズムが披露されているのも興味深い。要は、ゲノムの遺伝子操作を担うエピゲノムの本体、サーチュイン(長寿遺伝子)の迷子のような暴走が老化の元凶だということ。
具体的には、人が年老いるとDNA損傷など緊急事態で駆り出されたサーチュインが、回復後に元の場所に戻ってこれなくなる事態になるという。
本書では山中因子でエピゲノムを初期化するなど、こうしたサーチュインの暴走を抑止する方法が挙げられていた。
終盤にはWHO(世界保健機関)がついに老化を疾患コードとして明記したことも書かれている。こういう記述を見ると、希望がはっきり見えてくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
