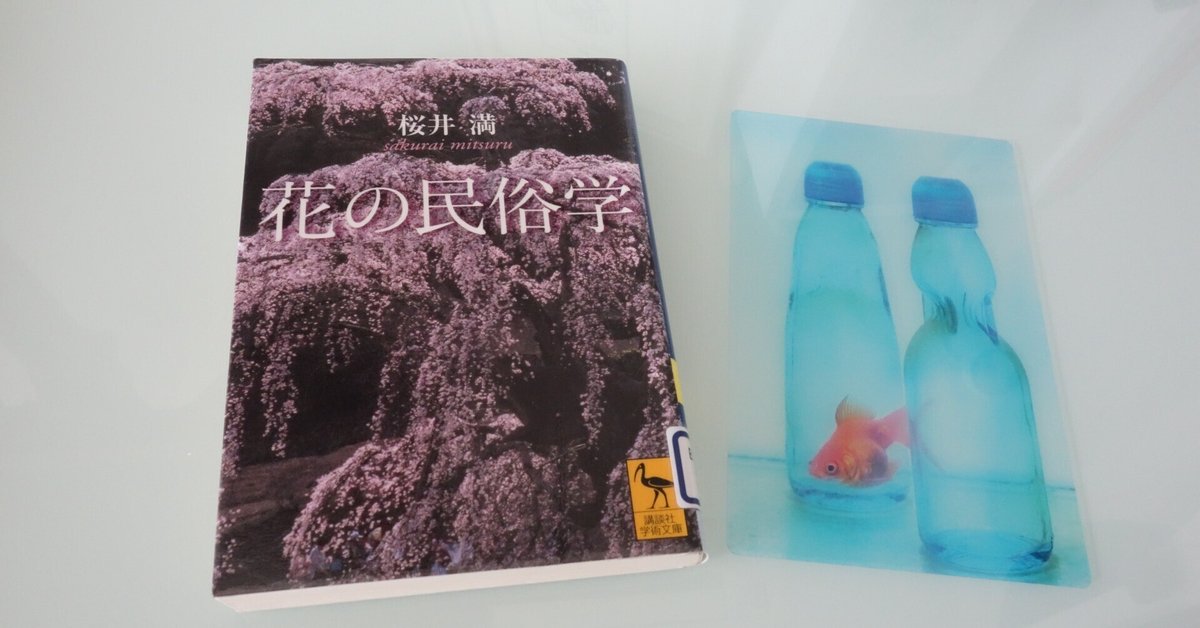
「花の民俗学」読了
新しめな本をサラサラと読む気分だった中、図書館で借りた古い本「花の民俗学」桜井 満・著を、今日、読み終えた。引用部分が古典や和歌なのだが、本文も一種の古典と感じる難しさだった。
わからない言葉を、かなり検索しながら読んだので、2週間近くかかったように思う。
伊勢神宮で行われる式年遷宮は20年に一度。いちばん最近の62回目が2013年。
この本の結びの中に、生き生きと描写されているのは60回目のこと。
さすがに古く、今の日本人の感覚と同じとは思われないが、今の日本人の花に対する感覚が作られた理由を感じられた。
私自身も十分に年を重ねているが、祖父母の時代の感覚を知るような内容だった。
中学生か高校生だったときの国語の授業で、「『花』と書かれているのは、何の花だと思いますか」という先生の話に、「桜」は連想できなかった。花なんてたくさんあり、一種類なのか?と思ったくらいだった。なので、「日本で花と言えば桜でしょう」というのは、後からの知識。
個人的には、既に、桜を心から楽しんできた日本人ではなくなってしまったらしいが、その桜への思いの背景が、古い話から書かれていたりする。
サは穀霊、クラは神座。ハナという言葉は、端緒とか前兆。というような、宗教的というのか呪術的というのか、そんな感覚で見てきた頃の話から、観賞の対象となったり、武士の心のように言われたりする背景も記されている。
桜の話だけではない。「歌は常に古典的」という話とともに、梅が歌に出てくるまでに時間がかかっていることなど、いろいろな季節の花の話が出てくる。
花ばかりでもなく、酒を飲み過ぎるまで飲む、日本人の宴会の感覚の元も感じられた。
昔の暦には、どこか不完全な印象を持っていたが、それは、今でも行事として全てが残っている訳でもなく、話題になっている訳でもないことからくることがわかった。自然の様子を見ながら、かなりシステマティックな暦に従って働いてきた様子を感じた。
何年前だったか、七夕について子どもが英語教室で習い、持ち帰ったプリントの内容に呆気にとられたことがある。だからといって、今の七夕の背景を説明できるほどに理解できていなかった。日本語でも難しい。
今の七夕の行事は、古来の日本の話や、中国から入ってきた行事、それに、近代化をプラスした背景で成り立っていることが書かれている。
七夕には晴れると良いという感覚でいたが、これも近代的なのではないかと思った。七夕には雨の方が良いという話も多いようだった。
住んだこともある東国の、花や「帰化文化の華」という内容もあり、いろいろと興味深く読んだ。
が、気楽に読む気でいたせいか、手間取ったという感覚が大きい。
もう一冊借りてある本も、奥付の発行日より15年くらい前に書かれた本のようだ。
貸出期間の延長はしたものの、読了できるのか、あまり自信はない。
