
天才ディラック(24歳)の1926年論文を解読するのだ
⇧の続きです。論文の第二章を見ていきましょう。

何やら小難し気な式が二つあります。

$${p_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}, -W=-ih\dfrac{\partial }{\partial t},}$$
エルヴィン・シュレディンガーが同年前半(1926年1~6月)に立て続けに学術誌に寄稿した画期的な一連の論文を熟読するうちに、ポールくんは上の二つの式を仮定します。「運動量 p とエネルギー W は、位置 q と時間 t の偏微分によって表される。すなわち運動量 p とエネルギー W は、微分演算子とみなせるし、位置 q と時間 t は数学的変数とみてええんやないやろか」と。
エルヴィンくんが導出したシュレディンガー方程式を分析するに、位置 q と時間 t は可換であり、一方で運動量 p と 位置 q は非可換であることから、同方程式を支える残る二つの因子、ハミルトニアン(力学的エネルギーと同義)と時間 t も非可換であるだろう、ということはこんな形の式が成り立つに違いない、と。
$${p_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}, -W=-ih\dfrac{\partial }{\partial t},}$$
「それはいいとして演算子ってなんやの~」 関数の関数と思えばよろしいです。$${f(x)}$$ の中にある $${x}$$ も関数になってる関数というところでしょうか。
さあてポールくん、くだんのこの二式の形をじーっと眺めた末に…
$${p_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}, -W=-ih\dfrac{\partial }{\partial t},}$$
こんな推理をします。
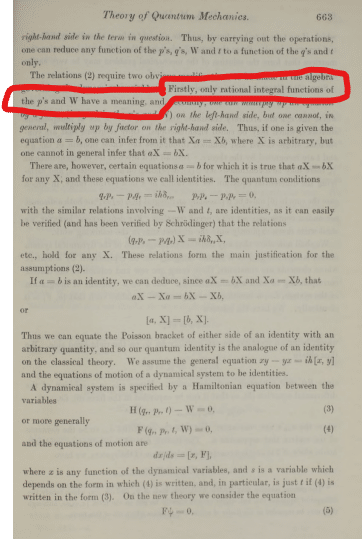
$${p_{r}}$$ と $${W}$$ が絡み合うとき、それは必ず分数の形式になるし、しないと不自然になると。いわゆる「有理整数関数」。こんなのがそうです。
$${\dfrac{3x^{2}+4x-1}{2x+9}}$$, $${\dfrac{2x+3}{x^{2}+x-1}}$$
もうひとつ、こんな前振りとともに、後で名推理を見せつけてくれます。前振りから見ていくと…

微分演算子は、左から掛ける場合と、右から掛ける場合で、違う結果を出すことがあります。
$${a=b}$$ という式があって、微分演算子 $${X}$$ を左から、つまり…
$${Xa=Xb}$$
…と掛けることはできても、同演算子を右から、つまり
$${aX=bX}$$
は成り立たないケースがある、というか、たいてい成り立たない。
ポールくんはそう前振りした後、こんな名推理を披露。

こういう演算子恒等式は、たいてい成り立たないけれど…
$${aX=bX}$$
絶対に成り立たないかというと、そんなことはなくて、成り立つケースもある。それはおそらく、シュレディンガー方程式に沿った演算子の場合であろうと。
ちなみに p や q の右に小さく r とか s とかあるのは、原子における異なる二つの電子(の電子殻)をひとつの数式で取り扱いますよーという宣言です。

⇧にある数式は、
$${q_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial p}}$$
$${p_{s}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}}$$
$${p_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}}$$
$${q_{s}=-ih\dfrac{\partial }{\partial p}}$$
…から導出できます。ちなみに上の四つの式は、先ほどポールくんが提示した $${p_{r}=-ih\dfrac{\partial }{\partial q}}$$ を含む四つ子さんです。
$${p}$$ と $${q}$$ が非可換の関係つまりどちらも互いに主であり従であることを踏まえれば、どちらもコインの表裏的に同じ形式の式になることと、さらにはこれらが一つではなく二つの電子(r と s でここでは区分)のことと見れば、以下の等式がごく自然に導出されますよーと、ポールくんはスマートに述べているのです。(スマートすぎてこの議論を追う方は当時大変だったろうと想像しますが)

$${X}$$ とあるのは(ポールくんはいちいち言及していないけれど)微分演算子のことです。左ではなく右側に付いてきてもこの等式が成り立つぞ、ということは $${aX=bX}$$ が成り立つ例外的なもの ⇔ 量子力学の恒等式 と推理して、ここからさらに議論を進めて行っても、差支えはあるまい… 彼はおそるおそる、しかし自信満々にアクセルを踏み込んでいきます。
ここに[ ]の括弧が出てきますね。ポアソン括弧。ハミルトン力学で必ず出てくる括弧。量子力学が前衛とすればハミ力学は古典でしたが、微分演算子が量子力学において恒等式を生ずること、そしてそれをポアソン括弧に落としこめることから…

「量子論の恒等式は、古典論の恒等式に相通じる」と宣言し、量子力学における運動方程式は、ポールくんが定義するところの恒等式になるであろうし、ならないと美しくないと言い切ります。
本当は「美しくない」とまでは言い切っていないけれど、彼はきっとそう考えていたと私は想像します。
うーん第二章の解読、一回ではとても収まらない、次回に続くのだ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
