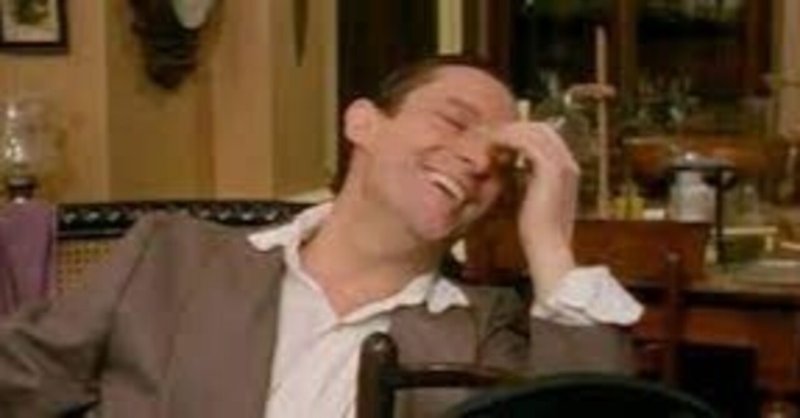
龍一教授の「Open the Door」を分析しましょ(その10)
その9からの続きです。これまでの分析の総括いきます。
映画「ラストエンペラー」冒頭。戦犯となった皇帝・溥儀がリストカットを図り、薄れゆく意識のなかでおのれの幼年期を蘇らせるという、心憎いシーケンス。音楽がとても劇的。ベルトルッチいうところの「ミゾグチ!」。
以下は楽譜の動画。
龍一の残した楽曲のなかでとりわけ分析困難といわれるこのイントロ、以下の様に3セクションに区分けして、これまで分析しました。


同じ話を繰り返すのも何なので要点だけ振り返ると…
①では旋律が半音で順下降して途中より半音の順上昇するシェイプを背骨というか推進力に置いて、下段ではゴジラがでかい図体を半歩づつ交互に前に出して前進していくようにして上昇していく。何か法則性を感じさせながらもカオスな響きが続いていく。
②では調が明確になる。Eメジャー(C♯マイナー)調。使われる黒鍵が四種類という理由で選ばれた調と思われる。旋律はドより全音音階で順下降していく。ということは調性のはっきりしたセクションになるはずなのだが、カオスな響きを保つために作曲者は小節ごとにモーダル・インターチェンジ的な変化をつけている。ド・ミ・ソの和音がけして生じないに各小節で六音音列が選ばれている。ちなみに七音音列を使うとクラスターな響きになってしまうので六音音列をもとにしているのであろう。
②’はA♭メジャー(Fマイナー)調。②と同じく黒鍵が四種類使われる調だが実際には②では三種類しか使われない。②→②’に転調する際に4→3に黒鍵の使用種類数が変化することこそがここの法則性であり、それを保ちつつ意表を突いた転調を目指したものと思われる。音楽理論でいくとE♭メジャー(Cマイナー)調こそが黒鍵を三種類使う調であるが、Eメジャー→E♭メジャー調などという先の読める転調を作曲者は避けたかったのだろう。
③で使用黒鍵種類が3から2に減る。Dメジャー(Bマイナー)調。「戦メリ」の最後の和音と同じくサブドミナント和音を使っているが、そこにさらに短三度音程と増四度音程を重ねることで、映画の主人公・溥儀のその後の人生が不安と波乱と非ヒーローな色彩に満ちたものとなることを予感させる響きを作っている。
*
こうやって箇条書きにするとつまらなくなってしまうのが悲しい。しかしこれが理解できるようなら、龍一教授がどうやってこのイントロを着想し、組み立てていったのかを、鍵盤を舞う運指の体感とともに追うことができます。

鍵盤楽器を弾けないひとは、ついてこられないかな。いいですか彼にとって鍵盤楽器は、そろばんでもあります。指先で高度な音楽的計算がなされて、それがそのまま音として現れてくるのです。ご本人による自曲解説がたいていピンボケなのは、指先での計算が高速すぎて、それをいちいち言語化する頭が追いつかないからとみます。
「いやはや、世界広しといえども、日本のサカモト教授の、鍵盤を舞う運指から繰り出されるこの音楽的魔法を支える暗号コードを、とうとう解読してみせたのは、ぼくひとりだろうねワトソンくん」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
