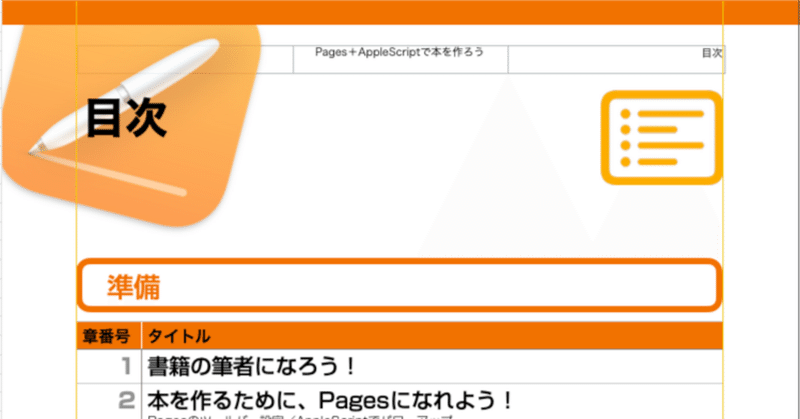
「Pages+AppleScriptで本を作ろう」を書き始めた⑧
電子書籍「Pages+AppleScriptで本を作ろう」をけっこう作り込んでいます。今月中に出る……のか?
本の部品の作り方を説明
全体は準備、実戦、応用という構成になっていて、かんたんなものから高度な内容へと徐々にステップアップする構造になっています。
当初、先頭にあった「本」に関するさまざまな知識を養う解説については、仲間内で、
「プロ編集者の養成本じゃないんだからさー」
「読者は、とりあえず本が作れればいいと思ってるんだから、そんな志の高い内容を読まされても困るぞー」
と指摘され、たしかにその通りだったので、巻末の「資料」に移動させました。このあたりの割り切りがよくないとダメだと思います。コンテンツを作るさいには熱血で、全体を見回すときには冷徹に。この切り替えが、1人で本を作っているときに難しいところです。
「見てほしい」内容と「実際に読者が読みたい/期待する内容」がズレることはよくあるので、そこは感情移入しないで客観的な目で見直すことがとても重要です。
ひととおり、本づくりに関連することだけピックアップしたPagesについての操作説明。
それをふまえた上で、表紙/目次/まえがき/登録商標表記/章トビラ/奥付/裏表紙などの「部品」についての作り方を説明しています。
奥付で出版社ごっこ!
そんな中、部屋の本棚にあった書籍の「奥付」を形式だけコピーした、ダミー奥付を作成。出版社ごとにどういう項目に特徴があるかといった、ほほえましいコンテンツを6ページほど書いてみました。
「ここに各出版社のロゴマークが入ったら説得力が上がるよなぁ」
などと考え、実際にグラフィックを配置してみたら、なかなかの出来栄え。
しかし、しかしです。
こういう「遊び」は勝手にやったらダメです。
そこで、関連する出版社の窓口を経由して、ロゴの使用について問い合わせを行なってみました。自分が連絡を受ける側の担当者だったら、判断に困るような「困った」問い合わせではあります。
反応はいろいろ……
「別にいいよ」というフランクなところから、ごていねいな「使用許可できない」メールをいただいたところまでさまざまです。
ウチは吹けば飛ぶような零細技術系同人誌ではあるものの、他のやっかいな人たちに「前例」として参照されるとやっかいです。会社側の対応は割と慎重になります。
こちらとしても、「ダメでもともと」ぐらいのつもりで問い合わせているので、打率が低くてもへこみませんが、もしもこれを打率10割にするためには、企画段階で企画意図を説明したりなんだりと、割とストロングな交渉をしなくてはならない(「今回の用途にかぎってのみ使用許可。引用や他の例には認めない」といったあたりの許諾でギリギリ?)ことでしょう。
そこまで手間暇をかけるべきものではないので、今回はこんなもんでしょう。
逆をいえば、会社のロゴを配置しなければ、レイアウトや項目自体に著作権はないので、そこは迷惑のかからない範囲でやってちょうだいね、という話にはなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
