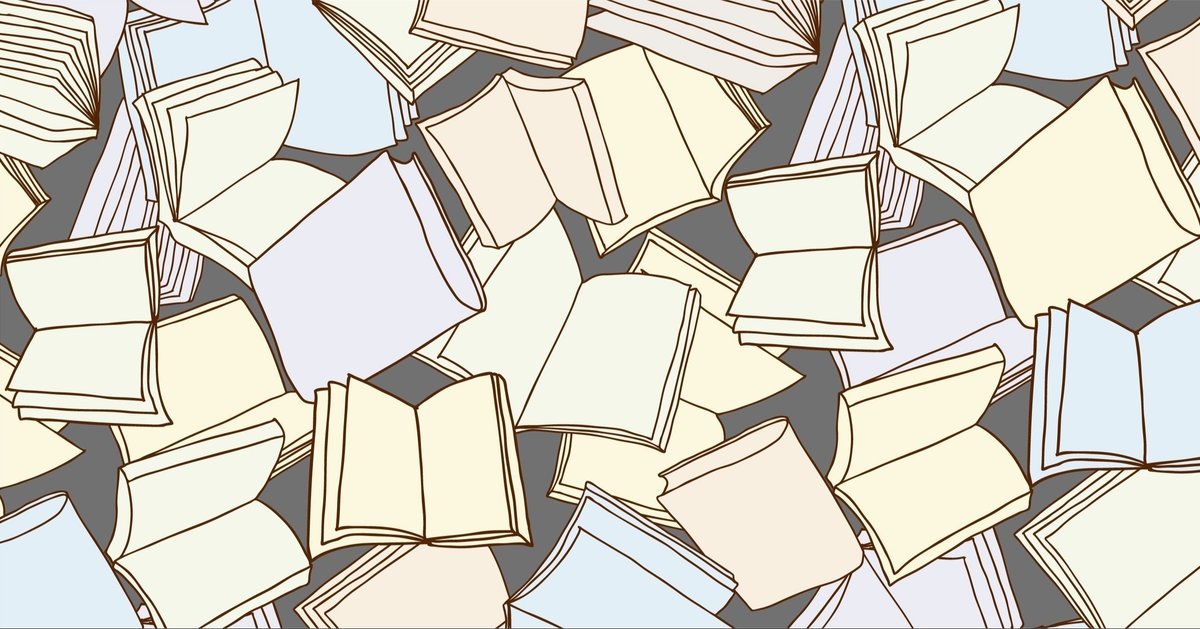
【書籍紹介】リーダーが身につけたい25のこと
皆さんこんにちは
まさまさまです。
いきなりですが本を読むっていいですね。
モチベーションが上がりますし、こんな風にアウトソーシングしたくなります。
よかったら私の自己満足にお付き合いください。
今回ご紹介する本はこちらです。
皆さんこう言われたことはないでしょうか?
「このプロジェクトは君のリーダーシップにかかっている!」
「この失敗はリーダーとしての力量が足らなかったせいだ!!」
そして思います…そもそもリーダーってなんだ??と
本誌はタイトルの通りリーダーとして身につけておきたいことを25に分けて事例も含めながら説明しています。
大きな枠組みで4つに分かれます。
第一章 リーダーになる人が最初に取り組みたい11項目
11項目の内、2つ抜粋してご紹介します。
・リーダーは聞く
話を聞くことによりメリットは3つ
1. 話を聞くことでいち早く軌道修正をすることができる
2.話を聞きアイデアを生むことができる
3.話を聞き社員のエネルギーを高めることができる
これほどのメリットがあるのになぜできないのか?という疑問が生まれます。
それはほとんどの方がこのように思っているからです。
「自分の権威が失墜すると思っている」
「自分より仕事ができない奴の話を聞いても無駄(内容)だと思っている」
「時間の無駄だと思っている」
全てが思っていることです。
メリットと全て逆のことを思っていますね。
そこで立ち戻って「リーダーシップ」という言葉を振り返ってみます。
リーダーシップ:1人では実現できない何かを実現したいと思い、他社に働きかけ、協力を仰ぎ、その実現を目指す力
さぁあなたがすべきなのは話を聞くことでしょうか?聞かないことでしょうか?
一目瞭然ですね!
ただし“全て”を聞く必要はありません。
用件をまとめることができていない話はしっかりと注意しまとめてあげることは大切です。
聞く聞かないのメリハリをしっかりとつけていきましょう!!
・リーダーは誘う
リーダーの中に「メンバーはついてきてくれる」と思っている人がいますがそれは大きな間違いです。
背中を見せるだけでついてきてくれるメンバーは稀だという認識を持つべきです。
リーダーから声をかけて誘ってあげることが大切です。
でもついてきてくれるという認識の方が多いので「誘う」ということに慣れていない方が多いのではないのでしょうか?
「誘う」に当たって大切なことはこちらです。
1.どのような内容でも構わないので「誘う」ことに慣れる
→ご飯でも遊びでもなんでも良いのでとりあえず誘うということに慣れることが大切です。
2.誘いの制度を高めるためにイメージを詳細に語る
→誘った後のイメージを相手に鮮明に印象付ける
3.それを実現することの相手にとってのメリットを語る
→実現後、相手がどのようなメリットを得るかを明確に伝える
この二つが私に特に響きました。
もちろん残りの9個も納得の内容が記載されてますのでぜひ確認してみてください。
第二章 部下のリーダーシップを育てる4項目
第二章では部下のリーダーシップを育てる項目の説明です。
こちらも一つだけ抜粋させていただきます。
・リーダーは約束を守らせる
約束しているよ!って方は多いと思いますがほとんどの方が指示だけで終わっているのが現状です。
例えばこのような会話はよくあっていると思います。
売り上げの悪い部下「毎日営業のロープレを行います!」
あなた「わかった!頑張れよ!」
これは決して「約束」したということではありません。「宣言」に近い状態です。
それでは約束するというとどのようなことでしょうか?
しっかりと「約束」をすることが大切です。
続けてこう言って見てください。
あなた「毎日ロープレすると約束できるか?」
部下「約束します!」
もちろん事前に約束を守ってほしいとしっかりと伝えておくことが大切です。
日本人は言語化することが苦手です。
阿吽の呼吸であったり言葉にしないことが美しいなどは確かにありますがしっかりと言語化しコミュニケーションをとることを意識するだけで受け手の印象が変わるのでぜひ意識してみてください。
第三章 自分自身とチームの主体性を高める10項目
・リーダーは組織の緊張感をコントロールする
組織の中で緊張感というものは大切です。
ただずっと緊張感がある組織というのもベストパフォーマンスは出せないですよね?
著者は「成功するリーダーの条件は怖くて、優しいこと」と述べています。
私も経験上、言い得て妙だなと思いました。
適度な緊張感を生むためにはリーダーのこれだけは譲れないという軸が必要です。
その軸がないまま組織を束ねていると様々な理由で信頼を失い、緊張感しかないor緊張感のない組織となってしまうため軸をしっかりと定めることから始めましょう。
・リーダーは反応を自分で選択する
「反応」と聞くとイメージしやすいの反射神経だと思います。
勝手に対応してしまうなどが一般のイメージですが対人でのコミュニケーションの場合、実は違います。
人から何かしら刺激を受けた場合、自身が反応するまでに「間」があります。
かの有名な『7つの習慣』での第一の習慣、主体性を発揮するでも紹介がされている内容です。
そして自分自身が反応を選んでいるのです。
例えばこのような経験はないでしょうか?
同じような指摘を受けた場合、Aさんに言われると納得するがBさんに言われると納得できず反発したくなる
これは同じ刺激に対して明らかに自身が反応を選んでいます。
当たり前のことではあるのです認識することが難しいことでもあります。
ただこれはトレーニングすることができます。
自身の反応で相手がどのように対応してくるようになるのか、しっかりと刺激と反応の「間」に考えるだけでとても組織を円滑に運営することができるようになります。
・リーダーは情熱を自分で生み出す
最後は情熱(やる気)についてです。
当たり前のことですが途中で忘れがちなことです。
やる気というものは基本外部からの要因ではなく内部からの要因で生まれるということです。
日々の仕事や業務などに忙殺されて忘れてしまうことが多いでのでしっかりとセルフコントロールを行い、自分自身に問いかけてやる気を思い出すことが大切です。
最後に
いかがだったでしょうか。
さらに著者は巻末にぜひ読んでほしいとリーダーシップに関する書籍を50冊紹介しています。
それほどリーダーシップを研鑽していくことは簡単ではないということです。
この本は定期的に読み返すことによりその時その時に響く項目が変わるのではないかと思います。
ぜひリーダーとして悩んでいる方などは読んでみてください。
この記事が皆さんのお役に少しでも立つことができれば嬉しいです。
ではまた
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
