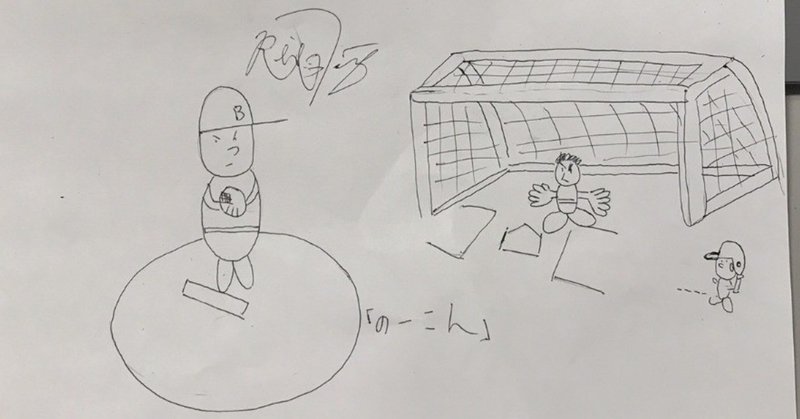
Welcome to the BatFlips! 草野球チームのユニフォームをデザインしました。
こんばんは、TJです。もうクリスマスですね。最近は11月始まってすぐぐらいから街中が柔らかい電飾に彩られているので、ざっと1年の6分の1をクリスマス気分で過ごすことができますよね。便利な時代になったものです(は?)
さて、今回は #uniformers 案件です。いや、 #バットフリップ部 案件なのか…?(知らない方はそれぞれTwitterでタグ検索してみて下さい。このnoteを開く勇気の持ち主なら多少は楽しめるかと)
更新をサボってはや5ヶ月の『さくさく読めないNPBユニフォーム史概略』もさっさと新しいのを完成させたいところですが、まあそれはいったん置いときましょう。
また自分語りnoteで申し訳ないんですが、部活の後輩が引退後にOB中心で草野球をやるためのチームを立ち上げてくれました。その名も「待兼バットフリップス」。チーム名を決める時にノリで提案したらうっかり通ってしまって焦りましたね。現状チームにフリップパーソンはぼくひとりなので、われこそはという方がいればぜひ参加して頂きたいものです。大阪の北の方を中心に活動予定です。
で、チーム名を決めたついでにユニフォームのデザインも担当させて頂けることになりました。というか誰もデザイン案を出さなかったので、意欲にあふれるぼくが一方的に決める形に。Twitterでプロ野球チームのユニフォームを上から目線で語っている手前、しょうもないデザインを発注してチームメイト(主に後輩)の顰蹙を買うわけにはいきません。一念発起して作り上げたユニフォームがこちら。



かわいい…。今どきのJKがこう言うのかは知りませんが「チョーカワイイ」です。カワイイですよね?あんまり言うとカワハラになって訴えられかねないのでこの辺にしておきますが、とにかく自分でデザインしたユニフォームを着用して野球をやるというのは(まだやってないんだけども)、それはそれは心躍るものがあります。ぼくは嬉しさのあまり家に帰ってから一人でユニフォームを着用してはしゃいでいました。もう少しでそのまま外出してしまうところだったのですが「さすがに学校の敷地の外だしやばい」というリミッターが正常に作動したので耐えました。まあ研究室でもこっそり着てたので一緒かもしれませんが。
というわけでですね、今回はそのユニフォームのこだわりポイントを、参考にしたプロ球団のユニフォームを紹介しながら振り返っていく回にしていきたいと思います。バットフリップスに興味のない皆さんも、これを読んでユニフォームのデザインに興味を持っていただければ幸いです。
メインカラーの選択と制約
まずは土台になるカラーデザインの選択。が、ここに関してはある程度制約が掛けられていた。先述の通り立ち上げたチームは筆者が所属していた部活の延長で設立されたもので、メンバーも多くが同部のOB。ユニフォームの上下両方をデザインすると費用はバカにならないし、アンダーシャツやソックスも今持っているものをそのまま使える方が安く済む。というわけで、アンダーシャツ・ソックス・ベルトはネイビー一色、パンツは白の練習用を着用することで基本方針が決まった。あとはこれに合うような上とキャップをデザインすることになる。
また、ユニフォームはZETTの昇華プリントオーダーシステムを利用してデザインすることになった。ユニフォームnoteやTwitterをご覧の皆さんはご存知だろうが、TJは昇華プリントのユニフォームには(少なくとも野球に関して)否定的な立場を取っている。
昇華プリントだと冒頭みたいな背中アップのカットで背番号がクシャっとなるんですよね。やはり中継のあるプロの番号とネームだけは縫って欲しい。
— TJ (@11_tjr) September 13, 2019
※意見には個人差があります#uniformers https://t.co/zfN0QnwO3A
が、刺繍・ワッペンにすると高くつくし、製作・到着にも時間が掛かる。自分のわがままで重厚感を追い求めるのもしょうもないので、ここは昇華プリントでも映えるデザインを!という意気込みでアイデアを出していく。
ボタンデザイン
ユニフォームのデザインはいくつかパターンがあり、カラーリングを変更できる箇所がそれぞれで異なるというシステム。まあよくわかんない人はさっきのオーダーフォームを覗いてみて下さい。
まず重要なのがボタンのデザイン。ボタンが縦一列についていて前が開くようになっている、要は普通のスタイルと、ボタンが1つないし2つで着脱が容易なプルオーバータイプから選択する。中日や西武のようなラケットライン(前立てライン)を採用するなら前開き型でもいいだろうが、近年になってこのラインを廃止する球団が続出、トレンドもこちらに向かっていく可能性が高いとみてプルオーバータイプを選択。昇華プリントなので前立てラインを採用してもどうしても厚みが出せず、シワができるとグニャっと曲がってしまう点もこの選択を後押しした(昇華プリント×ラケットラインの西武やソフトバンクのユニフォームをdisrespectしているわけではない、念のため)。
午後から雨の影響で室内練習に変更。#木村文紀 選手はマシン打撃に取り組みました!後半からはユニフォームを脱ぎシャツ1枚で練習継続!外の肌寒さを感じさせない熱気で一心不乱にバットを振り続けていました!#南郷秋季キャンプ #seibulions #NPB pic.twitter.com/fCD6LY8QWU
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) November 16, 2018
地色、カッティング
次にユニフォームの土台を造るメインカラー、そしてカッティング(※)を含めた基本デザインを決めていく。前述したように、ユニフォームは刺繍ではなく、昇華プリントでオーダーすることが決まっていて、TJが大好きなシンプルすぎる王道デザインはペラペラして重みが出せない。カッティングを適宜取り入れて遊んだものがいいだろうと判断した。
※カッティングとは
パーツごとに異なるカラーを採用するスタイル。NPBでは2000年代後半にこのスタイルが大流行。現在でも日本ハム(後述)・西武ビジター用、ロッテビジター用などでこのスタイルが採用されている
ボタンデザインはプルオーバー式を採用したため、ラケットラインもここでボツ。繰り返しになるが、昇華プリントの前ボタン・ラケットラインスタイルはどうしても安っぽく見えてしまう。プロ野球の来場者特典として配布しているユニフォームをイメージしてもらうと分かりやすいだろう。同じ理由でストライプも却下。
パーツごとに色を変えるカッティングスタイル、そして前立てラインなしのプルオーバーデザイン。この基本線を考える中で頭に浮かんだのが、北海道日本ハムの左右非対称デザインである。NPBでは非常に珍しい左右非対称型のユニフォームは、そもそもパーツごとに色を変えるという発想なくしては生まれ得ないもので、今回の制約を考えるとぴったりのスタイルと言えよう。
引退記念特番「ありがとう田中賢介~仲間たちと歩んだ道~」GAORA SPORTSで10/30(水)午後5時30分放送。
— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) October 28, 2019
ぜひご覧ください。https://t.co/VIFRAp8V9e
👉https://t.co/ofWuWBRzbv pic.twitter.com/RqiRRPUdaB
あくまで目標は「適度に遊ぶ」なので、あんまり遊びすぎても取っ散らかってしまう。やはり基本のカラーリングはシンプル路線を貫きたい。ベースカラーが白なのは、そんな思いの表れである。ただの白ではなく、迷彩気味の模様が入ったカラーを取り入れることで、遊び気味のデザインからも浮かないように配慮する。カッティングのカラーにはアンダーシャツと同じネイビー、どことなくオリックスを意識したゴールド、そして同じく迷彩模様の入った落ち着いた赤色を挿入。後述するが、迷彩・濃い目の赤を使用したことが全体との調和に重要な役割を果たすことになる。


文字書体
続いてはユニフォームの顔とも言える、胸文字の書体を考える。個人的な印象だが、プルオーバー・ラインナシのプレーンなユニフォームには筆記体が似合う。ラケットラインやストライプ、前ボタン式のデザインが、ユニフォームの"タテ"を意識させるのに対し、プレーンなユニフォームは"ヨコ"を意識させやすいデザインだと感じる。
縦書きやワンポイントの胸文字もどちらかと言えば前者寄り。ラケットラインを避ける形で配置できるのが大きい。プレーンなタイプにも対応できて個人的には好きなデザインの一つ。そもそも縦書きはアメリカでは生まれ得ないスタイルでもある。
横一列に並んだアルファベットを一筆で繋ぐ筆記体はまさにうってつけの存在。メインカラーのネイビーに、シルバーの縁取りを添えて採用した。
ここでちょっとだけ私情を挟む。筆者がNPB12球団の歴代ユニフォームの中で最高傑作だと考えているのが、"魔術師"三原脩が率いた西鉄ライオンズのユニフォーム。シンプルなデザインに厚みを持たせているのが、"Lions"の胸文字に採用されている飾り文字である。球団が公式で動画をリリースしていたのでこちらを参照してもらいたい。
筆者のバカみたいにアツいライオンズのユニフォームへの思いはこちら。
どうしても飾り文字を使いたい。でもチームの反応を見ると筆記体の支持者がほとんど。というか全員。
(勝手に)窮地に追い込まれた筆者に救いの手を差し伸べたのが冒頭の画像で紹介したこのフォント。基本的には筆記体のデザインを採用しつつ、先頭の1文字目だけが飾り文字フォントとして独立している。先頭のBをよく見ると、飾りの部分がなんとなくFっぽくて"BatFlips"の頭文字っぽくもあるので、怒られた時にも言い訳しやすそうだ。オーソドックスな筆記体をこちらの書体に変更して最終版を発表したところ、特に異論が出なかったので意気揚々と採用しておいた。


本当はFlipsのFも大文字にして、TBSベイスターズのBayStarsみたいな2単語スタイルにしたかったのだが、うまくいかなかったので泣く泣く没。
背番号・胸番号カラー
一つの項にまとめてしまったが、背番号と胸番号の役割は根本的に異なる。特に背ネームのないユニフォームでは、後ろ姿の見映えを決定づける"核"として働くのが背番号。一方胸番号はチーム名の下に添えられており、正面から見た図にアクセントを加える役割が主で(もちろん太平洋クラブのような例外はある)、それ自体が主役になることはない要素である。従って、当然それぞれに求められるデザインの主張具合は異なるはずである。
このポリシーを元に、採用したのは中日ドラゴンズ、というよりはロサンゼルス・ドジャース意識のデザインである。背番号にチームカラーのドジャー・ブルーを採用しているのに対し、胸番号は派手な赤。この赤色が、正面から見た時の印象をガラリと変える要素として機能している。
MVP? YOU BETTER BELLI-EVE IT. pic.twitter.com/hKCvHpCkgS
— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 14, 2019
偶然(なわけないが)チームカラーも青系ということで即座にこのデザインを採用。背番号はチーム名と同じネイビー×シルバーを使用、胸番号にはエンジ色を使ってほのかなドジャース感を漂わせることにした。




同時にこだわったのは番号の書体。最近はオーソドックスな角文字全盛の時代で、阪神伝統の丸文字、横浜ベイスターズのカッパープレート書体、レジェンドブルー変更当初の西武の○キった丸文字など、特徴的な書体が姿を消す流れにあるが、筆者はそんな流れに抗い、角文字をナナメにカットしたような不気味な書体を採用。手書きっぽさとも異なる独特の書体で味を出しにかかっているが、評価されるかは不明である。
ロゴマーク
一番こだわったと言っても過言ではないのがロゴマーク。ZETTのオーダーシステムを利用したので、そのロゴマークを左胸上部にプリントするオプションが表示されていた。別に使わなくてもいい機能で、実際ほとんどの利用者が使っていない気がするが、今回はあえてこれを採用。
こだわりポイントはそのカラー。選ばれたのは白。迷彩入りのデザインなので辛うじて見えなくはないが、要は白地に白の一番見にくいカラーチョイスである。

なぜこんなことをやっているのかは自分でもよく分かっていないが、意識の底にあるのはオリックス・ブルーウェーブの「見えないラケットライン」である。
『さくさく読める~』シリーズでも取り上げる予定だが、イチローが去った後のオリックスは、ビジターユニフォームでオリックス・ブルー(要はネイビー)の地色にオリックス・ブルーのラケットラインを乗せるという斬新なスタイルを採用していた。現地観戦時はおろか、TV中継を見ていても目を凝らさないと見えないラインの存在は、筆者に大きなショックを与えた。綱島理友さんの書籍を読むまで知らなかったし。
正直意図は全く読めないが、見えないところにこだわる姿勢は江戸っ子気質に通ずるところがあってすごくイイ。神戸のチームだけど。さすがにラインを白で~というのは反発を買いそうなので、今回はこのロゴマークにその意匠を取り入れたというわけである。
なお、オリックスは合併後のサードユニフォーム(ゴールドのやつ)でも同様の見えないラケットラインを採用している。
【ニュース】オリックス・バファローズでは、新たに第4のユニフォームを追加し、来シーズンよりユニフォームをリニューアルすることとなりましたので、お知らせいたします。 http://t.co/libV1S77mS #bs2014 #npb pic.twitter.com/xrkzdxXTl5
— オリックス・バファローズ (@Orix_Buffaloes) November 24, 2014
キャップ
ユニフォーム本体についてはここまで。最後にキャップをデザインした。ユニフォームのデザインが完成してからそれに合わせる形。


かわいいなあ。まあそんなに選択肢もないので、基本的にはカラーデザインがメイン。が、マークが刺繍なのもあってまあまあいいお値段をなさるので油断はできない。
とりあえず本体はチームカラーと同じネイビーで行くとして、問題はツバの部分。同色にしてもいいだろうが、本体にゴールドやら赤やらを入れているのに一色というのは硬すぎる感じもある。
そこで白羽の矢が立ったのはエンジ。複数色を使いつつ、雰囲気を浮かせないためにはもってこいのカラーであり、胸番号にも使用されているので相性もよさそう。あと最近気づいたのだが、野球ファンは総じてエンジ色が好き。早稲田系列のユニフォーム人気は言わずもがな。
ちなみに個人的な順位は
— あまなつ (@MattDavidson91) December 15, 2019
1位テキサスA&M大(1枚目)
2位テキサス工科大(2枚目)
3位オーバーン大(3枚目)
4位ベイラー大(4枚目)
です。 pic.twitter.com/XmU8WX8ddC
マークはアルファベット一文字しか使えなかったので"BatFlips"の"B"を採用。書体は当然飾り文字である。一文字になると余計に飾り部分のFっぽいところが活きてくる気がするし、まあいいだろう。天ボタンと穴はエンジを採用する小ネタを仕込む。
唯一メンバーから要望が上がったのはツバの形。筆者は割とどっちでもよかったが、いわゆるストレートキャップ(平ツバ)がいいらしい。最近はNPBの日本人選手にも使用する選手が増えていて、時代を先取りしている感があっていいので採用しておく。

そのほか、ツバの縁取りのカラーを変えるというオプションもついていたが(アディダス配給時代の巨人みたいなやつ)、「落ち着いたデザインにはあまり手を加えすぎるな」という自身の言葉を思い出し、下手な真似はしないようにする。
見えないところを凝る精神がチラッと顔を出したのはツバ裏のカラー。グレーが一般的だが、選べたのであえてブラックを選択。「一笑懸命」だの「勘とは経験の集積である」だのとクサいことを書くやつを一掃することができて一石二鳥だ。

また、キャップを2色にしたことの副産物として、ヘルメットとのデザインの差別化を図ることができた。筆者がこっそりゴリ押した艶消しタイプのヘルメットはネイビー1色。キャップとのデザインが大きく異なるため、攻守で印象がガラッと変わる仕様が実現。これでやりたいことはほとんど実現できたと言っていいだろう。刺繍ユニにするのはお金持ちになったらまた目指すことにする。
まとめ
以上が今回のユニフォームデザインにあたって、筆者がこだわった「説明しないと分からないポイント」である。全体的に遊んだデザインを採用しつつ、色味はやや落ち着いたものを使用することでシックな感じも出せたのではないだろうか。
後述すると言ってしていなかったが、実際に仕上がったものを見られないネットオーダーシステムを利用する過程で最も気にしていたのが、本体のカッティングに差し込んだ迷彩の赤色が目立ちすぎないかどうかである。ネイビーを基調とし、第二のカラーにはエンジを織り込んでいた今回のユニフォームの中で、この赤色があまりに目立ってしまうと全体的に浮足立った印象を与えてしまう。ここに関してはもう賭けであったが、何とかイイ感じに仕上がってくれて感謝している。
今回はこんな感じです。初めて自分でユニフォームをデザインした感想を書いておくと、「シンプルに楽しい!」ですね。自分で着るものをパーツごとにデザインして~という機会自体がそうそうあるものではないですし、貴重な体験だったと思います。気分はまさに我が子を見つめる母親です。まあそれはさすがに冗談じゃないですが、チームのメンバーにも好評のようで何よりです。
ちなみにですが、ぼくは色彩やらデザインに関して全くの素人であります。何色と何色を組み合わせたらどうなるみたいな知識は一切ありません。そんな小人でも楽しく、しかもそこそこのコストでデザインを楽しめるという点では非常にリターンの大きい遊びだと思うので、近々に草野球チームを作ります、みたいな方はぜひチャレンジしてみることをおススメします!
おまけ:今回のおんがく
まあユニフォームをデザインということでね、ズバリ『CUSTOM』です。あんまり関係ないんですが、奥田さんが今はなき広島市民球場でライブをした時のサイドストーリーという設定で製作された『カスタムメイド10.30』という映画がまあまあ楽しいので、興味のある方はぜひ。主題歌の『トリッパー』も良いです。木村カエラさん主演。
#野球 #プロ野球 #草野球 #ユニフォーム #デザイン #バットフリップ部 #uniformers
貨幣の雨に打たれたい
