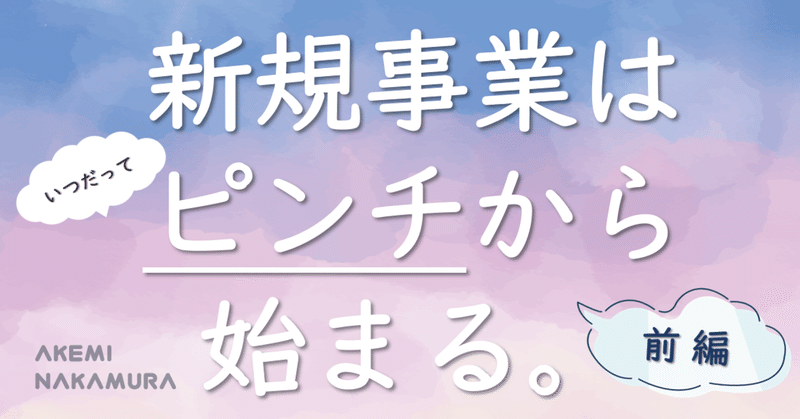
新規事業はピンチから始まる|アフターコロナの新規事業、作りました【前編】
コロナの影響で佰食屋は2店舗を閉鎖。その打撃で、思わぬ新規事業を発見する事になります。そんな、ピンチを新規事業へとつくりかえた私たちの1年7か月について、前編と後編に分けてお伝えします。
■2店舗閉鎖と口では簡単に言えるけど。
前回のnoteでお伝えしました通り、私たちは2020年4月11日に2店舗を閉鎖しました。
その時の様子は、2020年6月30日に放映されたガイアの夜明けでも密着していただきました。実際、このコロナでは多くの飲食店が閉店・廃業することとなりました。
2店舗閉鎖と口で言うのは簡単ですが、実際に閉鎖した後にどんな仕事が降ってくるのでしょうか。
テナントの解約通知
契約終了の手続き
保証金の返還請求
退去の立ち合い
水道・電気・ガス・電話の解約手続き
飲食店営業許可の閉業手続き
各納品業者への閉店のお知らせ
テナント撤退に伴う片付け
ゴミ廃棄と掃除
退去の際にスケルトン渡しにする場合は工事
町内会・商店街組合脱退手続き
近隣店舗へのあいさつ
お店を開業するときも同じ事をするのですが、開業するときのワクワクしたテンションとは相反して、謝罪やお別れの言葉、悲しい気持ちや残念な気持ちの中でひたすら進めていかないといけません。
商店街組合の皆様や近隣店舗の皆様には引き留めていただいたり、テナントのオーナーさんたちからは「残念だけど、また復活したら借りてな!」と応援していただいたりと、何度も涙を流しそうになりながらも、淡々と作業として続けていました。(ちなみに片付けの際も周囲の店舗さんが台車を貸してくださり本当に親切な人ばかりでした…泣)
■一番つらかったのは、身体。
こうやって閉店の片づけを進めていくわけですが、全ての「モノ」を撤去しなくてはいけません。客席の机・椅子・食器・厨房機器・調味料・電話機・掃除道具など、挙げればきりがないほどモノが沢山あります。
その量、
1店舗につき2トン。

この2トンのごみを、退去する2週間後までにすべて処理しなければいけないという非常に厳しいミッションに取り組む必要がありました。しかも、閉店したのは2店舗。つまり、たった2週間で4トンのごみを処理しなければいけません。
従業員にはお店の仕事を任せていますので、助けてもらうわけにはいかない。退去にも様々な費用がかかり、コロナ禍ですでに赤字に転落しているので、外注してお金をかけて片付ける余裕もない。
この合計4トンのごみを、私と私の夫のたった2人で処理するというミッションに挑むことになったのです。
もちろんごみの処理はパッカー車にお願いをしないといけない部分もあるのですが、京都市はパッカー車であってもごみの分別をきっちりしないといけないので、パッカー車への積み込みの際も分類ごとに積み込みます。木材・プラスチック・食器など。
鉄は捨てるよりも買い取ってもらえる場所があるため、椅子の脚や机の脚に使われていたアイアン部分をバラして、全て鉄だけ集めて(磁石がくっつくかどうかを確認しながら)車に積み込み、何度も鉄回収業者さんのところへ搬入しました。(鉄回収工場では、超大型磁石で鉄を動かすなど、大迫力の現場でとっても楽しかったです…!)

朝子どもたちを幼稚園に送り、夕方迎えに行くまでのタイムリミットまでの間、ひたすら2週間毎日、休憩も食事も忘れて作業に打ち込みました。
どのごみを運ぶのも重く、家具を解体するにも専門の工具が必要で、てのひらは痛くなり、腕はずっと筋肉痛、体力は消耗し、夜は毎日死んだように眠る日々。それでも、やらないといけないことがある。

食事を取る間も惜しいけれども、食べないと身体がもたない。重いものを運ぶ力が出てこない。だからこそ、この期間は毎日「プロテインバー」というタンパク質が多いチョコレートのバーだけを買い込んで、作業をしながら食べるという日々を過ごしました。
そうやって、私たち夫婦は2週間で4トンのごみを片付けるというミッションを乗り越えたのです。この2週間で夫婦2人合わせて体重15キロ減り、私はストレスによる脱毛症で驚くほど髪が抜けた、と聞けば、どれぐらい大変だったか想像できると思います…(最近やっと抜けた髪が10㎝ぐらい生えてきた。)


■有益な情報は、内閣府の調査結果から。
さて、この片付けをしている間に、身体はしんどい一方で、思考は自由でした。片づけをしながら色んなことを考え、想像し、思いを馳せる時間がたっぷりあったわけです。
何度も挫けそうになったこの片付けという大変な作業を、ただ「大変だった」で片づけるのはもったいない。何か今後に活かすことはできないだろうか?誰かの役に立てることはできないだろうか?ということをただひたすらに考えていました。
そんな時に、この片付けの作業は「災害復興の片づけに似ている」ということに気づいたのです。
洪水等で床上浸水した際に、家財道具が使えなくなって家の前に搬出する作業、地震で食器や家具が部屋の中にぐちゃぐちゃになったのを片付ける作業。

私たちの今の経験は、もしかすると「災害対応」に役に立つ可能性があるのでは…?そんな思いが駆け巡り、居ても立っても居られない、いろんな情報収集をしよう!と行動に出たわけです。
思いついたらすぐ行動、やりたいと思ったら他の物を差し置いてでも行動してしまうタイプの性格です。子どもたちを寝かしつけした後、疲れた身体にむち打ち、眠い目をこすりながら様々な情報収集をしました。
そこで出会ったのが、このグラフ。
27年前、阪神淡路大震災の際に生き埋めになった人がどうやって救助されたのか、という内閣府の調査結果です。災害時、生き埋めになった人が誰に助けられたのか?と聞かれたら、通常「レスキュー隊」と想像しがちですが、内閣府の調査結果はその想像を裏切るものでした。

「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」より内閣府作成
自力、家族、友人など、自助・共助による救出が97.4%だったのです。
つまり、大災害が起こったときは、レスキュー隊の到着が間に合わず、みんな自分たちで力を合わせて救助しているということになります。
私たちの店舗閉鎖片付けの経験と、この調査結果から、私は1つの結論にたどり着きました。
結局、人を救うのは、筋力だ。
生き埋めになっている人を助けるということは、重い瓦礫を除去しなければいけない。倒木を動かしたり、意識のない大人を担いで運んだりする必要があるかもしれない。その時に必要なのは、停電していたら使えないような特殊な道具や機械よりも、すぐに使える「筋力」なのではないか、そう結論づいたわけです。
■アイデアが、ビジネスになる瞬間。
そもそも防災訓練や防災に係る意識を高める必要があることは頭ではわかっていても、災害は頻繁に起こることではないので、どうしても非日常的になってしまいます。毎日防災のことを考えて生きている人は少ないでしょう。
一方、筋力についても、一部で毎日筋トレをしている人がいる一方で「今日は疲れたからやめておこう…」「ダイエットは明日から!」と、毎日継続が大切なことを頭で理解していても継続できない人も多く存在します。
しかし、この「防災」と「筋力」をかけ合わせれば?
災害時、大切な人を助けるために筋力が必要だという意識が広がれば、筋トレをする目的意識ができるのではないか。
毎日の筋力アップが、いざという災害時に大切な人を救うことに繋がると意識すれば、毎日の継続が可能なのではないか。

これは、日本の未来のためになるかもしれない。そこで、私は1つの商標を出願することに決めたわけです。
それが、
防災筋力®

2020年4月11日に2店舗の閉鎖を決断してからわずか3か月後の2020年7月、私は【防災筋力®】という言葉を商標出願、そしてそれから1年1か月後、無事この商標を取得することになります。
防災筋力®をビジネスに。
その詳しい内容は次回、後編で。(12月3日金曜日公開予定)

★
新規事業はピンチから始まる
|アフターコロナの新規事業、作りました【前編】|
でした!
★
株式会社minitts
代表取締役 中村朱美
★
Thanks!!
★
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
