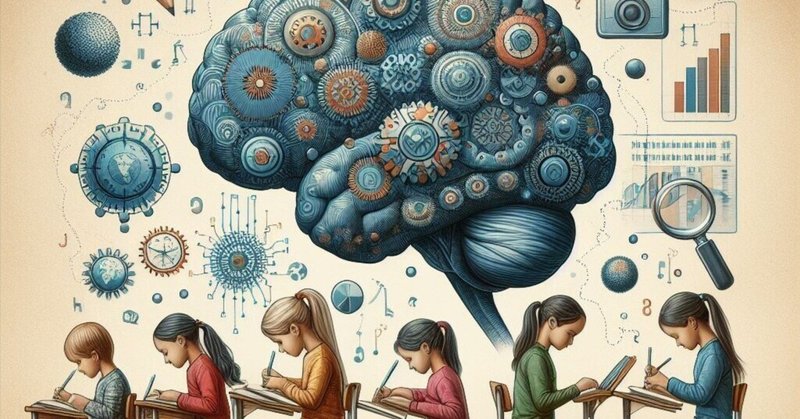
「知性を数値化したい」という人間の欲望
SNSなど見ていると、IQ (知能指数/Intelligence quotient)という概念があまりに無批判かつ盲目的に使われているように感じます。
実際のところ、現在確立されている知能テストも、歴史的・文化的・政治的な影響を経てご都合的に今の形になっているものでしかありません。
しかも、その設計思想を辿ってみると、実はそんなに高度な能力を測ることを目的としたものでもないようです。
この記事では、「知能観」が歴史の中でどう成立してきたか、どのように現代的な知能テストが生まれたかを解説します。
中世までの知能観
紀元前の詩人ホメロスは
「知能は一部の人に与えられた才能である」
と考えました。
そして16世紀に生まれたシェイクスピアは、
「ある問題を解ける人と解けない人がいる」
という事実を指摘しました。
ここから見て取れるのは、「賢い人と賢くない人」という二分法です。
中世頃まではこの素朴な知能観がごくありふれたものだったのでしょう。
生物学的性質としての知的能力
良くも悪くも有名な近代知識人として、フランシス・ゴールトン(Francis Galton: 1822-1911)という人がいます。
彼は間違いなく「賢さを測る」ための学術的基礎、すなわち心理統計学を築いた一人ですが、同時に「優生学」の始祖ともなった人物でした。
彼の足跡から「知能」概念の成立を見ていきましょう。
ゴールトンは裕福な家の生まれで、若い頃は医学や薬学や数学を学んでいました。父の財産を相続してからは地理学や気象学に打ち込み、顕著な業績も複数挙げています。
そんなゴールトンが「人間」に目を向けたのは、1859年に出版されたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』がきっかけだったと言われています。
実はゴールトンは、進化論の始祖であるダーウィンの従兄弟でした。
しかも医学統計学の祖であるフローレンス・ナイチンゲールも親戚だということですから、恐ろしい知的エリート家系です。
ゴールトンは、様々な知的能力を数値として測定することに情熱を注ぎました。
その過程で、相関係数や平均への回帰など統計学的に重要な貢献をしています。
心理学におけるゴールトンの功績を一言でまとめるならば、
「知能もまた生物学的な個体差であり、それは身長や体重のような生物学的パラメータとよく似た手法で扱うことができる」
というパラダイムを打ち出したことだと言えるでしょう。
しかし、その「目的」が何であったのかを、現代の我々は一歩引いて慎重に眺める必要があります。
ダーウィンが発見したことは
「生物の形質は遺伝する」
ということでした。
ゴールトンはこれに
「知能もまた遺伝子によって決まる生物学的な形質である」
という命題を乗せました。
この2つの命題から導かれるのが、ゴールトン自身が著書名にも採用した『Hereditary Genius(遺伝的天才)』という考え方です。
ゴールトンは、「優れた遺伝子を選択して残すことで、優れた知能を持つ人間を増やすことができる」と想定し、そうすべきだと主張したのです。
こうして、ゴールトンは優生学の開祖となりました。
知能テストやIQの話となると、現代でも「優生学的である」として批判されることがありますが、この批判も学問の源流を辿るとあながち的外れとは言えないわけですね。
近代的生物学の祖であるダーウィンの進化論をゴールトンが心理統計学に基づいて発展させた結果生まれたのが「優生学」なのだとしたら、「知能テスト」はその本質からして「優生学的思想に繋がるものである」と批判されるべき運命なのでしょうか?
それとも、ゴールトンには何か見落としていたものがあったのでしょうか?
ここに私が確たる答えを提示することはできません。
近代的知能テストの発明
公教育が知能テストを求めた
ゴールトンは人間の知的能力を様々な方法で測定して功績を残しましたが、「ゴールトン式知能テスト」は現代に残りませんでした。
彼は「知的能力は生物学的に規定される」というテーゼに重心を置くあまり、例えば「脳容積」や「単純な反応の素早さ」といった低次のパラメータに焦点を絞ってテストをデザインしました。
後世から見ると、こうしたパラメータは知能とはわずかに相関するのですが、それほど強い相関は持たないのです。ましてやゴールトンの時代には現代ほど測定精度が良くなかったので、こうしたアプローチはゴールトンが理屈から考えていたほど良い検査にはなりませんでした。
理論が立派でも、それが「意味のある知的能力の差」を十分に検出していなければ、実用的とは言えません。
近代的な知能テストを最初に考案したのはアルフレッド・ビネー(Alfred Binet: 1857-1911)でした。
彼の知能テストが生まれたのは時代の要請によるものであり、「時代の要請に答える」という目的にプライオリティを置いたからこそ(ゴールトンの理論先行のテストとは対照的に)、その有用性を認められて現代まで生き残ったとも言えます。
フランス革命(1789年)、7月革命(1830年)、2月革命(1848年)を経て、19世紀のフランスは「市民が統治する国」になりました。
そして、普通選挙制による民主主義が実現しました。
こうなると、市民の教育が重要な問題となります。
生まれつき職業が決まる社会であれば、誰もが自分の役割をこなすだけで十分でした。
貴族は貴族として、商人は商人として、農民は農民として生まれます。
そういう時代には、教育を受けるのは比較的上流の階級の人々だけでしたし、そこでは「他の子と比べて出来が良いか悪いか」などということが問題になることはあまり無かったはずです。
農民や職人に関しては、大抵の仕事は「手を動かしながら覚える」ことができれば十分で、勉強が出来ることはそれほど重要ではなかったでしょう。
「普通教育」の実現によって、人類は未知の問題に遭遇しました。
フランスで19世紀後半に始まった普通教育は、同じ年齢の児童全員に教育の機会を与えることになりました。ここへ来て「知的能力には個人差がある」ということが如実に明らかとなったのです。
特に問題となったのが「普通の子と同じ早さでは勉強についていけない子」の存在です。
こうした「勉強についていけない子」をなるべく統一的な形で就学前に検出することが出来ないか?
ビネーに与えられた問題は、ゴールトンとは対照的に、極めてプラグマティックなものでした。
知能テストの祖、ビネー式テスト
「子供の知能を測る」ことが目的であったため、ビネーは
知的能力は年齢に応じて向上する
という前提を置きました。
そして、「子供が発達するに従って出来るようになること」をとにかく列挙し、実際に様々な年齢でどのくらいの割合の子がその能力を身につけているかを測ったのです。
こうすると、「この問題が解決できるようになる年齢は平均4歳」「この問題は平均6歳」といったリストが出来ますね。
ここから適切な問題を選択して作られたのがビネーの知能テストです。
「最初の近代的知能テスト」と言われていますが、ビネーの知能テストは、言ってみれば「発達の到達度テスト」なんですね。
ビネーのテストでは、「この子のテスト成績は平均的な何歳に相当するか」という形で成績が出ます。
ビネーはこれを「精神年齢 mental age」と呼ぶことにしました。
「5歳の子の精神年齢が5歳ならば、年齢相応の発達」ということです。
単純に「発達の遅れている子を検出する」だけであれば、例えば一定の就学年齢に対して「精神年齢◯歳未満は特別支援教育へ」というような対応で良いと思うのですが、ここで「数値化」の欲求が頭をもたげてきます。
「テストで算出された能力の年齢は、実年齢に比して高いか低いか?」という関心を反映する数値として、シュテルン(Stern, W. 1871-1938)という心理学者が「IQ」という数値への変換を考案しました。
例えば、実年齢5歳の子が精神年齢5歳ならIQは5÷5=100、精神年齢6歳なら6÷5=120、精神年齢4歳なら4÷5=80、という感じです。
この「100を中心として、それより高ければ優れた知能、それより低ければ優れていない知能」という数値化は一見分かりやすく、後の多くの知能検査でも踏襲されています。「精神年齢と実年齢の割り算」という定義を採用しなくなったテストでさえ、これに寄せたスケーリングを維持していることからも、この数値化が如何に画期的な発明であったかが察せられます。
しかし個人的には「この数値化は良いことだったのかどうか」という疑問が今でも残ります。
というのも、「IQという数値化」には、「人間の賢さ」という曖昧模糊としたものが、「分かっていないのにナンダカ分かった感じになる」という魔術的効果を持っているからです。
元のビネーの「精神年齢」という表示のままだったら、「6歳なのに7歳の子でも半分くらいしか出来ないことが出来るなんてすごいね」とか「10歳なのに4歳相当の問題にも躓くのは、何か脳に異常があるのかもしれないね」といった「何を測っているか」と結びついた解釈が容易です。
これが「IQ」という数値で表されると、「何が出来て何が出来ないのか」という事実が置き去りにされて、「人間としての能力の優劣を示す数値」であるかのように錯覚されてしまう恐れがあります。
「数値化」の魔術は時に専門職でも陥るところで、「認知機能検査の結果を数字だけで見るな」という警句はまだまだ繰り返していく必要があると感じています。
初めに言ったように、知能テストは元々「精神発達遅滞の児童を就学時に見つける」という目的で作られ、ビネー自身はあくまで「支援教育での活用」を主張していました。
にも関わらず結果的に、ビネーの知能テストのパラダイムや「IQ」という考え方は「健常児の知能を数値化する」ことに転用され、ひいては全ての成人も含めた知的能力を序列化する際に用いられるようになっています。(これは詳しく言えばウェクスラーとターマンの寄与も大きいところですが)
私たちは、「IQ」という言葉を目にする時・口にする時に気をつけなければなりません。
「このIQとは、どうやって測ったもので、それはどんな個人差を意味するのか?」と。
「なんだか分からないものを分かったつもりになって崇めている」という振る舞いが極めて愚かであることは言うまでもありません。
何より、その理論的ベースを作ったビネーは、そのような盲目的な使われ方を望んでいなかったでしょう。
確認テスト
以下Q1~Q3の各文について、誤りがあれば修正しなさい。(解答・解説は下にあります)
Q1: チャールズ・ダーウィンは現代の心理学測定の基礎を築き、相関係数の考案や回帰の発見で統計学にも貢献した。
Q2: 現代の知能テストの原型は、20世紀のオーストリアの心理学者アルフレッド・ビネーが作った。
Q3: 「IQ」という数値化はビネーが考案した。
以下に解答と解説があります。
解答・解説
Q1: フランシス・ゴールトンは現代の心理統計学の基礎を築き、相関係数の考案や回帰の発見で統計学にも貢献した。
本記事を半分くらいを使って解説したように、ゴールトンが現代的な心理統計学の基礎を築きました。ダーウィンは彼に思想的な影響を与えた従兄弟です。
Q2: 現代の知能テストの原型は、19-20世紀のフランスの心理学者アルフレッド・ビネーが作った。
19世紀フランスという時代と地域が、彼の知能テストのコンセプトを決定的に方向づけました。このことは本文に書いた通りです。
Q3: 「IQ」という数値化はシュテルンが考案した。
ビネー自身は、精神年齢を「知的能力の格付け」に使うべきとは考えていませんでした。当初の「知的障害児のスクリーニング」という目的からすれば一定の年齢で一定の精神年齢をカットオフ値にすれば済む問題でしたし、実際に日本で現在最もよく使われているビネー式知能検査は「精神年齢」で算出される結果だけで十分に用を成しています。シュテルンによる「IQ」という発明が、「健常人間での数値の高低を比較する」という用途への扉を開いてしまったとも考えられます。賢さを自称する現代の人々が「知的障害を上手に検出する方法」から生まれた数値で高低を競っている、という状況にはなかなか皮肉めいた屈折を感じますが。
【参考文献】
高嶋正士, and タカシママサシ. "ゴールトン及びキャテルの生涯とその業績について." 基礎科学論集: 教養課程紀要 2 (1984): 67-81.
藤永保. 才能とは何か: 学力観の背景. 教育総合研究: 日本教育大学院大学紀要. 2010;3: 1–16.
Hunt, Earl. Human intelligence. Cambridge University Press, 2010.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

