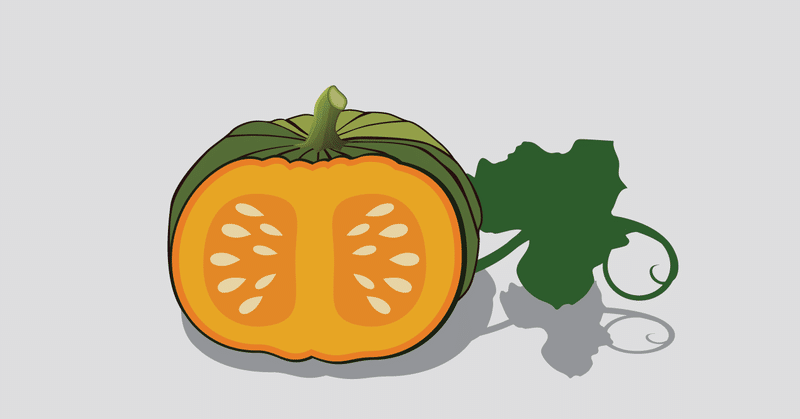
マネジメントに必要なのは…
こんにちは。今日は、カフェで『人事評価の教科書』(著者:高原鴨恭)を読んでいました。
その本でインプットした内容を、私の大学時代NPOでの営業統括の失敗経験と共に、共有していきたいと思います。
人事評価は、人が人をマネジメントする上でのひとつの手法であること
人事評価のことを私はただ、報酬を決めるためのツールだと思っていました。
NPO時代に営業の統括で人を動かすマネジメントをしたときに、「人事評価は、人が人をマネジメントする上でのひとつの手法である」ということを知っていたら、チームで目標数字を達成することができたのではないかと思います。
人事評価は、3つに分かれます。(本に基づく)
1 目標管理・成果評価→組織の方向性がみえる部分
2 能力評価→やる気が出ることに貢献
3 情意(態度)評価→やる気が出ることに貢献
この3つの観点から被評価者を評価することが求められるそうです。
私は、マネジメントの際に、①~③を考慮してメンバーを評価していたつもりではありましたが、しっかりとそれを公開にせず、自分の独断で毎週のMVPを選んでしまっていました。MVPの基準をしっかりと明確にして、また第2評価者をつけるべきでした。要、反省です。
評価者に必要なことは、以下の4点だと本には書かれていました。
1 目標(評価基準)の明確化
2 本人が目標を達成するために活動の明確化
3 期の途中で話し合うこと
4 本人の目標がどこまで達成できたか確認
目標の明確化とそれに対する行動の設定をして、定期的に話し合うことで被評価者の目標に対する意識が変わってくるのだと思います。私は自分の目の前の業務で精一杯で、メンバーの目標設定にコミットできていませんでした。また、数字が達成できない人に「どうして達成できないのか、なぜ動けていないのか、ちょっとした案」を出してはいましたが、定期的に話すことをしていませんでした、話すようになったのは、デッドの数字がやばい…!となったときでした。もっと期初に話し合って、個人の目標、チームの目標を設定しておくべきでした。
こうして、本を読んだことにより、なぜ以前私が数字を達成することができなかったのかわかりました。
私は社会人になって大学生と同じ失敗をして悔しい思いはしたくないし、また営業のマネジメントにもう一度挑戦したいと思っています。大学時代に一度マネジメントの失敗経験をしている私です。2度目の失敗はしたくありません。
入社して3ヶ月なので、マネジメントにすぐになる可能性は低いです。ただ、私の3つ上の先輩は入社してすぐにチーム長へと成り上がっています。もちろん上に立つということはとても大変ではあると思いますが、やりがいは十分にあると思います。だから、またマネジメントをする立場になりたいです。大学時代のリベンジを果たしたいです。
そのために、新人だからとあまえることなく、数字でしっかりと成果を出しつつ、マネジメント目線に立ってチームでの目標数字の達成にこだわりたいと思います。
やると決めたらやるしかない。
仲間のために。自分のために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
