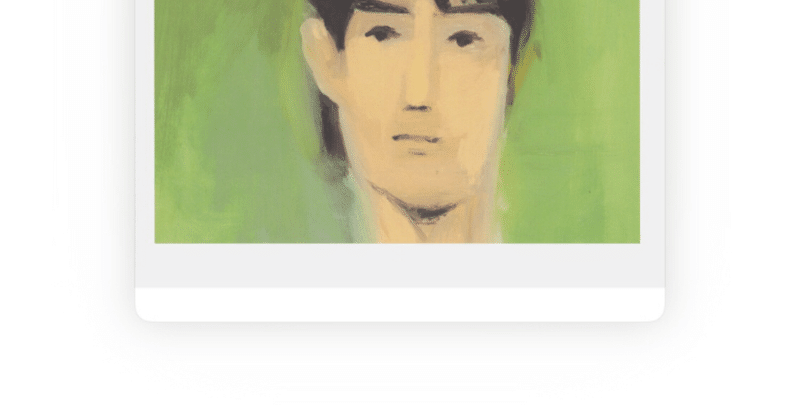
たとえ最初で最後の夜でも—①さらば—
僕はこれから旅に出る。
とてもとても、短い旅に。
七月。東北本線の座席、黒のG-SHOCKに目を落とす。午前11時。涼しい。
意味も無く眺めていたスマートフォンをポケットに仕舞い、車窓を見遣る。畑と山が広がり、蹴飛ばしたら倒れそうな小屋が偏在している。それだけだった。
それでも、夏の訪れを感じさせる何処にでもある青い風景、縁もゆかりも無い土地の退屈な風景は見ていて楽しかった。
しかし、そうではない運転士にとって、この風景はどう見えてるのだろうか。やはり退屈だろう。
電車がそんな風景の中を北上し続けると、駅に着いた。
矢吹。
ドアが開くと涼しい風が車内を包むのであろうが、人が降りもしなければ乗って来すらしない。
つまりドアは開かない。
今乗ってる人達は皆、あと15分くらいで着く郡山で降りるのであろう。
電車が再び走り出す。
青春18切符の期間外であった為、殆ど人は乗っていなかった。
車内には自分を含めて三人。
一人は日焼けした小説を読んでいる老婆。重そうなエコバッグを抱えている。多分地元の人だろう。
もう一人は高校生くらいの少女。
若い乗客は珍しい。
首元までの長さの髪は地毛であろうが、明るく、時々日差しが当たるとはっきりと茶髪に見える。
薄い生地の緑色のワンピースを着ていた。
初夏のおかげか肌はまだ焼けておらず、とても白く、透き通っていた。
小さな鞄を抱えながら、SONYのヘッドホンをして、項垂れるように寝ていたので、顔はよく見えなかった。
彼女らは一体何処へ行くのだろうか、そもそも何処から来たのであろうか。
注意していたわけではないので気づかなかったが、少なくとも、新白河では彼女らは乗っていなかった。
僕は再び車窓を眺めた。
相変わらず同じ風景だった。
この電車は本当に進んでいるのか?
そう思ったりもしたが、左に流れ去っていく景色が確実に電車が走っているということを証明していた。
郡山に着いた。
終着駅ではドアの横のボタンを押さずとも、勝手にドアが開くらしい。
東京では当たり前のことなのだが、自分は今福島県にいるのだから、福島県の当たり前を迎合するべきである。
電車を降りると、涼しい風に全身が包まれた。流石に東北はまだ関東に比べて涼しい。
違う気候の地に足を踏み入れると、東京から離れたという実感が湧く。
黒磯以来、二時間近く煙草を吸っていないので吸いたくなったが、次の電車はあと三分後に発車してしまうらしい。
その次の電車は一時間後だそうだ。
福島の当たり前は世知辛い。
煙草を諦め、ホーム先頭に止まっている2両編成の古めかしい電車に乗り込んだ。
乗客は全く居なかったので、空いてる端っこの席に座り込んだ。
背負っていたリュックサックは隣の席に置いた。
福島駅まで一時間くらい。
暇潰しに本でも読もうと、リュックサックからオリバー・ツイストを取り出し、続きを読み始めた。
気がつくと既に電車は出発していて、目を上げると、前の電車で乗り合わせた少女が目の前の席に座っていた。
こちらをずっと見ていたようで、僕も見返すと目が合った。
正確には目が合った気がした。
彼女は目を閉じていたのだ。
「こんばんは。」
彼女はヘッドホンを外して首にかけると、微笑みながらそう言った。
改めて顔を見ると、決して美人ではない顔立ちであるが、とても魅力的な笑顔であった。
鼻筋が綺麗に通っていて、特に口角の上がり方が何と言うか、妖艶であった。
ずっと目を閉じているのでどんな目なのかは分からないが、綺麗な二重の目を想像してしまう。きっとそうなのだろう。
彼女の顔に引き込まれている間に、彼女の言葉を心の中で反芻してみた。
ん?こんばんは?
今は昼の12時前だぞ。
「こんにちは。どうして『こんばんは。』なの?」
僕はオリバー・ツイストをリュックサックに仕舞い、彼女に尋ねた。
「ごめんなさい、私、目が見えないの。
それでいつでも—起きている時も、寝ている時も—真っ暗だから『こんばんは。』なの。」
彼女の顔からは悲しみの空気は感じられなかった。
恐らく、かなり昔から目が見えないのであろう。
電車は進み続ける。日和田。
「そうなのか。納得したよ。君は何処の駅に向かっているんだい?」
「うーんと、そうね。あなたは何処に向かっているのかしら。」
年齢の割にはえらく洗練された言葉遣いだ。
育ちが良いのだろうか、そう思った。
「僕は仙台までだよ。観光でね。」
「一人なのね。何処から来たのかしら。」
彼女は質問を続けた。
「東京の下町の方から。丁度今、試験休みで大学が無いんだ。それで当てもなく旅行しているんだよ。」と僕は答えた。
「東京は私は好きよ。色んな人が居て面白いの。
うってつけの言葉は無いけど、素敵な色をしている街よ。」
彼女は相変わらず目を閉じていたが、楽しそうだった。
色?多分感性のようなものなのだろう。
駅に着く。五百川 。
「そうか?僕は東京が嫌いだよ。色んな人が居るのはそうだけど、居すぎるんだ。
それに綺麗なんかじゃない。
実際の東京はドブネズミみたいな灰色をしている。加えて東京は空虚だよ。何でもあるけど、何も無いんだ。」
自分でも不思議だった。
僕は普段東京という、たかが1つの街に対して、これ程の考えを抱いていたのか。
それか、この少女と話をしているからなのだろうか。
「誰もいない福島より全然良いじゃ無い。それにドブネズミは美しいって、昔誰かが言ってたわ。」と彼女は楽しそうに言った。
再び走り出す。本宮。
「君は素敵な感性をしているね。」
と僕は返した。
「ありがとう。」
やはり彼女の笑顔は魅力的であった。
「ところで君の歳は幾つなのかい?」
僕は尋ねた。
「17歳よ。福島の高校に通っているの。日常に何も無くて退屈よ。ところであなたは幾つなの?」
彼女はそう答えると、今度は僕に尋ねた。
「20歳だよ。でも、何も無い日常を送れるだけ幸せなもんさ。世の中には普通が普通じゃない人が沢山いるんだ。ありがたいことに僕は多分普通の日常を過ごしているんだけど。」
僕が話終わると、彼女は頬にかかっている髪を耳にかけた。
小さな耳だった。
「意外と若いのね。22歳くらいだと思ったわ。うん、確かにそうなのかもしれないけど、私の日常が退屈なのは変わらないわ。」
橋を渡り、川を越える。杉田。
「よく言われるよ。でも何も無さそうに見える日常も、色んな奇跡的要素で構成されているものなんだよ。だから、見方と意識を変えるだけでも多少なり楽しいものになるさ。例えば雲とかも。」
見ず知らずの子に一生懸命だなぁ、とふと自分を俯瞰した。
「雲は好きよ。彼らは私達とは違う世界で過ごしているから、不思議に感じるの。雲は天才である。って石川啄木は言っていたけど、人間は昔から雲に色々な思いを馳せるものなのね。」
彼女の後ろの風景を見る。電車は進んでいるみたいだ。二本松。安達。
僕は雲の話を続けた。
「雲にそれだけの感覚を抱いているくらいなら、日常を楽しく見るだなんて、造作もない事だろう。僕も雲は好きだ。彼らは資本主義とは無縁だからね。時間を意識していないから。」
「では共産主義?無政府主義?」
彼女は不思議そうに尋ねた。
「分からない。平等主義ってわけでもない。けれど少なくとも、資本主義では無いんだ。」
僕は困りながら答えた。
「では明日の帰りまでに考えておいて。そして私に答えを教えて。」
彼女は再び微笑んだ。
トンネルに入る、真っ暗。松川。
「ちょっと待ってくれ。何故僕が明日東京に帰ることを知っているんだ?
それに明日、どうやって君に伝えれば良い?」
僕は彼女の発言が不思議で堪らなかった。
彼女はくすくす笑った。
不穏な空気は感じなかったが、明らかに車内の雰囲気は先程とは違っていた。
トンネルを抜けた。
涼しい風が体を包んだ。
窓とドアは閉まっている。
そして、電車が止まったような気がした。
いや、電車は止まっている。
少なくとも、風景が止まっている。
どんどん心拍数が上がっていく。
「仙台に行くのでしょう?仙台は二泊する程見るものが無いから、一泊で家に帰ろうとするだなんて少し考えれば分かるわよ。
でも明日会うのは偶然よ?必然的偶然。
ラプラスの悪魔みたいなもの。
それに今日も会うわ。そして私の日常の徒然の憂さ晴らしに付き合ってもらうの。」
彼女は耳に掛けていた髪を再び下ろした。
「何を言っているんだ?君は一体…。」
僕は動揺で声が上擦んでいた。
「言ったじゃない、私は普通の女子高生よ?
それにあなたはこの旅行中何も気にせず過ごして良いの。私が直接貴方に影響、それに悪影響を与えるなんて事はしないわ。」
そう言うと彼女は鞄を抱えて立ち上がった。
「待ってくれ!、まだ話は終わっていない!分からない事だらけじゃないか!」
僕は席の傍の金属のポールにしがみ付いて身を乗り出した。
彼女はドアの前まで歩いて立ち止まると、僕の方を振り返り、微笑んだ。
「貴方の旅行を楽しいものにする事を私が楽しむのよ。それ以上はつまらなくなってしまうから言えないわ。そろそろ行かなきゃ。
お話に付き合ってくれてありがとう、エイタ君。さようなら、また会いましょう。」
彼女が喋り終わると、ドアが一人でに開いた。
風が吹いた。ぬるい。
ドアの前にはプラットフォームが現れ、彼女はそのまま降りていった。
「何故僕の名前を…。あ、待ってくれ!」
僕はリュックサックを背負うとそのまま追いかけるように電車を降りた。
プラットフォームに出て、辺りを見渡すと、彼女の姿は見当たらなかった。
あの子は何だったのだろうか。
何故僕の名前を知っていたんだ?
僕は一度も名乗っていないし、僕の名前が記されている持ち物も無い。
では何故…。
その時、無機質な女性の声が耳に入ってきた。
「ご乗車ありがとうございました。福島、福島です。乗り換えは—」
どうやら自分は今福島駅のプラットフォームにいるらしい。
G-SHOCKを見ると、予定通りの時間であった。
でもあの時、間違いなく電車は止まっていた。風景が止まっていただけなのか?
どちらにせよおかしな事があの電車で起こっていた事は間違いない。
とにかく仙台へ向かおう。
そうすれば何か分かるかもしれない。
電光掲示板を見ると、仙台行きの電車は15分後に発車らしい。
近くに灰皿があったので煙草を吸う事にした。ホームに灰皿があるだなんて、福島の当たり前も悪くないと思った。
僕はポケットからロングピースとライターを取り出して、火をつけた。
煙草を燻らせながら、もう一度彼女の言葉を回顧してみた。
—では明日の帰りまでに考えておいて。そして私に答えを教えて。—
全く状況を飲み込めなかったが、考える為に空を眺めてみた。
しかし、生憎の快晴で雲は見当たらなかった。
これ以上は仕方が無いので、考えるのを止め、スマートフォンを開いて、一通りのアプリを弄った。
もちろん何の変化も無かった。
暫くして煙草を吸い終わったので、灰皿に煙草を捨て、次の電車に乗り込んだ。
同じホームに止まっていたので、乗り換えには苦労しなかった。
発車してからは一時間くらいで到着するみたいだ。
流石に仙台行きとなれば、老若男女が一定人数乗っていて、かろうじて空いている、という具合だった。
僕は変わらず端の席に座ると、リュックサックを足元に置いた。
電車が発車した。
僕は到着まで、音楽を聴く事にした。
そしてポケットからSHUREのイヤホンを取り出すと耳に掛け、スマートフォンに繋げた。
そのままミュージックアプリのシャッフルボタンを押すと、曲が流れ出した。
キンモクセイの「さらば」であった。
メロディが流れ出すと、彼女の発言が歌詞に絡んで走馬灯のように蘇った。
こんにちは、
「いつでも真っ暗だから『こんばんは。』なの。」
ありがとう、
「お話に付き合ってくれてありがとう、
エイタ君。」
さよなら、また会いましょう。
「さようなら、また会いましょう。」
うってつけの言葉は無いけど、
「うってつけの言葉は無いけど、
素敵な色をしている街だわ。」
帰ろう、家まで。
「一泊で家に帰ろうとするだなんて、
少し考えれば分かるわ。」
これも彼女の言う必然的偶然なのだろうか。
または、ラプラスの悪魔とやらなのだろうか。
早く仙台に向かって彼女の意図を確かめたい。
しかし、窓から見える風景は、相変わらずのスピードで、福島の方へ流れていった。
一人は退屈だった。
続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
