
ショートショート(2話目)夏祭りの日しか開かない喫茶店
夏祭りが終わり、わたしは自宅へと歩いて帰っていた。
夜の9時とはいえ、まだまだ暑さは厳しい。
Tシャツは汗を吸っていて、少し重みを感じる。
喉が渇いたので自動販売機を探したが、なかなか見当たらない。
身体は水分を欲しがっていた。
このままでは脱水症状になってしまう。
と、そのとき、古びた喫茶店があった。
看板には、「喫茶コロラド」と書かれている。
私は喉の渇きに耐え切れず、喫茶コロラドに入った。
中に入るとおじいさんが一人立っていた。
おじいさんは少しびっくりしたような顔で
「いらっしゃい」といった。
差し出された水を一気に飲み干した私はアイスコーヒーを注文した。
15分ほどして、アイスコーヒーがでてきて
ガムシロップを2つ入れた。
暑い夏の夜に飲むアイスコーヒーは最高に美味しい。
「こんなところに喫茶店があるなんて、本当に助かりました」
私はおじいさんに言った。
すると、おじいさんは私に言った。
「この喫茶店は夏祭りがある日しか、いまは開けてないんだ。だから、1年で営業しているのは今日だけなんだ。」
夏祭りの日にしか開かない喫茶店。
この5年間で、来客したのは私だけだそうだ。
おじいさんに、なぜ夏祭りの日にしかお店をあけないのか聴いてみた。
すると、おじいさんは昔を懐かしむように言った。
「30年ほど前、夏祭りの日に現れた女性に一目ぼれをしてしまってね。その女性のことがいまだに忘れられないんだ。それで1年に1回、夏祭りの日だけ店をあけるんだ。お店を開けていたら、もしかしてまた来店してくれるんじゃないかなとおもってね。」
30年の長い恋。
それはおじいさんが生きる意味になっているのだとおもった。
「どんな女性だったんですか?」
私が聴くとおじいさんは答えた。
「スラっとしてて、肌が真っ白で、とても綺麗な人だった。年甲斐もなく、一瞬で恋してしまったよ」
80歳を超えているであろうおじいさんは、屈託なく笑った。
何歳になっても、人は恋をするものだ。
私はアイスコーヒーの代金、500円を置いて、喫茶コロラドをでた。
外は、まだまだ暑かった。
~1年後の夏祭りの日〜
私は、再び喫茶コロラドに立ち寄った。
おじいさんは私のことを覚えていてくれたようだ。
「去年きた人だね。アイスコーヒーでいいかな?」
と、おじいさんは言い、私は頷いた。
アイスコーヒーがきて、私はガムシロップをいれながらおじいさんに話しかけた。
「そういえば、おじいさんが恋した女性の人って、もしかしてこの人じゃないですか?」
私は1枚の写真をさしだした。
おじいさんはジッとその写真を眺めた。
「この写真は30年前のもので、写っているのは私のお母さんです。母はすでに病気でなくなりましたが、先日、生前に母が書いていた日記がみつかったんです。そこに喫茶コロラドにいったことが書いてありました。」
私は日記をおじいさんに手渡した。
「8月3日の日付のところです。喫茶コロラドでコーヒーを飲んだと書いてあります。ちょうど、30年前になります。」
おじいさんは、日記を読んで、口を開いた。
「この日記、まったく同じものを私も使っていたよ。宝文具社の日記は、つかいやすいこととお洒落なことで有名だったんだ」
「それで、おじいさんが恋した人って、私のおかあさんですか?」
私が聴くと、おじいさんは首を横に振った。
「いや、違うな。似ているが違う。この写真の女性は、40歳くらいに見えるが、私が恋したのは、当時20歳くらいの女性だったんだ。でも、訪問した日は同じ日だ。こんな偶然があるんだなあ。」
30年前、おじいさんはおそらく50歳を超えていたはずだ。
私はてっきり、恋したのは同じくらいの年代の女性だと思っていたが、まさか20歳の女性だったとは。
ということは、いまその女性は50歳を過ぎているということだ。
「ごめんなさい。日記を見つけた時、てっきり、おじいさんが恋した人は私のお母さんだと思ったの。だから、おじいさんに教えなきゃと思って、今年の夏祭りの日をずっと待ってたの。でも勘違いだった。」
私がいうとおじいさんはいった。
「いやいや。気持ちだけでも嬉しいよ。それに、きみのお母さん、本当にその人に似てるんだ。もう少し若かったら、たぶん間違えていたと思う。それくらい似ているよ」
30年前に20歳くらいの女性。
ずいぶん前から過疎化が進むこの村で、男性が一目ぼれしてしまうような若い女性がいたら、きっと評判になっているだろう。
「30年前に20歳ってことは、いま50歳過ぎってことですよね。ちょうど、私と同じくらいの年齢ですね。」
そうつぶやくと、おじいさんはジッと私のほうを見た。
「どうしたんです?」と私がきくとおじいさんはいった。
「おかしいんだ。30年前の夏祭りの日、お客さんは一組しかこなかったんだ。お母さんの日記には、喫茶コロラドでコーヒーを飲んだと書いてあるのに、その日、ここにきたのは一組だけ。。。。。ま、まさか。。。」
30年前の夏祭りの日。
母と一緒に喫茶コロラドにきたのは、20歳のときの私だ。
20歳の時の私はスラっと痩せていて、村では評判の美人だった。
あれから、30年。
いまの私は50歳になり、体重は当時の2倍になった。
歳月は、よくも悪くも人を変える。
おじいさんは、茫然自失となり立ち尽くしていた。
いつまでも、幻影をみせてあげることもできた。
そのほうが、おじいさんにとって幸せだったのかもしれない。
~翌年の夏まつりの日〜
喫茶コロラドは閉まっていた。
おじいさんの年齢を考えると、もしかしたらこの世界から旅立たれたのかもしれない。
それとも、しがみつく幻影がなくなり、生きる意味をなくしてしまったのだろうか。
この1年で、私は2キロやせた。
来年までに20歳のときのプロポーションに戻すのは難しいけれど、5年あったら、もしかしたらもとにもどせる可能性はある。
おじいさんがそれまで生きていたら、もう一度私に恋をしてくれるだろうか。
セミの鳴き声が強くなった。
7日間しか地上で生きることができないセミは、きっと毎日を必死に生きているんだろうなと思った。
私は喫茶コロラドを背に歩き出した。
来年の夏祭りに、思いを馳せながら。
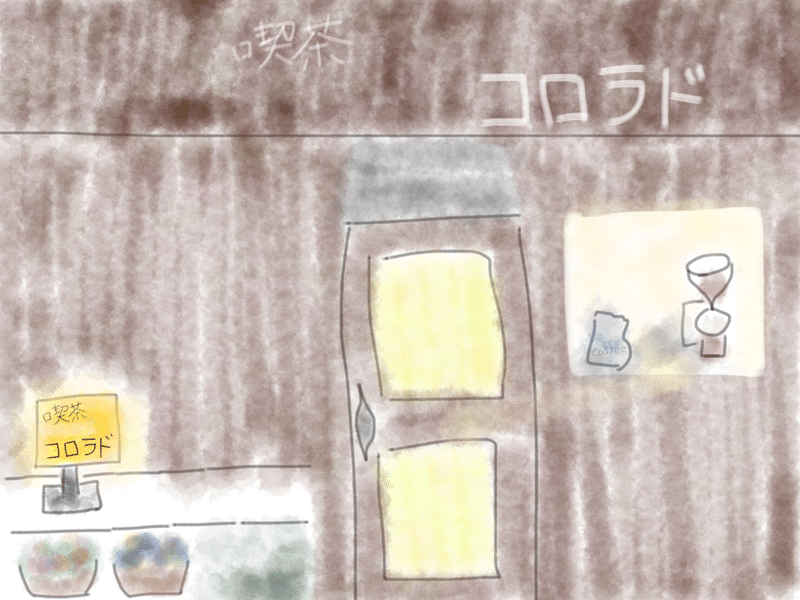
↓音声はこちらから。
お仕事の依頼は
nhnhnh1129@icloud.comまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
