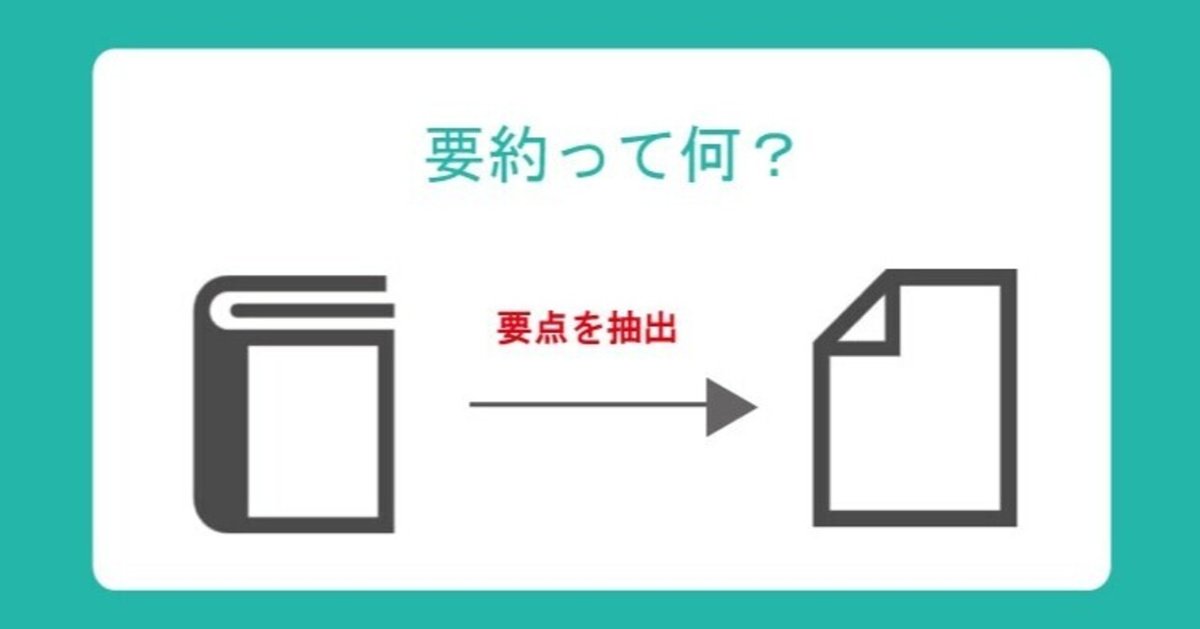
読解が苦手な小学生のための短文で学ぶ要約入門
国語の読解において非常に重要な力のひとつに「要約力」があります。
要約ができると、本文を読んで要点をおさえ、ざっと内容を把握することができるようになります。
特にここ最近の中学入試では問題文が長文化傾向にあるため、この力は必須であると言えるでしょう。
また、こうした入試の長文化の傾向を受け、各種塾の入塾試験や非受験学年の模擬試験であっても問題文が長文化しているように感じます。
そのため国語に強い苦手意識を抱く子や文章の読み方をそもそも学んでいない子だと、極端に低い偏差値が出て驚いてしまった経験のある方もいるのではないでしょうか。(ちなみに4年生の試験などをみていると、こうした極端な点数を出させないように、知識分野さえ解ければ最低限の偏差値が保証されそうな作りになっている模擬試験を見かけますが、個人的にはそれってどうなのだろうと思ったりしています)
さて、先程述べた通り、こういう長文を読みこなすためには「要約力」をつけることが不可欠なわけですが、一方でそのやり方を丁寧に教わる機会はあまりありません。
厳密にはどこの塾でも教えているのですが、苦手な子にとって授業時間内にそれを定着させる事は簡単ではなく、細かいステップにわけて繰り返し反復練習が必要であるため、十分に定着しきってはいないのではないかと思います。
文章を読むための要約力をつけるには、短い文章を使って、要約に必要な力を要素に分け、パターンプラクティスに落とし込んでひとつずつ身につけることが有効です。
というわけで、今回は要約の仕方について説明していきます。
要約に必要な力は何か?

そもそも要約とはなんなのでしょう?
「要約」という言葉を辞書で引いてみると、次のように書かれています。
話・文章の重要な点を短くまとめること。また、そうしたもの。(新明解国語辞典)
論旨などをまとめて短く言い表すこと。また、そう言い表したもの。(岩波国語辞典)
内容のおもな点をみじかくまとめること。また、まとめたもの。(三省堂現代新国語辞典)
要約に関しては「順番を崩さずに要点をわかりやすく説明したもの」とするものもありますが、ここでは、分かりやすく辞書の意味で説明していこうと思います。
要約の方法を非常にざっくりとまとめてしまえば次の2つの作業であるということができます。

この二つをいきなり同時に行おうとするとするから要約は難しく感じてしまうので、この説明ではそれぞれの要素に分け、今回は①について説明していこうと思います。
①情報を圧縮する
というわけでさっそく①について見ていきましょう。
「情報を圧縮する」というのをもう少し細かく説明すると、a同一情報と認識してひとつにまとめる、bその際抽象度の高い言葉にするという2つの作業になります。
例えば「カゴカキダイはハチのお尻のような黄色と黒の縞模様がある。」となっている時、「ハチのお尻のような」と「黄色と黒の縞模様」は同じ内容を指しています。
この「ハチのお尻のような」と「黄色と黒の縞模様」が同じ内容であることが認識できる力がa、そして比喩である「ハチのお尻のような」と「黄色と黒の縞模様」ならば後者の方が抽象度の高い情報であるということが分かるのがbの力です。
おそらく①の情報の圧縮という作業に置いてつまずくお子さんは、aかbのどちらかを苦手としているはずです。
どちらが苦手なのかを明確に意識しつつ練習に取り組むことで、確実に克服することができるようになるでしょう。
パターンプラクティス①110字→40字にする
次の問題を例に見てみましょう。(もしお子さんに取り組ませる目的でこの記事を読んでくださっている方がいましたら、実際に取り組ませてみてください。
次の文章の要点を40字以内でまとめましょう。
メダカは長さが三、四センチしかない小さな魚で、私たちが子どものころはほんとうにどこにでもいました。あまりにありふれていたので、フナやコイなどとくらべると、子どもたちにとってあまり魅力のない、雑魚(ざこ)の代表のような魚でした。(高槻成紀「野生動物と共存できるか」)
さてこの文章について、情報を整理していこうと思います。
まず、この段落をみると「メダカについての説明」であることが分かります。
そこでメダカについての情報をまとめると次のようになります。
⑴三、四センチしかない小さな魚
⑵私たちが子どものころはほんとうにどこにでもいた
⑶あまりにありふれていた
⑷コイやフナに比べると子どもたちにとって魅力はない雑魚のような魚である
さて、この4種類の文について、同じ情報がないかを見ていきましょう。
まずは⑴です。
⑴の情報には「三、四センチしかない」と「小さな魚」という同じ内容が含まれます。
この二つであれば数字を用いている方が具体的な内容なので、ここはカットしていいでしょう。
次に⑵をみると、ここには「私たちが子どものころ」という昔を表す内容と、「ほんとうにどこにでもいた」という情報がありますが、これらは違う内容なのでそのまま残します。
ただ⑶を見てみると、「あまりにありふれていた」とあり、これは⑵の後半部分の「ほんとうちどこにでもいた」と似たような内容ですので、「どこにでもいる」という言葉に集約してしまいましょう。
そして最後に⑷について。
「コイやフナに比べると子どもたちにとって/魅力はない」という内容と「雑魚の代表のような魚」という内容が同一です。
そのためここもひとつにまとめます。
前半の文はコイやフナという「ほかの魚と比べて魅力のないもの」というニュアンスが含まれています。
その意味をまとめるなら、「魅力のない魚→雑魚」、「コイやフナに比べる→代表」となるでしょう。(「子どもたちにとって」というところは⑵の「私たちが子どもの頃」という内容に含まれるのでカットします)
したがって⑷は「雑魚の代表のような魚」とまとめることにします。

これらを合わせて要約を作ると次のようになります。
「メダカは私たちが子どものころは小さくてどこにでもいる雑魚の代表のような魚だった。」
いかがでしょうか。
こうした練習をもう一例用いて行っていきたいと思います。
パターンプラクティス②140字→45字にする
先ほどの文章と同様に、今度はこちらの文章で要約の練習をしていきたいと思います。
少し自分の言葉で言いかえをしなければならない分、難しく感じるかもしれませんが、挑戦してみてください。
次の文章の要点を45字以内でまとめましょう。
ホンソメワケベラというスマートな魚がいる。せいぜい七、八センチの小魚で、左右にやや平たく細長い体をしている。背と腹は明るいマリンブルーで、体の左右に頭から尾端まで、一条の幅広い真っ黒な帯が通っている。おまけに、尾だけを上下に振る「うなずきダンス」を踊る。とにかく、よく目立つ魚なのだ。(鈴木克美「魚は夢を見ているか」)
こちらの文章も先ほどと同様に内容を整理していきます。
まず、冒頭から、この文章は「ホンソメワケベラ」という魚の話ということを押さえましょう。
その上で、ホンソメワケベラの情報を整理すると次のようになります。
(1)スマートな魚である。
(2)せいぜい七、八センチの小魚で、左右にやや平たく細長い体をしている
(3)背と腹は明るいマリンブルーで、体の左右に頭から尾端まで、一条の幅広い真っ黒な帯が通っている。
(4)尾だけを上下に振る「うなずきダンス」を踊る
(5)とにかく、よく目立つ魚なのだ
それぞれの情報をまとめていきます。
まず(1)と(2)については、形の話をしています。「七、八センチ」の「小魚」、「左右にやや平たく」「細長い体」はそれぞれ同じことなので「細長い体つきの小魚」とすればいいでしょうし、さらに「スマート」という言葉には「体つきがすらりとしているさま」という意味があるので、ここは「スマートな小魚」としておきます。
次に(3)について。
「背と腹は明るいマリンブルーで、体の左右に頭から尾端まで、一条の幅広い真っ黒な帯が通っている」とありますが、これは要するに見た目のことを言っています。そして、「明るいマリンブルー」や「真っ黒な帯」は一般的に「派手」という認識になるでしょう。
そこで、この部分は「派手な見た目」とします。
さらに(4)は「尾を使うダンス」くらいにします。
(5)に関しては(1)~(4)の要素をまとめる部分ですので、「目立つ魚」という情報はかかせません。

これらをあわせて、次のような要約が完成します。
「ホンソメワケベラは、派手な色合いのスマートな小魚で、尾を使うダンスをする目立つ魚である。」
こうした形で行うのが要約です。
こうした力を日ごろから意識して身につけていると、実際の文章を読むときも情報に階層がついて、情報処理を早く行うことができるようになります。
今回は要約に必要な力のうちのひとつを紹介しましたが、もうひとつの「話題の中心を掴む」に関してはまた後半の記事を作成しようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
