
Bill Taylorさんの考案したゲームについて書いてみる(2:Bill Taylorは「ループする盤面にこだわる」)
前回の記事はこちら。
今回も、Billさんの考案したゲームの紹介です。
これまた接続ゲームです。
「projex(プロジェックス)」と「ZeN(ゼン)」の2つを紹介します。
どちらも、かなりの変態ルールでした。
Projex(1994年)
「Projex(プロジェックス)」は、「Projective Hex」からの合成語です。
「Projective」は訳すと「射影」です。
意味はわからなくても、大丈夫です。
ただ、相当変なことをしている、と身構えてください。
まず盤面です。
1辺が5マスと6マスが交互にあらわれる、六角形の形をしています。

1辺飛ばしつつ3辺に
5マスを付け加えた、ともいえます。
「プロジェックス」のゲームの目的は、「自分のコマを盤面の2辺以上またがって、連結したひとつながりのループをつくる」ことです。
文にするとピンときませんね。
わかりやすそうな例は、

こんな感じですね。ところがですね……「プロジェックス」では、これもつながっています。

……どうなってるの?これ?
メビメビメビウス
「Projex(プロジェックス)」では、盤面の端にあるマスは、下の図のように
ひねってつながっています。

通常の盤面のマスは実線で縁取り、破線で縁取ったマスは向かい側でのつながり方を示します。
では、ちょっと前に描いた「どうなってるの?これ?」の盤面のつながりはどうなっているのかというと、

色をつけたコマは、実線縁取りのマスにもあり、破線縁取りのマスにもあります。
なので、ひとつながりになります。
辺と辺をひねってつなげた有名な図形はメビウスの輪です。

「プロジェックス」の盤面は3箇所もひねってつなげたメビメビメビウスです。
3次元で実際に表現するとどうなるのか、さっぱりわかりません。
最後に重要な余談。
「プロジェックス」は、Billさんが考案しましたが、Boardgamegeekではもう1人の考案者がいるようです。
ただし『ConnectionGames』での「プロジェックス」の項をみると、発案者はBillさんだけです。
調べてみると、なかなか興味深い方なので紹介します。
もう1人とは、Lloyd Stowell Shapley(ロイド・ストウェル・シャープレー)さん。
2012年にノーベル経済学賞を受賞しています。
さらに、シャープレーさんは、1964年に『So Long Sucker(ソー・ロング・サッカー)』というボードゲームを考案してます。
このゲームを共同考案したのが、John Nash(ジョン・ナッシュ)さん。
1994年にノーベル経済学賞を受賞していますし、『Hex』の考案者です。
……もう、クラクラしてしまうほどの人脈ですな。
ZeN(2004年)
「ZeN(ゼン)」は、別名「NZ」とも呼ばれます。
それは、Billさんはニュージーランド(New Zealand)在住なので、頭文字をあわせています。
盤面は、前回紹介した「Quax」と同じ、八角形マスと正方形マスを組み合わせた構成になります。

黒のプレイヤーは上下の辺を、白のプレイヤーは左右の辺を受け持ちます。
ゲームの目的は、「自分のコマを自分の受け持つ2辺をまたがって、連結したひとつながりのループをつくる」ことです。
少し小さい盤面での例だと、

黒プレイヤーの勝利のつながりは、こんな感じです。
盤面は上下の辺同士、そして左右の辺同士がつながっています。
ということは、左右をまたいだ場合、

これもOKです。
ところが、

これは「ZeN」では、勝ちとは認められません(NGです)。
何が違うのかというと、OKだったつながりは上から右→左と抜けて下にいく「\」の流れです。
NGのつながりは、逆に上から左→右へと行く「/」の流れです。
なんでこんな変な差別をしているの?
ゲームのタイトルに含まれている「N」に注目しましょう。
この字は、「|」と「\」で構成されています。
実は「N」は、
黒プレイヤーの勝ち条件を
示していたのです。
なななんだって〜〜〜〜っっっ!!!
まままさか「Z」は………

白は「―」でつながっているのでOK。

白は「/」でつながっているのでOK。

だけど「\」なのでNG、なのです。
同様に「Z」は、
白プレイヤーの勝ち条件を
示していたのです。
……(絶句)。
変てこりんな制限の理由
別に「\」と「/」どちらからでもいいじゃないですか。
なんでこんな制限をかけたのでしょうか?
1つ考えられるのは、双方とも「\」もしくは「/」方向につなげていくと、分断する手がないままゲームが進んでしまうからです。
「|」と「―」とでは、互いに自然と分断する手を打ちますね。
「\」と「\」とでは、互いに交わらずにつなげていく展開になりえます。
そこで、「Hex(ヘックス)」ではどうなっているのかみてみましょう。
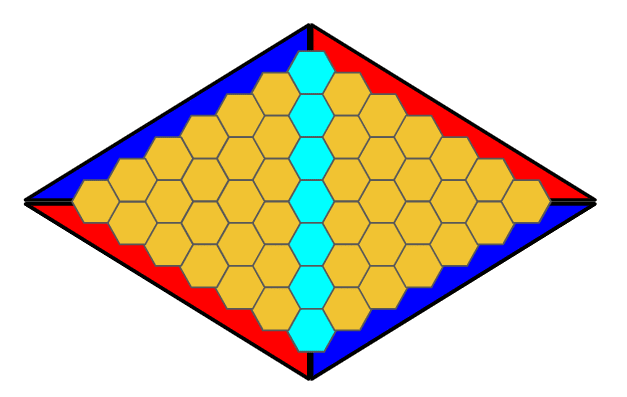
どちらのプレイヤーもコマを連結させて対辺につなげるためには、盤面の水色のマスにコマを最低1つ置かねばなりません。
一方、正方形マスの場合で、辺同士のみしか連結できない場合だと、
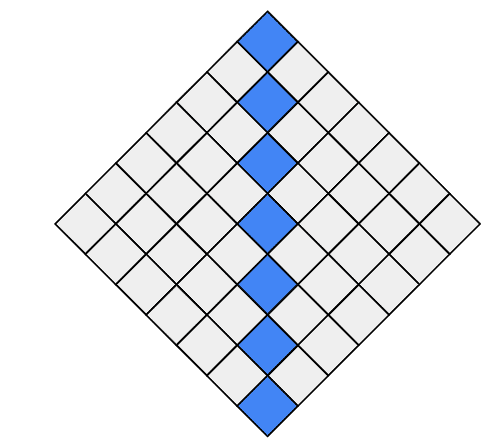
これも、青色のマスに最低1つコマを置かないと対辺を連結できません。
上から下へ降りるような(辺同士の)連結を考えると、六角形と正方形は2方向で八角形は3方向になります。

そこで「ZeN(ゼン)」では、3方向のうち1つを抑制するようにルールを付け加えたのではないかと推測します。
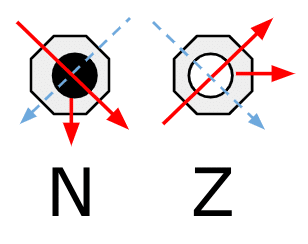
あくまで「ヘックス」らしさを求めて、変態なルールを思いついたのではないでしょうか。
3人用「ZeN」?
Cameron Browneさんの著書『Connection Games』では、「ZeN(ゼン)」を「Quax(クアックス)」の派生ゲームとして紹介しています(P100〜102)。
そこではなんと、「Three-player ZeN(3人用ゼン)」のルールがあります。
「ゼン」と全く同じ盤面で遊びます。
黒、白、そして3人目として灰がいます。
・黒は「|」でひとつながりのループをつくると勝ち
・白は「―」でひとつながりのループをつくると勝ち
・灰は「/」もしくは「\」でひとつながりのループをつくると勝ち
です。
パッと見、灰がほかの2人よりも有利そうですが、一方で黒と白は灰を止めようと結託する展開になるでしょう。
非対称なアブストラクトゲームとして、意外とバランスが取れているかもしれません。
締め
ということで、「Projex(プロジェックス)」と「ZeN(ゼン)」の紹介でした。
次回も、また接続ゲームを取り上げたいと思います。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
