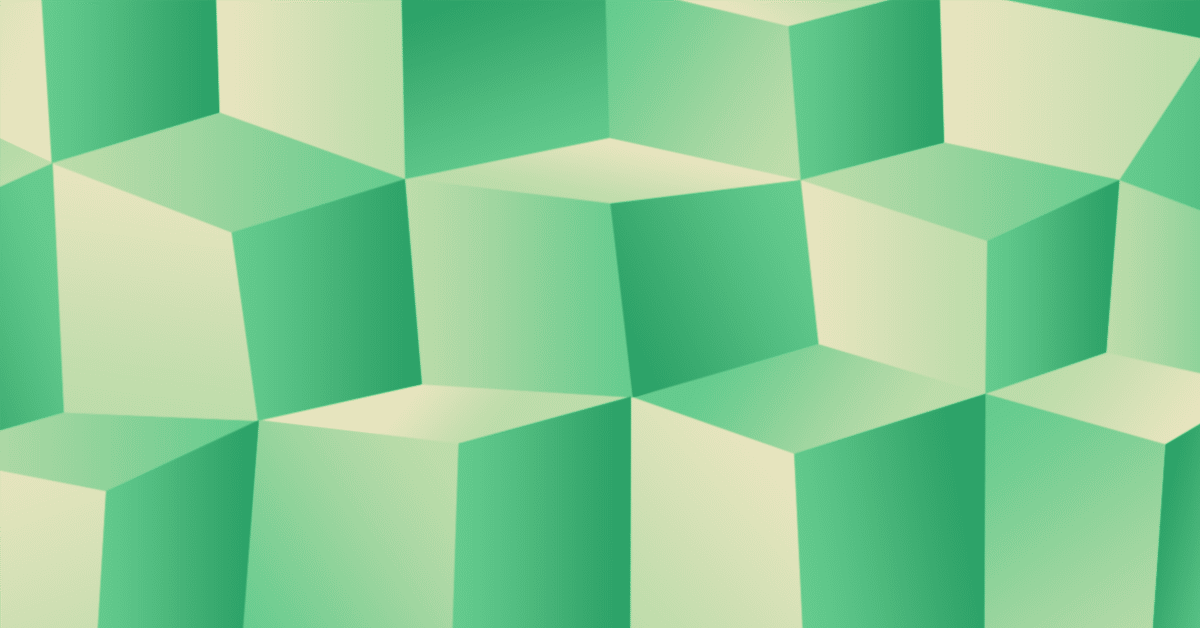
特殊相対論的運動方程式の導出
前書き
大学で相対論を勉強して以来、納得いってなかった運動方程式導出について、やっと自分なりに納得できる論が出来た。
状況の設定
宇宙空間で孤立した場所で実験を行う。
無限に長いx軸を想像する。
x軸の原点で静止した観測者をSとし、負の方向に高速Vで飛んでゆく観測者をS’とする。
小球mは、Sから見て原点に静止した状態であるとする。この小球は、S’から見れば正の方向に(Sと共に)速さVで飛んでゆくように見える。
小球をロケットで加速することを考える。
Sから見て、小球は正の方向に一定の加速度aで加速されてゆくようにセッティングされている。
ただし、このままだと小球は無限に加速されてゆくことになる。果たしてそのようなことは可能だろうか、という疑問は正当である。そこで、このシチュエーションを非常に短い時間内に限って観測していると考えよう。そうすれば小球の速度を光速に比べて十分小さな範囲に留めておける。小球が「正常な」速度の範囲内にあれば、そこでは(我々が良く知っているように)ニュートン力学が成立する。
これをS’から見るとどうなるか。
小球は高速で飛びながら、ロケットでさらに加速されているように見えるはずである。
では、その加速度はどれほどだろうか。
ローレンツ変換で考えてみる。
先に導いたローレンツ変換における加速度の変換公式を用いる。Sに対してS'は速さV=-Vで運動している。また、t=0の瞬間、小球はSに対して静止しているから、v=0となる。これを加速度の変換公式に代入すると、S’が観測する小球の加速度a'は
$$
a'=\left( 1-\left( \dfrac{V}{c}\right) ^{2}\right) ^{\dfrac{3}{2}}a
$$
となる。これは明らかにaより小さい。例えばS'から見て、小球が光速の90%の速さで運動していると、$${a'=0.082…a}$$となる。つまり、Sが観測する小球の加速度の約8.2%しか加速していない。
この傾向は、vがcに近づくにつれ大きくなる。
と、ここまではローレンツ変換から導かれる単なる計算であり、運動学的な話であり、力学は何も関係ない。なぜなら力という概念が登場していないからである。
運動と力という概念を結びつけようとして初めて力学となる。そしてその結び付けられ方を表現したものが、運動方程式なのである。
力学のイデオロギーでは、我々は加速度を生じさせる原因として力という概念を仮定する。そして運動と力を分離して、力の性質を調べることで運動を理解しようとする。運動と力を分けて考えること、この問題の切り離しが物事を非常に簡明にしたので、ニュートン力学は現在でも、我々が運動を理解するときの基本スキームとなっているのである。
注意したいのは、力は小球などのような物理的実在性はないということだ。実際にこの世界で起きているのは、小球の運動だけである。その運動の背後に力という存在があると我々が勝手に思っているだけなのだ。しかしこの勝手に仮定した力という概念があまりに便利なので、我々はこれをしばしば実在する確固たる存在のように考えてしまう。
さて、上で見たように、ローレンツ変換によればS,S’の間で小球の加速度は最早合意出来る値ではなくなった。(ニュートン力学では、どの慣性系でも同じ加速度の値が観測されていた。)加速度の値が観測者毎に異なるというは、まさに加速度の相対性である。
「速さが大きいほど加速度が小さくなる」ということが、実際に世界で起きていることである。では、このことを力学として、つまり力という概念によって解釈するとどうなるだろうか。2つ挙げてみよう:
小球の質量が増大している。
小球に作用する力が減少している。
1番目の解釈について考えてみよう。大体、以下のような思考過程を経ているはずだ:小球を2つ用意して同じ装置で加速することを考える。ロケットの性能が同じであれば、小球に作用する力は両者で等しいはずである。しかし一方を高速に、他方を低速にした場合、高速である小球の加速度の方が小さくなる。同じ力で押しているにも関わらず加速度が異なるので、これは質量が増大していることを意味する。
そもそも質量とは、力と運動を結びつける際に必要なクッション材のようなものである。質量とは、力がどれだけ効率的に加速度に変換されるかを表すパラメータなのである。同じ力を加えても、モノによって得られる加速度が異なることが実験的に分かっているから、モノが持つ「力に対する加速度の鋭敏性」を質量と名付けたのである。だから、質量とは純粋に力学的な概念なのだ。(厳密に言えば、ここでの質量は「慣性質量」のことである。)
2番めの解釈はどうだろうか。これはこれで力学的には筋が通っている。質量が増大すると考える代わりに、1番目の解釈では当然とされていた「力が両者で等しい」という仮定にメスを入れたわけだ。
以下では1の解釈を採ることにしよう。
運動方程式の導出
上で得ていた加速度の変換式の両辺に、Sで観測される小球の質量mを乗じて、Sでは(少なくともt=0から無限小時間dtが経過する間は)ma=Fが成立しているから、
$$
ma'=\left( 1-\left( \dfrac{V}{c}\right) ^{2}\right) ^{\dfrac{3}{2}}F
$$
を得る。しかしこの関係性はdtの間しか成立しない一時的なものである。
今欲しいのは、時間を指定せず、任意の時刻において成立する関係性である。しかし、それを得るのは数式上は難しくない。たった1文字変えるだけでよい。V(=Sに対するS'の速さ)をv(=S'で観測される小球の速さ)とする:
$$
\begin{equation*}
ma'=\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{\dfrac{3}{2}}F
\end{equation*}
$$
なぜこれでよいのか。混乱しやすいから、省略せずに丁寧に考えてみよう。
S'から見ると、小球は一般に非常に大きな速さで運動しつつ、ロケットによって加速されているのであった。
ある任意の時刻t'を選ぶ。この時、S'から見た小球の速さはv(t')である。(vの定義)
この時、小球とぴったり寄り添っている新しい観測者Sを想定することが出来る。S'から見ればSはt'の瞬間のみ小球と並走していることになる。
Sから見れば、ある瞬間、小球は静止して見えて、この時S'は-v(t')で運動しているように見える。止まっている小球の質量はmと分かっているし、ロケットが及ぼす力もFで同じである。
今までしてきた議論を改めてS,S'で行えば、時刻t'において上が正しいことが分かる。
どの瞬間でも「並走者」Sを考えて、Sが見たものをS'へ変換すればよい。これが任意の時刻において成立する理由である。
1の解釈では、上の式をこう見る:
$$
\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{-\dfrac{3}{2}}ma'=F
$$
ここで、増大する質量m'を
$$
m'=\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{-\dfrac{3}{2}}m
$$
で定義すれば
$$
m'a'=F
$$
となる。この結果を見れば、「Sで観測される力FはS'で変化しない」ことを仮定すればすれば、運動方程式っぽいもの
$$
m'a'=F'
$$
が得られる。
これでも数学上はちゃんと運動を解析出来るのだが、この質量の定義にはある不備がある。それは運動量保存則が成立しないことである。実際、2つの小球が外力を受けていない場合、
$$
m'_1a'_1+m'_2a'_2=0
$$
となるが、この質量の定義の場合はここから、
$$
m'_1v'_1+m'_2v'_2=const
$$
が成立しない。それは今や質量m'が時間に依存して変動するため、
$$
m'\dfrac{dv'}{dt}\neq \dfrac{d\left( m'v'\right) }{dt}
$$
となってしまうからである。
ニュートン力学で成立していただけの運動量保存則を、相対性理論でも成立させる義務はないのだが、保存則が成立するのはやっぱりありがたいので、上の質量の定義を運動量保存則が成立するように上手く修正することにしよう。
最後のひと押し
次の数学的に等価な式変形がある:
$$
\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{-\dfrac{3}{2}}m\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v
$$
これ自体は丁寧に計算すれば簡単に確かめられる。
そこで、これを用いて式を書き直せば、
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F'
$$
を得る。相対論的質量を
$$
m'=\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}
$$
で定義すれば、今度こそ「運動量変化率が作用する力に等しい」という形式を持つ、運動方程式
$$
\dfrac{d\left( m'v\right) }{dt}=F'
$$
を得る。
一般的に、力学では保存される量である運動量こそが運動の本質的な量であるという考え方があるようだ。であるから、ニュートンの運動方程式も、その本質的量である運動量がどう変化するのかを意識した書き方が「正統」だと言われることが多い。
ともあれ、相対論的質量を上のように定義すれば、相対性理論においても運動量保存則が成立することになる。
結論
特殊相対性理論における運動方程式(運動量変化と力を結びつける関係式)は
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F
$$
となる。
これは、ニュートン力学における運動方程式について、質量の修正を行ったものと解釈できる。これがまさに加速度の変換公式に対する1番目の解釈であった。
本質的には、この運動方程式は加速度変換公式を力という概念を導入して書き直したものに過ぎない。
まとめ
出発点は、2つの慣性系S,S'に対する加速度の変換公式であった:
$$
a'=\left( 1-\left( \dfrac{V}{c}\right) ^{2}\right) ^{\dfrac{3}{2}}a
$$
これは、2つの固定された慣性系S,S'に変換であり、したがって一般には無限小時間間隔でしか成立しない。そこで、Sを小球の「並走者」として毎時取り替えることで、任意の時間において
$$
a'=\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{\dfrac{3}{2}}a
$$
がS'において成り立つことが分かった。
加速度の変換公式は、加速度が既に存在することは前提であった。しかしここで「力」という加速度を生じる原因を仮定することで、力学を展開することとした。
加速度が、力によってどう引き起こされるのか、その結びつき方について知りたいのであるが、我々は「並走者」、つまり小球が静止して見える観測者については、その一瞬に限って
$$
ma=F
$$
という慣れ親しんだ関係がそのまま成立すると仮定した。
そこで、加速度変換公式に、「力の加速度への変換効率」としての質量というファクターを組み込んで、
$$
\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{-\dfrac{3}{2}}ma'=F
$$
を得た。
数学的に等価な式変形
$$
\left( 1-\left( \dfrac{v}{c}\right) ^{2}\right) ^{-\dfrac{3}{2}}m\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v
$$
を用いることで、これを
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F
$$
と変形した。我々はここまでの議論で、力がS,S'でどう変換されるのか考えてこなかった。もしF'=Fが成立するのなら、
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F'
$$
という式は、既に成立が確認されている
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F
$$
と、数学的に等価になるから、運動と力を結びつける式と言えるようになる。そこで我々は実際に、運動方程式がこの形式で成立するように、ローレンツ変換における力の変換性を定義する。今の場合はF'=Fがそれにあたる。
だから、運動方程式がこのような形式で成立するのは、力の変換性をそのために定義したのだから当然なのである。しかしこれはトートロジーには陥らない。ちゃんとここから力学的な内容を取り出すことが出来る。
確かに、力の変換性を決めることで運動方程式の形式は決まるが、その内容については変換性からだけでは定まらないのである。なぜなら、力の変換性からだけでは肝心要の値そのものについては、何も言えないからである。
値を決めるには、ある一つの座標系において値を決定することが必要となる。そうすれば、変換性に則って、あらゆる慣性系において力の値が計算可能となる。そして、一旦力の値が決まれば、既に形式の決まっている運動方程式を用いて物体の運動が決定される。それが現実と合致しているかどうか、確かめることが出来るようになる。では、力の値はどう決めるのか。
我々は、「並列者」と呼ばれる慣性系Sにおいて、相対論的な力について
$$
ma=F
$$
が成立することを出発点としていた。この仮定こそが力の値を決める基礎となる。これによってあらゆる慣性系でFの値が決まる。
つまりこの仮定が、我々が行った真に力学的な仮定であったわけだ。後は全て加速度変換公式の書き換えにすぎない。
こうして最終的に、特殊相対論的運動方程式
$$
\dfrac{d}{dt}\dfrac{m}{\sqrt{1-\left( \dfrac{\upsilon }{c}\right) ^{2}}}v=F
$$
に到達する。しかし上で注意したように、この運動方程式から物理的な意味を取り出すことが出来るためには、力Fの変換性を併記しておく必要がある。今の場合、「Fは粒子の静止系で観測される力と等しい」がFの変換性を規定するから、これを合わせて書いておこう。
つづき
今までの議論は全てかなり特別なシチュエーションを想定して行われていた。より一般の運動と観測者に対して運動方程式を考えようとすると、1次元ではなく3次元で考える必要が生じる。加速度や力の変換性も複雑なものとなる。
このような複雑な変換性を扱いやすくするために、ベクトルやテンソルといった概念を使ったほうが良くなる。そこで、この話の続きとしては、ベクトル概念を導入し、一般の運動と慣性系についての運動方程式を書き表すということになるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
