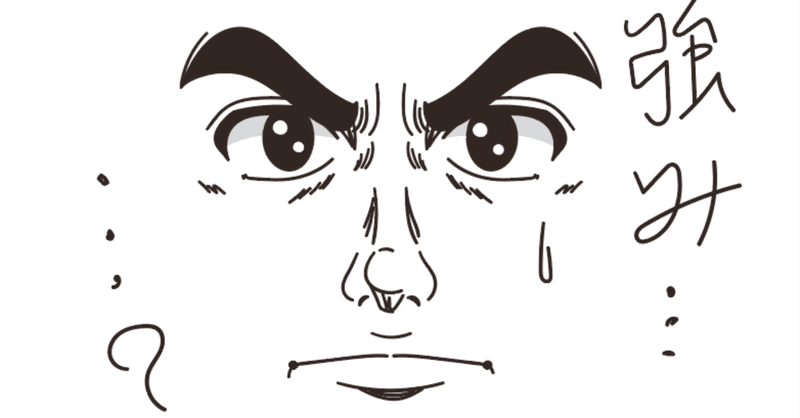
発明をブランディングするのが自分の役割
理系に進んだものの、自分は研究開発には向いていないと思った
それでも技術が好き、新しいモノが好き、ということに変わりはなく、それを活かせる職業として選んだのが弁理士
自ら研究開発をする才能はないけど、あたらしいアイデアに接することがとても楽しかった、と言いたいところだが、この仕事を始めたときは、発明者と同じ視点で発明を見ていたため、まず発明が理解できない、技術が理解できない、発明者の話が理解できない、という悲惨な状態だった
とくに発明者、企業の知財部を交えた「打ち合わせ」は、発明者へのインタビューを通じて、発明を特定し、発掘し、さらに発明を発展させていくということをリアルタイムで行っていく作業であり、何も分からない当時の自分にとって拷問でしかなかった
最初のうちはベテランの先輩と同伴するのだが、自分は一言も発言することなく打ち合わせが終了するということもあり、そんなときは事務所に戻って明細書を書いてみようとしても、まったくお手上げという状態だった
発明者と同じレベルの技術がないと、この仕事は務まらないと半ば諦めていたのが数年続いた
しかし技術が解らないなりにも、様々な技術分野の要素技術を少しづつ蓄積していったことが良かったのか、あるときブレイクスルーが起きた
質問するノウハウを身に着けたのである
事務所のスタイルやクライアントの方針にもよるのだが、発明者がまとめた提案書に基づいて出願書類を作成していく方法と、書類がない、あっても一枚程度で、打ち合わせによって得た情報に基づいて出願書類を作成していく方法がある
自分の場合は圧倒的に後者の割合が多かったことも幸いした
発明者にまかせて喋らせてしまうと、とんでもない高い技術レベルから話が始まるのだが、それまでの自分は、発明者の話をそのまま理解しようとして挫折していた
あるときから自分が理解できる技術レベルに合わせて発明者から情報を聞き出せるようになった
情報を聞き出すにもテクニックが必要で、あまりに素人っぽい聞き方をすると、発明者は親切に教えてくれるものの、知財部からは白い眼で見られる
発明者と知財部の双方を満足させて初めて「打ち合わせ」が成功するのである
この仕事を始めたとき、一人前になるには10年の経験が必要と言われた
文章作成力、質問力、審査官対応力、発明が特許になるかならないかの目利き力を揃えるには、それだけの経験年数が必要なのは間違えない
これまでの30年ほどの経験を振り返ると、10年を超えた頃から、この仕事に向いているのかもしれないと思えるようになった記憶がある
技術力がなくても質問力がある、と自負するようになって以降、「打ち合わせ」が楽しくなってくる
発明者との打ち合わせは真剣勝負なので、楽しい、という表現は不適切かもしれない
高いレベルでのインターラクティブが実現できたことに対する満足感と言えばよいだろうか
自分なりの打ち合わせスタイルができてくると、打ち合わせの目的も、発明を理解することではなく、発明をどのように発展させることができるか、ということになる
もはや発明を理解するのは当たり前で、その発明をより概念的に上位に展開し、またバリエーションを提案して横方向に拡大していくのである
このレベルになると、発明者に対する質問の内容は、こちらが考える展開を発明者に確認的に問うことになる
そうなると、発明者の口から、なるほど、という感嘆を聞くことができる
依頼者からすれば、「弁理士」はどれも同じだと思うかもしれない
でも、その人の考え方やキャリアを考慮すると、弁理士は皆、個性派揃いなのである
そんななか自分の役割は、発明者が気づいていない「何か」を、さまざまな角度から聞き出して発掘、そして展開することであり、発明をブランディングすることであると思っている
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
