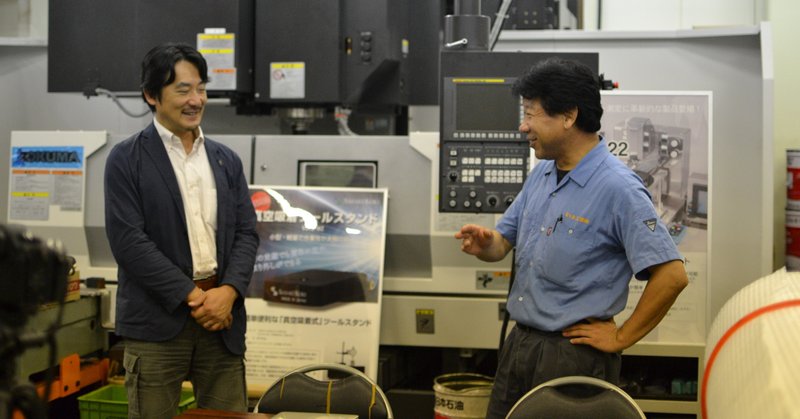
第137回MMS(2016/09/16対談)「1996年からネット活用したり自社製品開発にも積極的に挑戦する、川崎の町工場」後編 佐々木工機株式会社 代表取締役 佐々木政仁さん
本記事は2016年に対談したものです。情報はその当時のものですので、ご了承ください。
⇒前編から続く
●高精度の厚さ測定器――OZUMA22

enmono三木 先程途中までお話された自社商品開発について色々伺っていきたいと思います。ご自身でネタを見つけられて開発した自社商品(OZUMA22)が今こちらの方にパネルで出ておりますけども。これをご紹介いただいてもよろしいですか?
佐々木 はい。これは非接触厚さ測定装置といいまして、半導体のシリコンウェハーや液晶のガラスといったものの厚さ/厚みを測る装置なんです。厚さを測ることに特化しているので、厚さを測ることしかできないんです(笑)。ただ、それを高性能に測るというのがミソで、分解能が0.1ミクロン。
三木 すごいですね。
佐々木 方式としては、こういうウェハーを測るものですとレーザーとか分光干渉計とか、光の屈折を利用したものが色々あるんですけど、これはエアーを使ってまして――エアーといってもクリーンエアーなんですけど――。
佐々木 上下にノズルがあって、ノズルの先からエアーが出ていて、ウェハーを挟みこむような形でエアーを出しまして、その当たった時のエアーの圧力を――中身の圧力なんですけど――そのエアーの圧力を演算して高さに換えてリニアスケールとかリニアゲージといったもので高さを見て厚さを出すものなんです。
佐々木 エアーを使うということのなにが良いかといいますと、例えばレーザーとかですと測定物に個体差があったりすると光の加減とか曇りとか色艶とかが違うと誤差が出てしまうんですね。そのたびに構成し直さなくちゃいけない。
佐々木 エアーを使うと反射とか一切影響を受けませんので、光り方や磨き方が違ったとしてもそういうものに一切影響を受けないという利点があります。
三木 これを開発するにあたって、なにか「こういうのが欲しいよ」みたいなヒントをお客様からいただいたんですか?
佐々木 これは元々ウチが開発したというよりは、原理としてはエアマイクロメーターというものの原理なんです。それをあるところで――私の仲間なんですけど――精度を上げていったということがありまして、そこでこの装置を作るにあたって精度を上げるのが結構難しいこともあって、「こういうものってできないですか?」と頼まれたんですね。
佐々木 それでやってみたら意外とあっさりできちゃって。
enmono宇都宮 それは言っちゃっていいんですか? すごく苦労してできたという方が(笑)。

佐々木 あっさりできたというのは加工の部分です。もっと違うところに色々ノウハウがあるんですけど。それから色々一緒にやるようになって、元々OZUMA20っていうところからOZUMA22ってなって。
三木 バージョンアップしているんですね。
佐々木 どんどんバージョンアップして測定精度も上がって、測定速度も上がって、現在のバージョンになったんですけど。
宇都宮 お客さんが一定数いて、どんどんバージョンアップして……ということですか?
佐々木 そうです。たまたまこの22になった時に、その前までのバージョンは鉄製だったんです。鉄で作ったんですね。今回これはステンレスなんですけど、バージョンアップした時にバタバタッと4台くらい売れたんですね。
佐々木 今までなにも宣伝もしてこなくて、欲しいっていうお客様に売ってたという形で。本当に必要とされるところって大手さんの半導体部門とかで、どこでもっていうものじゃないので。
宇都宮 かなり限られますよね。
佐々木 その時にそれだけ売れたので、宣伝したらもっと売れるのかなって(笑)。それでこういうチラシやパネルも作って、ホームページにも載せたりして、本格的に宣伝し出したんです。
宇都宮 今年ということですか?
佐々木 いや、これは3~4年前です。
三木 本格的に宣伝を始めたら、またさらに受注が増えたんですか?
佐々木 結構引き合いはあるんですけど、値段がそこそこするので、現場ではいいと言ってくれても、なかなか予算が通らないということがあって。まぁ売れる時は売れるんですけど、売れない時は売れない。
三木 競合製品みたいなものはあるんですか?
佐々木 ありますね。
三木 それもエアーを使う?
佐々木 そうです。ただ、競合製品は価格がまず安くて。価格が安いということは精度も……。
三木 あまりよくない。
佐々木 あまりよくないって言うと怒られちゃうんですけど、測定するものによってそこまで精度はいらないっていうものはそれで充分だと思うんですよ。
佐々木 そこまで精度が欲しいよというものにこちらを使っていただければ、住み分けみたいな感じにはなるかなと。
三木 半導体もどんどん精度が上がってきていますから、こっちの方にみんな行くんじゃないですか?
佐々木 そうですね。あと、ウェハーとかも最近すごく薄くなったりだとか。
宇都宮 装置の行き先は海外とかではないんですか?
佐々木 特に海外の方へアピールしたってわけではないんですけど、一時韓国とかからすごく熱烈なラブコールをいただきました。
三木 大体なにをするかわかります。でもこれは精度モノだからそう簡単には真似できないですね。
佐々木 だと思いますね。精度を上げるというところで、ブラックボックス化しているところはあるので、そこはなかなか真似できないところがあると思います。あとは、エアーの質とか圧力をいかに安定させるかがミソです。
三木 なるほど。これで売上が上がっていると。
佐々木 上がっているというか、つい先日売れたのでこれから作るんですけど、結構あのー。
三木 いいお値段するんですよね。
佐々木 はい、数百万ですね。
三木 ちょうど我々が訪問した日に受注されたと。
佐々木 そうですね。
三木 我々、幸運を運んでいきますので。
佐々木 今後ともよろしくお願いします(笑)。
●真空吸着ツールスタンド――VSTS-WZ
三木 あともう一つ別の製品があるので、こちらもご紹介いただいて……。

佐々木 こちらは真空吸着ツールスタンドといいまして、世界的な測定器メーカーのミツトヨさんって皆さんご存じだと思うんですけど、ミツトヨさんと特許使用許諾契約というのを結ばせていただいて、そのライセンスを使って開発したツールスタンドです。
佐々木 この上に支柱を立ててダイヤルゲージとかピックテスターとかを載せて測定する時に使うスタンドなんですけど、従来は定盤(じょうばん)というと鋳物とかで作った鉄製のものが主流だったんですけど、最近は石の定盤の方が主流になってきまして。一番大きい理由は錆びないということ。あとは経年劣化が少ないとか、温度による変化が少ないとか。
佐々木 チッピングといって鉄だと落とすとまわりがへこんだりするんですけど、石だと欠けるだけで――底はへこみますけど――色々石の方が有利だということで、ほとんど石の定盤が主流になってきまして、石だとマグネットってつかないんですね。
佐々木 鉄にはマグネットをつけられるんですけど。それで結構お困りの皆さんがいらっしゃって。それにはなんとなく我々も気づいてたんですけど。で、こういうのがあるよとミツトヨさんからご紹介いただいて、じゃあその特許を使って開発してみようと。
三木 そちらに実物があるということなので。
●真空吸着、実演していただきました
三木 これが石の定盤なんですけども、通常こういう石の定盤でゲージとかを測ろうと思ったら、どういうことを通常の人はされているんですか?
佐々木 普通はどこもマグネットスタンドをお持ちなので、石だとつかないのでこういうスタンドの下に鉄の塊を置いて――重たいものを置いて安定させて、その上にマグネットスタンドを載せて。
宇都宮 二度手間ですね。場所も食っちゃうし。
佐々木 そうですね。こういうところに置いておけば落っことして足を怪我することもありますし。それぞれの会社で色々工夫はされてるんですが、こういうところにネジを立てちゃうところもあるかなぁと思います。
宇都宮 せっかく石定盤なのに、そういう加工をしてしまうんですね。
三木 これは(ただの石だから、上に置いたものは)スーッと動くわけですね。
佐々木 もう自由に動いちゃいます。で、この状態から、これはどこの工場にでもあるコンプレッサーからのエアーなんですけど、このエアーをウレタンチューブで入れるだけなんですけど……入れますね。
※エアー注入・排出
佐々木 これでもう動かないです。思いっきり横に力を加えると多少動くんですけど、真上方向には30kgくらいの力をかけても動きません。
佐々木 もちろんこれでエアーを止めれば動くんですけど、エアーを入れたまんまでも、この状態で指をちょっと(エジェクターに)添えてやると多少エアーで浮上するんですね。
三木 これはどういう仕組みになっているんですか?

※本体を裏返す。
佐々木 ここ(底面の外周)は吸着面なんですけど、ここにちょっと溝が彫ってありまして(内側の黒い部分)、チューブからずっとエアーが流れてるんですね。これ(本体側面の器具)はエジェクターというんですけども、小型の真空発生器と思っていただければ。エアーがチューブから流れて、エジェクターの反対側から出ています。
佐々木 このエジェクターの中と本体の底面に開いている穴が繋がっているんです。エジェクターから排出される空気によって気流が生まれて、この底面の溝の中にある空気が穴から一緒に排出されるんです。巻きこまれて。
三木 なるほど。それでこの中(吸着部内側の底面)が真空になる。
佐々木 そうですね。
三木 この装置のポイントというか、作る時にどのようなご苦労がありましたか?
佐々木 色々検証したんですけど、要は吸着力というのはこの溝の面積によるんですね。最初はちっちゃい溝から色々試していって、十字にしたりバッテンにしたり丸にしたりとか色々やったんですけど、安全性を考えるとできるだけ面積をとった方がいいとなって、こういう形になりました。
三木 これ、横にもくっついたりするんですよね。
佐々木 はい。

宇都宮 あ、垂直面にもいけるんですね。
三木 これはいいですね。
佐々木 平らな面であれば、もうなんにでもつきますんで。
宇都宮 石定盤じゃなくても……。
佐々木 石じゃなくても、鉄でもくっつきますし。
宇都宮 家庭の冷蔵庫でも。
佐々木 はい(笑)。こうした機械の板金のカバーとかにもつきますね。ただ、それが推奨できるかとなるとアレなんですけど。
佐々木 支柱はここをまわせば取れるので、これを取ってしまえば、お手持ちのマグネットスタンドをここに載せていただければ、そのままマグネットスタンドを石定盤の上でご使用になれます。
宇都宮 じゃあ、このベースだけ買えば。
佐々木 ここだけ買えばすぐに使えます。
※コンプレッサー等のエアー供給源が必要となります。0.4MPa~0.6MPaの圧力のエアーを供給してください。
宇都宮 そのジョイントもですか?
佐々木 本体というのはこれで、チューブ等は別売りになってしまうんですけども、これもバルブつきでだいたい3メートルくらいの配管セットをご用意しております。

佐々木 あとはこの支柱も、大体皆さんお持ちなんですけど、支柱も欲しいという方には支柱セットもご用意しております。
宇都宮 じゃあもう、いつでも佐々木工機にご連絡くださいということですね。
佐々木 はい、こちらへ(笑)。
宇都宮 こういうのは展示会とかでデモしたことはあるんですか?
佐々木 展示会は出させていただいております。
宇都宮 エアーとか持っていけないですね。
佐々木 エアーは小型のコンプレッサー。ここにあるんですけど。
宇都宮 それを持ちこんで実演販売も。
佐々木 はい。そうですね。
●開発にあたってのご苦労について
三木 ご紹介ありがとうございました。製造業であれば確かにモノを作ることはできると思うんですね。企画をして作るという。多分、製造業が経験したことのないのが販売ということだと思うんですけど、その辺のご苦労が色々あったと思うんですが。
佐々木 そこは実際、苦労というか苦戦しているというところはありますね。
三木 OZUMA22の方は引き合いが来ていると思うんですけど。
佐々木 真空吸着ツールスタンドの方も売れていないというわけではないんですけど、こういう工具とか測定器とかを自分で売るといっても、ホームページで売るとか、結局限界はあって、そういう専門の商社さんにお任せするのが一番いいかなと。それでいくつかの商社さんに取り扱いいただいて、というところがありますね。
佐々木 あとは商社さんにお取り扱いいただいてるんですけど、逆に宣伝してまわる営業マンの方たちに「これがどういうものなのか」とか、さっき言ったエアーの原理ですとか、どういった仕組みで吸着するのか、どういった仕組みで測定するのか、それをお伝えするのが大変で。
佐々木 お客さんのところで「なんでこれでくっつくんだ?」と言われて、それでわからないで私のところへ教えてくださいと来るから、そういう方たちに説明して理解していただくのが、やっぱり難しいなっていうというところがありますね。
三木 製造原理を知らないとそうなっちゃいますからね。
●どうして自社商品を生みだしたいと思ったのか
三木 我々の考え方にマイクロモノづくりというものがあって、自分で企画して、自分で製造して、自分で販売する。町工場がちっちゃいメーカーになるという風に捉えていて、それをどんどん町工場さんがやったらいいなぁと色々なところで言っているんですけど、そういうことに関してはどういう風にお考えになりますかね。
佐々木 それに関しては今まさにウチの会社が取り組んでいて、今2点だけご紹介させていただいたんですけど、そのほかにも福祉機器とかもやったりしてるんですよね。
三木 ああ、そうなんですか。
佐々木 ええ、ウチの製品として。やってるんですけど、そういうものを――本業を蔑ろにするわけじゃないんですけど、本業をキチッとやりつつそういうアイテムを一つ一つ増やしていきたいなと思っていて。
佐々木 一つ開発するのにやっぱり最低でも1年とか。1年でできれば本当に最高なくらいで、やっぱり何年ってかかるわけじゃないですか。
佐々木 まぁ、まだまだ私は何十年とやっていかなきゃならないわけですけど、その中であと何品世の中に出せるかなって思いますけど、ただそういうのを着実に、一つずつでも、少しずつでも出していきたいなと思っています。
三木 自社商品を生みだしたいと思ったきっかけはなんだったんでしょうか? 本業をやっていれば、売上は立つ状況だったと思うんですけど。どうして敢えて自社商品を持ちたいと考えたのか、といったところを伺えれば。

佐々木 そうですね。なんとなくそれって昔から夢っていうかね。中小企業の特に下請っていうのは脱下請みたいな気持ちでやっていきたいという、なんとなくそういうものもあるし。
佐々木 あと、今実際に少しずつやり始めて、色んなことをやると、新しいことをやると、色々なことが返ってくるので、色々勉強になるんですね。
佐々木 モノを作って売れるか売れないかって考え方もあって、そこも重要なんですけど、とにかくやってみようというところもあると思うんです。
三木 チャレンジ精神。
佐々木 そうですね。そうすると例えばそれが思ったほど売れなかったにしても、だけどそこで学んだことってすごく。
三木 なぜ売れなかったのかと分析したことが糧となるんだなとわかって。
佐々木 それとか例えば今まで作るだけだった人が売らなきゃいけない。売るためにはどうしたらいい? どうしなきゃいけないかとか。あるいは特許を取らなきゃいけないとか、色んなことを調べるわけですよ。
佐々木 そういうことが一つ一つ勉強になって知識として自分の中に溜まってくるので。
宇都宮 プロモーションしてみたりとか、人前で色々語ってみたりとか。
佐々木 色んなことが勉強になって。世の中的には「じゃあ、おまえそれでいくら儲かったんだ?」というところで評価されると思うんですけど、結構そういうのってお金には替えがたい部分ってあって、すごく勉強になってるなぁと思います。
三木 自社商品をやり初めて社員の方はどうですか? 変わったこととかありますか?
佐々木 あまり言わないですけど、多少夢を持って仕事ができるっていう部分はあるかと思うし、例えば開発段階とかでも「ここどうしたらいい」「ああしたらいい」とみんなで考えたりすると、自分のアイデアが盛り込まれるというところがあるじゃないですか。そこは多分いいところかなと思います。
三木 モチベーションが上がるということですね。
佐々木 ええ。次はどうしようとかこうしようとか。今の吸着スタンドにしても、次はこういうものも出したらどうかというアイデアは結構いっぱい出てるんです。
三木 社員さんの方から提案していただいて。
佐々木 そうです。
三木 素晴らしいですね。
●日本の○○の未来
三木 色々お話は尽きないんですけども、そろそろお時間の方が来まして皆さんに一番最後にお伺いしている質問がありまして。佐々木社長の考える「日本の○○の未来」。○○はご自身で入れていただくですけども。
佐々木 あ、そうなんですか。
三木 これはお好きなもので結構です。モノづくりでもいいですし、自社商品開発でもいいですし、町工場でもいいですし。関心のあるものの未来について教えてくださいという。
佐々木 そうですね。町工場の未来っていうと、どういう未来が描けるかっていうとわからないですけど、下野毛なんかの地域を見てもそうなんですけど、せっかく残ってる人たちがみんな元気ですごいヤル気があってっていう人たちが私のまわりにはいっぱいいるので、そういう人たちが協力して切り拓いていけたらというか。
佐々木 じゃあなにができるかというと、いい例でいえば下町ボブスレーとか頑張ってる人たちがいるじゃないですか。
三木 はい。
佐々木 ああいうことをやると宣伝効果というか。我々もそうなんですけど下野毛っていう土地でやっていて、下野毛っていうところが「モノづくりといえば下野毛!」というのを目指しているところがありまして、ものづくり共和国も下野毛工業協同組合もそうなんですけど、なんの団体だって関係なくて、とにかく下野毛っていうところがモノづくりのメッカだという認知をされれば仕事も集まってくるでしょうし。
佐々木 あそこで頼めば間違いないみたいな、なんでもできるみたいな、そういうブランド化をしていきたいなと思います。
三木 いいですね。

宇都宮 佐々木さん的にはモノづくりっていう表現と製造業は若干違うニュアンスなんですか?
佐々木 と思いますね。最初にモノづくりって聞いた時に、私は自分たちがやっている製造業がモノづくりなのかっていうと、なんとなくギャップはあったんですけど、最近は製造業っていうとなんとなく大手さんから流れてきた仕事をやってるみたいな感覚が。
佐々木 モノづくりっていう方が大きな意味で含んでいるのかなと思って。例えば学校の先生は人づくりっていう言い方ができるかなと思うんですけど、そういうことも含めて色んな新たな……。
宇都宮 創造的な。
佐々木 創造的な、そういう意味をこめてモノづくりって言いたいなと思いますよね。
宇都宮 下野毛もクリエイティブな、創造的な、ワクワクするような雰囲気に。製造業以外にも色んな人が関わって、なにか生み出せると……みたいなイメージですよね。
佐々木 今までの概念を壊してほしいなっていうのはありますよね。製造業はモノ作ってる。モノづくりって言ったらモノだけじゃない――モノづくりなんだけど、色んな広い意味でっていうことで、色んな人たちと連携して新しい分野ができれば面白いですよね。
宇都宮 FM出てる方もいらっしゃいますしね。
佐々木 ああ、そうですね。そういう突拍子もない、我々にはない考えを持つ方たちの意見っていうのはすごく刺激にもなります。
三木 ありがとうございます。下野毛から新しいモノづくり文化を発信するみたいな。
宇都宮 面白いモノを考える人は下野毛の飲み屋にフラッと来ていただければ。
三木 そうですね。飲み屋があるといいですね。
宇都宮 コミュニティスペースみたいな。
佐々木 お待ちしています。
三木 どうもありがとうございました。
佐々木 ありがとうございました。

▶対談動画
▶佐々木政仁さんFACEBOOK
https://www.facebook.com/masahito.sasaki.12
▶佐々木工機株式会社WEBサイト
▶ものづくり共和国WEBサイト
▶真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ
■「enmono CHANNEL」チャンネル登録ねがいます。
■MC三木の「レジェンド三木」チャンネルもよろしく
■対談動画アーカイブページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
