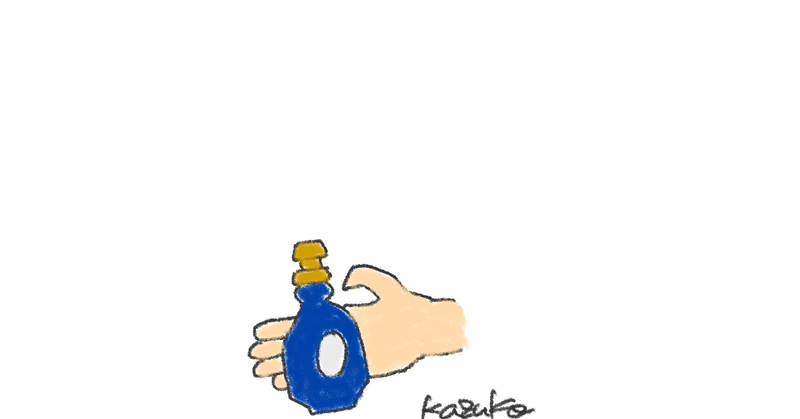
『パフューム ある人殺しの物語』 大ヒット小説の映画化。斬新な題材だけに芸術趣向の観客にはお勧め。
評価 ☆☆
あらすじ
18世紀、パリの魚市場。悪臭が強い場所でひとりの女性が男の子を屋台の下で産む。女性は死亡し、男の子はジャン=バティスト・グルヌイユなづけられ孤児院に預けらることになる。その後、5歳に成長したグルヌイユは無口だった。
2006年公開の『パフューム ある人殺しの物語』は、監督がトム・ティクヴァ。出演はベン・ウィショー、レイチェル・ハード=ウッドなど。この映画にはいくつかの誤解がある。
ひとつは乱交映画と思っているひとがいる。そんなのはAVにまかせておけばいいし、一般映画でそんなことできるわけがない。また、香水の話でもない。「匂い」がテーマになっているのは間違いないけれど、香水がこの映画のすべてではない。この映画は娯楽作品とは一線を画している。
以下は映画を観てから読んでください。
18世紀のパリが舞台。異常なほどの嗅覚を持つ主人公ジャン=バティスト・グルヌイユは世界を匂いによって識別していた。青年になった彼はこれまで嗅いだことのない女性の匂いと出会う。そこから悲劇的な殺人が行われることになる。
誰かが指摘していたけれど、この映画では主人公の食事シーンつまり「食べる」カットがない。彼は生きていない。生きるとはどういうことか? その存在を周囲に認められるといってもいい。彼は魚市場で産み落とされ、売買され、成長する。彼を人間として認めている他者は誰もいない。
そんな彼を誘惑したのはある女性のフェロモン。その匂いを再現するためにグルヌイユは人殺しを行い、女性の匂いを集める。作り上げた香水はほんの数滴で人々の幸福感を絶頂にまでたかぶらせる。
連続殺人犯として捉えられた彼は媚薬によって天使と見なされる。この映画にはやたらとカトリック司祭が出てくる。人々に節制を促し、神の到来を予言するのが司祭の役割だが、宗教も媚薬の前には無力である。
この映画における香水は科学のメタファーだろう。実験中のグルヌイユは何万匹のペットを殺す遺伝子学者、少数の人間たちの命なら仕方がないと考える製薬学者たちの姿だ。彼らには純粋な好奇心はあるがモラルは存在しない。
しかし、そんな彼らが作り上げたものが人間にとって非常に魅力的なものだとしたら? 映画のクライマックスはリテラシー、人間の作り上げた倫理の終わりを意味している。
ところが、それで物語は終わらない。科学の発達は本当に我々を幸福にしているのか? 映画のラストはカニバリズムの渦の中に消える。人間の欲望の深さが伝わるシーンとも捉えることができる。
映画表現のクオリティは高い。美術も素晴らしい、カメラワークも申し分ないし、音楽もパーフェクトだ。ベルリン・フィル、さすがです。映画でしか表現できないシーンも数多くある。これほどに面白いのに一般受けをしない題材とは! まさに問題作と呼ぶにふさわしい。
パトリック・ジュースキントの大ベストセラー小説の映画化。確かにすべてがゴージャスです。お金がかかってますね。
初出 「西参道シネマブログ」 2012-6-17
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
