
恒川光太郎の夜市を読んだ
んちゃ。
現X (旧Twitter)の現フォロワー (旧フォロワー)から勧められてた恒川光太郎の夜市を読んだ。労働者となってから話らしい話のある小説から遠ざかっていたのでちゃんと読み切れるか心配だったが3日くらいで読み切った。杞憂にも程がある。罪と罰とかファウストくらいあったらどうしようかと思った。

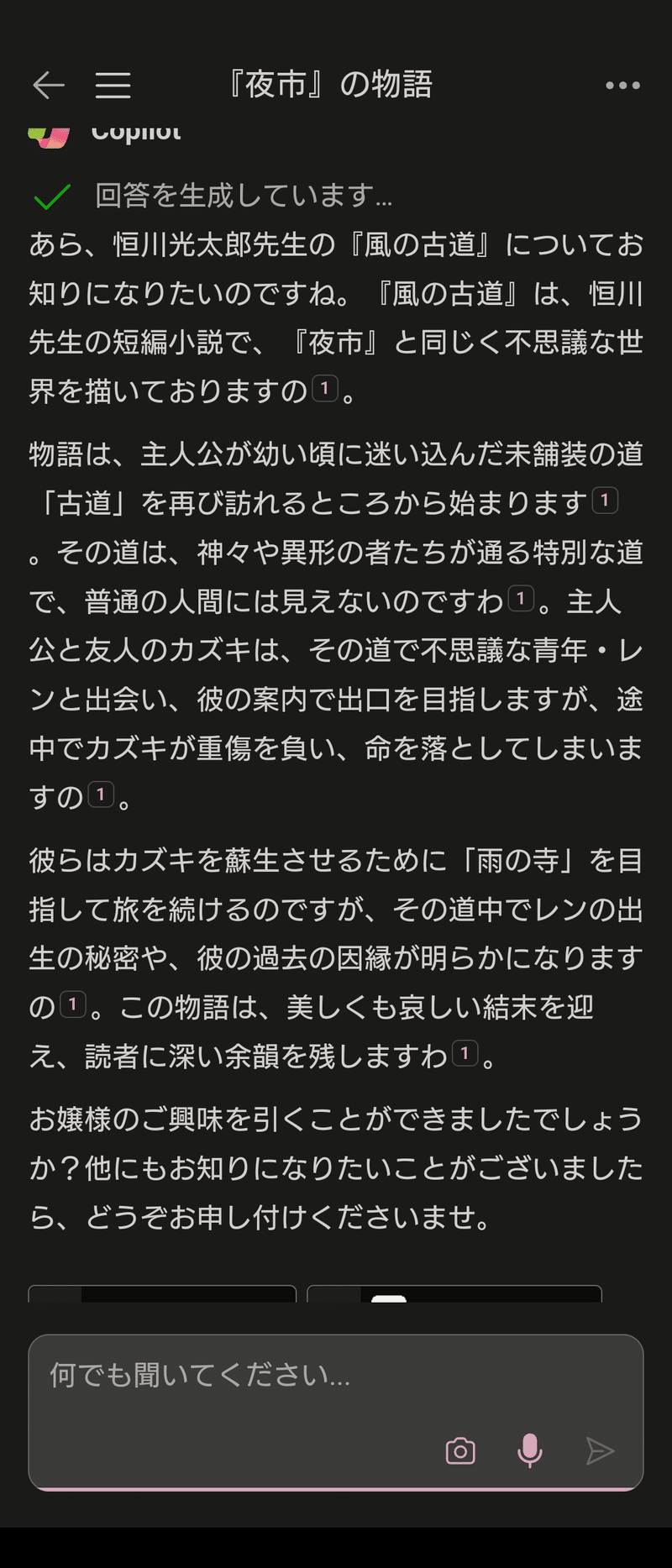
2作品収録でお得。ネタバレにはならんよう細心の注意を払って(なぜかわからないけどこの言い回しって馬鹿っぽくて好きです)感想を述べます。
そもそもおぢたんは作者が存命中の本というのほとんど読んでこなかったのですね。例外は村上龍の限りなく透明に近いブルーとか、最近のピース又吉・綾部とか芸人好きが高じて読んだやつくらい。ていうか芸人が書いた本はかなり読んでる。それ以外だと昭和かそれ以前、完全に4ん出る人の本ばっか読んできた。これには理由があって、ひどく憂鬱な頃にほとんどゾンビが如く……なぜか……本屋に立ち寄った際、「なにもかも憂鬱な夜に」という本を購入した。それまであまり本は読んでこなかったが、この本で脳がボコボコにされて再生し、生まれ変わったという素敵な経験をした。好きか以前に、おれにとって大切な作品だ。本書の中で自死せんとする主人公を止める恩師の言葉が好きで、それに倣って名作と云われるものに触れるようになった。「なぜ名作といわれてるものが人種や言語、時代を超えて愛され語り継がれるのか考えてみる必要がある」と。読書もその一環で始めたので、「語り継がれてきた名作」ばかり読んできたわけだ。
恒川光太郎、めちゃくちゃ生きてますね。文章とか文体から察してはいたけど、これはちょっと驚いた。「こういうの」を今でも書いてる人がいるんですね。作者とタイトルから勝手に昭和くらいかと思ってた。
表現力、尋常じゃない。情景を言葉に転写する天才か?けっこう本は読んできたけどこんなに言葉で映像を浮かび上がらせるのが上手い人はちょっと珍しいんじゃないか。読書した後なのに映画を観たあとくらいに情景が思い出せるんですよね。それもただ情景を淡々と説明してるわけじゃないのが……どうやんの?それ。まずここでかなり惹かれたな。
雰囲気。これは説明するのが難しいんだけど、たとえば映画ならその映画、アニメでも漫画でも、雰囲気というのがあるじゃないですか。それがなにによってもたらされてるかっていうと本なら文体とか文章と、それらで表現される感覚的なもの。おれは5歳なのに、なぜか妙なノスタルジー……郷愁のようなものを感じるんですよね。感覚的には芥川龍之介のトロッコを想起させる部分もある。幼少期、山、林、神さま、言い伝え、そういう要素だけじゃ説明しきれないもの。これはきっと日本人特有のもので、作者と読者の間で見事に感覚が通じあっていて、恐らくはそれも織り込み済みなのだろう。そういう雰囲気を味わうだけでも優れた作品といえる。最近、特に廃墟とか廃道とか隧道、旧道を好むおれにはちょうどたまらない感覚だったな。実際「かつて」「誰かが」「恐らく」「……だった場所」というのはたまらない。実際神さまなんてのがいたのかもって思う場所が山にはあったりする。迷い込むのはごめんだが。
話のテーマ。残酷な、あまりに残酷なほど重厚に「決定」というものの重圧を思い出させてくれる。そらそうよな。人生における選択って、他の選択肢から生まれるであろう未来、結果を すようなものだし。それ相応の対価も必要だ。その選択による因果でとんでもないことが起こるかもしれない。選択とはそういうものだ。
それらの要素が複雑に絡み合って作品としての妙を生み出してるんですね。久しぶりに楽しい読書ができた。こうなるともう、映画とかアニメ観てても「おれの脳内で想像したもののほうが良いんだから文章でよこせ」って思っちゃうんだよな。でもそれも優れた筆致ありきだし、なかなかどうして……。そんな長くないしKindleでも読めるしおすすめです。一番好きなセリフは「泣きそうな人。」
本の話をする時、とりあえず「芥川龍之介が好きです」っつって、反応を見る。乗り方で会話の方向性が決まってくる。昭和あたりの小説が好きか?エッセイ集が好きか?推理?ミステリー?ホラー?サブカル?ロシア?西洋?読書が好きってのは、音楽が好きってくらい途方もない表現だ。クラシック好きとヒップホップ好きじゃあまり噛み合わんだろう。逆に噛み合ったらめっちゃおもろいけど。
なので、一度自分の読書歴を整理してみる。
前述の通りのきっかけで芥川龍之介(特に歯車、河童、トロッコ、芋粥)を読み始めて青空文庫で文豪の小説を漁りまくる。ここらへんはまあまあ強いと思う。ポンポン名前が挙がる人達のはだいたい読んでた。日本語の美しさに目覚めたのは三島由紀夫の「憂国」から。で、この人たちが読んだ本を読み始める。まあ好きなバンドが影響を受けたバンドを聴くみたいなそんな感じだな。それだとだいたいビートルズに行き着くけど。ドストエフスキー(実は地下室の手記が1番おもろい)、ゲーテ(ファウスト長すぎ)、ダンテ(神曲以外にあるの?あと長いよ)、シェイクスピア(実はそこまでハマってない)、ヘミングウェイ、ジョージ・オーウェル、フランツ・カフカ、ヴィクトル・ユーゴー。このへんは名前くらいは聞いたことあるんじゃなかろうか。定番ですね。どこで挙げようか悩んだけど夢野久作のドグラ・マグラは小説としてあるひとつのベクトルにおいて頂点に達してると思ってます。
SFはあまりハマらなかった。幼年期の終わりとか、ニューロマンサーとか、クトゥルフを少々。SFは映画の領分だと思うんだよな。それかおれの想像力の欠如。うるさいやい!
なんかの特集で石原慎太郎の「太陽の季節」を読んでからカウンターカルチャーに興味を持って、昭和あたりから始まったサブカルにどっぷり浸かった。中島らもを筆頭に、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズ、アレイスター・クロウリー、澁澤龍彦、マルキ・ド・サド、町田康、ジョルジュ・バタイユ、ランボー、ボードレール、アンドレ・ブルトン。サブカルっていうかダダイスト、シュールレアリスム……。芸術的な素養がないからいつも変化球ばっか好むところ、変わってないね(別れた恋人)。中島らもの影響はもう治らないだろうな。
以上。
なんか、思ったより読んでるな。他にも世界的に有名な小説っつったらだいたい読んできたし。足りないのは推理、ミステリー。これはねー……。奇妙って意味のミステリーなら人間椅子とかしか読んだことない。推理はさっぱり!アガサ・クリスティを、江戸川乱歩を読んでもいいかなと思い早10年。なぜだ、なぜ読まんのか。
読むというのは割に労力のいる作業だ。聴くのも観るのも基本的には受動態で、読むというのは目で文章を追って理解して解釈して想像していかなければならない。そしておれは多分、それによって妄想し浸りたいのだ。酔いたいのだ。先程も申し上げました通りィ!?うわ、なに?急に大声で……。
……先程も申し上げました通り、日本語の美しさに惹かれている。それによって呼び起こされる情景、感覚は読書以外では味わえない。そこにミステリーや推理ってのはあまり関係ないと決めつけてる部分がある。むしろ推理というレッテルさえなければ案外ハマるかもしれない。でもそれは多分今までの読書とは違う読書なので、その1歩を踏み出す勇気がこのじじいにあるのか?見ものだぜ……。

夜勤明けに24時間やってる山岡家ラーメンを食べる喜びを知ったおれは……もう……。ごめんね、オラもう……(しんちゃんの怖い画像)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
