
越境のための分断──『小市民シリーズ』第1話における “線” について
はじめに
線に惹かれる。
建物の境界線、窓の枠線、山の稜線、あるいは陰を落とす光線さえも──『小市民シリーズ』第1話はまごうとなき “線” アニメだ。線にフェチズムを感じると言ってもいい。
むろんそれは、徹底された水平的構図やねばり強い長回し、特徴的なシネスコのフレームといった(広義の)カメラワークに支えられてもいる。絵づくり(レイアウト)はもとより、演出や美術、撮影、そして音楽によってさえ、 “線” は引き立てられているのだ。
アニメーション全体に支えられたそれはだから、「線の美学」とでも言うべきひとつのスタイルを形成しているとすら言えるかもしれない。
──と言って、「だから、何?」なのだろう?
なるほど『小市民シリーズ』第1話には “線” のフェチズムがあるかもしれない。 “線” を通じて生じさせるアニメーションの快楽があるのかもしれない。
しかしその源泉は何なのか、 “線” は何を意味するのか、あるいは意味するところが分かったとして、「だから、何?」なのか。
ぼくが思うに、この件は画面の分析で片がつく。
1 分断としての “線”
1.1 「狐」と「狼」の分断
たとえばこんな “線” があった。

「狐」と「狼」を分断する “線” 。『小市民シリーズ』において、「狐」とは小鳩を指し、「狼」とは小佐内を指す(本作のOPでも、それは暗示されている)。[1]
意味はきわめて明快だ。「互恵関係にあるが、依存関係にはなく、まして比翼連理の類では全くない」[2]、いつもどこか “線” 引きした二人の距離感を、どのショットも暗に、しかし如実にあらわしている。
声を掛けるなら物陰から(左上図)、手を差し伸べるも触れはせ(右上図)、引き留めるにしても一歩退いて(左下図)、並び立つとも陽が二人を分かつ(右下図)──。
いずれにしても、画面に配された物体の “線” (看板、カトラリー、ベンチの端、陰影)を利用して、ほんのり “線” が引かれているように感じる構図が、ささやかに二人を分断している。
1.2 「探偵」と「犯人」の分断
あるいはこんな “線” もあった。

ここでは、「探偵」(小鳩・画面右手前)と「犯人」(高田・画面左)とのあいだに分断 “線” が引かれている(念のため付け加えれば、高田(画面左)こそ、第1話のポシェット事件の犯人だった)。
柱を隔てて左に寄った高田は、あとから見れば、なるほど独りだけ浮いているようにも見えるが、人数的に右に比重がかけられ、加えて、消失点も右奥に配されていることで、動画で短い時間見る分には、なんとなく右に視線が誘導される。
*
「犯人」が分断されるショットは、このあとも引き続き描かれる。

たとえば上図では、「犯人」(高田・画面右)と「被害者」(吉口・画面左)がやはり建物の “線” (と堂島)を隔てて分断されている。
明確に距離感を感じるこの構図はしたがって、高田がポシェットを盗んでまで遂行しようとしたふるまいが、おそらく成功しなかったであろうことを予感させる。
*
それから「犯人」というなら、いちごタルトをつぶした憎き「犯人」もまた “線” で隔てられていた。

ただしここではこれまでとは一風変わった、言ってみればトリッキーな “線” で分断されている。
それはすなわち窓ガラスだ。コンビニの窓ガラスが、左右ではなく、手前と奥とを隔てて、小鳩(手前)と「犯人」(奥)を分断している。
これまでとは別種の “線” ではあるかもしれないが、こうした “線” の縦横無尽さが、のちのち効いてくることになる。
それについては後述するとして、もう少し分断 “線” を見てみよう。
1.3 他者との分断
トリッキーな “線” としてはこのようなものもあった。

ここでは堂島(画面右手前)と小鳩(画面中央奥)が、陰影を隔てて配されている。
一見して明らかなように、堂島が「陽」の側、小鳩が「陰」の側に位置するのだが、それは単なるパーソナリティの反映というより、操作を主導する堂島と、ここではまだあくまで「小市民」として、波風立てない程度に友人を手伝う小鳩のありようを示したものと見るのが妥当だろう。
*
あるいは「小市民」に徹する、という構図ならこんなものもあった。

ここにはなんともきわどい “線” が引かれている。
堂島の上半身になかば沿った掲示板のガラスの境界(および掲示板の支柱)がそれなのだが、それがほんとうに分断 “線” なのか、これだけではなんとも言い難い。
しかし、こういう情報が付け加わったらどうだろう。つまり、小佐内のふるまいが「小市民」を象徴するそれだと分かれば、そこにたしかに距離を感じられるのではないだろうか。
「小市民たれ」。これ。日々の平穏と安定のため、ぼくと小佐内さんは断固として小市民なのだ。もっとも、その表れ方はちょっと違う。小佐内さんは隠れる。ぼくは、笑って誤魔化す。
そう、「小佐内さんは隠れる」のだ。小鳩を隔てて堂島に向かう小佐内はだから、「小市民」として、たしかに他者とのあいだに線引きをしている。
幕間:「小市民」としての “線”
ところで「小市民」を示す “線” というならば、何も特定の場面にかぎらず、最初からずっと、つねにすでに、そこに現前しているとも言える。
いわゆるシネスコがそれだ。アスペクト比2.35:1というその比率は[4]、現在のTVアニメーションの多くが採用する16:9という比率とは異なり、同じスクリーンで見れば、縦に窮屈に感じられるようなつくりになっている。
つまり「“小” 市民」たる小鳩や小佐内はいわば、ふつうの世界よりも “小” さな画面のなかに、最初から閉じ込められているのだ。
シネスコはそのように、いつも抑制されたふるまいを求められる「小市民」の世界そのものを反映していると読める。
もちろんそのさい、抑制の効いた水平的なレイアウト、つまり、決して “俯瞰” しないレイアウトもまた、「小市民」の世界をつくるのに一役買っている。
*
だが待て。その理屈なら、堂島やほかの人物たちだって同じシネスコのうちに映されているのだから、彼らもまた「小市民」ということになってしまわないか?
厳密にはそうかもしれない。あるいはもっとシビアに考えるのなら、「小市民」を演出したいときには、「小市民」たる小鳩や小佐内のPOV(point of view:一人称視点)でのみ、シネスコを使うべきとも言えるかもしれない。
これに対しては、べつに制作の都合上、シネスコが「小市民」的世界を演出していると端的に言ってもいいのでは? と、やや寛容になることもできよう。しかし本稿は、もう一歩踏み込んで、シネスコがさらなる意味合いを持たされていると解釈してみたい。
すなわちシネスコは、(小鳩や小佐内というキャラクターというよりは)『小市民シリーズ』という作品そのものが、 “抑制” された/”制約” を受けた世界であると見る、メタ的な視点の反映なのだと解釈してみたい。
*
その視点とは、鑑賞者(自分の作品を鑑賞する作者も含む)の視点である。というのは、そもそも『小市民シリーズ』は、「探偵」役を果たしてしまうような思春期の「全能感」が “抑制”・“制約” され、「無能感」に転ずる、アンチミステリーとして読むことができるからである。
そもそも『小市民シリーズ』においては、ミステリーに必要不可欠なはずの「探偵」役がそもそも牙を抜かれ、「小市民」たらんとすることが出発点だった。
気持ちはよくわかる。目の前で探偵めいた真似をされるのは決して気持ちのいいものではないと、ぼくは知っている。
小鳩は過去の失態から、「探偵」≒「狐」としての役割を発揮してしまう性を反省し、それを抑制することで「小市民」たらんとしていた。このふるまいはしたがって、「探偵」役がいつも “出しゃばって” しまうミステリーへのアンチテーゼと読解できるのである。
*
あるいは、作者である米澤穂信もこう述べていた。
この全能感と裏返しの無能感、これを試練にかけることで自分を客観視することのできる視点を獲得する、そこまでの物語として〈古典部〉シリーズと〈小市民〉シリーズは考えています。
この「全能感」と「無能感」のせめぎ合い、そしてそれを遠くから「客観視」する鑑賞者の視点のそれぞれが、シネスコや各種の “線” によって制限された画面をうまく利用して表現されているのではないか。
すなわち、シネスコで狭められた画面は、この「全能感」が「無能感」で “抑制”・“制約” されていることの(そしてそれを「客観視」する鑑賞者の)メタファーとして、ひとまずは読めるのではないか。
2 越境のための “線”
2.1 「無能感」としてのフレーム
たとえば、そうした「無能感」がよくあらわれたシークエンスとして、以下のような場面があった。

このシークエンスでは、カメラが固定(FIX)され、あいかわらず水平的である画面から、「犯人」を追いかけようとした小鳩が一度フレームアウトし、再びがフレーム内に戻ってくる。
この演出はしたがって、「犯人」を追いかけようとして、一時的に「探偵」役に転じるために小鳩は「小市民」=シネスコのフレームから脱出し、しかし「犯人」を徹底的に追いかける「狐」にはなりきれず、シネスコのフレーム内=「小市民」の枠組みに舞い戻る演出だと解釈できる。
加えて言うならば、小鳩は結局、コンビニの(きわめて背の低い)外縁すらも超えられずに、その内側にとどまる。そこではレターボックス(=シネスコのフレーム、黒い帯)だけでなく、コンクリートの外縁すらフレームの役割を果たし、「小市民」をより “小” さなフレームのなかに、惨めなまでに収めるのである。
「犯人」を徹底的に追う「狐」には成り切れず、穏やかに事態に向き合うほかない「小市民」の「無能感」が、よくよく表現されているカットと言えよう。
2.2 「全能感」としての越境
だから反対に、「小市民」的ふるまいを逸脱するさいには、キャラクターは(疑似的な)フレームを乗り越えてゆく。OPの以下の一幕は、まさにそれを代表するカットだろう。
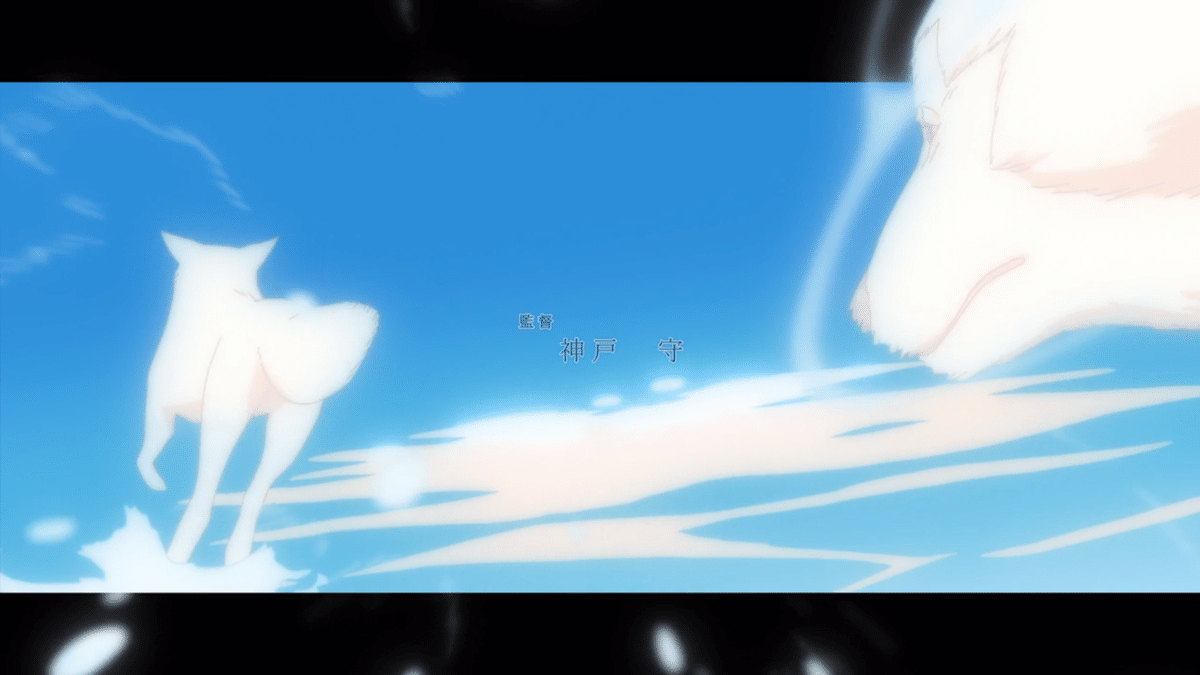
ここでは「小市民」から解放され、「狐」や「狼」と化した二人が──最初にややミスリードに書いてしまったが、「狼」や「狐」は、二人が「小市民」ではないときの姿であり、むしろそうした行き過ぎたを反省して、「小市民」を志したのだった──、まさに「全能感」を味わうかのように、縦横無尽に画面を駆け巡り、レターボックス(=黒い帯)さえ越境してゆく。
本編では徹底的に破られることのなかったその越境はだから、今後は(OPだけでなく)本編においてさえも、レターボックスを越境する可能性、小鳩や小佐内が「小市民」を脱する可能性すら予感させる。
2.3 小さな逸脱としての越境
「小市民」を(一時的に)逸脱するようなふるまいは、しかし1話にしてすでに示されてもいた。たとえば二人乗りのシークエンスは象徴的だ。

この直前、小佐内は「警察に捕まっちゃったら、いちごタルトどころではないけどね」と、あらかじめ「小市民」を逸脱するような、緊張感を持たせるようなセリフを口にする。
それだからこそ、越境はよりチャレンジングに映り、「小市民」から(一時的に)逸脱した小佐内はやはり、フレームの外へと脱出する。
*
あるいは、この二人乗りにおいて初めてフォロー(Follow:被写体がつねに同じ位置になるようにカメラが追う)が解禁されるのもまた意味深だ──それでもパン(PAN:位置を固定してカメラの首を振らせる)はしない!──。

これまでほとんど徹底的にフィックス(FIX)を貫いてきた画面は──かろうじて序盤のカフェのシーンでほんの少し小佐内に併せてカメラが揺れる──、ここにおいてようやく動き始める。
二人乗りという、ささやかな逸脱行為に併せて、川を、そして橋を越境するのだ。
そしてもちろん、この川/橋の越境こそ、第1話の頂点(見せ場)にほかならない。
2.4 「完全なる小市民」への越境
第1話の後半、それまできわめて控えめだった劇伴が盛り上がりを見せる一幕で、小鳩と小佐内は、明らかに現実とは異なる、空想的な世界での運動を始める。
陸橋の道路を横切り、小佐内が川のなかに小鳩を誘い込む描写がそれだ。

とはいえ、ここでは先の「狐」と「狼」の描写のように、フレーム自体が乗り越えられるということはない。道路の中央線や河畔と水流の境界線といった、画面内の “線” をミニマムに越境するのみである。
加えて、この場面はあくまで想像の、イメージの世界である。したがってこの越境は、「小市民」からの離反を示すものでは決してない。むしろ「小市民」(=シネスコ)の枠組みのなかで、さらには現実には干渉しない想像のなかで、「穏やかな時間を作り出」すという、それこそ「完全なる小市民への飛躍」のための、小市民宣言なのだ。
この疑似的な越境、渡っているようで、その実、渡り切ってはいない絶妙な在りようこそ──実際アニメーションにおいても、橋を渡っている最中の描写はあるが、橋を渡り切った瞬間の描写は無い──、小市民そのものの在り方だと言えよう。
2.5 川の “越境” が示すもの
ところで、橋の越境はよいとして、川の越境はなぜこんなに中途半端なのだろう?
橋を端から端へと渡ったように、川においても、こちら側からあちら側へ、此岸から彼岸へと渡らせてもよかったのではないか? どうしてアニメスタッフは、川の水のなかにいる小佐内のほうに小鳩もいっしょに入るという描写を採用したのだろうか?
もちろん真意は分からない。だが、以下のように解釈することができるのではないだろうか。

すなわち、小佐内が、自らが位置する水のなかへと小鳩を誘い込むかのようにも見えるその描写は、「互恵関係にあるが、依存関係にはなく、まして比翼連理の類では全くない」と銘打ったはずの「小市民」としての二人の関係性が、その実、水底の見えないような陥穽へとおちいってしまうことを予感させる、いわば “呼び水” としての描写なのではないだろうか。
それはつまり、一言で言えば、破綻への予感である。思えば第1話は、これまでずっと、固定的な画面や水平的な構図によって、“安定” のための描写が選ばれてきた。あるいはシネスコの、通常よりも狭いフレームのなかで、“制限” がかけられてきた。
これは裏返せば、いつ “不安定” に転ずるか分からない、いつ “無制限” に暴走するか分からないという緊張感がつねに背後に潜んでいるとも受け取れよう。こうした破綻への予感を、それとなく暗示するモチーフとして、ともすると流されかねない流水に二人が沈むという表現を選んだのではないか。
*
なにより、そう解釈すると、原作をカットして、ポシェット事件から間を端折っていっしょに水に浸かるこの描写を接続させたことにも得心がゆくと思うのだ。
ポシェット事件のとき、高田のジャージの裾が濡れていることを見逃さず、小鳩はこう言っていたのではなかったか。
「濡れてしまったものはそう簡単には乾かない。」
一度結んだ関係は、たとえそれがどのような関係に陥ろうと、簡単に解消することはかなわない。
はたして二人の関係性がいかなる路 “線” をたどるのか、言葉よりもむしろ雄弁に物語るアニメーション描写とともに、今後を見届けたい。
おわりに──あるいは「探偵」役を演じてしまうことについて
本稿は、『小市民シリーズ』第1話における “線” に着目し、画面を分析することを通じて、そこにさまざまな意味を見出してきた。
まずもって、 “線” は分断のために用いられ、小鳩/小佐内、探偵/犯人、小市民/他者という分断を、さまざまな道具立てにおける直線を利用してほのめかしていた。
あるいは “線” は、そもそも初めから、「全能感」を去勢され「無能感」を味わう運命にある小市民を限界づけていたとも受け取れた。このことを暗示するひとつの道具立てとしてシネスコがあり、一般的な画面よりも窮屈に見えるそのフレームは、通常よりも抑制された小市民の世界を、つねにすでに、鑑賞者に「客観視」させていた。
ただし、こうしたフレームは、「小市民」という枷を(一時的にせよ)外されたときに乗り越えられるものでもあった。「狐」や「狼」と化した小鳩や小佐内は、ときにフレームを乗り越えるが、第1話の山場である橋/川の越境においては、あくまで限られたフレームのなかで、さらには想像のなかで、むしろ「完全なる小市民」への “越境” がミニマムに目指された。
*
ところで、こうして何かを暴き立て、ともすると意味がないかもしれないところにまで意味を見たくなってしまう批評の営みは、行き過ぎた「探偵」行為かもしれない。
そうだとすれば、「ぼくが思うに」という、「探偵」役の前口上から始まった本稿はしたがって、「決して気持ちのいいものではな」かったかもしれない。
加えて、こうして自己反省/自己言及するその身振りさえ、もはやパフォーマンスにしか映らないかもしれない。ほかならぬ小鳩常悟朗も、あるいはミステリーへの自己言及も含めて『小市民シリーズ』(あるいは『さよなら妖精』や『王とサーカス』などほかの作品も含めて)を書いた米澤穂信も、このジレンマに絡めとられていたはずだ。
いったいこの救いようのない身振りに、「解決編」はあるのだろうか? 事件を起こさなければ、それを読み解く快楽を得られないというこの「トリック」を、解きほぐすことはできるのだろうか?
*
おそらく答えはない。「探偵」としての「批評」は、つとめて雄弁に語るほかない。言葉を紡ぐことを宿命づけられた「探偵」=「批評」はしたがって、つねにすでに、そこに意味を生産してしまう。
これは一見すると、言葉に還元しがたい質感を示すアニメーションと非常に取り合わせが悪い。「語るに落ちる」という言葉のありがちな誤用として、語ることで興をそがれるという意味合いがあるが、行き過ぎた「探偵」としての「批評」はまさにそのようなイメージを持たれてしまうのかもしれない。
そこでひとつには、「語るに落ちる」が本来持っている意味、つまり、相手に勝手に語らせることで告白させるという方法が思いつく。つまり、アニメーションそのものに語らせるのである。要するにそれは、アニメーションを見よ、ということであり、批評から一方で距離をとるという点においては、分断 “線” を引く営みである。
なるほど、それもかまわないと思う。というより筆者自身も、アニメーションそのものの雄弁さ、あるいは語らなさにむしろ惹かれてきた。べつにそれだけで生きられることもある。
しかし他方で、「語る」ことで、逆説的に「語れなさ」を指し示すことならばできる。そのとき「批評」は、「犯人」を名指すことができないという点において、「無力」な「探偵」かもしれないし、やはりそのとき初めて「全能感」をそがれるのかもしれない。
しかしながら、そうやって「全能感」が「無力感」に転ずることを描き、逆説的に、ミステリーとして成立した『小市民シリーズ』のように、「全能感」とその裏返しの「無力感」を露呈させる批評と、それを「客観視」する読者があって初めて、批評は成立するのではないか。
つまり、批評が「全能感」にまかせて語ろうとして、表現しきれないその頂点にこそ、それが対象とするアニメーションの見どころがあるのではないか。批評はそうして、分断 “線” を引きつつ、アニメーションへと鑑賞者を送り返すことができる。
だからもし、本稿を読んで、ここが語れていない、本稿のここが「無力」であると思う箇所があるならば、まさにその点について、アニメーションを見なおしてほしい。
その越境のための分断 “線” がいま、ここに引かれた。
※本稿は、筆者がはてなブログに掲載した記事「越境のための分断──『小市民シリーズ』第1話における “線” について」からの転載です。
註
[1]「狐」や「狼」という呼び名は、厳密には、「小市民」的ふるまいを逸脱したさいの呼称である。これについては後述する。作中には当然少なくない言明があるが、たとえば代表的なものとして、以下の一節を参照されたい。「ぼくが狐だったとたとえるなら、あれは昔、狼だったんだ」(米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』東京創元社、2004年、224頁)。
[2]同上書、112頁。
[3]同上書、18頁。太字は引用者による。
[4]筆者が測定したかぎりでは約2.35:1であったが、多少ズレている可能性があり、21:9≒2.37:1という説もある(あるいは厳密に測るともう少し違う比率の可能性もある)。
[5]同上書、104頁。
[6]米澤穂信「ミステリという方舟の向かう先 「第四の波」を待ちながら」『ユリイカ』第39 巻4 号(通巻 533 号)、青土社、2007年、85頁。太字は引用者による。「小市民」シリーズが完結した2024年現在から見れば、このインタビューはあまりにも古く、これまでの間に作中においてもテーマの更新が図られた可能性はあるが、少なくとも、TVアニメーション『小市民シリーズ』第1話の原作に当たる『春季限定いちごタルト事件』(2004年)の範疇においては、このインタビューにおける米澤の意向は妥当性を失っていないと考え、引用した。
参考文献
・米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』東京創元社、2004年。
・米澤穂信「ミステリという方舟の向かう先 「第四の波」を待ちながら」『ユリイカ』第39 巻4 号(通巻 533 号)、青土社、2007年。
※引用で用いた画像(図01~12)はすべて、TVアニメ『小市民シリーズ』第1話に拠るものであり、権利は ©米澤穂信・東京創元社/小市民シリーズ製作委員会 に帰するものである。
