
フィンランドデザイン史:1910-1930年「変わらなければならないに至るまで」
こんにちは、Mayuです。私は現在デザイン関係の仕事をしていますが、フィンランドのデザイン、特にその歴史に興味を持ったことがきっかけでデザインに関わるようになりました。デザインの文脈を理解することは、今の自分の仕事を考える上でもとても重要だと思っています。教科書的な本は読んでいてもスンナリ頭に入ってこないことが多いので、勉強して自分なりの言葉で解釈したものを、noteに記録していきたいと思っています。
はじめに「フィンランドデザインがその地位を獲得するまで」
フィンランドデザイン史の黄金期は1950年代と言われています。この時代に、ミラノトリエンナーレなどの国際的なデザイン展で、フィンランドのプロダクトがいくつも賞をさらっていきました。今回取り上げる20世紀初頭(1910年~30年頃まで)は、50年代黄金期に向けた基盤を築いていった時期です。
今でこそ、フィンランドデザインは世界中で注目されていますが、20世紀初頭のフィンランドは、ヨーロッパ諸国の中でもとりわけ田舎の小国で、特にデザイン産業に秀でているわけではありませんでした。同時期に、ヨーロッパでは鉄やガラスやコンクリートといった、工業的な素材を建築やデザインの主流にし、「近代化」を進めていくのですが、フィンランドには、それに追従できる物資も十分にはありませんでした。その代わりあったのは、広大な自然、そして当時は若干時代遅れとも見なされつつあった木材。
それでも何とかヨーロッパ諸国と対等に渡り合っていくために「変わらなければならない」、というジレンマを、新興のデザインのエッセンスを取り入れつつも、自国に実現可能な素材や手法で、建築やプロダクトデザインに落としていく、という方法で昇華していきます。
こうしたデザインに対する姿勢が、シンプルでタイムレスな美しさと機能性の絶妙なバランス感覚に繋がっていったのではないか、と思います。今回はその入り口の部分、「変わらなければならない」に至るまでの背景を辿ります。
ロールモデルとしてのスウェーデン

フィンランドデザインの近代化は、1930年代を皮切りに本格化したと言われています。というのは、この年に隣国スウェーデンで大規模な博覧会が行われた為です。スウェーデンは歴史的な統治関係もあって、長らくにフィンランドにとってのロールモデルであり、その動向はフィンランドにとって重要な見本になっていました。
1920年代、ドイツやフランスといったヨーロッパの国々では、機能主義の思想が広まっていました。これは物の機能性が最優先されるべきであり、華美な装飾によって機能性を損なうようであれば、本末転倒だ、という主張です。元々は、これは一種の「考え方」であり、特定の意匠を良しとするものではないものの、この考え方を踏襲したデザインが「スタイル」として建築やデザインのトレンドになっていきます。白い箱型、機械的な直線形、地域性や作家性を感じさせない、どこの国の誰が作っても同じようなものができる、そんなスタイルです。
こうした流れはじわじわと北欧諸国にも伝わってきて、1930年にスウェーデンで開催されたストックホルム博覧会で、大々的に取り上げられることになります。この博覧会を仕切ったのが、スウェーデン工芸協会の理事長だったグレゴール・パウルソン(Gregor Paulsson, 1889-1997)という人物です。彼はスウェーデンデザインの未来を熱心に考え、抜群の影響力を持っていました。グンナール・アスプルンド(Gunnar Asplund, 1885-1940)を筆頭に、スヴェン・マルケリウス(Sven Markelius, 1889-1972)などの建築家たちが会場構成を手がけます。彼らは当時のスウェーデンでもトップレベルに知名度があり、かつ、諸外国での新しいトレンドにも敏感な建築家でした。

ストックホルム博覧会の目玉となる建築には、真っ白で、明瞭な構成の、装飾もない簡素なものが登場しました。こうした建築は、ドイツやフランスでは既に普及していたものの、少し離れた北欧の人達には非常に衝撃的でした。博覧会を訪れた人達からは、多くの批判的な意見が寄せられたと言われています。実際、人々の戸惑いに応える形で、パウルソンらは、翌年に『受け容れよ(Acceptera, 1931)』と題された書籍を発表し、新しい生活様式、価値観を「受け容れ」変わっていかなければならない、と説いています。

ストックホルム博覧会をめぐる一連のエピソードで興味深いのは、実のところ、博覧会で人々に衝撃を与えた建築の多くは木造で、外壁をアスベスト・スラブで覆うことでコンクリート造のように見せていたと言うことです。つまり工法的には特に目新しいものではなかった。これは、博覧会修了後に建築を撤去しなければならない、という実際的な事情もあったようですが、とにかく、彼らにとって重要だったのは、建築の工法的な目新しさを確実丁寧に伝えることではなく、「新しい時代が来ている」ことを自国の人々に鮮烈に印象づけることでした。
フィンランドの変化「内向きから外向きへ」
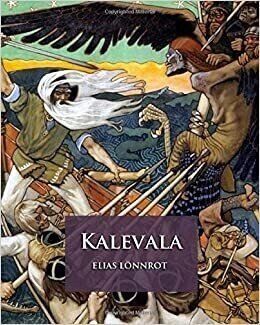
ストックホルム博覧会は当然、フィンランドにも衝撃を与えます。ちょうどその頃、フィンランドの建築家やデザイナー達も、新しい時代が来ている、という意識を持ち始めていました。
20世紀初頭のフィンランドでは、ナショナル・ロマンティシズムが建築や応用芸術の主流でした。ナショナル・ロマンティシズムは、フィンランドの民俗伝承に登場するモチーフや材料、その世界観からインスピレーションを受けた表現を特徴としています。特に、19世紀前半に編纂、発表された民族叙事詩『カレワラ(Kalevala, 1835)』は今日でも有名で、カレワラの世界観にインスパイアされた絵画、音楽などの諸芸術が多く発表されました。絵画ではアクセリ・ガレンカレラ(Akseli Gallen-Kallela, 1865-1931)、音楽ではジャン・シベリウス(Jean Sibelius, 1865-1957)が有名です。建築や応用芸術では、花崗岩や丸太材を使ったゴツゴツとした重厚な造形や、クマやリス、ツタといった動植物の装飾を特徴としています。

今日でこの様式の建築を感じられる場所は、フィンランドの観光名所でもあるフィンランド国立博物館です。おとぎ話に出てくる建物のようでありながら、メルヘンというよりも少し怖い、未開の地のような不気味さがあります。自国のルーツをモチーフにすることで、愛国心を高めることが期待されていました。
1900年を少し過ぎたあたりから、ナショナル・ロマンティシズムは時代遅れだ、という風潮が段々高まってきます。特徴的なエピソードに、1904年のヘルシンキ中央駅のコンペがあります。このコンペでは、エリエル・サーリネン(Eliel Saarinen, 1873-1950)、ヘルマン・ゲセリウス(Herman Gesellius, 1874-1929)、アルマス・リンドグレン(Armas Lindgren, 1874-1929)のチームによる設計案が優勝しています。彼らは、当時フィンランドで実力・名声共にトップクラスの建築家トリオで、ナショナル・ロマンティシズムの代表格でした。彼らのそれまでの作風はこんな感じ。これはポフヨラという保険会社のオフィスビルです。

この設計コンペに敗れたジグルド・フロステルス(Sigurd Frosterus, 1876-1956)という建築家が、サーリネンらの設計案を時代錯誤だ、と声を上げました。サーリネンらはこの批判を頭ごなしに否定せずに、設計案を若干修正しています。ふんだんなナショナル・ロマンティシズムの要素は若干抑えられ、ヘルシンキ中央駅は現在の姿になりました。完成当初はこんな感じです。

1920年代になる頃には、フィンランドでのナショナル・ロマンティシズムへの熱狂はほとんど冷めていました。変わって、建築やデザインは新古典主義の時代を迎えます。それまで、カレワラといった自国のルーツをどのようにデザイン言語に翻訳していくか、に熱中していたのが、だんだんと他国のデザインを意識した、外向きの視点に変わっていったのです。
フィンランド版ストックホルム博覧会「トゥルク700年祭」
ストックホルム博覧会の開催は1930年の5月から9月にかけてですが、実はその前、1929年に、ストックホルム博覧会の小さい版とも言える博覧会がフィンランドのトゥルクという都市で開催されています。このトゥルク700年祭の主任建築家として会場設計や建築物を手がけたのが、エリック・ブリュッグマン(Erik Bryggman, 1891-1955)という建築家です。彼はアルヴァ・アールトの先輩にあたる人物で、トゥルク市にとても美しい礼拝堂を残しています。ブリュッグマンについても別の機会にまとめたいです。
ブリュッグマンはモダニスムの動向を熱心に観察してトゥルク700年祭に臨みました。

ストックホルム博覧会と同様、新しいものに批判はつきもので、このレストランを「宇宙船」と揶揄する声も一部にはあったようです。当時の新聞ではこんな風刺画が出されたそうです。

またこのトゥルク700年祭の設計には若きアルヴァ・アールト(Alvar Aalto, 1898-1976)も携わり、アールトが非常に尊敬していたアスプルンドからストックホルム博覧会の構想を聞いていた、そうです。どういった企画過程があったかとても興味深いです。
ともあれ、このトゥルク700年祭や、ストックホルム博覧会を皮切りに、自国の過去の遺産をデザインに翻訳し続けるのもそろそろ限界だし、新しい生活様式に適応するためには、新しいデザインを模索しなければならない、という気運が高まり、住宅展や工芸デザイン展の開催、という形で現れます。こうして、アールト夫妻を始めとする建築家や応用芸術家たちが積極的に構想を発表できる土壌が整っていきました。

この「最小限の住宅展(1930年)」は、開催中の世田谷美術館「アイノとアルヴァ 二人のアアルト」展で実寸模型が展示されています!(現在は臨時休館中です)
小国フィンランドが、自国のアイデンティティを大事にしつつも、少しずつ外に目を向けて自国の立ち位置を獲得しようとしていく過程が、この20年余りのデザインの変化に見られます。
冒頭に書いたように、とは言え、フィンランドはヨーロッパの流行りをそのまま真似をすることは結果的にしませんでした。その背景には、経済的、入手可能な物資といったかなり実際的な事情があります。このジレンマを巧みに昇華して、「フィンランドデザインの魅力」に変えた代表的な人物が、アルヴァ・アールトであったと言えます。次回は、この点を切り取ってまとめていきたいと思います。
#finnishdesign #フィンランドデザイン #デザイン史 #デザイン
図の出展
川島洋一『E.G. ASPLUND アスプルンドの建築1885-1940』TOTO出版, 2005.
鈴木敏彦『アルネ・ヤコブセン ヤコブセンの建築とデザイン』TOTO出版, 2014.
Lahtinen, Rauno. The Birth of the Finnish Modern: Aalto, Korhonen and modern Turku, Mayow. trans. Hameenlinna: Kariston Kirjapaino, 2011.
Nikula, Riita. Wood, Stone and Steel, Helsinki: Otava Publishing, 2005.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
