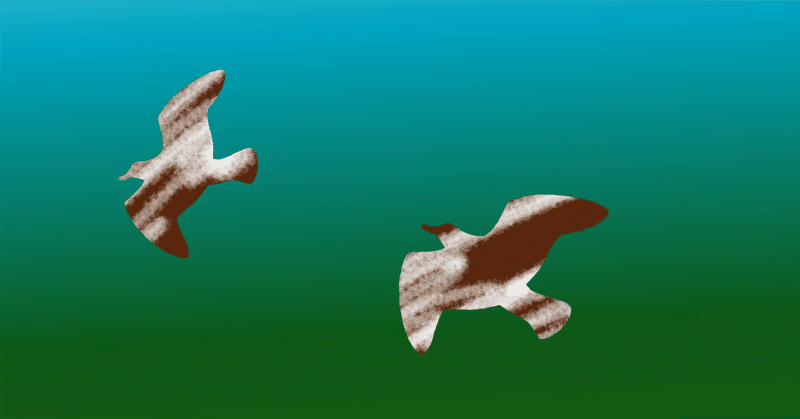
松村圭一郎『旋回する人類学』【基礎教養部】
文化人類学とはどんな学問だろうか。学問としての歴史はそこまで深くないが、何度も大きなパラダイム・シフトを経験している。そういった意味で「旋回」し続けてきた文化人類学の歩みを振り返るのが本書の内容となっている。この記事ではなぜ僕が文化人類学に興味を持ったのかということを本の内容と関連付けながら述べる。
以下800字書評URL↓(後日掲載)
なぜ文化人類学か
文化人類学のことを知ったのは、予備校の英語の授業であったと思う。自己紹介でも少し紹介したO先生である。大学に入った後に、面白いから是非勉強するべきだとお勧めされていたのをよく覚えているし、そのことを思い出そうとしなくてもなんとなく、文化人類学は面白いはずだから勉強するのだ、講義が取れそうなら取るのだという意思は常に持ち合わせていた。内容も実際に入試問題にそういう文章(『銃・病原菌・鉄』とかああいうの)が出てきたりするので断片的に知っていた。
大学に入学して、専門の勉強に打ち込んでいた僕はもうそれらを日々こなすだけでキャパオーバーの域に達していたので、2年間ぐらいは物理、そして数学に全ベットすることになった(たのしすぎて)。教養科目もあまりとっていなかったので、文化人類学があることを知ったのは3回生の履修を決めているときだった。ということで今期ようやく文化人類学を受講中だが、大学に来て取った科目で一番面白いと確信している。専門科目は勉強したことや知っているようなことを薄めたような内容なのでいつからか行かなくなってしまったし、歴史系の科目もいくつか取ってみても面白いのだが、どこか物足りなさがあったりもした。
でもいったい、文化人類学のどういった側面が、物理や数学を好きな僕に"刺さった"のだろうか?
現在の文化人類学で展開されている内容は特に人類学的な側面、どこどこのなになにという民族はどういう暮らしをしていて、どういう共同体を形成していて、こんな慣習があって、というのをフィールドワークを通じて記録していき、分析するという態度を取る。フィールドワークをする際に気を付けるのは外部者である我々もその民族の一員として参加する参与観察という手法を取るということである。外部であり内部の構成員という特に自然科学と比較すると矛盾したような立場を取る。この点で文化人類学は自然科学とはもはや違う道を歩むようになった。一時期は自然科学に寄せていこうという動きがあったようだが、色々あって違う方向に進むようになった、旋回したということがこの本に書いてあった。
まず僕が魅力を感じているのは、フィールドワークの結果として得られるデータそのものもそうだが、その分析が、実は我々自身の分析にもなっているという部分である。特に記録に残っていることというのは我々の目についたものであるが、それは裏を返すと我々の普段目にしないものだったり、我々の慣習に無いものであることが多い。逆に、全く我々と接点がないのに、似た点があればそれも考察の対象として興味深かったりする。なぜそういった共通項が発生したのか、とか。
採取してきたデータを個別具体的に、博物館的に整頓して並べて終わりというのにとどまらず、なぜそうなったのか、というのを考えていく過程が面白く感じるのだろう。こういった面で自然科学的、といえるのかもしれない。
また、文化人類学のスタンスも僕にとって好ましい。元々150年ぐらい前に始まった段階では、文明と未開社会の比較という視点だったが、これは明らかに自民族中心主義的態度である。当時のフィールドワークをする学者の手記にも、どこか他者を馬鹿にするような態度が見られ(彼の死後それが公になって、問題になったりしたみたいだが)、徐々に問題視されるようになり、やがて文化相対主義という態度を掲げるようになった。つまりこれは自民族中心主義(エスノセントリズム)とは逆の態度であり、個々の文化には個々の論理があり、それを尊重するという態度のことである。
要するに、(自民族で培ってきた)価値判断はしないようにする、ということだ。そうはいっても実際には価値判断をしてしまいそうになるものだと思う。しかし立ち位置を変えるという態度そのものが大事だと思った。
おわりに
他にも松村圭一郎の著作を読みたいと思った。僕の出ている講義の先生は文化人類学の本なんて読んでると眠くなってきますよ、と言っていたが、この人の本はよくまとまっていて面白いと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
