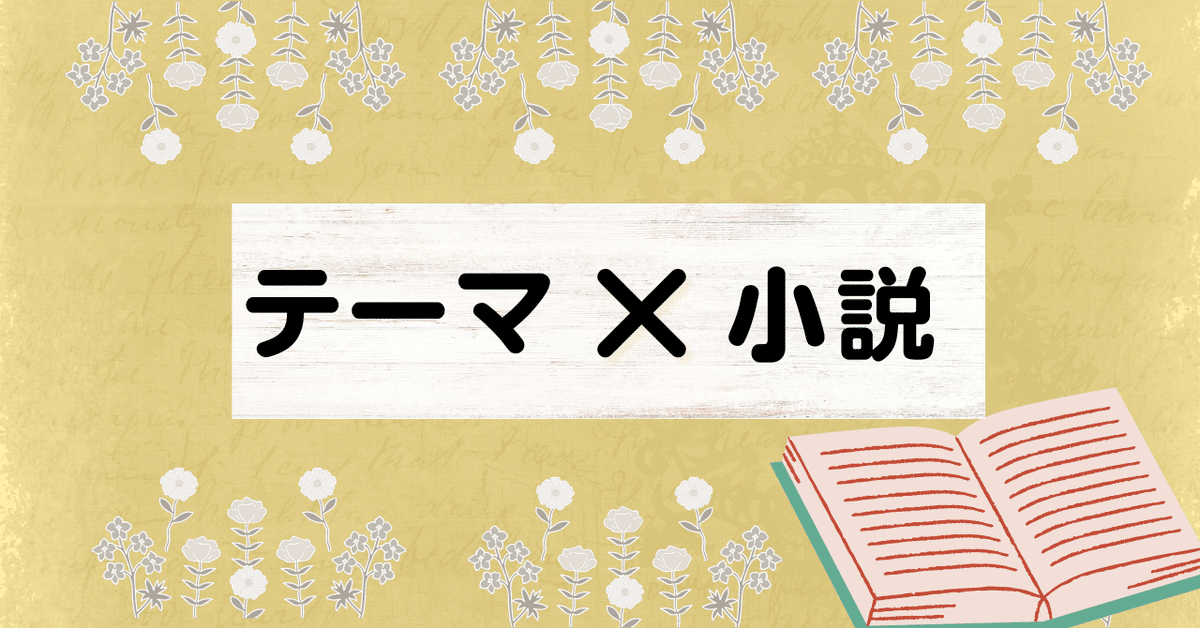
黒いコートの女(55作目)
「またいる。」
健吾は電柱の影に佇む女を横目で見て、その不気味さに怯えていた。
恭一との待ち合わせ場所で待っていると、黒いコートの女が自分の方を向いている気がしたのだ。
数分後に恭一がやってきた。
「おはよう。」
爽やかに挨拶をする恭一に対して、健吾は沈んだ声で「おはよう。」と言った。
「なんだ?暗くないか?」
「いや、あそこの電柱の影に黒いコートを着た女の人がいるだろ?」
健吾は女の方を見ないで恭一にそう言った。
「電柱?誰もいないけど。」
「えっ?」
健吾が振り返ると、電柱の影には誰もいなかった。
「さっきまでいたんだ。それに、今日で見たの三回目だし・・・。」
「ということは、霊だな。」
「幽霊ってこと?そんなものこの世にいるわけないだろ。」
「だってお前しか見てないし。ま、そんなことどうでもいいから早く行こうぜ。」
恭一にそう言われて、健吾は腑に落ちないまま、学校へと向かった。
数日が経ち、健吾がいつものように恭一を待っていると、また黒いコートの女が電柱の陰に佇んでいた。
やっぱり、いる。
気のせいでも幽霊でもない。
健吾は証拠を残しておこうと、自撮りをする風を装って、黒いコートの女も映るように写真を撮った。
女は健吾が写真を撮るのにも気づかず、どこか違うところを見つめていたようだった。
しばらくして恭一が来た。
眠そうな顔をしている。ふと横目で女の方を見ると、恭一の方を見ていることに気がついた。
健吾が電柱の方を気にしているのに気付いたらしく、恭一が「なんだ?」と言い、健吾の視線の方に顔を向ける。
「まさか、また変な人がいたとか言うんじゃないんだろうな。」
「いたよ。ほら、写真見ろ!映ってるだろ?」
健吾がさっき取った写真を恭一に見せた。
「なんだこの写真?」
「なんだって、黒いコートの女が映ってるだろ?」
「うーん・・・」
恭一の煮え切らない返事におかしいと思い健吾が写真を見ると、健吾が撮った写真はブレていて、確かに黒い人は映っているのだが、顔は判別出来なかった。
「とにかく、誰かいたのは証明出来ただろ?」
「確かに。でも、誰だ?」
「この女、恭一が来るのを見つめてた気がすんだけど。」
「俺を?」
「もしかして知り合いなんじゃないか?」
健吾がそう言うと、恭一は少し考えて、「分からん!」と言い、「遅刻するから早く行こうぜ!」と言った。
その後もしばらくは、電柱の陰に人がいないか確認するような日々が続いたが、黒いコートの女が佇んでいることは無かった。
健吾と恭一はだんだんとこの話のことを忘れていった。
数週間が経った頃、突然恭一が黒いコートの女の話題を出した。
「あのさ、前、健吾が黒いコートの女の話をしただろ?」
「え、いきなりなんだ?そんな話をしたことなんてすっかり忘れてたぞ。」
「いや、それがさ・・・。」
恭一が話始めたことは、健吾にとって驚愕の内容だった。
恭一の家庭は父子家庭で、恭一は母親の顔を知らないと健吾は聞いていた。
小学生の頃から恭一のことを知っているが、恭一と彼の父親の関係は良好で、良い親子だなと思っていた。
そんな父親からある日、話があると言われたらしい。
「それで、親父が俺の本当の父親じゃないってことを知ったんだ。」
「え?どういうことだ?恭一と親父さんめちゃめちゃ似てるじゃないか。」
恭一と彼の父親は、顔立ちもスタイルもよく似ていた。
「親父の妹が俺の母親らしいんだ。俺は親父の妹が10代の頃に出来た子で、父親は誰か分からないらしい。親父は既に家を出て働いていたから、妹が若くして子供を産んだことを後から知ったらしいんだ。」
「まじか。そういえば、恭一は親戚にあったことがないって言ってたよな?」
「そうなんだ。俺は、親父の家族は誰もいないって聞いてた。でも本当は両親も妹もいたらしい。」
「何があったんだ?」
「親父の妹、つまり俺の母親は、ある日突然姿を消したらしいんだ。育児ノイローゼだったのかもしれないと親父は言ってた。母親は実家に住んでたらしいんだけど、残った俺を祖父母は施設に入れようとしてたらしいんだ。誰との子かも分からないし、若くして産んだことで世間体が悪いと考えて、俺を育てたくなかったらしい。それを聞いた父親が、子供に罪はないと俺を引き取って育ててくれたんだと。」
「そうだったんだな。でも何で親戚はいないなんて言ってたんだ?」
「それが、親父が俺を引き取ることに、祖父母が良い顔をしなかったらしいんだ。親父は未婚だったから、子供がいたら、もっと結婚が遠のくからやめろって言われたらしい。それで祖父母と大喧嘩して、それ以来、家族は俺だけだと思って生きてきたって言ってた。」
恭一は嬉しいような寂しいような顔をしていた。
「親父は、始めは、俺の母親が帰ってきたら、俺を返そうと思ってたらしいんだ。でも、母親は一度も連絡をよこさなかったらしい。それに、一緒に過ごすうちに愛情が芽生えて返したくなくなったって言ってくれた。それが、つい最近、母親から連絡が来たらしいんだ。」
「まじか。何て連絡が来たんだ?」
「俺を放ったらかして家出したことの謝罪と俺に会いたいって書いてあったらしい。親父は随分悩んで、俺に相談してくれた。どうしたいか聞かれて、俺は親父と3人で会いたいって答えたんだ。」
「え?じゃあ会ったのか?母親に。」
「ああ。」
「どうだった?」
「それが、何とも思わなかった。ずっと母親はいないと思ってたし、いざ会っても、親父の妹としか思えなかった。母親は家出をした後宗教にハマって借金を作ってたらしい。その借金を返し終わって、俺を迎えにきたと、そう言ってた。今まで放ったらかしにしてたくせに、いきなり一緒に住みたいとか言われても意味分かんないよな?だから俺は、俺の親は親父だけですって言ってやったんだ。そしたら、あっさり、良かったって言ったんだ。お兄ちゃんが大切に育ててくれたんだね、って言って目に涙を浮かべてた。」
健吾は、恭一の母親が酷い母親じゃなくて安堵した。
「健吾が言ってた、黒いコートの女は俺の母親だったんだ。本当は俺に声をかけようとしてたけど、友達との楽しそうな姿を見てやめたらしい。」
「そうか。やっぱり恭一を見てたんだな。」
「とりあえず、悪かったな。俺のせいで怖い思いをさせて。」
「いいって。それよりも、話してくれてありがとうな。」
健吾は、恭一と恭一の父親がこれからも仲良く暮らしていけることを祈った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
