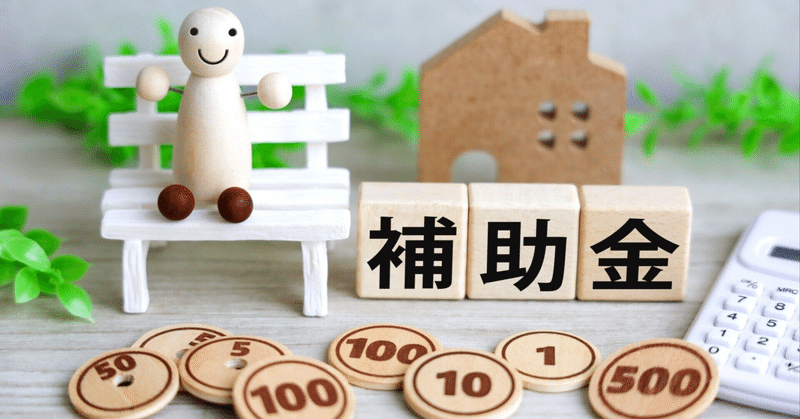
働き方改革✕保育園✕エンペイ
お久しぶりの投稿です。
なかなか続かないのが私の悪い癖。。。(笑)
ということで短い記事ではありますが、先日受講したエンペイさん主催のセミナーでの学びを忘れないようにメモとしておきます。
※enpay :株式会社エンペイhttps://www.enpay.co.jp/
なるほどなぁというポイントが盛り沢山でした。
登壇された野上さんは営業やコンサル、人材のご経験があられるので戦略的に進められていながらも、ヒトを大事にして事業されているなんだなぁと伝わってきました。
本記事は
去る5/15に開催されたセミナー内容のまとめ記事です。
補助金ってそもそも
では、さっそく。
こちらのセミナー

登壇者:社会福祉法人風の森 統括野上美希氏
保育者の働き⽅改⾰を実践、国基準の 2 倍以上の保育⼠確保を実現
〜〜応募が耐えない保育園の補助金活用法とは〜〜
野上さんがおっしゃるには、
「まずは、補助金の前提として、
補助金は国や自治体が支援したい事業に対して交付されるものですが、、、
交付されるかどうかは自治体の担当者の意識次第でも変わってくるんですね。なので、国の事業として始まっているが活用していない自治体もあるんですね。」
そして
「福祉事業として、社会のため、地域のためにやりたいという事業者がいても、そもそも、事業をやるための補助額が少な過ぎて単体では赤字になるという課題がある、やりたいのに、やれなという悩ましいという本音がある。。。。国への提言もしっかり推めていきたい」とのこと。
と言っても、そんな中、国の2倍以上の配置基準で人材を確保しながら、補助金を確保して、経営としても事業を拡大していっている風の森さんの秘密とは?
「やはり、人を増やさないと事業継続は難しい。。。保育士の疲弊感を肌で感じ、園長・主任・看護師がなんと1年で退職。。。
働き方方改革→人材確保→補助金をフル活用」
では、
どうやって人を増やして補助金・加算を取っていくのか。
【補助金を分類する】
・人を増やして出る加算
・事業に紐づく加算
事業ごとでマイナスにしないためには複数の事業を展開しながら一体的に捉えて人を確保して配置していくことを実践
※補助金、加算の種類などはここでは割愛します。
1配置を手厚くしたうえで→2新規事業に着手しながら事業のための人材を採用し→3同一拠点で同時に行うことで効率化する
※加算の専従要件など、加算対象かどうか難しい部分もある
例えば、病児保育や一時保育事業などを同一拠点で一緒に行うことで各事業ごとに確保した人材が+α的に充実した人員配置で運営できて効率化できる
「自治体の補助の内容と要綱を細かく確認しながら推める事が必要で大事なことは、自治体の担当者と話合いながらインクルーシブを目指す」
【必ず取りたい補助金の特徴】
・生産性向上につながる補助金
・人の手がかからない補助金
※ICT化推進事業の補助金対象(キャッシュレスサービス:byエンペイ)
「ICT補助のようなシステム化を進めて働き方改革につながる補助金は必ずとりに行く。」
また、自治体への提案も忘れない。
「自治体が国の補助を使っていないケースがあり、他の自治体の例をあげて補助の必要性を訴える」
まとめ
・地味な作業だけど国や自治体のそれぞれの補助加算を洗い出す
・加算の分類をし、人を増やして出る加算を採用計画に盛り込み、落とさない
・赤字事業は複数事業掛け合わせて、各種加算を取りに行き、相乗効果で成果を上げていく
・ICTなどの生産性向上につながる補助金は落とさない
感想
最初の補助金の『分類』のところで、「なるほど!!」「そういうことだったのか!!」と、なんとなくモヤモヤ考えていたことを構造化してもらった感覚がありました。
最後の質疑応答でも質問させてもらいました。
Q) 「補助金の申請や書類作成届け出、自治体との交渉などはどなたがやるのでしょうか?」
A) 届け出申請などは、野上さんや、経理事務スタッフさん、様式が決まっているものなどの書類作成などは園長や現場の管理職など。自治体との交渉などは理事長や野上さん自身がされるそう。
そして、日々の園運営するにあたって一番大事だなぁと思っている連携が、一番難しいなぁと思っていることで、感想とともに記しておきます。
⇓⇓⇓
「職員を多く抱えているとそれぞれの業務の偏りが生じてくるのではないかと思います。一日の流れの中で、休憩やノンコンタクトタイムをとるためのスタッフの配置や業務量のバランスをはかったり職員同士の連携は現場ではどのようにしているのだろう?」
例えば、病児保育や一時保育事業などを同一拠点で一緒に行うことで各事業ごとに確保した人材が+α的に充実した人員配置で運営できて効率化できる→具体的には、クラスを持つ担任のノンコンタクタイム創出のために一時保育の職員がヘルプなどに入るなどの方法があるとのことですが、そのような事業と事業の間の人の往来をスムーズに行うにはかなりの連携力が必要なのではと思いました。そしてそれは、配置基準以上の+αから生まれる余裕により、その連携するために職員同士の対話が必然的に生まれて、好循環的に、対話が増えて連携力が高まり、より良い保育につながっているのかなと思いした。
このことについて詳しく聞けなかったのが残念でしたが、自分なりに考えてきた働き方改革を実現、実践するには概ね間違っていなかったなあと思ったセミナーなのでした。
どちらの事業所さん、保育園さんも働き方改革が進み子ども達への良い循環が生まれますように!
終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
