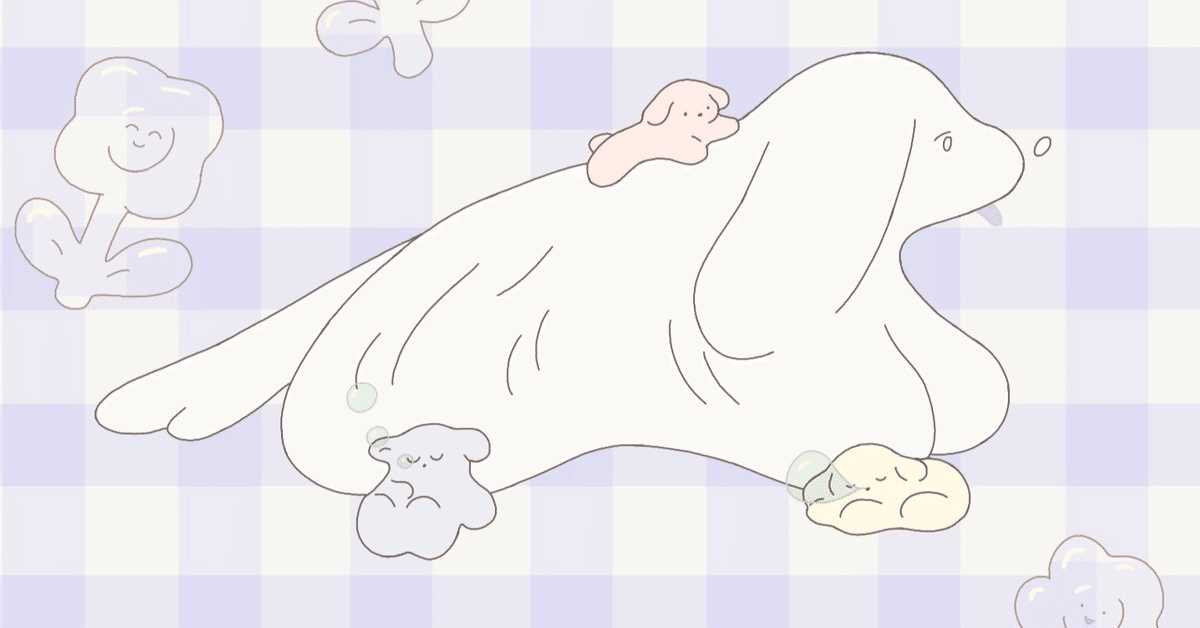
命を見送って
年が明けてすぐ、祖母の飼っていた犬が亡くなりました。
13歳でした。犬にとっては平均的な寿命でした。
数ヶ月前までは元気にしていたあの子は、年末から数度体調を崩して、みるみるうちに衰弱していきました。亡くなる数日前はとうとう歩けなくなったけれど、それでも最期の日、数十メートル離れた私の家まで歩いてきたのです。ご飯を食べず、水も飲まないで、何日も眠っていたのに。
人も含めて、動物は最期が近づくと急に元気になると聞いたことがあります。歩けなかった人が自分の作った庭を見て歩いたり、声すら上げられなかった犬が大きく吠えたり。
あの子もそうだったのでしょう。
あの朝、お別れを言いに来たのでしょうか。震える足で私と母と弟の一人ひとりのもとへ来て、俯いて撫でられるままになっていました。
それまでは人が触れることを許さなかったのに。野生動物のようだったのに。
最期でようやく慣れてくれるなんて、遅すぎやしませんか。
あの日の夜、私は物心ついて初めて亡骸に触れました。あの子の寝かされていた玄関先は寒かったけれど、空っぽになった体はまだ温かくて、それでも生きていた時のような柔らかさはなくて、私は泣きました。泣いても泣いても涸れそうにありませんでした。
次の日の朝、あの子が焼き場に連れて行かれる前にもう一度お別れをしました。
実感が湧いてこない夜を明かして、再びあの子の前足に触れて、また涙が止まりませんでした。
昨夜はまだ温もりの残っていた体は、今度こそ冷たくなっていました。
本当にお別れでした。
あの子の居場所だった、ガレージの横のスペースを今でも覗き込んでしまいます。がらんどうになったその場所を。
何年も前から続けてきたこの習慣は消えてくれなさそうです。
何度見ても、昔に比べて白くなった尻尾も、アーモンドの形をした目も、綺麗な三角形の耳も、どこにもありません。
私が初めて触れた、ある命の終わり。私はこの次に誰を見送るのでしょう。
生きるというのは、見送ることなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
