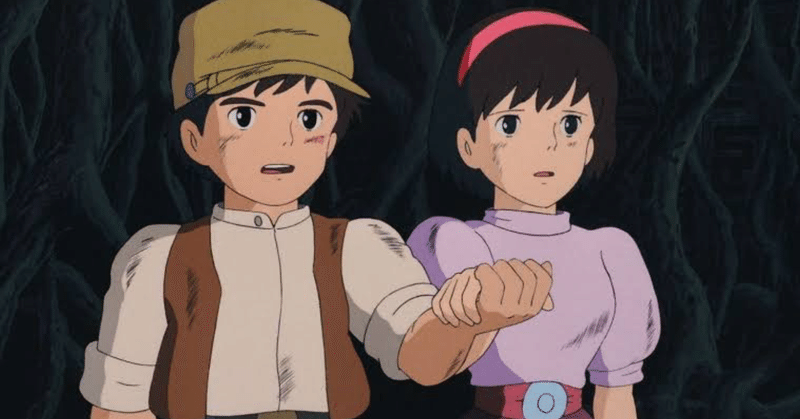
滅びの呪文
言語化による区別
ここ2.3年でいろんな映画を見るようになって、念頭に置いているのは、「好き嫌い」と、「おもしろいorおもしろくない」をきちんと分けて考えるということ。さらにいうと、後者に関しては、きちんと言語化しておくようにしている。
例えば、私はディズニー映画が大好きなんだけど、無条件におもしろかった。とはならず、どこがおもしろかったかは、言及するようにしている。逆におもしろくないポイントも考えている
「おもしろくない」の積み重ね
きちんと「おもしろい」と「おもしろくない」を積み重ねると、自分の中で好き嫌いがはっきりしてきたのが、最近の発見。引用先の人たちが正にそう。何本も作品を見て見た上で、明確に「嫌い」とはっきり断定できる。
そう、言語化の繰り返しにより、自分の中の感性が熟成されたのだ。
思考停止の罠
「好き嫌い」や「おもしろいorおもしろくない」を語ると、議論になることがあるが、これは健全。
いや、むしろ議論にならないと言語化した意味がないくらいに思っている。
ところが、この議論以前を最終的に無にしてしまう「滅びの呪文」があるのだ。
「人それぞれ」
もう、これを言われたら,なんもできん。話し合いの余地すらない。一見、全体を慮っての言葉に見えるが、自分の感覚に踏み込んで欲しくないから、出てくる言葉なのだ。
なぜ、滅びの呪文が生まれるのか
人は自分の好きなことや、よかったと思うことへの嫌な評価は避けたい。それは自然な感情。だけど、他の人の話を聞かず、突き放したままでいたら、いつまで経っても、感性は磨かれないんじゃないかなぁ。と、最近は思うを
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
