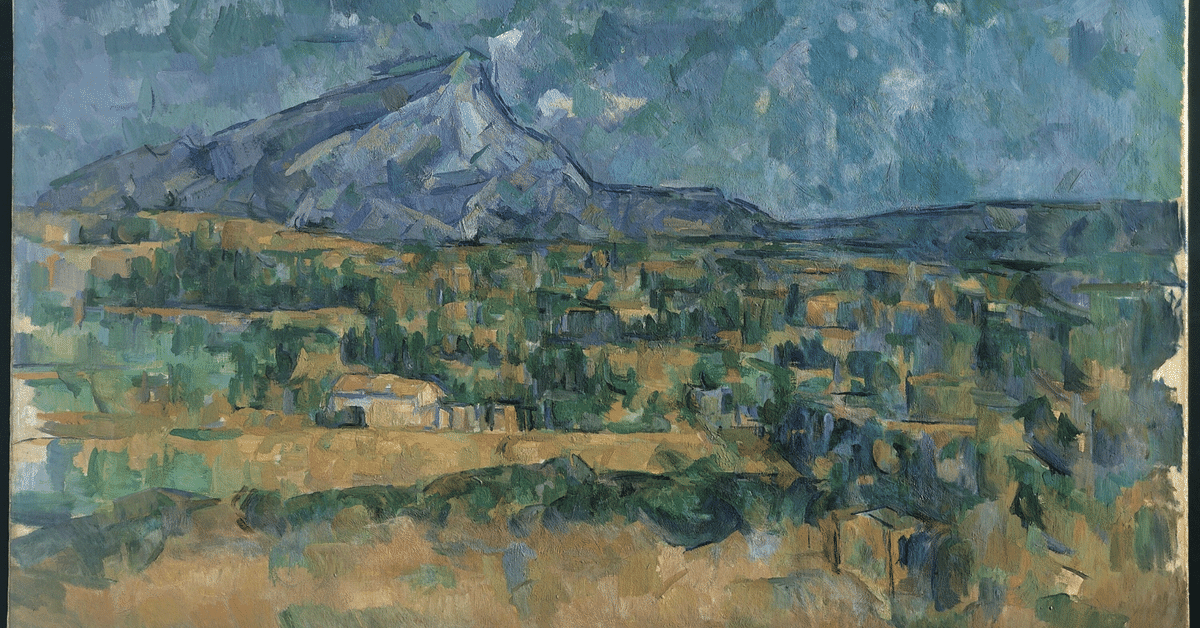
(小説)星の降る街 2
両国駅の切符売り場前で掛井有里に電話した。幼馴染で、二十代の一時期に交際したが、結婚には至らなかった。しかし半年前の同窓会でお互いが離婚していたこともあり、付き合いが復活していた。有里は宮城県石巻市に住んでいることから関係はなかなか前進しないままだったが、子供のころからの付き合いなので、恋人というより家族のような関係でもあり、濃厚な間柄には違いなかった。
「もう診察は終わりましたか。手術の日はお休みが取れそうなので、付き添いに行きますからね」
年齢よりはるかに若い容姿に見合った声が弾けていた。
「いや、手術はとりあえずなくなった」
情けない表情をしているはずだが、声の起伏を抑えてそう答えた。
「どういうこと、薬で治るってことなの?」
私の声で何かを察知したのか、電話の向こうから、あまり聞いたことはない強い調子の声が返ってくる。
「右の肺にね、癌らしきものが見つかって、手術をする予定だった日に二泊三日の検査入院をすることになった」
有里は少し間をおいて、
「それは辛いね。でも、癌って決まったわけじゃないし、そんなはずはないわ。だって嚢症以外は元気そうだもの」
逆の立場なら私もそう言う。
「それならいいけど検査してみないとね。もし癌だとしても私みたいな憎まれ者は簡単には死なんさ。今病院近くの両国駅だから、アパートに帰って落ち着いたらまた電話するよ」
私は心配かけないように平静を装った。
「あのね、私たちにはまだ物語が少なすぎるわ。たとえ癌でもきっと治るよ。だってこれからよ、まだ何も人生を重ね合ってないわ」
愛の告白ともとれるその言葉に少し熱くなったが、それはもっと苦しくなることではなかろうか。癌であれば確実に私が先に逝くことが約束される。とても未来に向けた考えには及ばない。
私はその日から江戸川区の平井にあるアパートの自室を一週間かけて掃除をした。寝室はもちろん、仕事部屋、台所、押し入れの中まで整頓した。これでどうなっても恥ずかしくないと思うまで片付けた。七十リットルのゴミ袋が毎日もう限界だと言わんばかりに膨らんだ。案外必要なものが少ないのに愕然ともした。無駄なものばかりがあったことになる。実は部屋の中だけではなく、私の生きて来た、過去のすべてが無駄の連続だったのではないかと思った。
神は多くの選択肢の中から最適な答えを出す、と有里に聞かされたことがある。
石巻の教会で説諭されたという。「それには究極の理由もあるそうよ」と。確か、二人はなぜ知り合ったか、そんな恋人同士らしい会話の中の話だった。
そうであるならば、受け入れなければならないのだろうか。
究極の理由とはなんなのだろうか。いつかはそれを知りたいとは思っていたが、恐らくこれからも分からないはずだ。癌の告知をされて、暗然としていることが神の示した道だとはとても思えないからだ。
精密検査をすれば癌ではなかった、ということもあるかもしれない。少しは期待していたが、いとも簡単にその希望はついえた。入院二日目には癌は確定していた。中規模の総合病院のいいところで、各検査の連携がよく、血液検査などの結果も驚くほど早かった。
「絶望するほどではないですが、初期とはいえませんね。ステージでいうとⅡBでしょうか。扁平上皮癌だと思いますが、確かなことは今の段階では分かりません。ただ間違いなく進行は早くない非小細胞癌ですね。まだ細胞検査していないので、確定ではないです」
三日目の朝、退院準備をしていると女医は深刻な顔をして病室に現われ、そう説明した。
「まだ間に合いますか」
二○一一年一月二○日は最悪の日と決まったようだ。私は覚悟を決めていたので、特別な記念日を作る趣味はないが、日付を脳裏に刻んだ。
「的確な治療をすれば十分間に合います。今の段階ではなんとも言えないけど。抗癌剤治療、放射線などいろいろな方法が考えられるので、気を落とさずに頑張りましょう」
笑顔で話し始めたが、急に深刻な表情を浮かべて続けた。
「本当は手術で病巣を全部摘出出来ればいいのですが。その辺りも含めて後日治療方針を立てましょう」
私は入院中の二晩とも膵臓癌で亡くなった叔母、肝臓癌で亡くなった友人を思い出していた。酷く痛がっての最期であった。身近な二人以外でも、自分が怪我で入院した時などに、多くの癌患者を目の当たりにしたが、抗癌剤や放射線治療の患者が楽に亡くなっているのを知らない。みんな一様に苦しんでいた。
延命するのは家族の願望であって、患者本人は苦しい時間が長くなるだけだと思っている。現に入院している二晩も看護師に無理やり癌患者の部屋を教えてもらい、こっそりと訪れると、断末魔のような叫びをあげている人さえいた。早く旅立った方がいい。化学療法での延命はしない、その結論は、治療方針を考える前に出ていた。
長いやりとりをした。女医は初診時の態度とは違っていた。入院患者には親切なのか、それとも外来の時の態度を反省しているのか、丁寧に分かりやすく入院しなくても出来る何種類かの治療法も説明してくれた。
「緩和治療以外はするつもりはないです」
私は何度も訴えた。女医はそれには取り合わず、退院手続きの後、もう一度診察室に来てくれと言い残して部屋を出て行った。入れ替わりに二人の息子が現れた。長男の龍也と次男の直也はそれぞれ東京と横浜に住んでいた。十二年前に離婚した時はまだ高校生だったので元の妻のところにいたが、二人とも社会人になってからは独立していた。
「なんだ、元気そうじゃないか」
二人は口をそろえた。
「だから来なくていいと言っただろう」
私は患者ではなく、父親に戻った。不安な顔も弱気な態度も見せない。
「じゃあ、飯でも行くか」
普段より明るく振る舞う二人の息子は、すでに癌が確定したことは知っているのだろう。女医とすれ違いざまに「先程はどうも」と挨拶をしていた。
息子たちと一緒に診察室に入った。私はもう説明は必要ないと思っている。
「さっき新宿の国立国際医療研究センター病院の呼吸器外科にお願いしておきました。どうやらそう遠くない時期に手術が出来ると言っていました。抗癌剤治療をしないのであれば、それがベストでしょう。すべて悪いものは摘出しましょう。場合によってはそれで寛解ということもあるでしょう。ここまでの手術はどこの病院でも出来るわけではないのでラッキーでした」
女医は笑顔を作って朗報を報告するかのような早口で少し甲高い声で言った。
「リンパに浸潤していたら手術をしても手遅れじゃないですか」
「右の肺だけじゃなく、リンパごと摘出する拡大全摘出も出来ます。大丈夫です、まだそこまでの進行はしていません。あそこの外科の先生はかなりの凄腕ですので、期待を持っていきましょう」
肺が一つになってどれくらいの生活が出来るのだろう。臓器が一つ無くなるとは、どんな気分なのか。想像したが、何も思い浮かばなかった。胸のあたりに違和感があるとか、呼吸がし辛いとかの症状があれば実感も湧くのだろうが、なんともなく現実感はない。精神的な圧迫だけがあるという妙な状態だった。
私は治療に関しては興味を失っていたけれど紹介状は受け取った。
「一般論ですが、余命は三年くらい。大細胞癌であるなら、あるいは一年」
女医に無理やり、どれくらい時間があるか聞くとそう答えた。それを意識してか、龍也は旅行に行く話を何度もした。旅行は私の唯一と言ってもいい趣味だからだ。
直也は「親父、早く女作れよ。楽しいことがあると免疫力が高まって元気になると医者も言っていたじゃないか」と力説する。何も心配はしていないという風に笑い声で「女がいるから楽しいとは限らないぞ」と返した。
癌と確定しているのにも関わらず、医者はさらにPET検査をして確認したいといい、私は代々木の検査センターに出向いた。結果は「腫瘍部分がピンクに写っているからやはり癌ですね」と映りだされた画像を指さしながら医師は言ったが、診立て違いを防ぐ意味もある重要な検査らしいが、本当に必要なのだろうか。放射線を浴びる機会が増え、お金が余分に掛っただけだ。検査の順番待ちの日数を含めて、肺に影が認められてから検査終了まで一ヵ月も経過していた。それでも、胸部には痛みなどの症状は全くなく、医者が言うから、死に向かって前進しているのだろう、という感慨しかなかった。
東京都営地下鉄大江戸線の若松河田駅を出て、緩やかな坂を登りきったところに国立国際医療研究センター病院がある。三棟あるなかでも新館は十六階建ての綺麗な病院だ。大きければいいわけではないが、なんとなく安心できる強固な城構えに思える。
対応してくれた医師に「前の病院を疑っているわけじゃないけど、もう一度検査入院して欲しい」と言われた。高額のPET検査までして画像はすべてCDに焼き付けて来ているのに無駄ではないか。
「紹介状にも書いていると思いますが、手遅れなら治療をする気はないのですが」
そう言うと主治医になるという井原医師は、
「大丈夫でしょう。二ヵ月くらいの間に手術すれば、これくらいなら十分に間に合いますよ。生死を分ける局面にはない段階です。それに前の病院の医師の判断より、私が診たところでは初期に近いと思いますね」
自信ありげに答える。
「あのー、自分で病院に来ながら少し言いにくいのですが、延命してもらおうという気持ちはないのです。健康ではなくても普通に生活できなければ生きている意味はないと思っています。ですからそれに合った治療をお願いします」
私はその方針だけは譲れなかった。
「右肺を全部取るとは決めていませんよ。なるべく残します。たとえ肺が一つになっても術後に元気になりゴルフに興じている患者さんもいますよ」
医師は私の精神的なものにはとりあわず、手術が出来るかどうかだけが問題だ、という感じだった。私はあまり医療の技術に興味はない。人は人で治すのだから、人としての心模様が知りたかった。腕は二の次だ。冷たい態度に不満を並べた。
「本谷さん、気持ちは分かりますが、今は現状把握に努めましょう。この段階であれこれ思うのは間違いです。うちは最新の設備ですから再検査の入院は当然必要です。治療方針、手術の時期なども検査しないと、なんとも言えません」
私は肺の奥深くまでカメラを入れる内視鏡検査だけは嫌だったが、そんな気持ちはお構いなしだった。
少し怒ったような口調になったが、それは病気を治すという役目の医師として当然の反応ではないかとも思えた。一緒になって精神論を言われると不安になるのは間違いない。検査入院、手術の日程を二月下旬、三月下旬で押さえてくれた。私は検査結果の末にかなり進んでいるとすれば手術はしない、と言ったが、病室や検査機器の仮押さえしておかないと、治るものも治らないからと井原医師は次々に決めた。
「場合によってはですね」
私は念を押した。
「最終判断はご自分でなさってください。ただ手術をすれば抗癌剤よりも健康余命は、はるかに長い。残された時間は、今は分からないけど、それだけは確信を持って言えますね」
少し薄くなりかけた頭を撫でながら井原医師はそう言い、さらに「本谷さんは頑固者ですね」と笑った。命に限りがあるなら自分に正直に生きたいと思っているだけだ。その後の雑談とも思える話にも応じてくれた。井原医師は私の言葉に何度かうなずいた。その姿に人間性が垣間見え、幾分救われた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
