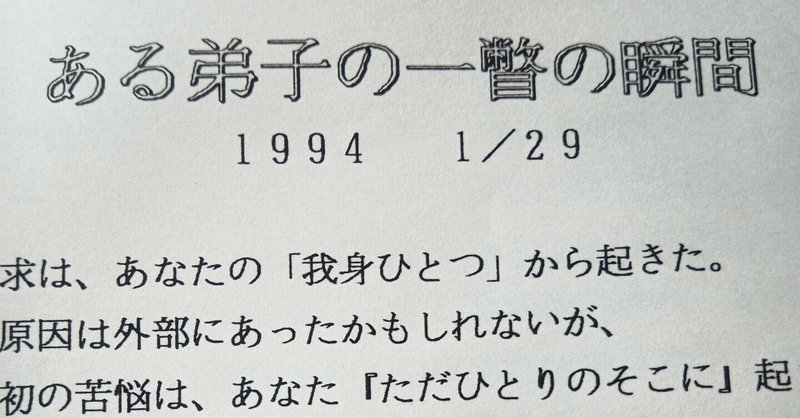
EOからの手紙16・ある弟子の一瞥の瞬間
1994 1/29
人のあらゆる探求は、あなたの「我身ひとつ」から起きた。
そのきっかけの原因は外部にあったかもしれないが、
最初の求心や最初の苦悩は、あなた『ただひとりのそこに』起きた。
そして、それが終焉を迎えるのも、あなたの我身ひとつの中であり、
最後にあなたが死ぬ瞬間も、あなたはひとりだ。
もしも『・』を探求せんとするならば、決して複雑なことをしてはならない。
また、むやみに単純な工夫もしてはならない。
探求に必要なのは、あなたの『我身ひとつ』だけであり、
あなたはたったひとりで探求出来るし、その絶頂の『・』にも帰還できる。
どんな教えも、導師も、工夫も、本来は必要ない。
あなたは、そこでただひとりで座って、それになることも出来る。
ただ、あなたは『まったく何もしないこと』があまりにも出来ないので、
導師たちは、何も出来なくなるような事をあなたにやらせて、
善意を込めて、あなたを騙すのである。
・・・・・・・・・*********
まず、ひとりで座りなさい。
ただし、この『ひとり』がなんであるかを決して誤解してはならない。
『ひとり』でやるということは、あなたが勝手に一人っきりで、自分で学習した物事や方法を組み合わせて、自分の力でやるということではない。
本当の『ひとり』の中には、
あなたの学習した一切の物事も持ち込んではならない。
学習したものとは、「全部他人からのもの」だからだ。
私の言う『ひとり』とは、『一切の記憶からひとりになる』ということであり、
「記憶の集まりとしてのあなた一人」になれということではない。
完全にひとりであるということは、
あなたはその時点で、一切の肩書も立場も、学んだ事も、趣味も、
過去の経験からも自由でなければならない。
つまり、ひとりで座るということが出来ることが
まず座することの第一の条件である。
その一人の中には、願望を持ち込んではならない。
それらはあなたがひとりであることではないからだ。
願望は社会や寺や宗教があなたに「教え込んだ」ものであり、
それを持っていたら、あなたはひとりではない。
どんな願望も社会的なものであり、いうなれば、あなたの思考全部が、
『ひとりっきりのあなた』とは別のものだ。
では、本当に一人で座るというのはどういう状態だろうか?。
******************
座ると、あなたは、ただ自分の肉体の存在を感じる。あるいは意識がある。
外界の物音や光が見える。
ただ、そこから始めることである。
禅寺で与えられた工夫や目的も、それを持つということは、
すでにあなたの内面は二人連れ、あるいは集団行動になってしまう。
座禅の最初の始まりは、『あなたの我身ひとつ』である。
ただそこにいるという事実(別名=幻想)から始めなさい。
導師や寺の存在は、とても厄介だ。
というのも、あなたは課題を与えられたり、あるいは緊張、採点、工夫、と
そういうものが邪魔になって、
あなたがあなた本人と本当に向かい合う場所ではないからだ。寺というものは、
そこで何かが学べる場所などではない。
あなたの存在ただ一人が本当の寺だ。
だから、本当は、まったくの一人の環境がよい。
そして、あなたが、本当に内面奥深く一人でいられたら、
その時は、外へ出ても、寺にいても、どこもかしこも寺である。
では、そこで真の寺の導師の役割は何かと言えば、僧侶たちに
『あなたは、断固としてあなた一人でいなさい』と言い続けるオウムである。
たとえ導師と向かい合っても、あなたはひとりであるべきであり、
周りに誰がいても、あなたは一人である。なぜならば
その『ひとり』のなかに、そこに全世界が映し出されているのであるから。
あなたは、あなた以外の場所において世界にかかわれるものではない。
たとえば、、あなたが、死ねば、ただの事実などもない。
事実の存在は、あなたの存在と感覚器官を中心に存在している。
事実などというものは、この宇宙のどこにもない。
あるのは、認知された事実の『<感覚>だけ』である。
さて、そのように、あなたの知覚の中に事実や妄想があるにしても、
その本当の現場は目の前のテーブルでもなく、空間でもなく、あなたの脳にしかなく、また、その脳の情報を意識しているあなた本人にしかない。
だから、あなたは、もともと、生まれて死ぬまで、たった一人なのだ。
4人の者が同席していても、そこにあるのは、ひとつの環境にいる4人ではなく、
4つの環境を感じている者が、ひとつの場所にたまたまいるということである。
極論すれば、世界だの事実などというものは、どこにもありはしない。
全部、それは主観、あるいは感覚、脳、そして意識の産物だ。
外界の事実などはなく、あるのは、外界からの温度や圧力の刺激のみであり、
それがあなたに認知された時点で『事実』と呼ばれるのみである。
盲目の者の事実は我々と異なり、聾唖者の事実は我々と異なり、全身麻痺の者の事実は我々と異なり、別の生物の事実は我々と全く異なる。
したがって、
禅師は特定の物体や現象を指さして弟子に問うことは決してならない。
たとえばテーブルのみかんをさして、「それはなんだ」と問う。
そして、それはそれであり、説明も名前もなく、ただ、それはそれだ。そして、「それだ」も余計で、「そのまま」、というのが無数の回答のうちの「ひとつの」回答となるが、そうではない。
これでは着眼点が全くずれている。
本当の『仏教者』の正しい問い(着眼)は、「たったひとつ」しかない。
それはこうなる。みかんを指さして
師『そのみかんはどこにありますか?』
弟子「そこです」
師『そこです、と言って見ているあなたはどこにいるのか?』
弟子「ここです」
師『ではみかんはテーブルにあるのか、あなたの目にあるのか?。』
弟子「みかんはテーブルにあります」
師『ある、と言っているあなたは、どこにいる?』
弟子「ここです」
師『このようにみかんをどけたら、どうなる』
弟子「みかんはなくなり、テーブルがあります」
師『では、みかんがあっても、なくてもかわらず在ったものは何か』
弟子「それを見ていた私です」
師『では、そのあなたとは何か?』
弟子「このからだです」
師『本当にそう思うか?』
弟子「はい」
師『ならば聞くが、夜寝ているとき、そのあなたという肉体はあるのだから、
ちゃんと、夜中に、あなたもそこにいるのだな?』
弟子「そういうことになります」
師『そうじゃないだろう。夜寝ているときにそこにあるのは、あなたの肉体であって、あなた本人じゃないだろう。なぜならば、いま、こうしてあなたが、みかんを見ていた自分はここにいます、という、そういう自覚が睡眠の中にあるかね?』
弟子「ありません」
師『ならば、あなたが、あなたと自分を言うときに、そこにあるものは、本当は何なのだね?』
弟子「よくわかりませんが、存在感でありましょうか?」
師『では、その存在感は寝ている間、なぜないのか?』
弟子「感覚器官が休息しているからでしょう」
師『そうではないはずだ。目は閉じていても、臭覚も触感も聴覚も生きている。
寝ているのは、感覚ではなく、君の脳じゃないのかね?。しかもときおり、それは夢まで生み出している。夢の中でも、君は存在感があるだろう。確かに夢の中には君は存在しているから、その中で恐怖したりできたのだから。君が夢の中に存在しなかったら、汗びっしょりで跳び起きるなんてことはあり得ない。そこに知覚しているあなた本人がいたからそういうことになる。
とすると君の存在感は脳が起きていればあり、脳が寝ていればなくなるというわけかな?』
弟子「そうなってしまいます」
師『ここで、ひとつある現象を説明しよう。
この現象、いわば人間にとっての事実は、太古から修行者によって確認され、
また最近では、脳生理学者によっても確認されている完全に科学的に立証されている問題だが、、
それは、人間は全部のあらゆる感覚を遮断しても意識は残るということだ。
全身麻酔の麻酔が、もしも脳だけを避けて視聴臭味覚と全身に渡ったら、その者は、5感は完全に麻痺して何も感じなくなるが、脳は生きており、そこで勝手に想像の世界を作り出す。そうなったら、ひきもどす現実の事実などは麻酔が覚めるまで存在しないので、もしもその者がそのまま昏睡状態になったらば、本人はその夢そのものだけが、本人の現実世界となる。だから、本来夢から覚めるだの、覚めないなどというものはどこにもない。
君が夜に夢を見るということは、
肉体が作り出すひとつの夢から、脳が作り出すもうひとつの夢に移動するということに過ぎない。
事実や現実など、「実体」としての区別は、どこにもありはしない。
全部が、いわば夢なのだ。
たまたま昼間の夢は現実と呼ばれ、夜は夢と呼ばれるだけで、本人にとっては、全部が夢であり、またどっちも全部が現実だ。
夢とか現実ではなく、本当にそこにあるのは感覚または脳の『情報』である。
・・・・・・・・・
さて、仏教徒の真の探求とは、その夢、または現実、
どっちでも呼び名は無意味だが、その「情報」を見ている者は誰かということだ。
問題は雑念を切ることじゃない。
雑念もまたひとつの「情報」だ。
ここにあるテーブルだって、ただの視覚情報だ。
問題は、対象物じゃない。
夜夢を見ていたら、これを見ているのは誰だ、と自覚ぐらいできなかったら、
その者は禅師じゃない。夜に見る夢に流されるような者は、死んだら、あっという間に輪廻の夢に迷い込む。
毎晩、毎日の、その夢の中で、夢を見ているのは誰だと工夫もできない者は禅師ではない。
さて、問題は雑念があるかないかではなく、
雑念があったら、誰がそれを見ているのかだ。
そんなものは、雑念でなくて正念でも同じことだ。
たとえば、みかんを見る。それは、ただのそれだ。
だが、思考を挟まずに、その、ただのそれを見ているのは、誰なのか?。
誰というより、『何』なのか?』
弟子「ただの意識?でしょうか」
師『今、そのただの意識を自覚したならば、それを自覚したものは何か?』
弟子「意識それ自身でしょうか?」
師『ならば、そこで、よーく、注意してみなさい。
その意識そのものを見詰めようとしてみなさい。最終的にあなたに起きる全部の自覚を意識しているものを捕えて離さないようにしてみなさい』
弟子「・・・・・・・・・・・
なんだか、まったくよくわからなくなりました」
師『そこだ。そこが入り口だ。出口ではないが、そこが本当の仏教への入り口だ。
だから、その自分の意識を見詰めて、いまそこで座禅しなさい。
鼻を流れる呼吸や座っている自分の体の感覚や動作を工夫として使うのではなく、
そのただ存在しているあなたのその意識、観察者、自覚したときには、自覚を見ている意識、、それと対面して、にらめっこをしなさい。
さて、どうかな?』
弟子「ますます、なにも分かりません。
それを見詰めることすらも薄らいできて、安定しませんし、思考もないです。」
師『ならば、今、どんな感じだ』
弟子「すべて、が止まっています。思考も、観察も止まっていますし、自覚しているのは誰かという問いも止まっています」
師『それだけしゃべっていて、止まっていると言うつもりか?』
弟子「はい。自分でこのようにしゃべり、あなたの言葉を聞いていますが、
それでも、私の内部は、全く何も動いていません。」
師『ではそこに何が存在している?』
弟子「ただ、{これ}です」
師『これ、とはなんのことだ』
弟子「わかりませんし、言葉になりませんが、確かに、これです。
これは、たとえどんな早い行動の中でも、雑事の中でも、あるいは睡眠の中でも失われないものだと思います。というのも、これは外部の世界に属していません。
かといって、自分の作り上げる妄想でもありません。私の個性でもありませんし、
{これ}は失われようがありません。
形や内容とかがある経験ならば、それは状況によって失われたり、忘れ去られるでしょうが、どうやって体験性そのものを忘れられるでしょうか?。私は何かに夢中になれば肉体を忘れることもあるでしょうが、どんなに夢中になっても、どんなに肉体や雑念や囚われは忘れられても、これだけは忘れることはできません。
なぜならば、これは記憶ではないからです。
これは常に現在進行形で『生きているもの』だからです。
呼吸の工夫などは忘れてしまえるし、呼吸の自覚も雑念でさまたげられて忘れることができるし、そういうものは忘れられる。自分がやろうとして留意するものは、どんなものでも不注意になる瞬間がくる。
でも、{これ}は無理です。忘れられません。忘れようとしても忘れられません。
他人としゃべっていても、働いていても、なんらその行為に支障なく、忘れられませんし、たとえば美女と性行為していても忘れられません。それは何か忘れられないこだわりに囚われていると言う意味で忘れられない、ではなく、
{これ}は、しゃべったり、行為したりの同一の次元にあるものではなく、
もともとそれに全く影響されないものです。」
師『それは、自分の存在感覚を忘れられないということかね?』
弟子「いいえ、まったく違います。
忘れられないのは、自分でもなく、自覚でもなく、
私が、もはや、一生、忘れられなくなった{これ}は、
{観照そのもの}です。
観照の対象物でもなく、見ている私でもありません。
観照{そのもの}です。
それは観照者の主体としての私ではありません。
ただの観照という『現象そのもの』です。
ですから、これはどんなものにも囚われる事なく自由に流れて行き、どんな行為の中にも存在し、またどんなに静まって心身脱落して対象が消えても、なおも、そこにあり、これは動中、静中にまったく無関係に
もはや、失うことは絶対に、不可能です。」
師『ならば、そんなにどうしても失えなかったものを、
今まで、失っていると思い込んで、どこにほっぽらかしていたのだね?。
失えない筈のものを、どうして今まで求めて修行などしていたのかね?』
弟子「着眼点を、全く間違っておりました。それが原因です。
どんな着眼点も、着眼点とは、ただの方便にすぎませんでした。
実は着眼することによって、結局は着眼できなくなり、{これ}がただ{在る}状態になるべきでした。
着眼とは、悟りの『発見の』手段ではなく、
悟りの『実現の』手段でした。
禅では、最後の最後まで観察者が残ってしまい、進歩しなくなり、そんな時、
導師たちは忘却するまでひたすら、なんでもただ続けて成り切れ、と申しますが、
それは、完全に間違っておりました。
どうしても観察し、自覚してしまうならば、
その自覚、観照者そのものにまっこうから、対面してにらめっこをすればよかったのです。
邪魔なものを断ち切るのではなく、
まさに『邪魔なもの自体に深く着眼』を維持すればよかったのです。
その着眼の結果は、
着眼とか、発見とか自覚とか、知る、知らない、分かる、分からない、
事実、妄想、只と雑念、・・そういう一切の分別の介在しない、
ただの観照そのものとして、ただ存在することでした。」
師は弟子をひっぱたいた
『ならば、これで忘れるか?』
弟子『いいえ、和尚、そりゃ無理ですよ。
たとえば、私が何か考えているときに和尚が私を殴ったら、
確かに「考え」は吹っ飛び、
そこにはそれまでの思考の代わりに痛みそのものがあります。
しかし、そういう「対象は」ただ無常に入れ代わり、とどまることがありません。
一方、{これ}はその全体をくまなく体験し続けているものですから、失われません。
すなわち{これ}とは
体験内容なのではなく、絶えざる体験性そのものです。
観照内容なのではなく、絶えざる観照性そのものです。』
師『明日から、わしは、ちょっと地方へ出掛ける。
留守や手紙の応対は、お前が私の代わりにやれ。
今のそのお前なら、
たとえ提唱で嘘ハ百こいても、
全部、方便として真実になってしまうじゃろからな。
ふぉっほっほっほっ!!!。
***************
ここ数日に出て来た行法と工夫のまとめ
1*ただ、座り、存在して只管になりきろうなどとしても、困難だ。
そこで、ただ座っていることを眺めている自分は何かを見てみよ。
それは、あなたの意識だ。あるいは知覚主体だ。あなたは、そこにいる。
そこに何が「いる」のか?。あなたの全部を見ているその観察者の意識を
それを凝視する時のような気持ちで捕えてみよ。意識があるというその事実だけを意識してみよ。その結果、必ず呆然と意識の輪郭が溶けて分からなくなる。
これまた絶対に開眼か半眼のままで行うこと。脳天の留意も忘れずに。
2*どうしても分からない問いがあったら、はっきりした短い言葉にして、一回の座禅に一句の問いを持ち込め。そして座禅中に何度も、静かにゆっくりと心の中で反芻して(はんすう→繰り返し味わって)みよ。自分の問いを自分で味わって心の中で聞くのである。これまた開眼か半眼で。脳天留意のままで。
3*問い詰められて、分からないときは、分かろうとせず、分からないそのままで、分からないことをあらわして『さぁー?』と言うべし。実際には、分かるも分からないも、どちらも真実とは違うのであるが、我々は、あまりにも分かることの方が善だと脳を教育されたので、逆の弾みをつけてやらねばならない。
『さぁー?』は、やがてあなたには禅定のための呪文のようになる。
何事も、分かったと思った時から、浮足立つのだ。
分からないで無知そのものになると、足は底に立つ。とうぜん開眼、脳天留意。
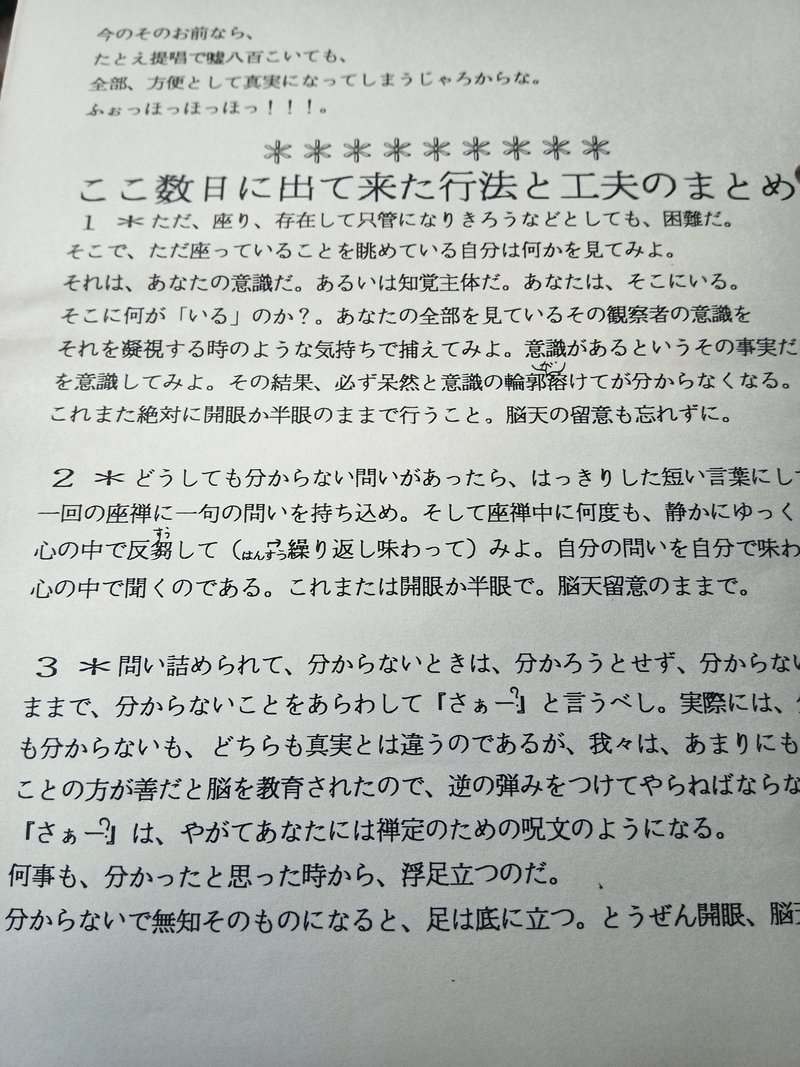
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
