
世帯所得の推移について
厚生労働省は、国民生活基礎調査という大規模調査を実施している。かつて実施されていた厚生行政基礎調査、国民健康調査、国民生活実態調査、保健衛生基礎調査という4つの調査が統合された調査だ。昨年は状況が状況なだけに中止されてしまったが、その前の2019年は大規模調査の年であったため、ニュースでも話題になっていた。
この調査は、「世帯数と世帯人員の状況」「各種世帯の所得等の状況」「世帯員の健康状況」「介護の状況」という4つのパートから成るが、今回は上記のニュースでも取り上げられた世帯所得について確認してみたい。

まず、世帯の姿を見てみよう。20年前の2001年では、世帯数は4566万世帯で、1世帯あたりの平均人員数は2.75人。これに対して、2019年では5179万世帯、1世帯あたり2.39人となっている。
内訳をみていくと、単独世帯は1102万世帯から1491万世帯に、夫婦のみの世帯は940万世帯から1264万世帯に、ひとり親と未婚の子のみの世帯も261万世帯から362万世帯へと大幅に増えている一方で、夫婦と未婚の子のみの世帯は1487万世帯から1472万世帯と微減傾向にある。
また、別の切り口でみると、高齢者世帯(65歳以上の者またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)は、665万世帯から1488万世帯と倍増以上の伸びを見せていることがわかる。
これらのことから、まさに少子高齢化が急激に進行中である構造が見える。

次に、世帯あたりの平均所得金額の推移を見ていこう。全世帯の平均所得は1994年の664万円をピークに、20年前の2001年には602万円、2010年には538万円まで落ち込んだあと、やや持ち直して2018年には552万円となっている。
なお、国民生活基礎調査の「所得」とは、税・社会保険料を差し引く前の税込み所得のことをいう(用語の説明より)。会社員の場合は、収入(総支給額)に相当するもので、国税庁が税額を計算する上で用いる「(給与)所得」(=総支給額−給与所得控除額)の定義とは異なることに注意したい。

さて、この間、米国のITバブル崩壊やリーマン・ショックなど、世界経済に大きな影響を与えた出来事が起きているが、その米国では世帯あたり年間所得は2013年ごろより増加に転じており、2018年では中央値で6万1937ドル(当時1ドル113円くらいなので、日本円にして約700万円)とだいぶ差が開いていることがわかる。
世界経済の影響など外的要因で片付けるほど単純な問題ではなさそうだ。この20年間で、実質的に年金暮らしとなる高齢者世帯が大幅に増えた一方、現役世代についても非正規雇用労働者が増加するなど構造的な要因で、平均所得を押し下げるだけのインパクトがあったということだろうか。あるいは経済成長を果たした諸外国に比べ、付加価値の高い産業が伸びなかったということなのだろうか。私は専門家ではないので答を持ち合わせていないが、何か大きな要因があるようには感じる。


上に挙げた2つのグラフは、2000年と2019年の国民生活基礎調査による世帯所得の分布だ。ここでは中央値(真ん中の順位の値)がわかる。2000年は世帯所得の平均値では626万円であったが、中央値だと506万円となり、平均値は高額所得世帯の影響を大きく受けていることがわかる。所得については、中央値の方が「普通の世帯」のイメージに近いであろう。
グラフには書いていないが、別表から計算すると、所得が300万円未満の世帯が27.2%である一方で、1000万円以上の世帯が16.5%となっている。
次に2019年のほうをみると、平均552万円に対し、中央値は437万円となっている。こちらも中央値の方が実態をよく表しているといえる。また、300万円未満世帯が32.3%に増えた一方、1000万円以上世帯が11.6%に減っている。平均値・中央値ともに押し下げる要因としては、やはりこのあたりの構造的な変化が大きそうだ。
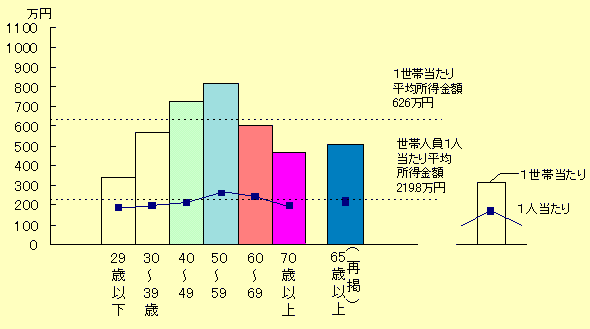

次に、年齢階級別の変化を見ていこう。2000年では29歳以下では338万円であるが、30-39歳では一気に上がって566万円、40-49歳で727万円、ピークを迎える50-59歳で819万円、60-69歳でも600万円、70歳以上で468万円となっている。
2019年では29歳以下が301万円、30-39歳で551万円、40-49歳で679万円、50-59歳で732万円、60-69歳で540万円、70歳以上で407万円という結果になり、全世代で世帯所得が落ち込んでいることがわかる。つまり、単に高齢者世帯が増えたから平均を押し下げているのではなく、そもそも全ての世代で所得が減っている傾向が読み取れる。


調査のアンケートでも、暮らし向きが悪くなったと答えている世帯の割合は、ここ数年はやや持ち直してきているものの、20年前と比較すると、やや増えている傾向が窺える。
国民生活基礎調査調査では、この他に国際機関であるOECD(経済協力開発機構)が定めた基準で算出された日本国内の「相対貧困率」も出しているが、2000年の15.3%から2018年の15.4%(新基準で15.7%)とそれほど大きく変化していない。しかしながら、全般的には所得が減り続け、生活が苦しい世帯が増えているというのがいまの日本の現状といって良いだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
