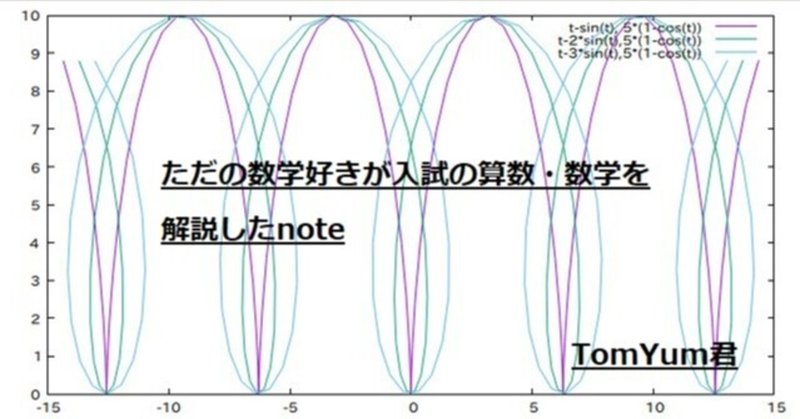
【桜陰中学校2021年度入試算数第4問】歯ごたえのない時計型問題
いよいよ最終問題です。時計タイプの問題(円周上を点が移動する問題)ですが、あまり難しくはないようです。

桜蔭中学校・高等学校
2007年10月22日、杉山真大撮影、Wikipediaより
問題
円周率は,3.14を使って計算することが多いです。しかし,本当は3.14159265…とどこまでも続いて終わりのない数です。この問題では,円周率を3.1として計算してください。
図のように点O を中心とした半径の異なる2つの円の周上に道があります。A さんは内側の道を地点 a から反時計回りに,B さんは外側の道を地点 b から時計回りに,どちらも分速50m の速さで同時に進みはじめます。A さんと B さんのいる地点を結ぶ直線が点 O を通るときに,ベルが鳴ります。ただし,出発のときはベルは鳴りません。

(1) A さんと B さんが道を1周するのにかかる時間はそれぞれ何分ですか。
(2) 1回目と2回目にベルが鳴るのは,それぞれ出発してから何分後ですか。
(3) 出発してから何分かたったあと,2人とも歩く速さを分速70mに同時に変えたところ,5回目にベルが鳴るのは速さを変えなかったときと比べて1分早くなりました。速さを変えたのは,出発してから何分後ですか。
解答解説
円周率を3.1としていることに大きな意味はありません。計算を複雑にしないためだと思います。
(1) は、Aさんは (50 × 2 × 3.1)/50 = 6.2分、Bさんは (60 × 2 × 3.1)/50 = 37.2/5 = 7.44分となります。
(2) は、1分辺りに何度動くかを求めておくといいでしょう。
・Aさん … 360 ÷ 6.2 = 分速1800/31度
・Bさん … 360 ÷ 7.44 = 分速1500/31度
さて、ベルが鳴るのは2人が合計で180度、360度動いたときなので、1回目は180 ÷ ((1800/31) + (1500/31)) = 180 × 31 ÷ 3300 = 93/55 = 1(38/55)分後、2回目は1(38/55) × 2 = 3(21/55)分後となります。
(3) は、A, B の速さが分速50mから70mに変わると、1分辺りに動く角度も70/50 = 1.4倍になります。したがって、ベルのなる時間の間隔が 1(38/55) 分から 1(38/55) ÷ 1.4 = (93/55) × (5/7) = 93/77 分になります。
ベル1回あたり 1(38/55) - (93/77) = 93 × {(1/55) - (1/77)} = 93 × (2/385) = 186/385 分早くなるので、1分早くなるためにはベル 385/186 回分だけ速度を速める必要があります。
したがって、速さを変えたのは {5 - (385/186)} × 1(38/55) = 5(38/11) - (7/2) = 5(5/11) - (1/2) = 4(21/22)分後となります。
感想
この問題も桜陰としては簡単な問題だと思います。しいて言えば (3) がちょっと難しいでしょうか。とはいえ、落としたくない問題です。
全体を見渡すと第1(3), 2問がやっかいで、後半の第3, 4問がやさしく、時間配分を間違えそうな並びになっているので注意が必要だったかもしれません。
(何なら 第1問 (1) の計算問題も時間を取られるので面倒です。)
とにかく問題の並びだけが気になるところで、前半に時間を使いすぎて焦って自滅した受験生がいたのではないかと思います。それが学校側の狙いだとは思いますが。
入試は受験生を落とすための試験
ということです。
しかし、昨年と比べると今年は難易度が下がっているのではないかと思いますが、塾の見立てはどうなんでしょう?
コベツバさんを見ると、第3, 4問を難しいと評価しすぎていると私は思います。この2問は悩んだり手間取るところがほとんどない、素直な問題だと思うのですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
