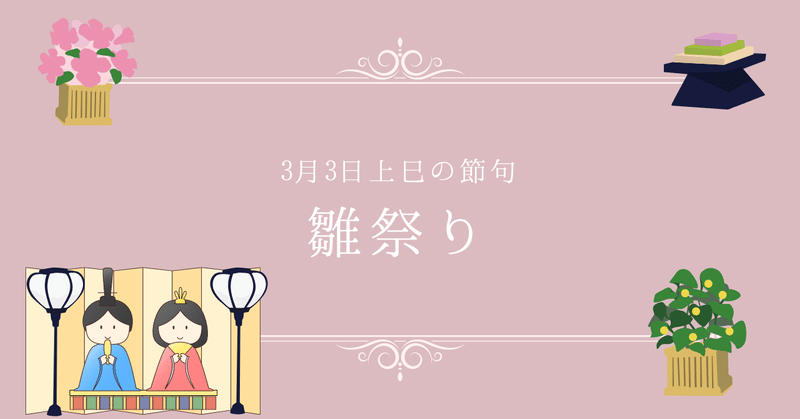
上巳の節句 雛祭り 3月3日
女の子の成長を祝ってひな人形を飾る行事
上巳の節句(じょうしのせっく)
上巳の節句は3月3日の雛祭りのことです。昔は、3月初めの日の日に雛を祀ったところからこの名が残りました。この日が、五節句に数えられたのは江戸時代に入ってからのことです。"桃の節句"とも呼ばれる女子の節句で、雛壇をかざり、女児の誕生を喜び、末長く幸福であるように祈るための行事です。
中国では、この日に川で身を清め、不浄を取り払う習慣がありました。平安時代にこの習慣が日本へ伝えられました。その後、身代わりとして紙で人形を作り、穢れを人形に移して川や海に流す風習が各地に広まりました。
さらには、人形を飾る風習が盛んになり、江戸中期には雛壇も作られ、今のような雛人形になっていきました。
ちなみに、桃の節句が過ぎたら、できるだけ早くお雛様をしまわないと、その娘さんが嫁に行けなくなる、婚期が遅れるという言い伝えは今でも
残っています。
雛祭り
「雛祭り」は「流し雛」と平安時代の貴族階級の子女が人形で遊ぶ「ひいな遊び」という、ままごとに近い人形遊びが起源とされています。
室町時代には、端午は男児の節句であり、それに対して上巳は女児の節句とされ、江戸時代に入ってだんだん庶民に伝わり、次第に三月三日に、女の子のお祝いの儀式として人形を飾るしきたりが定着していったとされています。
雛人形は幸せな婚礼を象徴
雛飾りは、そもそも婚礼を表現したものです。
一段目に飾られる男雛と女雛は、内裏雛や親玉雛と呼ばれ、天皇・皇后の姿を模したものです。
その下の二段目には、婚礼の三三九度の世話をする三人官女、さらにその下には笛や太鼓のお囃子でお祝いする五人囃子やお供の随身、一番下の段には華やかな嫁入り道具が揃い、幸せな婚礼を象徴しています。
内裏雛の並びは、左右が違う地方も
かつては、陰陽道の「男=陽=左」という考えから、内裏雛は男女が並んだときの左側(向かって右側)に男雛を飾りました。
その後、文明開化で西洋文化が取り入れられ、大正天皇が即位式で西洋に倣い右側(向かって左側)に立った影響で、特に関東では右側(向かって左側)に男雛を飾るようになりました。
雛人形は節句が終わった翌日に片付ける
雛人形は、前日に飾る一夜飾りは縁起が悪いとされており、三月三日の二週間ぐらい前から飾るのが一般的です。
また、節句が終わった翌日には片付けたほうがよいといわれています。
これは、いつまでも出しておくと婚期が遅れるとされていますが、片付けの出来ない娘はよいお嫁さんになれないという戒めと、厄を移した形代の雛人形を、雛祭りが終わっても飾っておくのは縁起が悪いという考えに基づいているようです。
雛祭りのご馳走
草餅
雛祭りは「草餅の節句」ともいわれ、欠かせないご馳走になっています。
使用されるよもぎは薬草で、邪気を祓う効果があるとされています。
菱餅
菱形は、竜に襲われそうになった娘を菱の実で退治して救ったという、
インド仏典の説話に由来しています。使われている三色は、赤が「魔よけ」、白は「清浄」、緑は「邪気を祓う」とされています。
雛あられ
餅や豆などに砂糖をからめて炒ったものです。炒ったときのはぜ具合で、
昔はその年の吉凶を占ったといいます。よくはぜると吉、あまりはぜないと凶とされていました。
蛤のお吸い物
雛祭りのお吸い物に蛤を用いるのは、採った貝類を神様に供えた後に、お下がりとして食べて祝った名残りといわれています。
白甘・酒酒
甘酒は子供でも飲めるように、餅米の粥に麹を加えて作った甘い香りの
する飲み物です。白酒は蒸した餅米にみりんや焼酎などを加え、熟成さ
せ、すり潰したアルコール度10%前後のお酒です。雛祭りに飲まれるようになったのは、江戸時代後期からとされています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
