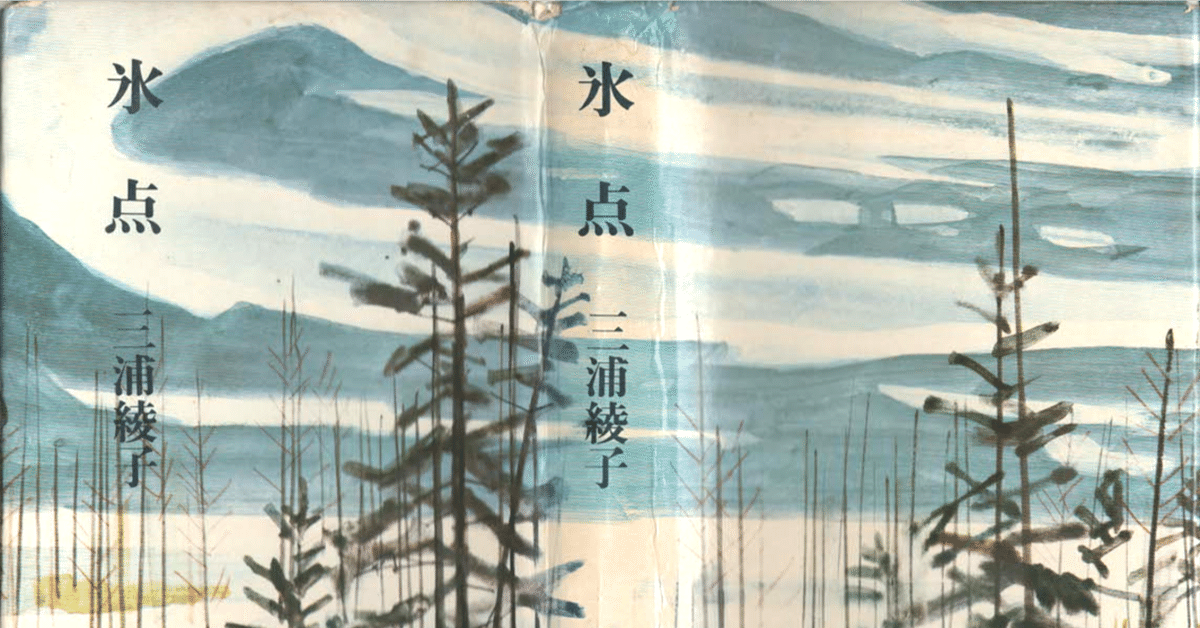
『氷点』はこうして出来た (三浦綾子初代秘書として生きて - 7)
第二次世界大戦の敗戦から二十年も経っていない1964年7月、北海道旭川市郊外の田んぼの中に建つ雑貨屋の主婦であった三浦綾子は処女作『氷点』で彗星の如く現れた。
初めの一行から書けば良いのだ
1963年の元旦、朝日新聞に「一千万円懸賞小説募集」の広告が掲載された。
「大阪本社創刊85周年 東京本社創刊75周年の記念事業」として掲載されたこの広告は、朝日新聞に連載される小説の原稿を募集するもので「プロ、アマを問わず。長さは原稿用紙800枚から1000枚。新聞連載の為、一日分は3枚半 締め切り12月31日」と有った。当時は、高卒の初任給が一万円にも及ばない時代で、一千万円の賞金は、世間を驚かせた。
この広告を、三浦綾子さんの弟さんが見つけた。一年前に雑誌「主婦の友」が募集した「主婦の書いた実話」という企画に綾子さんが入選し、全国各地から夥しい反響の手紙が来ていたのを、近くで見ていた方であった。
綾子さんが書いたのは「太陽は再び没せず」というタイトルの自伝エッセイだった。戦時中、懸命に軍国主義教育をしたことによる自責の念、そこから生まれた虚無感、その虚しさの中での肺結核発症、更に脊椎カリエスになり13年に及ぶ闘病生活。癒されて今の結婚生活への感謝等、綾子さんの人生が綴られていたその実話は多くの読者に感動を与えた。
弟さんは、お母さんに「母さん、これ綾ちゃんが来たら見せて」と「一千万円懸賞小説募集」の切り抜きを渡して、出かけて行った。ご両親に新年の挨拶に行って広告を渡された綾子さんは「私には、全く関係の無い事ね」と一笑に付した。それまで、綾子さんは小説を書いたことが無かったからだ。
私は、このブログを書くにあたり、残されている様々な手記メモ等を読み返し、夫の光世さんの手記を見つけた。そこには、綾子さんが相当昔から小説を書きたいと願って居たことが書かれていた。「太陽は再び没せず」の反響を受けて、綾子さんのその気持ちは更に高まっていたようだ。一般方々のもとに届く媒体に載るような文章をもう一度書きたいと。
一笑に付した綾子さんだったが、家に帰ったのちにあれこれ考えを巡らせた。そして、1000枚の小説も、初めの一枚から書けば良い、と気づき、その初めの一枚も、初めの一行から書けば良いのだと気づき、私にも書けるかもしれない、と思ったそうだ。眠れぬまま思いを巡らせていた綾子さんは、闘病中に遠縁の人が殺された事を思い出した。そしてその夜、『氷点』の構想が出来た。
涙がボタボタと原稿用紙の上にこぼれおちた
当時、雑貨屋をやって居た綾子さんにとって、原稿に取り組める時間は、閉店後の22時以降だった。22時から書き始め、時には午前1時、2時まで、寒い日は布団に潜り、凍るインクを突き崩しつつ、原稿を書いた。一年書き続けて、書きあがったのは締め切り日12月31日の午前2時だったという。こうしてギリギリに書きあがった小説『氷点』は、旭川郵便局本局の12月31日のスタンプが押されて朝日新聞社東京本社に届いた。これは、病が癒されてたった5年後の事だった。
この懸賞小説企画の担当者の、当時の記録ノートを見せて頂いた事がある。そこには「40-50編の応募が有れば企画は成功と思う」と記されていた。新聞連載小説は難しいジャンルで有り、プロも応募できるとなるとハードルが高く応募する人は少なくなるだろうという読みだったらしい。しかし、正月明けに担当者が出社してみると12畳程の部屋に、天井迄いっぱいに原稿が山積みになっていた。応募総数は731編だった。
そのノートには他にも興味深い記録が有って、第一次審査で原稿を読む人を増員するための計画、二次審査にあたる人を探している様子、審査員に支払う謝礼金の予算変更などの記述もあった。
当時の朝日新聞文芸部長だった扇谷正造さんは、選考委員のひとりだった。朝日新聞社から1984年10月に出版された「三浦綾子作品集8」の月報18に、選考過程でのエピソードを以下のように書いて居られる。
新聞連載小説は、毎日読者を引き付けなくてはならないため、素人には無理だと文壇の人々も思って居たと言うが、三浦綾子が書いた初めての小説『氷点』が一位入選したのだった。
社会現象になるほどの人気だった『氷点』
当初、入選発表は4月位を予定していたが、余りの応募数の多さに、発表は7月10日になった。発表当日は、春から教会で計画していた三浦家での家庭集会第一回目の日であった。本来家庭集会とは、牧師が信徒の家に赴いて、誰にでも分かりやすく聖書の教えを、お話したり語り合ったりするフランクな集会なのだが、その日は、朝日新聞社からの依頼で、取材が入るので牧師のガウンを着て話をして下さいと、依頼があったそうだ。当時の牧師が、嬉しそうに思い出を語って居られたのが、忘れられない。
一千万円懸賞小説に入選したのは、北海道旭川市の町はずれの小さな雑貨屋の主婦であること等、このニュースは、日本中を駆け巡った。
『氷点』の新聞連載が始まると、社会現象になるほどの人気になった。連載が読みたくて新聞の配達を待っていた、朝が楽しみだったと語る方に今でもお会いする。寮などでは新聞を奪い合う様にして皆が楽しみに読んでいた。連載終了後に単行本として発売されると、『氷点』は、300万部を遥かに超えるミリオンセラーになった。又、生まれた女の子に主人公の「陽子」の名前を付けた人も多数いたと言う。
『氷点』がテレビドラマになると、旭川では銭湯から人が消え、商店街からも人影が消えたと語り伝えられている。当時は、自宅にお風呂が有る家は、多くは無く、夜は皆銭湯へ出かけていたように記憶している。ビデオも無かった時代なので、皆、放送時間に合わせて帰宅したのだろう。あの長寿番組「笑点」は『氷点』を捩って(もじって)付けられた名前である。旭川の近くで笑点の収録があった時、綾子さんに出演の依頼があったと聞いているが、綾子さんは「とてもあのようなウイットにとんだ回答は出来ないと、辞退した」と言う。私は、綾子さんなら、司会者がタジタジとなる、絶妙な回答をして面白かったはず!と残念に思っている。三浦夫妻は殆どテレビを見ないのに、この番組が大好きで、「笑点」だけは欠かさず見ていたのだった。
綾子さんが亡くなった後、私は『サザエさん』で有名な長谷川町子美術館に伺った事がある。そこには「ふっとう点」というタイトルで主婦が懸命に小説を書く漫画が、展示されていた。又、NHKの朝の連続ドラマで水木しげるさんが主人公の「ゲゲゲの女房」が放映された時、ドラマの中で水木さんが「三浦綾子綾子さんと言う人は、長年病気で~~」と2分近く綾子さんの事を話している場面が有った。綾子さんは、このことを知らなかっただろうと、残念に思う。
因みに、「主婦の友」で入選した『太陽は再び没せず』は、『氷点』入選の後「道ありき」というタイトルでもう少し詳細な綾子さんの自伝を「主婦の友」に連載しミリオンセラーになった。大好評で続編を望む読者の声が多く「続道ありき この土の器をも」が出版され、、これも又、反響が多く更に「道ありき三部作 光りあるうちに」も出版された。これらは、「道ありき三部作」と呼ばれ、三部通して読まれることが多い。
自分に出来ることを工夫して精一杯生きる
綾子さんは「私なんか駄目」「私には出来ない」と言うのは、謙遜ではなくごうまんだと常々言っていた。神様は、1人1人を愛して素晴らしく誕生させてくださっているのだから、自分に出来ることを工夫して精一杯生きることが大切なのだと言いたかったのだと思う。
綾子さんが、1000枚の小説も初めの一枚から、初めの一枚も始めの一行から書けば良いと思って書き始めた『氷点』は、私を前に歩ませてくれている。この言葉を私は「始める一歩が道を拓く」と言葉を替えて、語り伝えている。
余談となるが、この「始める一歩が道を拓く」は、私の長女の道も切り拓き、彼女の人生を変えてしまった。長女が中学生の頃、家庭用の小さなCDプレイヤーが大ヒットしており、音楽好きの彼女も、もれなく、CDプレイヤーが欲しいな、と言った。タイミング良く旺文社の中学生向け雑誌に「旺文社&ソニー全国中学生テープ大賞」という作曲コンテストの広告が載り、その賞品の一つが、大ヒット中のソニーのCDプレイヤーで、私は長女に「自力でCDプレイヤーを獲得したら?」と言った。
私も長女も、綾子さんが懸賞小説からスタートしたこと、病弱な体をおして、最初の一行から一歩ずつ書いていったことを思い出していたのだ。三浦家にお見えになる様々な有名人にお会いするうち、私はいつしか「皆、人間なのだよねー」と、思う様になり、肩書で人を恐れないようになっていた。誰にでも可能性が有るのだと思えるようにもなっていた。
長女はなんと本当に作詞作曲に挑戦し、綾子さんと同じように締め切りの最終日にそれを仕上げ、締切日の消印をもらうために郵便局に駆け込んで応募した。そして何と、この作曲コンテストの作詞作曲部門で全国優勝した。娘は、音大には行かず、一度は会社員になったが転身して、プロの作曲家、演奏家になってしまった。ピアノは習っていたが、作曲を習ったことは一度もなかったのに。
出来ない、駄目、と言わずに、最初の一行、最初の一歩、最初の一音から始めてみることは、本当に素晴らしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
