
読書記録 あい〜永遠にあり〜
読書記録 あい〜永遠にあり〜
高田郁(たかだ かおる)著
角川春樹事務所
2013年
高田郁先生は、1959年生まれ。
中央大学の法学部を卒業した法曹界を目指していたそうです。
お父様が山本周五郎先生がお好きだったので、小さな頃から、郁先生も山本先生の時代物をよく読まれて、時代小説を書こうと思ったとのこと。
私は、「みをつくし料理帖」を読んだだけでしたので、今回、高田郁先生のコーナーで「あい」という一代記らしい物語を見つけて読んでみました。

◎あらすじ
時は江戸末期。主人公のあいは、貧しい農村の末娘。ある日、母親から伯母の家への使いを頼まれて、そこで、機織りを知る。
あいは、農閑期に伯母から機織りを度々習うようになる。
伯母の家は、伯父が私塾を開いていて貧しい家庭の姉弟には無料で読み書きを教えていた。
伯母は子どもはいなかったが、そこに親を亡くした甥(後の寛斎)が一緒に暮らし、伯父から読み書きを習っていた。
ある日、あいは機織りの帰り道、山桃の木にとりすがって、拳を幹に叩きつけて、泣いてる豊太郎(後の寛斎)をみつけた。
父母を亡くしたとはいえ、故郷から離れてひとり暮らすにはまだ、豊太郎は幼すぎたのだろう。
しかし、勤勉な豊太郎は寛斎と名を改め、伯父の尽力でやがて佐倉にある医学の学問所に進学することになる。
あいは、叔母の家に相変わらず機織りを習いに行っていたが、その頃には、近隣でも評判の織り手になっていた。
そして、蘭方医学をおさめた寛斎とあいは、結ばれて、夫婦となる。
また銚子では、生涯の支援者ともいうべき、実業家の浜口梧陵との出会いがあった。
その後は、関寛斎は、蘭方医として幕末から明治にかけて、各地で活躍して、、、。
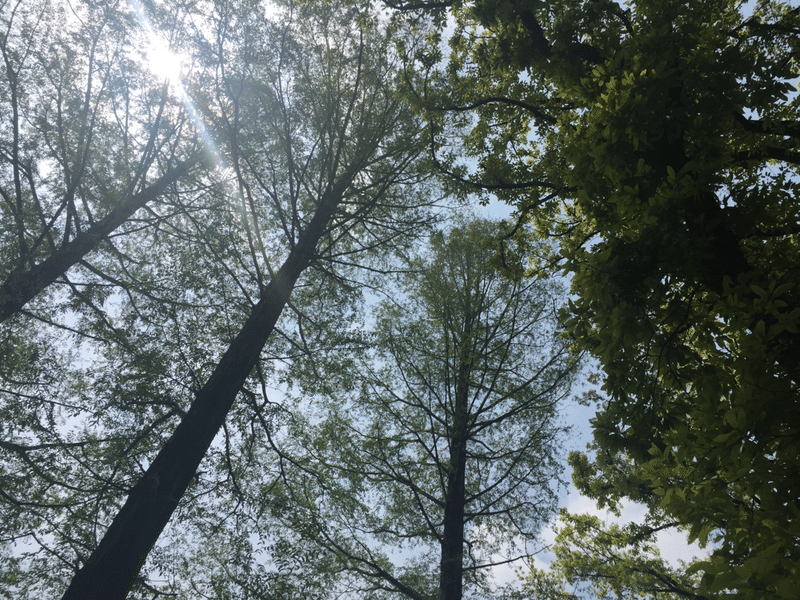
◎気になった箇所
(自分が見にくいので、引用の方法は取っていません)
148ページ
梧陵は、あいを振り返り、深い眼差しを向けた。
「人たる者の本分は、眼前にあらずして、永遠に在り、と」
永遠に在り、とあいは低く繰り返した。
そうです、と梧陵は大きく頷いてみせる。
「目先のことに囚われるのではなく、永遠を見据えることです。関寛斎、という人物は、何時か必ず、彼なりの本分を全うし、永遠の中に生き続けると、私は信じます」
あいは、両の掌で唇を覆った。そうせねば、激しい嗚咽が洩れそうだった。関寛斎に寄せる梧陵の厚い信頼があいの胸を打ち、とめどなく涙を溢れさせる。
◎感想
✴︎関寛斎と人についてあまり知らなかったのですが、この本を読んで、医学を学び、世の人を助けたい、そして医学を志す後進を育てたい、というものすごいエネルギーもち、この波乱の多い時代を生き抜いた人だなあと、感じました。
✴︎✴︎
この本の主人公のあいさんは、その寛斎先生の奥様。忙しい寛斎先生の分も飢饉や水害などの中、家庭を守り、八男四女をもうけ、育てていきました。
あいさんは、収穫がない年も新しい料理を考えたり、どんな時でも、明るさを失わず、むしろピンチの時ほど、知恵を絞って夫を支えて、家族を盛り立てて、そんなところ、素敵です。
最後の職場となった遠方の地に、子どもたちの反対をおしても、夫である寛斎に寄り添って生きていく姿に、胸がつまりました。
✴︎✴︎✴︎
昔は今とは違い、家事労働も肉体的に違う大変さはあれど、貧しい中でも、家族や兄弟が支え合って生きていく姿は、大切なものを心に、残してくれました。
✴︎✴︎✴︎✴︎
「人たる者の本分は、眼前にあらずして、永遠にあり」
今の生き方、目先のことばかりに囚われていないか、、、それを考えるのが、これからの私の宿題です。

◎今日も最後までおつきあいいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
