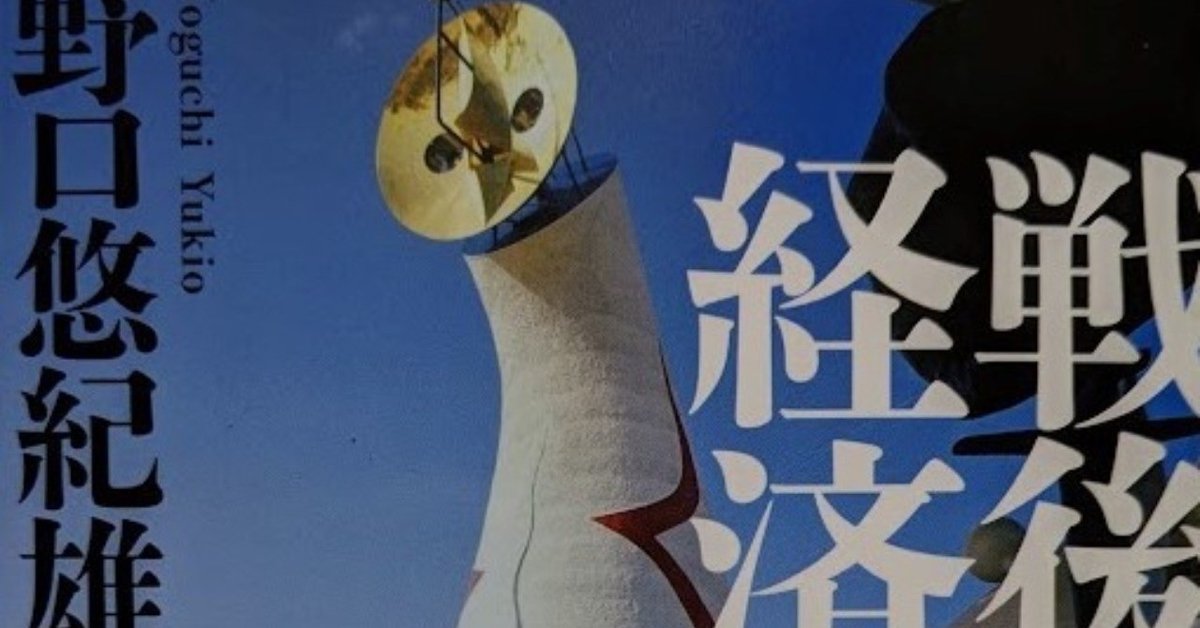
プロローグ(『戦後経済史』全文公開:その1)
『戦後経済史』が刊行されます(日本経済新聞出版社、2019年4月1日)。「はじめに」「プロローグ」「第1章」を全文公開します。なお、本書は,『戦後経済史』(東洋経済新報社、2015年6月)を文庫化したものです。
◇ 私は3月10日を生き延びた
私の記憶は、1945年3月10日の深夜に始まります。
猛火で赤く染まった空を背景に、B29の大編隊がこちらに向かってくる。圧倒的な力を持つ敵が、私たちを殺しに来た。それに対して、どうすることもできない。その極限の恐怖を、いまでもはっきりと思い出します。
私たち5人の家族(私、母、祖母、姉、妹)は、近くの小学校の地下防空壕に向かって逃げました。全員が防空頭巾をかぶり、幼かった妹をうば車に乗せ、途中でお地蔵様の前を、本当に転げるように走り抜けた記憶があります。そして、まったくの偶然によって生き延びたのです。
私たちと同じ防空壕に逃げ込んだ人々の大部分は、窒息死しました。多くの人が長時間、鉄の扉を閉めた状態の狭い空間に閉じ込められていたため、壕内の酸素が欠乏し、奥にいた人から順に死んでいったのです。私たちの家族はたまたま入口近くにいたため、扉の隙間からわずかに流れ込んでくる空気で、窒息死を免れました。
朝になって、警防団の人たちの手で外に引きずり出されたときには、家族全員が意識不明だったそうです。気が付いてみると、校庭には、黒焦げになった無数の焼死体が山積みになっていました。それを見たときの東京の空は、一片の雲もなく、綺麗に晴れ渡っていました。
これが東京大空襲です。私はこのとき4歳少々でしたから、この日より前の記憶があってもいいはずなのですが、まったくありません。この夜の経験があまりに強烈だったため、それ以前の記憶は抹殺されたのでしょう。
深夜の爆撃開始から鎮火した10日未明までのわずか8時間程度で、約10万人が死亡しました。これだけの短い時間で、一地域でこれだけ多くの人間が死亡したのは、人類の歴史で稀有のことです(関東大震災の死者は、2日間で約10万人とされます。広島の原爆による死亡者数は45年12月末までの合計で約14万人と言われます)。
なぜこれほど多数の人々が死亡したのか? それには、2つの原因があります。第一は、日本軍が防衛できなかったからです。高射砲部隊は約500発の砲撃で応戦しただけで、爆撃によって潰滅。迎撃戦闘機も現れず、334機(279機との説も)のB29の大編隊は、高度1500メートルから3000メートル程度の低空で、悠々と東京に侵入したのです。つまり、東京市民は、まったく無防備の状態で、B29の大群の前に放り出されていたのです。
その事実を、私たちは知らなかったのですが、米軍は知っていました。B29は、接触事故を防ぐため、尾灯をつけていたのです。自らの姿を隠すこともなく低空で侵入してきたため、友軍機と誤認した東京市民が多かったそうです。
私はB29の機影をはっきり見た記憶があるのですが、「B29は高度1万メートルを飛行するので、機体が地上から見えるはずはない。すると、この記憶は疑似記憶だったのだろうか?」。私は、長い間、そう疑っていました。しかし、1500メートルであれば、機体は見えます。私の記憶は本物だったのです。
多数の死亡者が出た第二の原因は、空襲がきわめて「科学的、効率的」に行われたことです。まず、東西5キロ南北6キロの長方形の縁に焼夷弾を投下して、炎の壁を作る。これによって後続機は正確に爆撃することができます。しかし、炎の壁に閉じ込められた住民は、外に逃げられない。私たちはこの四角形の北西の角に近いところにいたので、北西に向かえば、もしかしたら逃げられたかもしれません。でも、地上にいる人間に、そんなことは知りようがありません。多くの人は、水の近くなら安全と考え、隅田川に向かったのです。そして、対岸から逆方向に逃げようとする人たちと橋の上でぶつかり、身動きができなくなったところに焼夷弾が降り注ぎ、大惨劇が起きました(私は長い間、言問橋には怖くて近づけなかったのですが、いまでも橋の親柱は、焼け死んだ人々の血や脂が焼き付いて、黒ずんでいます)。
母は、防空壕に辿り着いたとき、「隅田川まで行くのはもう無理だから、ここで死のう」と言ったそうです。それを聞いた姉が、「死ぬのは嫌だ」と強く思ったというのですが、結果的に見れば母の判断は正しかったことになります。
この空襲を指揮したのは、数か月前にドイツの歴史都市ドレスデンを空爆で「平らにした」功績を持つ米戦略空軍司令官カーチス・ルメイ少将。日本政府はのちに、彼に勲章を贈りました。
◇「国家」に対する不信の原点
防空壕での窒息死者が多かったのは、人々が、奥ほど安全と考えて奥に逃れたからでしょう。しかし、そここそが危険な場所だったのです。私たちの家族が入口近くにいたのは、遅れて逃げ込んだという、ただそれだけの理由によると思います。日本国民は、防空壕で窒息する危険について、何の知識も持っていなかったからです。
後になって知ったことですが、ドイツでは、「防空壕に退避した場合、最も危険なのは窒息」と国民に教育していました。そして、3つの小さなヒンデンブルク灯(底の浅いボール紙のボウルに樹脂を入れ、短い芯を立てたもの)に点火し、一つを頭の高さ、一つを腰の高さ、もう一つを床の上に置き、もし一番上の明かりが消えれば、排気ポンプを動かしました(ロジャー・ムーアハウス『戦時下のベルリン』、白水社)。あるいは、床の灯が消えたら立ち上がり、腰の位置の灯が消えたら子供を持ち上げ、頭の位置の灯が消えたら、外がどんな猛火でも防空壕から出よ、と指導されていました(アントニー・ビーヴァー『ベルリン陥落1945』、白水社)。
それに対して日本では、防空壕での窒息の危険について教えられていなかっただけでなく、「焼夷弾を落とされたら、消火せよ」と指示されていたのです。このとき用いられたのは、ベトナム戦争で密林を焼くのに用いられたナパーム弾と同じ高性能焼夷弾です。ゼリー状の燃料の燃焼温度は1000度にもなり、水をかけても消えません(「ガソリンの匂いがしたので、ガソリンを撒いたのだろう」という証言があるのですが、ガソリンより強力な燃料だったわけです)。これほどの威力を持った焼夷弾が、20万発以上(32万発との説も)、1平方メートル当たり平均3発投下されたのです。それを消火しようとして逃げ遅れた人も、数多くいました。
3月10日の経験は、「国家」というものに対する、私の不信の原点になっています。究極の危機が降りかかってきたのに、何の助けにもなってくれなかった。それどころか、危機であることを伝えてすらくれなかった、という不信です。
それだけではありません。これも後になって知ったことですが、ドイツでは、戦争末期にソ連軍が侵攻してきたとき、ポーランドによってドイツ本土と分断されている東部地区(東プロイセン)の住民をソ連兵の残虐行為から救うため、ドイツ海軍の全艦艇を動員して、脱出させました。これは海軍提督カール・デーニッツの命令によるものです。
それに対して日本ではどうだったでしょうか。半藤一利『ソ連が満洲に侵攻した夏』(文藝春秋)は、次のように述べています。
「敗戦を覚悟した国家が、軍が、全力をあげて最初にすべきことは、攻撃戦域にある、また被占領地域にある非戦闘民の安全を図ることにある。その実行である。ヨーロッパの戦史をみると、いかにそのことが必死に守られていたかがわかる。日本の場合は、国も軍も、そうしたきびしい敗戦の国際常識にすら無知であった。(中略)本土決戦となり、上陸してきた米軍を迎撃するさい、避難してくる非戦闘員の処置をどうするか。この切実な質問にたいし陸軍中央の参謀はいったという。『やむをえん、轢き殺して前進せよ』」
また、日本は、ドイツが降伏した1945年5月8日以降も戦争を継続しました。いったいなぜだったのでしょう? せめて6月に終戦になっていれば、多くの日本人の運命は、劇的に変わっていたはずです。
これは私が戦後ずっと抱き続けてきた疑問です。この間の事情は、最近になってようやく分かってきました。降伏の遅れは、指導者の誰もが責任を取りたくなかったために、決定が引き延ばされ続けただけのことです(吉見直人『終戦史』、NHK出版)。
6月終戦ができなかったために、どれだけの人々が無為に死んだことでしょう。勝利の可能性などまったくない戦場で、絶望的な戦いを強いられていた兵士たちは、5月以降、いったいどんな気持ちで戦っていたのでしょうか?
私は3月10日に、黒焦げの焼死体になることはなく、窒息死もしませんでした。そして、戦災孤児にもなりませんでした(仮に生き延びても、私1人であれば、他の戦災孤児と共に、上野の地下道を彷徨い続けなければならなかったはずです)。その後も徴兵されることはなく、「戦後70年」を迎えることができました。それは幸運な偶然が積み重なった結果です。いま振り返ってみると、誠に狭い何枚もの運命の扉の隙間を、辛くも通り抜け続けて来たからです。それは、奇跡としか言いようがありません。
◇40年頃、革新官僚が国の形を変えた
私たちが防空壕の中で殺されかけていたときから5年ほど前、「革新官僚」と呼ばれる人々が日本を変えようとしていました。
彼らが目指したのは、第二次世界大戦遂行のため、国家の総力を戦争に振り向ける「国家総動員体制」の確立です。彼らが作った経済制度は、戦後もほぼそのままの形で生き残り、戦後日本の基本を形成していくことになります。
この経済制度については、本書でこれから何度も言及することになりますが、ここでその概略を述べておきましょう。
革新官僚と呼ばれたのは、満州国に派遣されて国家経営に当たっていた官僚群で、その中心人物の1人が岸信介です。彼は1939年に満州から帰国して商工次官に就任。自分と同じ考えの人々を登用しました。41年には東条内閣の商工大臣となり、反対派を一掃。統制派と呼ばれた彼らが商工省を掌握したのです。岸と、その腹心として統制派を主導した椎名悦三郎の名を取って、このグループは、「岸・椎名ライン」とも呼ばれます。
彼らの理念は産業の国家統制です。企業は公共の利益に奉仕すべきであり、利益を追求してはならない。また、不労所得で生活する特権階級の存在を許してはならない、という考えです。
これは、社会主義の思想です。事実、岸が目指したのは、日本型社会主義経済の建設でした。これに対して、阪急電鉄の創始者で戦前の経営者の代表的人物だった小林一三商工大臣は、当時次官だった岸を「アカ」と呼んで非難しました。
岸たちの考え方は、当時の世界で広がりつつあった思想でした。共産党が一党独裁体制を敷くソビエト連邦では言うまでもなく、ドイツでも「国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)」が政権を獲得しました。資本主義の本家であるアメリカ合衆国においてさえ、フランクリン・ルーズベルト政権の下で、ニューディール派が社会主義的な政策を次々と打ち出していたのです。
◇金融・財政制度の大改革
岸たちが産業の国家統制を目指していたとき、金融面でも大きな改革が行われました。
戦前の日本では、株式や社債で企業が投資資金を調達する「直接金融」が中心であり、銀行借り入れで賄う「間接金融」の比重は低かったのです。革新官僚たちは、それを日本興業銀行を始めとする銀行が資金を供給する仕組みに変えていきました。一連の施策により、企業金融における銀行中心主義が確立され、株主の支配が排除されました。
1942年に制定された「日本銀行法」は、統制的金融改革の仕上げともいうべきものです。旧日本銀行法第二条「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」は、戦時経済体制の理念を明確に規定しています。
40年度には、税財政制度でも大きな改革が行われました。まず、源泉徴収制度の導入によって、勤労所得に対する所得税の徴収が強化されました。日本の源泉徴収制度は、ドイツに次いで、世界で2番目に導入されたものです。また、法人税が独立の税として確立され、これによって、それまで間接税中心だった日本の税体系は大きく変わり、製造業など経済の近代部門に課税することが可能になりました。新たな税制による税収は、地方自治体ではなく国に入ることとなり、国がそれを地方に配付する形が構築されたのです。
また、農地改革の準備も進められました。戦前の農村が極貧にあえいでいた大きな原因は、地主の存在でした。小作料は収穫物で支払われ、その割合は平均して収量の約5割にも及んでいました。このため、農村の生活水準は、江戸時代からあまり変わらないままだったのです。
中央官庁の官僚には、このような農村の現状を改革しなければならないと考える者が少なくなく、特に農政官僚には、そうした意識を強く持っている人々がいました。彼らは、42年に「食糧管理法」を制定し、この状況を大きく変えました。小作人は、地主にでなく国に米を供出し、地主にはその代金の一部を小作料として支払うこととなったのです。こうして、それまで物納制であった小作料が、金納制に転換しました。
小作料は政府により定められ、物価変動にかかわらず据え置かれたため、インフレが進行するにつれて、小作人の実質負担は急減しました。40年に収量の50・5%だった小作料は、45年には18・3%にまで低下し、小作制度は形骸化したのです。また、政府が小作人から買う場合には米価を高く、地主から買う場合には低く設定する「二重米価制」も設けられ、これによっても地主の地位は低下しました。こうして、江戸時代から変わらなかった日本の農村が、戦時体制の中で大きく変貌し始めたのです。
以上で述べた改革の目的は、戦争遂行です。岸らの企業改革は、企業を国家の手足として用い、生産活動を軍需目的に集中させるためのものです。間接金融体制への改革は、産業資金の供給面からその体制を支えるためのものです。そして、租税改革の目的も、軍事費の調達であることは言うまでもありません。
農村改革を行った農政官僚は、社会主義的救貧思想に影響されていたのでしょう。ただし、農村を貧困から救うことは、軍事的な観点からも必要なことでした。なぜなら、農村は兵士の供給源だったからです。農村が疲弊すれば、強い兵士は得られません。したがって、軍部(特に陸軍)は農村改革に強いシンパシーを持っていました。
◇戦後日本の企業は、戦時期に作られた
戦時体制によって、日本の企業も大きく変わりました。
戦前には、日本の電力事業は多数の民間企業によって運営されていました。しかし、1939年、政府の命令により、各地の電力会社を統合する国策会社、日本発送電が設立され、さらに9つの配電会社が再編されました。これが、戦後の9電力体制の基礎になっています。
自動車産業も同様です。戦前の日本の自動車生産は、フォード、GM、クライスラーという、アメリカのビッグスリーに支配されていました。このため、満州事変当時の日本軍トラックはフォード製だったのです。政府は、この状態を変えるため、36年に「自動車製造事業法」を制定し、自動車関税を引き上げ、自動車製造業を許可制としました。許可を得たのは、豊田自動織機製作所と日産自動車です。許可会社には営業税を免除し、資金調達に特別の優遇を与え、機械・部品の輸入税を免除しました。この結果、ビッグスリーは日本からの撤退を余儀なくされたのです。
電機産業も戦時期に大きく成長しました。39年に芝浦製作所と東京電気が合併して東京芝浦電気(現・東芝)が誕生し、20年に久原鉱業から独立していた日立製作所とともに、軍事経済を背景として規模を拡大しました。松下電器産業も軍需生産に従事して成長しました(このため、松下幸之助は、戦後、公職追放処分を受けています)。
鉄鋼業は明治期から続く産業ですが、34年に官営八幡製鐵所が母体となって製鉄会社が大合同し、日本製鐵株式会社という半官半民の国策会社が誕生しました。
これらはいずれも、戦前の企業とは性格が大きく異なる企業群です。戦前の日本の製造業の中心は、紡績会社でした。太平洋戦争開戦時の売上高第1位の企業は、鐘淵紡績(カネボウ)です。軽工業を中心とするこれら伝統的企業は、資金面で銀行に依存せず、政府の介入や統制には強く反発しました。
アメリカの歴史学者ジョン・ダワーは、日本の大企業について、「純粋に戦後生まれの企業は、ソニーとホンダしかない」と述べています。これは正しい見方です。戦後日本の大企業の多くは、戦時中に政府の手で作られたり、軍需で急成長した企業なのです。
企業経営、労働組合、都市の土地制度などについても、同様のことが言えます。つまり、戦時中に作られた仕組みが戦後に生き残り、重要な役割を果たしたのです。また、戦後の業界団体は、戦時中に作られた「統制会」がもとになっています。そして、統制会の上部機構である「重要産業協議会」が「経済団体連合会(経団連)」となりました。
なお、新聞についても、同様の事情があります。戦前の日本では、全国各地に多数の独立紙がありました。しかし、言論統制のため38年から内務省と情報局を中心として進められた「1県1紙主義」によって、これらの統合が行われました。その結果残った地方紙の多くは、今日に至るまで有力な地方紙として存続しています。
また、一般紙3紙(『朝日新聞』『毎日新聞』『読売新聞』)と、経済専門紙2紙(『日本経済新聞』と『産業経済新聞』―現在の『産経新聞』―)に対して全国配布が認められました。これら5紙が全国配布体制をとっていることは、いまでも変わりません。世界でも珍しい大部数の全国紙体制は、戦時体制として確立されたものなのです。
戦時に作られたこうした経済体制は、戦前期の日本経済のそれとは異質のものです。本書ではそれを「1940年体制」と呼ぶことにします。総力戦のための国家総動員体制として作られた40年体制は、終戦によって何の影響も受けることなく生き残り、戦後の日本経済の基盤となっていったのです。
◇ われわれはいまどこにいるのか
本書の目的は、戦後70年間に起こった事件を列挙することではありません。その目的のためには、多くの歴史年表があります。本書の目的は、「われわれがいまどこにいるのか」を明らかにすることです。
歴史年表にはさまざまな出来事が列挙されていますが、それらの中には、生じた時点で世の中の大きな関心を集めたものの、現在との関連が希薄な事件は、いくつもあります。それらは、私が描くストーリーにおいては、あまり重要なものとは言えません。
では、どんな出来事が現在の日本社会のあり方に大きな影響を与えたのでしょうか? その評価を行うためには、「視点」が必要です。
本書では、次の2つの視点によって、戦後日本経済を捉えることとします。
第一は、「犬の目」です。これは「地上からの視点」であり、私自身の目を通して見た戦後日本社会と経済の変遷史です。つまり、自分史的なクロノロジー(年代記)です。
第二は、「鳥の目」です。これは「空からの視点」であり、これを通じて社会と経済の俯瞰図を描いてみたいと思います。
「鳥の目」、すなわち歴史観の違いは、「われわれはいまどこにいるのか」という現在の歴史的位置づけについて、大きな解釈の違いをもたらします。
本書における鳥の目は「1940年体制史観」と言えるものです。この見方は、教科書的な見方、つまり一般に受け入れられている見方とは大きく異なる歴史解釈です。
一般には、「戦後の民主主義改革が経済の復興をもたらし、戦後に誕生した新しい企業が高度成長を実現した」としています。それに対して、40年体制史観では、「戦時期に作られた国家総動員体制が戦後経済の復興をもたらし、戦時期に成長した企業が高度成長を実現した」と考えます。40年体制は、その後の石油ショックへの対応においても、重要な役割を果たしました。
この2つの歴史観は、日本の歴史がどこで断絶しているかという判断において、大きく異なります。一般には、45年8月時点において日本の政治・経済・社会体制に大きな断絶があったとされています。それに対して40年体制史観では、そこには断絶はなく、本当の断絶は40年頃にあったと見ているのです。
40年体制史観という鳥の目で眺めれば、80年代のバブルとは、日本経済が40年体制を必要としなくなったにもかかわらず、その体制が生き残りを図ろうとしたことから生じた事件です。
また、40年体制史観からすれば、経済政策において安倍晋三内閣が行おうとしているのは、「戦後レジームからの脱却」ではありません。まったく逆に、「戦時・戦後体制への復帰」です。その基本的な方向は、市場の働きを否定し、経済活動に対する国の関与を強めようとするものです。これは、40年体制の考え方そのものなのです。この点については、「エピローグ」でもう一度触れたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
