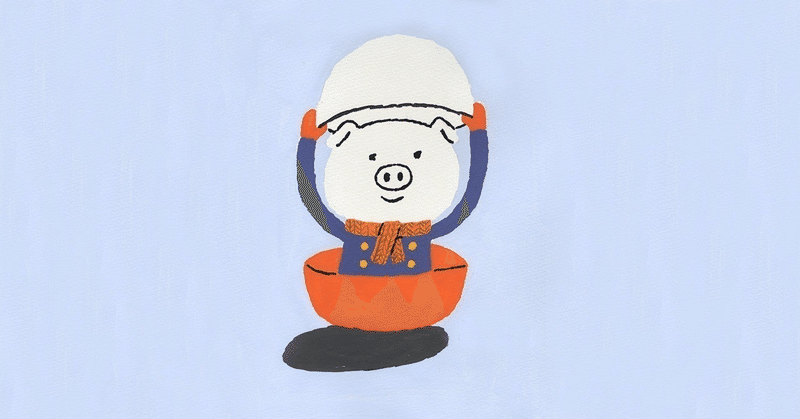
立ち現れたものをどう感じるのも自由
先日『星野源のおんがくこうろん』のジョン・ケージを取り上げた回の録画を見終わってテレビに戻ると、『日曜美術館』のイヴ・クライン展の特集をやっていて、なんてつながり方なんだ!と驚きました。
共通点があるように感じられたから。
そのふたりを見て思い出したことがあります。
かつて、現代アートなるものがちょっと苦手でした。
今でも大好き!てほどではないけど。
苦手だった理由は、どう受け止めたらいいのかわからないというのが大きかったかな。
向き合い方がわからないといいますか。
わかったような顔するのも自意識が許してくれない(何かっこつけようとしてるんだ、ほんとにわかってんのか、と胸のなかで自分が言う)。
だけど、少し自分のなかの垣根が低くなったと感じた出来事がありました。
だいぶ昔ですが、大学生の頃のこと。
私は、1920年代の文化やモダニズムを学ぶゼミに所属していました。
さまざまなモダニズムのイズム(キュビズムとかダダイズムとか)を担当割りして、基本の考えや代表作を発表するという授業があり、私の担当は「シュルレアリスム」になりました。
コントなんかを見て「シュールだねぇ」とか言う、その元になっているもの。
ふむぅ…と思いながら調べていくと、その成り立ちが目から鱗だったのです。
自分の作為を除き、言うなれば天からのメッセージを下ろすみたいなイタコのような感覚で実験的な試みとして始まったものでした。
たとえばコラージュなら、じーーーっといろいろな写真などを見つめているうちに、浮かび上がり引き合う画像たちがあるからそれを並べつなげる。
文学なら、ただ手が動くままに浮かび上がるままに言葉をつなげて紡いでいく。
だから、不条理な仕上がりになるわけだ。
作者の意図をいかにちゃんと排除するか、ということが初期の頃は大切だったのだそう。
シュルレアリスムとは訳すと「超現実主義」。
現実を超えたところからやってくるアイデアをそのまま形にするもの、ということだったわけ。
それを知ったら、「あぁ、わからなくていいんだ」と思いました。
だって、作者の意図がないのですから。
その後、シュルレアリスムの作品は本来の意味から離れた作り方をされるようになり、意図やメッセージ性を持つようになります。
ある意味元来のものも、「作者の意図を排除するんだ」という意図が強烈に反映されていたとも言えるか。
そこにあったのは、意図を超えたところに生まれるものの力を信じていたということなのではないか。
自分の意図だけでは見られない世界。
ジョン・ケージもイヴ・クラインもそう。
根本的な考え方に共通点があったのでは。
『おんがくこうろん』で林田さんが言った、「聞き手に対して強い信頼があった」(正確じゃないかもしれないけどこんな感じ)の言葉が印象的でした。
受け手それぞれで聴こえ方見え方が違ってよいという前提があり、受け手それぞれのなかで作品が完成するというか…
まぁ、これまた私が勝手に感じていることなんですけどね。
勝手に感じていいんだ、と知ると、向き合うことが怖くなくなる。
わからんなぁと思ってもいいし。
わかんないけどなんか楽しいなんか好き、でもいい。
なんか不快だと思うのも自由。
現代アートに訳知り顔の人を斜めに見たりすることもありましたけどもね、本気で感じようとしているならば、ごめんなさいね、なのでありました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
