
農業をひも解く12 ~分析のやり方~
「それって、遅れて出てきた結果だよね?」
以前、工学系の研究者の方に指摘されたことである。
どういうことか、説明しよう。
例えば、新しい肥料が開発されて、その効果を、「生育調査」という形で調べるとする。皆さんもよくやられていますよね。

で、肥料を与えてから、1週間ごとに草丈とか葉っぱの枚数とか、つまり、「生長」の度合いを調べるわけだが、この生長ってものは、この新肥料による直接的な結果ではなく、結果として現れた結果、つまり、遅れて現れた結果でしょ?というのが、先の指摘だ。
つまり、新しい肥料は、例えば何か植物の生理の今までと違った部分に作用し、そのために吸収が早かったりするんだろうから、そこを押さえないといけないんじゃない?と言われたわけ。
なるほど・・
と思ったんです、ハイ。m(_ _)m
それともう一つ。
今の例でいえば、グラフを描きますね、横軸に日付、縦軸にcm、みたいな。要は、2次元のグラフ。
とある、機械系の方がおっしゃった。
「要素って、一つだけなの?」
つまり、日付つまり時間だけじゃなくて、気温とか日射量とか、そういうのも考えないとおかしくない?ということだ。あまり要素を増やすと収拾がつかないが、その業界では、3次元のグラフを描くことが当たり前なんだそう。
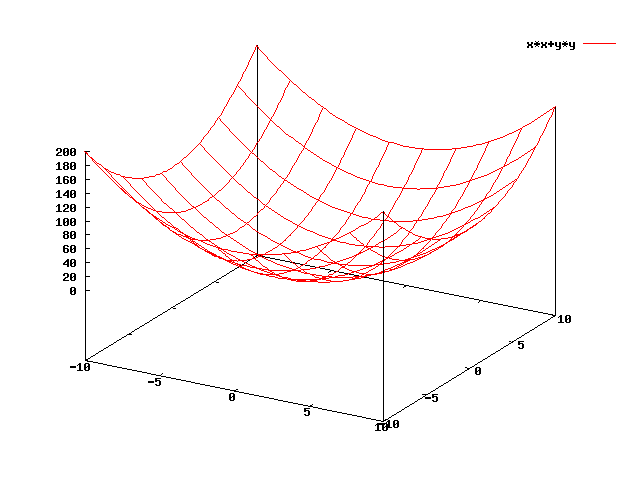
またしても、
なるほど・・・m(_ _)m
と思ったんです。
ちなみにこの方からは、
グラフの要素を絞り込むことが命
ということを教えていただいた。
農業には農業の特性がある。先の機械系の方は農業を、
「ファジーの塊ですね。」とおっしゃった。
また、農学系には、農学系の手法もプライドもある。室内での固定的な環境と、屋外での多要素な環境とでは、置かれた土台は違うだろう。
しかし・・と思う。
そんな異業種から学ぶことは、
絶対に!
ある。
産業において、未開の大地と言えるフィールド、農業。
今は投資マネーもだぶついているようだ。だが、常に自らをアップデートする姿勢がないと、投資家に話は聞いてもらえない。
僕はそう考えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
