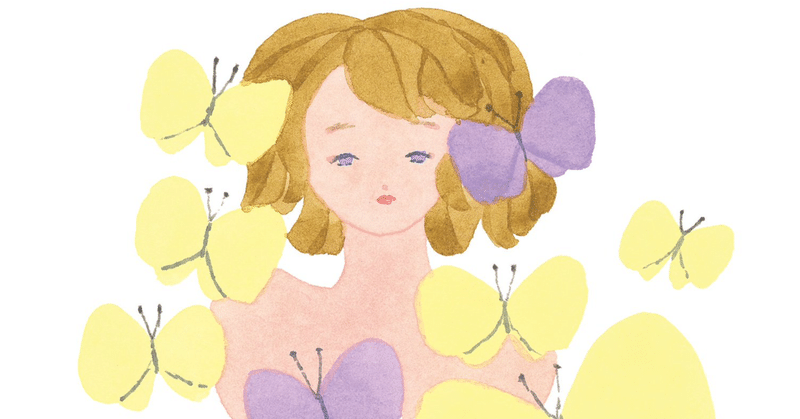
「近くのものばかり見ていると目が悪くなるよ」というのは、心もきっと同じだ
今日はあたたかい一日だった。風がつよく吹くので体感温度はさほど高くはないけれど、ベランダに出た瞬間の空気の肌触りが冬のそれとはまったく違って、少しだけ、と座り込んでしまう。
枝垂桜は五分咲き、ソメイヨシノのつぼみもふっくらふくらみ、こぶしの花は青の上にくっきりと白く咲いている。太陽は光の強さを増し、植木に水やりしたあと部屋に戻ると目の前が緑色でいっぱいになってくらっとしてしまう。
いままであまり春の太陽の強さを知らなかった。こんなにはっきりと日差しを意識するようになったのは植物と語り合い、向き合うようになってからだ。冬のように肌寒い日が続いていても、植物はきちんと春を知っている。そこへやってくる鳥もまた春を知っていて、花から花へと飛び移りながら時折ヒーヨヒヨと高く鳴いている。そこへ冷たい風が吹いてきて、わたしはあわてて上着を着る。室内の小鳥の白い羽根は、すこしずつ真新しいものに生え変わっている。
まさに春雷、というような雷があった。清々しく洗い流してくれる雨と雷に気持ちが高まって、その日はうまく眠れなかった。胸の上のあたりがどきどきして体がうずき、うまく眠りに入ってゆけないのだ。萌え出づる気配が体から吹き出してくる。季節の変化は自分の体をも変えているのを、体は知っているのに頭はよくわかっていない。だから眠れないことを頭で考えていると不安になる。
そんなふうに眠れない一方で、毎日眠くて仕方がない。家族に心配されるくらい時間を問わず毎日眠っている。春眠暁を覚えず、とは本当に日本の春を表現した言葉だなあとほれぼれしながら、またうとうとする。
仕事は相変わらずばたばたしている。なにせ頭がぼんやりして眠くて仕方がないので、集中して仕事できる時間が短くなっているのだ。光陰矢の如し、あっという間に過ぎていく暮らしの流れに抗えず流されて、近くのものしか見えない目になってくる。手を伸ばせば済むもので簡単に心の渇きを埋めようとする。潤っていないと気づいたころにはすっかりカラカラで、最後の水が涙となって出てくる。それは血のようにぬらりと生暖かく、放っておくと心と体の自由が失われていく。
あわててコートを羽織り夜の扉を開く。「近くのものばかり見ていると目が悪くなるよ」というのは、心もきっと同じだ。歩きながら空にかかる星を見上げる。目の奥にじんわりと星の光が染みていく。そうして星座にピントが合うころには、心は詩に戻っている。
追記(2023.7.16)
本稿はコロナ禍となって家にこもりながら感じていたことを書いたものです。マスクを外しているひとがずいぶん増え、自由に外出を謳歌することができるようになったいま、当時を振り返って考えることが多く、2023年の創作大賞に応募することで2021年からの手紙のようにいま誰かの元へ届けられたらいいなあと思っています。
いつもお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、これからの作品作りに使いたいと思います。
