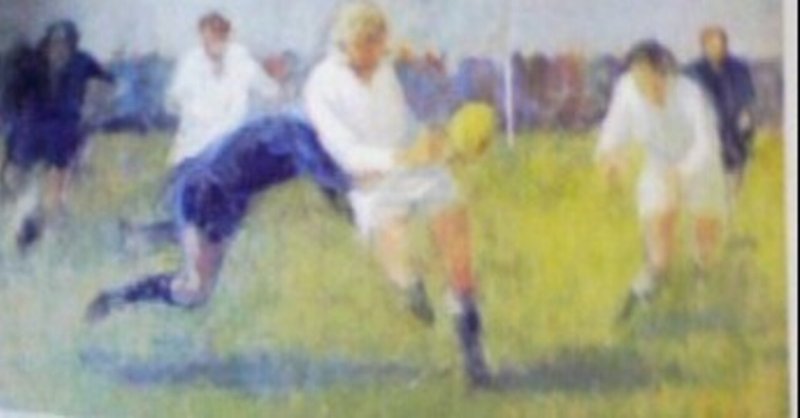
<ラグビー>ラグビーの愉しみ(その7)
アタックのスペースを見る
アタックのときに一番重要なものはなんだろうか。私は、相手の陣形のスペースを見つけることだと思う。そして、そのスペースをどうやって攻略するかの戦術的判断は、ラグビーをプレーしまた見る楽しみでもある。さらに言えば、アタック担当コーチの最大の喜びでもあろう。
もちろん、試合中にそのようなスペースは勝手に出てくるものではない。多くのアタック担当コーチは、そうしたスペースをどうやったら作れるかに、いつも頭を悩ましている。しかし、いくらアタック担当コーチが苦労してスペースを作り出す戦術を考案したとしても、アタックする選手たちにそのスペースが見えていなければ、宝の持ち腐れとなる。
そして、このスペースが見えるか見えないかは、練習だけでは絶対に身に付かない。ひたすら厳しい実戦を経験することで、ある時急に見えてくるものなのだ。だからこそ、選手の経験値が重要になるが、その経験値もただ試合を重ねるだけで得られるわけではない。やはり、試合毎にどこにスペースがあるかを必死に繰り返すことによってのみ、見えてくるものなのだ。
それは、別の言葉で言えば努力であり、哲学用語を使用すれば「先験的経験」となる。
タックルポイントを見る
アタックで、スペースを見るのが重要なように、ディフェンスでも自チームのディフェンスの穴となるスペースを見ることが重要になる。
そして、常にアタックするチームはスペースを的確に突いてくるわけではないので、ディフェンスのタックルというのは、特定のエリアだけで発生することが多くなる。たいていのチームは決まったパターンのアタックをしてくるから、自ずとタックルが発生することが予想できるポイントが見えてくる。それが、タックルポイントであり、ディフェンスの良い選手は、単純にタックルが強いだけでなく、ディフェンスのときに常にそのタックルポイントが見えていて(予測できていて)、そこへ最短距離で駆けつけることができる選手なのだ。
そして、タックルポイントが予測できることにより、タックルする方向、姿勢、強さなどを相手に当たる前に自分で調整することができるし、何よりも仲間に対して、誰がどこを守るかを的確に指示できることになる。こうした選手は、まさにディフェンスのリーダーとして欠かせない存在になる。
また、こうした選手は、自チームのディフェンスに空いたスペースが見えているから、アタック側がそこを攻めてくる前に、自チームに指示してスペースを埋める(防ぐ)こともできる。
タックルする
タックルは、だいたい走っている相手に向かって、こちらも走って向かっていき、身体と身体を思い切りぶつけるのだから、当然勇気のいるプレーだ。ラグビーの華と言われるくらいだから、まさに力と力の激突は、相撲の立ち合いのように迫力がある。
しかし、ラグビーのタックルの全てが相撲の立ち合いのように激突しているかと言えば、実は違う。タックルの基本は、走っている(立っている)相手の足をすくって転ばせることであるように、タックルは相撲の立ち合いではない。もちろん走ってくる相手に向かっていく場面もあるが、密集近くであれば、ボールキャリアーはあまり勢いを付けられずに立っていることもあるから、そこで足元をすくえば比較的簡単にタックルができる。また、誰かがボールキャリアーを止めた後に参加する場合も立派なタックルだが、そこではぶつかり合いというよりも、レスリングのような倒す技術が要求される。
また、たとえ走ってきている相手であっても、必ずしも正面から衝突しなければいけないわけではない。相手の正面から少し角度をずらして、足元をすくうように肩と腕を入れることによって、案外力をかけずにタックルができたりする。また、これは、相手も自分も比較的ダメージが少ないので、安全な怪我防止のタックルだと思う。
それから、走っている相手を追いかけるタックルがある。余裕があれば、相手の肩に両腕をかけて倒すこともできるが、そうでない場合は、相手の足首を手で払う技がとても有効だったりする。これはアンクルタップというものだが、一流選手はこの技が皆得意で、抜けたと思った選手が足元をもたつかせて転ぶのは、全てこの技の結果だ。
なお、こうした技を屈指したタックルがある一方、南太平洋系の選手は、当たり合いが楽しいらしく、正面衝突のようなタックルを好む。そのため、怪我や反則も多くなってしまうのだが、これはやられる方はたまったものではない。そのため、最近はこうした南太平洋系の荒々しいタックルを危険としてぺナルティーを取るようになってきた。
ラグビーは、だんだんと軟な方向に向かっているのかも知れない。
スクラムを組む
スクラムを組む醍醐味は、なんといっても一体感だ。8人が息を合わせて組むというが、実は相手の8人とも息が合っていないと、きちんとスクラムを組めない。そういう点では、スクラムというのは8人ではなく、16人で組んでいるものだと言える。
スクラムを組むのは、FWの特権だとも思う。そして、スクラムの愉しさは実際に組んだものでないとわからない。もっとも、一般的にスクラムは、苦しいもの、辛いもの、キツイものとされているので、組まないでラッキーと思うBKの選手がいるかも知れないが、ラグビーをやっている以上、スクラムを組む経験は、BKであっても一度はしてみて欲しい。また、スクラムの姿勢は、モール、ラック、タックルのいずれにも共通するので、ラグビー全体の良い練習になるだろう。
その一体感から、「ラグビーをしている!」という気持ちに思いっきりなれるのだから、スクラムを組んだことないラグビー選手がもしいたら、組む練習を大いにお勧めしたい。
モールを組む
モールは、スクラム同様にFWの仕事だ。たまにBKも参加していることがあるが、傍目で見ていても、BKの選手のモールに参加している姿勢は頼りなく、力になっていない印象が強い。
モールは、スクラム同様に8人を基本に作るが、またこれも、スクラム同様に相手がいないとモールが成立しない。そのため、アタックする側は、モールを成立させるために、相手選手のジャージをひっぱって無理矢理モールに参加させている場合がある。
モールプレーは、スクラム同様に参加している選手の協力と共同作業が重要だ。ただ押すだけでなく、方向を決めるもの、モールが崩れるのを防ぐもの、相手選手を抜けさせないようにするもの、ボールを保持するものなど、意外と多くの役割がある。そして、その個々の役割が十分できていない場合は、ディフェンスにモールを割られてしまって、アタックが成功しないことになる。
モールのディフェンスは横から入れない(オフサイド)が、最初からモールの中心に残っている場合は、そこでディフェンスをすることができる。たまに、強力なLOがそこから長身と長い腕を生かして、ボールキャリアーを捕まえてモールをつぶしてしまうプレーを見ることがある。こういうプレーが見られたら、それはけっこう幸運なことだと思っていい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
