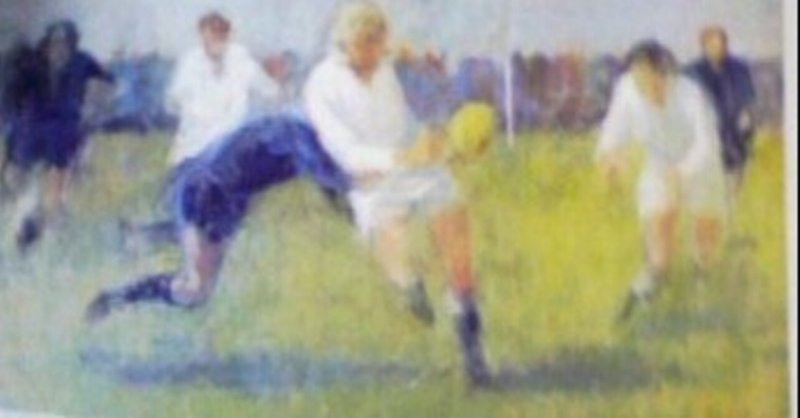
<ラグビー>ラグビーの愉しみ(その3)
第2章 ラグビーの面白さ
どうやってトライを取るか
ラグビーの楽しさを最も象徴するのは、なんといってもトライだろう。トライは、トライを記録した選手、そのチーム、またトライを取られた選手、そのチーム、さらに見ている観客にエクスタシーを与えてくれる。
トライを取るのは簡単ではない。15人のディフェンダーを交わしながら、そして、仲間の14人が我が身を犠牲にして、タックルを受けながらボールをつなぎ、最後の1人がタッチダウンする栄誉を得ることになる。
もちろん、野球のピッチャーやホームランを打つバッター、またはサッカーのストライカーのように、仲間の協力は関係なしに、一人でトライを取る場合もたまにはある。しかし、それは極めて稀だし、そんな一人だけが勝手にプレーしてトライを取っているゲームは、ラグビーとして全く面白くもなんともない力の差がありすぎる凡戦=ミスマッチでしかない。
やはり、ラグビーのトライが面白いのは、15人全員が協力してボールをつなぎ、一方ディフェンスする側も15人が必死に諦めることなくタックルし続けた結果、30人が疲労困憊するようなプレーと時間を経たのちにタッチダウンされるものが一番面白い。
だから、歴史的な名トライは、多くの選手がスキルを屈指してつなぐとともに、相手チームはもちろん強豪で、猛獣のようなタックラーが次々と押し寄せるものとなっている。
こういう中で、どうやってトライを取るかは、ラグビーのアタックの醍醐味だろう。例えば、戦術的にスクラムを1cmでも押すとか、相手のいないスペースにタッチキックを蹴って陣地を取るとか、アタックの一部となるプレーは多々あるが、最後のトライを取るまでのアイディアに勝るものはない。
そういうわけだから、モールやスクラムを押してトライを取るアイディアは、面白くないものになってしまう。また、単純に足が速い、または身体が大きいWTBが、1対1で相手を抜き去るトライも、アイディアとしては芸がない。
やはり、3次攻撃(ポイント)以上まで想定して作られたアタックによるトライは、見ていても非常に面白いと思う。
例えば、相手陣22mライン中央やや右よりのスクラムからのアタックとする。スクラムの際に、右PRは前に出て、スクラムを少し左に傾ける。こうすることで、右側のディフェンスが数cm後ろに下がる。スクラムからの展開は、NO.8がボールをピックアップし、右側を攻める。すぐにSHにパスして、SHは内からサポートに来た7番FLにボールを返してポイントを作らせる。そのラックに、NO.8や6番を中心にFWが殺到してマイボールをキープする。SHは右側に位置しているSOにパスするようにして、遠い左側の11番WTBにロングパスを通す。11番WTBは、左タッチライン際をまっすぐに走り、ゴール前5mでラックになる。そこから、SH→SOに素早く繋がれたボールを、SOは右インゴールに入る手前の、14番WTBがキャッチしやすいところへキックパスをする。14番WTBは、ゴールラインすれすれでどうにかキャッチするが、すぐにタックルを受けたので、内側にサポートに上がっていたFBにつないで、FBがトライする。
こんなトライを次々に見られたらとても面白いし、楽しいと思う。そして、実際にこうしたトライを次々に見せてくれるのが、NZラグビーであり、その頂点にあるのがオールブラックスなのだ。
どうやってトライを防ぐか
今度は、こうやってアタック側がいろいろとアイディアを練って攻めてくるのに対して、どうやってトライを防ぐかが問題になる。これは、トライを取るアタックが一番面白いとすれば、その次にラグビーの面白さになるものではないだろうか。
一般にディフェンスの種類は2つに分かれる。1対1で相手をマークするのと、エリアを決めて担当するものだ。特に後者の場合は、ドリフトといって、アタックする側をタッチラインに追い詰めていくようにする。さらに、最近は早く前に出て、アタックする側にパスやキックする余裕を与えないディフェンスが主流となっている(ラッシュアップディフェンスまたは「詰め」)。これは、エリアを決めて行うものの進化系だろう。
しかし、いくら組織で良いディフェンスをしても、一人一人が良いタックルをできなければ、その組織ディフェンスも機能しない。
ディフェンスは組織でやるものだとよく言われるが、結局は個々のタックルの強さに影響されるので、根本は1対1のタックルにあるのではないかと思う。
その1対1のタックルでは、アタックとディフェンスとの読み合いや騙し合いがある。これはけっこうやっていて面白いと思う。また、お互い裏と表を交互に使い分けてアタック&ディフェンスをするのだから、ディフェンスというのは、見ている側は「タックルしろ!」、「止めろ!」と勝手に叫んでいるが、当事者同士は、案外冷静にプレーしているものなのだ。
分析
昔は相手チームのプレーを分析するなんてことはしなかった。相手チームのことよりも、自分たちがどういうプレーをしたいかを常に考えていた。もしも、相手チームが予想と違うプレーをしてきたら、後半に対応すれば良いだけだった。
それが、日本では2000年頃からだったと思う。強豪チームはみな専門の分析担当者を置いて、次に対戦するチームのプレーを分析させ、その分析結果に合わせたプレーを予め練習して試合に準備するようになった。これが当たり前になってからは、強豪チームの練習は非公開にされるようになり、重要な試合の前にある試合では、敢えて自分たちのプレーを全部出さないようにすらなっていた。
単純に世知辛くなったなあという感じだが、プロ化することにより、アマチュア時代と比べて勝利の意味合いが大きくなったことから、仕方ないことだろう。そして、分析することによって、ラグビーのプレーはより繊細に、より細かく行われるようになったと思う。また、それによってラグビーの勝敗を決める要素として、選手よりもコーチの比率が高くなったように思う。それまでは、単純に良い選手を集めたチームが勝っていたのが、分析が進んだ以降は、良いコーチに指導されたチームが勝つようになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
