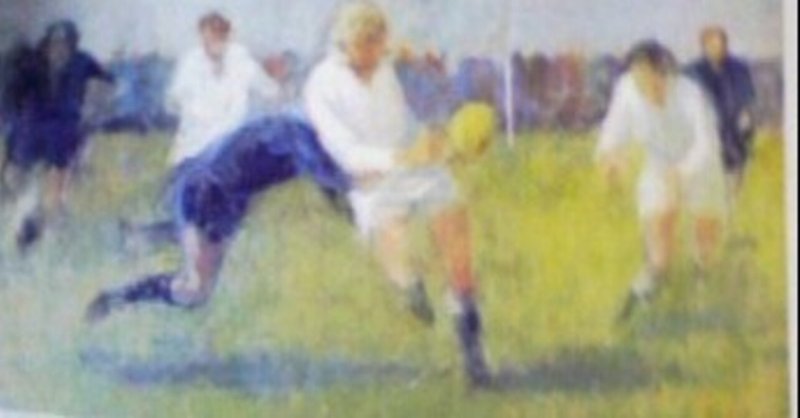
<ラグビー>ラグビーの愉しみ(その9)
第5章 私にとってのラグビーの愉しみ方
これまでの4章では、私が考える、感じるラグビーの面白さ、楽しさを、各パーツに分けて紹介してきた。もうこれだけで、ラグビーの楽しさについては、十分わかってもらえたと思っているので、この最後の章は、私が実際にどうやってラグビーを楽しんでいるか、あるいは自分のものとして愉しんでいるかをご紹介したい。
勝手に選手選考
ラグビーを見る楽しみは、試合前から始まっている。それは、監督やコーチになった気分で、勝手に選手選考することだ。
FWは誰それ、BKは誰それ、リザーブにこの選手を入れて、後半60分頃に入れ替える。または、同じレベルの力量があるので、前後半を分担させる。
あるいは、相手チームがキック中心で来るので、バックスリーはハイボールに強い選手を入れる。または、FWが強く、ラインアウトからのモールを武器としているので、LOには長身でフィジカルに強い選手を入れる、などなど。
こうして、監督やコーチになった気分で、勝手に選手選考するのは、なかなか楽しいものだ。もちろん、選手の立場に立ったら冗談じゃないが、これは実際にチームに関わっていない外野の特権ではないだろうか。
試合前の予想
競馬の予想が好きだ。馬の血統、個性(先行型、追い込み型、その極端なものや万能型)、レースへの適正(長距離系、短距離系、またはその中間型や万能型。多くは血統で決まっている)、調子、騎手の力量、調教師の思惑、ゲーム展開、馬券の掛け率(配当金)などを総合的に見て、どの馬が勝つか予想するのは結構楽しい。たとえ馬券を買っていなくても、予想してからTV中継を見ると、何も予想していないで見るよりも数倍楽しく、またレースに感情移入して見てしまう。これが、馬券を買っていたら、当然にもっと興奮するだろう。
ラグビーも同じといっては失礼だが、予想をしないで見るよりも、勝ち負けだけでなく、試合がどう展開するか、どちらがどうやって攻め、またどちらがどうやって守るか。ある選手は好調だから、多くボールキャリーするだろうが、ある選手は最近調子悪いから、アタックよりもディフェンスに集中するだろうとか、いろいろと勝手な予想をするのは楽しい。
もちろん、予想するための情報をマスコミ報道から沢山仕入れて、それらを吟味して予想すると、予想通りになる確率が少しでも高まったような気になって、さらに楽しくなる。
だから、ラグビーをもっと楽しみたい人は、是非とも競馬のように予想をすることをお勧めする。
試合後の再現
予想した上で、実際に試合を見る。予想している分だけ、試合のどこを見るかが分かっているから、漠然と見ても気づかなかったところが見えてきたりする。さらに、予想通りの内容になる、または予想と違った内容になった場合でも、試合のどこが勝者に作用して、どこが敗者に作用したかが自然と見えてくる。
こうして試合を見た後は、まるで、将棋の棋士が対局を振り返るように、局面ごとの試合の流れが変わったところや、勝負の決め手となったところがよくわかったりする。棋士が、ここでこうやっておけば勝ったのに、と思うような一手が、ラグビーの試合中にもある。それは、選手交代の時期だったり、トライを狙うか、PGを狙うかの選択だったりする。
よく、試合が済んで結果がわかってしまうと、もう録画で試合を見る気がしないという人がいるが、ラグビーの愉しみは勝った、負けただけではない。勝った、負けただけであれば、競馬の馬券と同じになってしまう。ラグビーは勝負事であっても、賭け事ではない。結果が全てではないのだ。贔屓のチームが負けても、その中で良いプレーがあれば、それはずっと記憶に残る。勝ったのであれば、なおさらその喜びを何回でも繰り返して味わいたい気持ちになるだろう。
そして、ラグビーの試合は芸術作品でもある。ひとつのパス、ひとつのキック、ひとつのタックルは皆、優れたダンサーが踊る舞台のように、観衆に喜びを与えてくれる優れた芸術なのだ。そして、そうした個々の優れたプレーの集積によって成立したゲームは、何回の鑑賞にも耐え、また感動することができる優れた芸術作品だと思う。
興奮とエクスタシーとカタルシス
ラグビーには、興奮とそこからもたらされるエクスタシー(陶酔)と、達成感から得られるカタルシス(浄化)がある。
例えば、トライに至る連続プレーはその典型だ。密集からボールが出て来て、SHからSOにボールが渡る。SOとCTBで仕掛けをして、WTBやFBが独走する。そこにディフェンダーが戻ってきて、タックルをしかけようとするが、ボールキャリアーはスキルとスピードを使って振り切る。フリーになったアタッカーは、ボールを大事にインゴールにタッチダウンする。この一連の過程には、ボールを奪い合い、ボールキャリアーにタックルする興奮と、トライにつなげるためにスキルを屈指するエクスタシーと、最後にトライを挙げたことによるカタルシスがある。
これをタックルに限定して表現すれば、タックルするまでのディフェンダーの気持ちと身体の高ぶりによる興奮、タックル成立によるエクスタシー、そしてタックル後のボールを奪うカタルシスがある。
ゲーム全体には、こうした一つ一つのプレーによる勝利へ至る小さなドラマの積み重ねがあり、その小さなドラマを興奮しながらつないで行くと、最後の勝利と言うエクスタシーと、ノーサイドというカタルシスに至る。もちろん、負けた側であっても、精一杯ゲームをしたというエクスタシーと、試合を終えたカタルシスを感じることができるだろう。
これはプレーしている側だけでなく、見ている側も同様に味わえる、優れた演劇のようなストーリーなのだ。しかも、予めシナリオがなく、局面毎に、ドラマの展開が変わっていきながら、大きな流れを作り出して、ノーサイド(大団円)を迎えるのだ。
これ以上面白いドラマは、果たしてこの世にあるのだろうか。
最高のチームとしてのオールブラックス
こうしたドラマの演出家、劇作家、俳優として、世界最高の存在は、NZオールブラックスだ。エンターテイメントなラグビーという点では、オールブラックスの前にオールブラックスなし、オールブラックスの後にオールブラックスなしだ。世界に唯一存在する、ラグビーのあるべき姿を、また理想的な姿を具現した、極上のエンターテイメントを見せてくれるのが、オールブラックスというラグビーチームなのだ。
まず試合前のハカがある。これだけだって、十分にお金を取れるレベルにある素晴らしい演技だが、これは試合を面白くする前座でしかすぎない。
試合が開始されれば、スポーツ競技と言う枠を超越した、各選手のエンターテイメントとしてのスーパースキルとその連携が、スーパーアスリートたちによって、連続して途切れることなくプレーされる。その連続したプレーのほとんどは、常人には想像もつかないような奇抜な発想を含めたフレアー溢れる優れたプレーに満ち溢れている。
そうしたプレーの連続による、ラグビーゲームとしての優れた創造性、魅惑的な即興性、誰もが予想できない意外性が、見るものを感動させる。そして、まず負けることがないと言う、世界最強チームという勝負強さ。この強さは、見ているものに対して、最高の陶酔と満足をもたらす中心的な要素にもなっている。
オールブラックスのラグビーとオールブラックスの存在は、私がラグビーを愉しいと思うそのものであり、オールブラックスのラグビーと出会えたことは、生涯最高の僥倖としか思えないものとなっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
