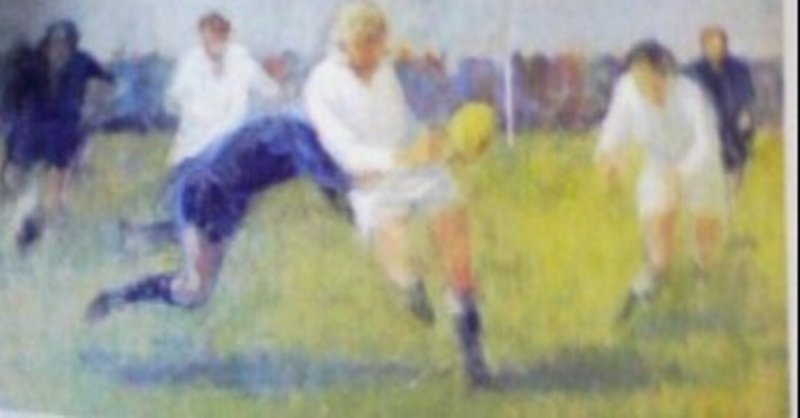
<ラグビー>ラグビーの愉しみ(その4)
選手選考
その進化したコーチという前提から、試合用メンバー23人の選手選考も大きく違ってきた。昔は、ラグビーの上手い15人を選んで試合をさせれば良かった。しかし、今は、コーチの考えるラグビーを再現できる23人を選ぶようになった。だから、あるコーチが選ぶ23人と別のコーチが選ぶ23人は異なるものとなる他、ラグビーの上手さや身体の大きさだけで23人を選ぶことはなくなった。
だから、試合前に発表される23人の選手を見ると、そのチームのコーチがどういうラグビーをやろうとしているのかが、ある程度予想できるようになった。さらに、23人の中でもそのコーチが考えるラグビーの中心的役割をする選手が怪我で交代などした場合、普通の一番上手い選手がいなくなる以上に、チームへの影響が大きくなるようになった。
また、自分の好きなチームの23人を、自分がやらせたいラグビーを想定して選ぶと言う楽しみもできてきたし、また予想する楽しみもある。
試合の流れ(駆け引き)
ラグビーの進化によって、ラグビーの勝敗は単純な精神論や根性論で決められなくなった。試合前の分析、それを元にしたゲームプランの練習、試合での実践、前半を参考にした後半のプレー修正などが大きな要素となった。そして、試合が始まった後、相手のプレー振りを見ながら自分たちのプレーを柔軟に変えたり、相手の弱点を見つけ出してからどこを攻めるかを決めるようなプレーが多くなった。例えば、オールブラックスが前半は大人しくしていても、後半残り20分に連続してトライを奪取するプレーはその典型だ。
それでも、試合の流れというコーチにも選手にもどうしようないものがある。後半逆転できるからと考えて、前半力を抑えていても、逆に相手チームが勢いづいて、流れを変えられないことがある。また、劣勢だった流れが、一人の勇敢なタックルや、一人の鬼神のようなアタックで、自分たちのものに変わることもある。ラグビーは、チームスポーツであるとともに、個人のスポーツでもあり、科学的なプレーをしていても、どこかで言葉で表せない情熱としか言いようがないプレーで、勝敗が決まることがあるのは、とても愉快なことだと思う。
第3章 ラグビーを見る喜び
監督及びコーチ
ラグビーを見るポイントは、なんといっても選手一人一人のプレーだが、やはりチームスポーツである以上、最高の選手15人を揃えても、チームとして機能していなければ、弱いチームになってしまう。野球が一人のピッチャーで勝ったり、サッカーが一人のエースストライカーで勝ったりするようなことは、ラグビーではない。
まず、スクラムなどのセットプレーは一人ではできないし、トライに至るプレーも他の14人が自己犠牲の精神でプレーしない限りは、一人がトライするまでには至らない。
そうした、チームの全てをアレンジするのが監督であり、その監督の指示に従って、選手個々のスキルなどを教えこむのがコーチの存在だ。そして、監督には、選手にスキルや戦術を教え込むコーチ型のタイプと、チーム全体の方向性や役割分担を決めるマネージメントタイプの2通りに分かれる。例えば、昔の大学ラグビーの早稲田の大西鉄之祐監督や、明治の北島忠治監督は、マネージメントタイプの監督と言えるだろう。
最近ではオールブラックスのスティーヴ・ハンセンやグラハム・ヘンリーはマネージメントタイプである。エディ・ジョーンズはマネージメントタイプと見られるが、やっていることはコーチタイプになると思う。
神戸製鋼で最近活躍している、元オールブラックスのウェイン・スミスは、神戸ではマネージメントタイプで成功しているが、オールブラックスでは、細かい分析や戦術を担当していたコーチのお手本のような人だった。
日本代表では、ジェイミー・ジョセフはマネージメントタイプ、トニー・ブラウンはコーチタイプだろう。だから、ブラウンが監督になるのはあまり合っていないような気がするし、彼は優秀なマネージメントタイプの監督の下で、戦術やスキルを常時考え実行するコーチの方が合っていると思う。
マネージメント
ここでマネージメントというのは、先に書いた監督やコーチのことではなく、現場以外のところでチームを運営するスタッフのことだ。通常表舞台に出てくることはなく、試合の勝敗には関係ないように思えるが、実は優秀なチームほどマネージメントが優秀である。もっといえば、マネージメントがしっかりしていないチームは、マネージメントの仕事がコーチの負担になってしまい、チームの戦力が低下してしまう。
マネージメントの仕事は、試合日程、グランド管理、移動手段の手配、宿舎の手配、道具の準備など、裏方の事務的なものが多いが、会社の総務同様に、実はチーム運営ではなくてはならない縁の下の力持ちなのである。
強いチームはマネージメントスタッフがしっかりしている。マネージメントがきちんとしていないチームは、それだけで試合前からゲームに負けているようなものである。
レフェリー
当然のことだが、レフェリーがいないと試合は成立しない。だから、選手やチームはレフェリーを尊重しなければならない。負けるとレフェリーが悪いとなる傾向があるが、本来は避けるべきことではある。しかし、2007年RWC準々決勝のウェイン・バーンズのように、明らかなミスジャッジを公然とする未熟なレフェリーが大事な試合を担当することもあるわけで、重要な試合には経験あるレフェリーを起用すべきだという、グラハム・ヘンリーの提言は極めて正論だ。
また、現在のフランス人レフェリーのように、オールブラックスのプレースタイルに合わない笛を吹くレフェリーがいることも事実だ。これはレフェリーとの相性とでもいうべきものであるため、優秀なチームは例えレベルが低いレフェリーであったとしても、そのレフェリーに合わせて低いレベルのプレーを選択するなどが、実は賢い対応となる。
各ポジション
続いて、各ポジションについて書いてみたい。
プロップ(PR)
ひと口にプロップといっても左と右では違う。左PRは頭の左側が自由なのに対して、右プロップは頭の左をHO、右を左PRに挟まれていて、どちらが厳しいかと言えば、絶対に右PRの方が厳しい。しかし、スクラムを組むときは、右PRは単純に相手2人の間に頭を突っ込んで、押されないように頑張ればいいが、左PRは相手PRに首をどのように入れるかで、スクラムの優劣が決まってしまうため、結構テクニックがいる。また、首を右に曲げて内側に押し込もうとすると、不正アングルの反則を取られてしまうし、外側に首を出せば、必然的にスクラムを組めなくなるので、これも反則を取られる。一番良いのは、相手右PRの首の根元に頭を付けて力を出させなくすれば良いのだが、相手もそう簡単には組ませてくれない。
昔、明治の北島監督は、左PRに対して、「空を見ろ」と指導したそうだが、確かにスクラムを組んで、左に首をひねると、自然と相手PRの首の根元に頭がねじ込まれ、さらにアングルの反則を取られないくらいに内側に押し込めるので、これはスクラムの金言だと思う。
今は、昔と違ってPRでも、ブレイクダウンからのパスやボールキャリーの役割が多くなって、必然的に運動量が増えているが、実はラグビーをやっていて、一番ラグビーをしたという実感を持てるのがPRではないかと思っている。
それを証明するように、ラグビーをしていなければ単なるデブと思われるPRだが、一番美人と結婚する率が高く、事実美人の奥さん率は高い。つまり、縁の下の力持ち的プレーを黙々とする性格の良さと、スクラムを支える頑丈さがあるので、理想的な夫像になるのではないか。
フッカー(HO)
PRに比べるとHOは、もっと華やかさがある。なにしろ、スクラムの際にボールをフッキングするし、ラインアウトではスローイングをする。BKに比べて目立たないプレーが多いFWにあって、実はHOはけっこう目立つプレーができるポジションなのだ。
そういう理由だろうか、最近のHOはNO.8から移動した選手が多くいて、元NO.8だけあって、機動力もあり、パスやキックまでできる選手がいる。日本代表の堀江翔太、オールブラックスのダン・コールズがその代表である。また、NO.8同様に意外とプレーの自由さがあるので、FWでは楽しいポジションかも知れない。
ただし、スクラムの先頭中央で組むのは、かなりきついし危険も伴う。スクラムがつぶれて一番怪我をしやすいのは、真ん中にいるHOであり、私もNZにいるときにスクラムを組むのを失敗して首を痛めたことがあったくらいだ。また、スクラムを組むテクニックは両PRに負うところが大だが、実はスクラムを組むタイミングをリードするのはHOで、HOが下手だとスクラムも負けてしまうことがあるので、ラインアウトのスローイングとともにHOの役割は重要だと思う。
ロック(LO)
LOは、伝統的にチームで一番大きく(体重ではPRに負けるが、身長ではLOだ)選手が担う。その理由は、ラインアウトやキックオフボールのキャッチがあるからだが、一方では、チームのケンカ番長的な役割があって、乱闘になった時はLOが先頭に出てくる習慣がある。人は、背の高さ=ケンカの強さと思ってしまうらしい。
しかし、LOには、PR以上に地味な選手が多い。日本代表の大野均やルーク・トンプソンがそうだが、寡黙でチームプレーにひたすら徹し、タックルはもちろんいくらでもするし、ボールキャリーもするが、トライをする、あるいはトライにつながるパスをすることはあまりない。密集には常に頭から突っ込み、タックルはチームの誰よりも勇敢にする。モールでは、先頭に立つかあるいは前進する原動力になる。そういう点では、LOをFWのエンジンルームに例えるのは非常にあっていると思う。
ちなみに、私は身長が低いのでHOでのプレーが多かったが、身長があればLOをやってみたかった。たまにLOをプレーすることもあったが、実はHOやPRよりもやりがいがあった感覚が残っている。
フランカー(FL)
実は、私がプレーした中でわりあい好きなポジションは、このFLだったりする。スクラムの横に付いているので、結構マイボールでも相手ボールでも、ボールの位置が見えるし、その後の展開も良く見える。だから、ラックやモールの中に巻き込まれていない場合は、次のポジションに素早く行けるし、場合によってはボールをもらって走ることも多くなる。
さらに、ディフェンスの際は、特にスクラムからボールが出る時にSHにタックルしやすい位置にいるので、結構いい感じのディフェンスをやれたりする。また、ラインアウトでも、PRよりはジャンプしてキャップすることもあるし、最後尾についていると、スクラム同様に次の展開が見えるので、プレーに関われる場面が多くなるのが嬉しい。
ただし、その分だけ運動量が非常に多くなるので、フィットネスは相当に鍛えていないと80分は絶対に持たないポジションだと思う。
そういうわけで、私がこのFLのプレーを見る場合は、最近流行りのジャッカルよりも、サポートプレーに注目してしまう。その点でオールブラックスのジョシュ・クロンフェルドは、とても素晴らしい選手だった。
NO.8(ナンバーエイト)
FLも好きだが、どこでも好きなポジションをプレーしていいと言われたら、間違いなくNO.8を選ぶ。特にインドのチェンナイにいたときは、スクラムもちゃんと組めないインド人とプレーしていたので、このポジションから指示をしてプレーしようとした。しかし、スキルのある奴がいないからということでHOをやらせられたため、上手く指導できなかった後悔がある。
それだけ、NO.8は特にFW全体を見ることができるので、FWリーダーには相応しいポジションだと思う。また、プレー自体も、オールブラックスが昔ウィングフォワードとして8番を使っていたくらいに、FWとBKを足して2で割ったようなポジションだから、FWのプレーに徹することもできるし、BK並みに走り、パスすることもできる。オールブラックスのジンザン・ブルックなんて、DG(ドロップゴール)まで決めてしまったのだから、そういう点では、チームで一番上手いスーパープレヤーがやるポジションなのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
