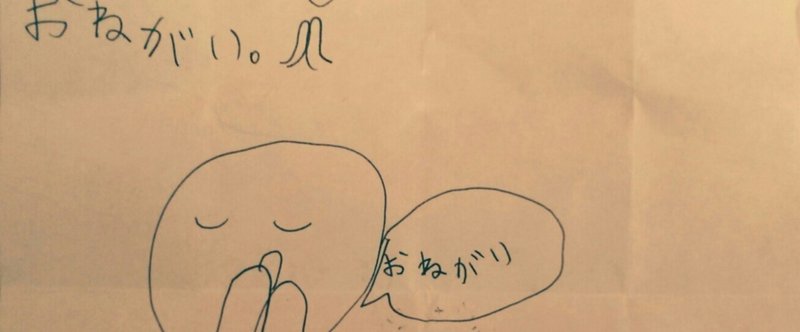
小説「雪だるま」
寒い日が続いている。今朝のニュースでも「今日はもしかしたら、雪になるかもしれません」と、三日前から同じことを言っていた。けれど、未だに雪は降っていない。
「タイヤ、変えてないのよねぇ、どうしようかしら」母は、困ったなぁとつぶやいたが、どれだけ寒いと思っても、この街に雪が降るのは年に数回程度しかない。車じゃなくても交通手段があるのだし、おそらく、タイヤは変えないだろうと思う。
一方で、まだ幼い妹は今日こそ雪が降らないかなぁと、このところ、窓の外をずっと眺めている。「雪だるま作るんだ」そんな妹を見ながら、母は「結衣の小さいころとそっくりね」と、うれしそうに笑った。私も幼いころは、そんなふうに窓に張り付いていたのだろうか。十も年の離れた妹は、まるで自分の子供みたいに愛しい。だから今日こそ雪が降って、妹の喜ぶ顔が見たいと思う。そんな想いで、空に祈りを込めながら、私は家路を辿っていた。
そのとき、強い向かい風が吹いてきて、私の体は押し戻された。そうして「あっ」と声をあげて、気が付く。教室に忘れ物をした。それは、図書室から借りてきた絵本だ。両親をなくした少年が、雪の日に作った雪だるま。それが冬の間だけ、少年と一緒に暮らす。春になって雪だるまは溶けてしまうのだけど、暖かい思い出がいつまでも残る、という少しせつない話の絵本。昼休みにその絵本を見つけて、妹に読んであげたくなったのだ。明日でもかまわないけれど、やっぱり、今日がいい。くるっと体を反転させると、向かい風は追い風に変わった。それに背中を押されて、思いのほか早く学校に戻れた。
ガラガラと教室のドアを開けると、窓際の一番後ろの席に誰かが座っているのが見えた。その席はタナダくんの席だ。「おぅ」と私に気付いたタナダくんは、右手を小さく上げた。私も「やぁ」と軽く手を上げる。タナダくん以外、誰も教室にはいない。タナダくんは本を机に広げている。そして手には別の本を持っている。手に持ったその本の装丁の色合いが、遠目から見る限り、私の借りた絵本と似ているように見えた。気になってタナダくんのほうに近づいてみると、それはやっぱり私の借りた絵本と同じだった。
「タナダくんも、その絵本、読んでるんだ?」
私がそう声をかけると、タナダくんは、のんびりとした口調で返事をした。よく見るとタナダくんの目は少し赤い。泣いていたのだろうか。
「あぁ、これかい? 佐崎さんの机のそばに落ちてたから、拾ったさ。やっぱり佐崎さんの借りた絵本だったんだ? 面白い絵本だね」
タナダくんは今年の春に北海道から転校してきた。両親が離婚して、今は母親の実家で一緒に暮らしていると、どこからともなくそんな話を耳にした。タナダくんの話し方のイントネーションには、今もまだ、なまりがある。標準語圏で生まれ育った私は、そのなまり方が少し羨ましくもあって、タナダくんと話すと、そのなまりに少しつられる。
「やっぱり私のかい」
隣の席に座ってそう言うと、タナダくんは首を傾けた。そして口角を上げながら、私に絵本を返した。たぶん、私のなまり方は、変なのだ。私は恥ずかしくなって、視線を下に向けた。視界には机の上に広げた本が見えた。それは地図だと気付く。私は、体を地図の方まで近付けて、それを覗きこむ。
「なしたの?」
タナダくんの声が、私のつむじのあたりから聞こえてくる。一瞬、ドキッとしたあと、何事もなかったように体を戻した。
「え、いやぁ、どこの地図?」
できるだけ冷静な声で私はそう言った。
「あぁ、これは北海道のページだけど」
「北海道かぁ。故郷が恋しくなったとか?」
「そんなんじゃないけど。ただねぇ、見てると、いろいろ、思うことがあって」
「思うこと?」
そう聞くと、タナダくんはパラパラと地図をめくり、関東のページを開いた。それから、指を県境の赤い線にあてて、それをなぞった。そうしながら、タナダくんは言う。
「たとえばこんなふうに、県堺が引いてあるしょ? でも、地図にしかないじゃん、そんな線。それが面白いなぁって。雪なんか降ったら、真っ白でどこがどこだかわかんないかもしれないよね」
悪いけどタナダくんの言いたいことが、全然わからなくて、私は「そ、そう」と不器用な返事をした。タナダくんはマイペースに今度は世界地図を取り出して、ヨーロッパのあたりを広げた。どこ? と聞くと、旧ユーゴスラビアあたりだ、と答えた。私は首をかしげる。
「この辺はちょっと前まで内戦を繰り返していたとこだよね。でも、戦争をやめたのは、雪が降ったからなんじゃないかって思って」
「雪が降ると、戦争が終わるの?」
私の首は斜めのままだ。このままではまっすぐに戻らない。
「雪が降ったら、足跡が付く。楽しいから、あっちにもこっちにも。して、そのうち国境なんて越えちゃってさ、線があったことなんて忘れちゃうんだよ。いや、忘れるというか、もともと国境なんてないことを思い出すというか。そうやって平和になったらいいなぁって思う」
タナダくんの言わんとしてることが、私にもなんとなくわかった。たとえば、友達とケンカした日、もう絶対話すもんかと心に決めたのに、その日に雪が降って、すぐに仲直りしたことが遠い昔にあった。それを思い出したからだ。私の首は真っすぐに戻る。
「男と女にも国境があるなら、雪でそんな線、消してしまえればいいのな」
タナダくんは独り言のように、つぶやいた。それはタナダくんの両親のことだろうか。そしてタナダくんは絵本のように、ここで雪だるまを待っていたのだろうか。私は何とも言えずに、タナダくんから視線を外した。視線を窓の外にやると、ちらちらと白いものが落ちてきているのが見えた。
「雪かな?」
「雪だ」
タナダくんが窓を開けると、強い風が入り込んできて、私のスカートは巻き上げられた。
「あ! ごめん!」
タナダくんはすぐに窓を閉めた。風の消えた教室は、すぐに静まり返って、チクタクと時計の音だけがやけに大きく響いた。その音よりもはるかに速く、私の胸の鼓動が波打っている。耳たぶが赤くなるのが、手にとるようにわかった。
「あ」
タナダくんが抑揚なく、そんな文字を口にした。
「え」
まるで猿芝居かのような感嘆詞を私が吐くと、タナダくんは「おー」と言って、地図を見た。国境の上に雪がちらほら。雪が原型を留めていたのは一瞬で、すぐに水になった。
「佐崎さん、ちょっと離れて?」
「え」
感嘆詞が、また口からこぼれる。
「窓、開けたいから」
私は、後ずさりをして、窓から離れていった。気が付けば、ドアのそばだ。
「そこまで離れなくても」
タナダくんは小さく笑い、それから窓を開けた。強い風がタナダくんの前髪をふわっと持ち上げる。ドアの近くの私のスカートは巻き上げられなかったけれど、冷たい空気が耳たぶを心地よく冷やした。
「うわぁ、しばれる!」
タナダくんは地図を手にして、それをベランダに置いた。そして、バタン! と、勢いよく窓を閉めた。タナダくんは窓の外を見て、私を手招きした。
「え」
また同じ感嘆詞を口にしながら、私は、窓の方へと近付いていく。
「ほら」
タナダくんは、ベランダに置かれた地図を指さしている。
「国境がなくなっていくよ」
地図の上には、雪が積もっている。窓に張り付いて、それを眺めるタナダくんは、「面白いなぁ……」と、ため息のように、つぶやいている。その姿は、雪を待つ妹のように思えて、私はタナダくんが愛しくなった。
「うん、国境なんて、ないね」
私は優しい想いでそう答えて、タナダくんに笑いかけた。タナダくんは、いつまでも窓に張り付いている。風が、次のページをめくった。そこにもまた雪が降り積もり、国境を消していった。
「帰ろうか」
チャイムが鳴ったところで、タナダくんが窓から離れた。
「うん」
私は静かにうなずいて、タナダくんの横を歩いた。校舎を出ると、地面も白く色づいていた。私たちは、それに足跡を付けていく。私はタナダくんの雪だるまになれたのだろうか。タナダくんは、そっと私の手を握った。その手は、とても、暖かい。その熱で溶けてしまってもいいと、私は思っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
